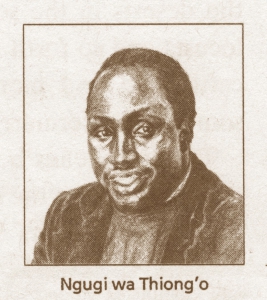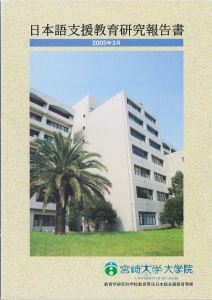「日本語支援教育専修」と私
概要
宮崎大学教育文化学部大学院修士課程学校教育専攻日本語支援教育専修の報告書に書いたものです。
本文
「日本語支援教育専修」と私 玉田吉行
なぜ日本語支援教育専修を推したのか
「なぜ日本語支援教育専修を推したのか」には、理由が2つあります。1つは、統合・法人化という名のリストラ政策の渦中で「日本語支援教育専修」が大学の生き残り策の1つの要素になり得ると感じたからです。もう1つは、言語をもっと大きな視点で捉えようとする「日本語支援教育専修」の目指す方向性なら、「日本語支援教育専修」とのかかわりを今までやってきた延長線上に位置づけるだけで何とかやれるかも知れないと考えたからです。
国や国際社会の大きな枠組みの中で考えても、そう遠くない将来に、膨らみ過ぎた経済が破綻するのは目に見えていますから、統廃合や人員・経費の削減などによる制度の再構築は避けられないでしょうし、少子化によってその傾向は強まり、学生の確保が大きな課題ともなるでしょう。定員確保は大学院ではすでに差し迫った問題で、大学の生き残り策の1つの大きな要素になっています。医学部では実際に定員が埋まらなかった分の年度当初の配分予算を返却していますし、その傾向が続けば学生定員の削減、その結果による教員定員の削減という事態は避けられないでしょう。また、留学生を増やすことも評価の対象になっていますが、円高や地理的な条件もあり、現実には留学生の大幅な増加は見込めない状態が続いています。そういった事情を勘案しますと、国内にいる外国人か海外の外国人かに日本語学習の支援をするための「日本語支援教育専修」を開設して留学生も含めた受験生を集めるのは充分に意義があり、実際に、韓国や台湾、中国などの日本語学校や大学、JICAや国際交流基金などの国際機関、国内の地方自治体や大学など、卒業後の就職の需要も見込めるようですから、将来性はあるように思えました。
昨年度2月に本学で行なわれた第一回マルチリンガリズム研究会の創設記念集会での、文化庁の野山広さんによる基調講演「多言語教育の時代:国内外の現状と共生の街づくりへ向けての始動」も大きな刺激となりました。第1線で活躍中の人でないと語れない勢いがありましたし、多文化共生への取り組みの具体的な事例には説得力が感じられましたから。また、計画した「日本語支援教育専修」のカリキュラムが、文化庁により提示された領域、日本語教育に必要とされる5領域(言語、言語と教育、言語と心理、言語と社会、社会・文化・地域)に沿い、言語教育、言語文化、言語心理の領域で日本語支援教育を行う上での教育内容・方法、心理について学び、国際文化、文化共生の領域で国際的な視野での共生、文化理解の在り方について学ぶという教育内容であったからでもあります。
今回行なわれた入学試験では、広範囲の地域から様々な年齢層の16名が集まりました。まだ問い合わせも続いていますし、学内からの進学者や留学生の応募も見込めます。定員割れだったり、応募者がいなかった専修もありましたから、健闘したと言えるでしょう。
医学部では、17年間、1・2年生を対象に、英語を手段として、アフリカやアフロ・アメリカの歴史や社会問題、音楽やスポーツ、エイズやエボラ出血熱、BSEや土呂久砒素問題、臓器移植などの医療問題、山頭火とHAIKUなど、色々な問題を取り上げ、今まで持っていた価値観や歴史観を再認識したり、自分について考える場を提供してきました。統合後は、主題教養科目の南アフリカ概論とアフリカ文化論でも、同じような問題提起をしています。
その意味では、「グローバルな視野にたち、複数文化への理解をもとに、国際舞台で活躍できる人間を育てる」という目標を掲げる「日本語支援教育専修」を、今までの延長線上に置くのは、それほど難しいようには思えませんでした。
そのようなことを念頭に置き、今までに書き残したものも考慮に入れて、専修の審査に必要な業績調書を書きながら(結果的には、要りませんでしたが)「日本語支援教育専修」でどんな科目が実際に担当出来るかを決めたのですが、「アフリカ論特論」と「翻訳論特論」なら、「日本語支援教育専修」で学ぶ人たちに何らかの問題提起は出来るかも知れないと考えました。
アフリカ論特論
では、「アフリカ論特論」と「翻訳論特論」を通して、どんな問題提議が出来るのか。
「アフリカ論特論」では、言語を取り巻く実情を踏まえて、「アフリカ人にとっての言語とは」と「日本人の自己意識」、とに焦点を当てたいと考えています。
今年度の主題教養科目(アフリカ文化論160、南アフリカ概論70)と英語(医学科90、農学部55、看護学科30)で約400名の1年生を担当してアンケートに答えてもらいましたが、アフリカに文学があるのを知っていたのは海外青年協力隊にいた医学部の学生1人だけでした。将来、国内にいる外国人か海外の外国人かに日本語学習の支援をする人たちが、アフリカに文学があることを知らない、では支障があるでしょう。今回の入学試験で英語の功罪についての問題を出しましたが、「国際語」のお陰で非常に多くの人の意思疎通が可能になった、あるいは経済的に優位に立つ人たちが開発し、英語で発信する技術や医薬品などについての最新情報を獲得出来るなどの「功」の部分と同時に、国の関係が経済的に対等でない場合は言語も対等ではなく、何百年と続いている「白人優位・黒人蔑視」が言語の面でもまかり通る可能性が高いという「罪」の部分も認識する必要はあるでしょう。
ケニアの作家グギは、「20世紀のアフリカ人作家」の立場を次のように書き記しています。
60年後半、私がリーズ大学の学生の頃に初めて、自分の置かれた作家としての立場の矛盾を意識して、絶望的な感覚に襲われたのを鮮明に覚えています。ちょうど、ケニアの人たちの独立闘争を扱った『一粒の麦』を出版したところでした。しかし、私が書いていたその人たちは、決してその小説を読むことはありませんでしたし、その小説が読まれはしません。私は言葉のケースに、細心の注意を払いながらその人たちの命をそっと収めていたのです。私がケニアの国の中に拠点を持とうと国外に持とうと、英語という言語を選ぶ限り、そのことで亡命作家としてのレッテルを自分に貼り付けてしまっていたのです……。アフリカの作家は、教育を受け言語を選択した時点で、既に人々から顧みられることはないのです。
20世紀アフリカの作家の立場は、より広範なアフリカ社会の立場を映し出しています。というのも、もし作家が、心身ともに亡命の立場に居るというのなら、人々自身も、自分たちの経済や政治的な関係から見ても、亡命しているような立場にいるからです。1
グギは1982年から最近まで、実質的に亡命を強いられ、ケニアに帰れませんでした。体制の脅威であったからです。ウガンダのマケレレ大学を出て、イギリス、アメリカで教育を受け、ジェイムズ・グギの名前で書いた小説『夜が明けるまで』(1964)や『一粒の麦』(1967)などで国際的な評価を受けていましたが、英語で書くことを辞め、農民や労働者のために母国語のギクユ語で書き始めたてから、体制の脅威となりました。グギたちが指導した農村での演劇活動で、母国語のギクユ語で書いた脚本を、ギクユの農民と労働者が見事に演じきってしまった、つまり、多数派である搾取される側の農民と労働者が、演劇活動を通して自らの隷属的な立場に気づき、団結して体制側に挑み始めたからです。グギは、反体制側の象徴となりました。
グギ・ワ・ジオンゴ
侵略を始めた西洋諸国が奴隷貿易で暴利を得て、その資本で産業革命を起こし、作った製品の市場獲得のためにアフリカ争奪戦を繰り広げ、結果的には2つの世界大戦を引き起こしたあと戦略を変え、「開発」や「援助」の名のもとに、国連や世界銀行などに守られながら新しい形の支配体制(新植民地体制)を築き上げています。
ケニアも南アフリカからの白人入植者がアフリカ人労働者を元に搾取機構を打ち立てた国です。激しい闘争の末にイギリスから独立は果たしたものの農民や労働者を搾取するという基本構造は変わらず、大統領となったケニヤッタもモイも、先進国と組んで体制維持をはかってきました。少数の金持ちと大多数の貧乏人という歪な世界で、日本は貿易のよき相手です。
そういった現状と、「アフリカは貧しいから助けてあげる」、「日本はODAなどでアフリカに援助している」と考えている大半の日本人の意識との間には、余りにも隔たりがあります。JICAや国際交流基金で派遣されても、現状認識が出来ていなければ、やはり支障があるでしょう。異文化理解、国際理解などは望むべくもありありません。
翻訳論特論
元ナイロビ大学の教員で農学部の大学院にいた留学生が、「グギを卒業論文に取り上げたナイロビ大学の同級生が、卒業してから刑務所に入れられた」という話をしてくれましたが、1992年に私が飜訳した南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマ (Alex La Guma, 1925-1960) の『まして束ねし縄なれば』は、アパルトヘイト体制の下では発禁処分を受けていました。ケープタウン郊外のスラムの日常を描いた作品ですが、体制側が世界に実情を知られたくなかったからです。
1987年にケント州立大学英語科教授の伯谷嘉信さんからMLA (Modern Language Association of America) のイギリス文学、アメリカ文学以外の英語による文学 (English Literature Other than British and American) の部会で発表しませんかとお誘いを受けたのがラ・グーマを調べるきっかけだったのですが、その過程で、思わぬ「日本の南アフリカ事情」を垣間見ることになりました。
アジア・アフリカ作家会議の季刊誌にラ・グーマが書いた「アパルトヘイト下の南アフリカ文学」(“South African Writing under Apartheid," 1975) が「新日本文学」(1977年4月号) に飜訳されていることを知り、図書館でコピーを手に入れた時、次の一節が目に飛び込んできました。
アレックス・ラ・グーマ
このことは、南アフリカの創造的な作家にとって、なにを意味するのか。明快なことは大多数の黒人の利用できる文化施設が白人よりもはるかに劣っていることだ─率直に言えば、様々な面でなにもないということだ。ヨハネスブルグがその大部分の労働源を引き出すソウェト族の都市には、ほぼ百万人の人口にたった1軒の映画館があるだけで、実際に観ることのできるフィルムの数は検閲で夥しく制限されている。
(What does all this mean for the creative artist in South Africa? In the most obvious sense, the cultural facilities available to the Black majority are far inferior to those of the Whites – and in some cases simply nor existent. In the giant African township of Soweto, from which Johannesburg draws most of its labour force, there is only one cinema for a population nearly one million, and the number of films which may be seen by audiences at that cinema is grossly restricted by a censorship which places all Africans on the same level as White children under 16. )
この文章を飜訳した石井碩行という人は、「ジョハネスバーグがその労働力の大半をまかなっている巨大なアフリカ人居住区ソウェト」を「ヨハネスブルグがその大部分の労働源を引き出すソウェト族の都市」と訳しているのです。Soweto は South West Township of Johannesburgの略語で、金鉱で開けたアフリカ大陸でも有数の大都市ジョハネスバーグの南西の方角にあるタウンシップ(居住地区)のことですが、それをこともあろうに、人と間違えているのです。おまけに族までがついています。族はtribeの日本語訳ですが、その言葉には西洋人がアフリカ人を蔑んだつけた否定的な意味合いが含まれますから、使うのを嫌う人も大勢います。発行されたのが1977年ですから、その前年のソウェトの蜂起を知らない人がこの文章を訳したということになります。「新日本文学」は共産党の機関誌で、アジア・アフリカ・ラテンアメリカの特集を組んだりして精力的に新しいものを紹介していますが、この程度の飜訳を掲載していた訳で、内容に全く無知な人が飜訳をした典型と言えるでしょう。
ラ・グーマの第1作品『夜の彷徨』の日本語訳の場合も同様です。主人公の青年が老人を殺害したあと、街をうろついている場面が次のように描かれています。
やつにしても、ほかのやつらにしても面白くねえ。きっとおれはやつらに話しにいったらいいんだ。ベドナード。おまえは警官がどうするかわかっているな。やつらはおれたち茶色い人間ことなど、これっぱしも聞いてくれやしない。
(To hell with him and the lot of them. Maybe I ought to go and tell them. Bednerd. You know what the law will do to you. You don’t have any shit from us brown people.)
当時明治大学の教授、と解説にあります。この人は多分英語の辞書では見つからないBednerd がわからないので、ベドナードと書いたのでしょう。このすぐあとにも1カ所同じ日本語訳が出てきます。もちろん、その当時アパルトヘイトが厳しくて南アフリカの人に聞けたかどうかはわかりませんが、この人は、アパルトヘイト政権を担った人たちの言葉がアフリカーンス語であったことすら知らなかったのではないでしょうか。知っていたとしたら、少なくともアフリカーンス語の辞書を見ていたでしょうから。たとえ辞書になくても、領事館か外務省に電話を一本かければ済むことです。それに、この本が出た1970年なら他のラ・グーマの本、たとえばAnd a Threefold Cord (1964) を図書館で探し当てるのは、それほど難しくなかったはずです。探してさえいれば、その本の付録につけてあるGLOSSARYのなかにbednerd=crazy, mixedの解説を見つけていたでしょう。第一、わからなくても文脈からその意味を推測できなくて、飜訳など出来るのでしょうか。学藝書林から出版され、大きな図書館の本棚に『全集現代世界文学の発見』シリーズの『9 第三世界からの証言』として並べられてあるのですから、驚きです。
南アフリカ問題の古典とも言える『差別と叛逆の原点』を書いた野間寛二郎さんは、ガーナの初代首相クワメ・エンクルマの自伝を飜訳する際に、わからないことが多かったので若いガーナの書記官のいる大使館に日参したと書いています。それが普通でしょう。brown peopleを茶色い人間と訳していますが、brown peopleがcolouredだと知らないで飜訳を引き受ける無謀さに、言葉もありません。先人が残したこんな業績に出くわすと、かなしくなるばかりです。
アフリカ系アメリカ人詩人のダンバー(Paul Laurence Dunbar)にLittle Brown Babyという詩があります。長く、きつく、汚い労働から帰ってきたあと、我が子と戯れる父親を詠んだ短かい詩です。
Paul Laurence Dunbar
Little brown baby wif spa’klin’ eyes,
Come to you’ pappy an’ set on his knee.
What you been doin’, suh – makin’ san’ pies?
Look at dat bib – you’s ez du’ty ez me.
Look at dat mouth – dat’s merlasses, I bet;
Come hyeah, Maria, an’ wipe off his han’s.
Bees gwine to ketch you an’ eat you up yit,
Bein’ so sticky an’ sweet goodness lan’s!
Little brown baby wif spa’klin eyes,
Who’s pappy’s darlin’ an’ who’s pappy’s chile?
Who is it all de day nevah once tries
Fu’ to be cross, er once loses dat smile?
Whah did you git dem teef? My, you’s a scamp!
Whah did dat dimple come f’om in yo’ chin?
Pappy do’ know yo – I b’lieves you’s a tramp;
Mammy, dis hyeah’s some ol’ straggler got in!
Let’s th’ow him outen de do’ in de san’,
We do’ want stragglers a-layin’ 'roun’ hyeah;
Let’s gin him 'way to de big buggah-man;
I know he’s hidin’ erroun’ hyeah right neah.
Buggah-man, buggah-man, come in de do’,
Hyeah’s a bad boy you kin have fu’ to eat.
Mammy an’ pappy do’ want him no mo’,
Swaller him down f’om his haid to his feet!
Dah, now, I t’ought dat you’d hub me up close.
Go back, ol’ buggah, you sha’n’t have dis boy.
He ain’t no tramp, ner no straggler, of co’se;
He’s pappy’s pa’dner an’ playmate an’ joy.
Come to you’ pallet now – go to yo’ res’;
Wisht you could allus know ease an’ cleah skies;
Wisht you could stay jes’ a chile on my breas’
Little brown baby wif spa’klin’ eyes!
ある人はLittle brown baby wif spa’klin’ eyesに「きんきら目玉の褐色の赤ちゃん」という訳をつけました。何冊も著書や飜訳書もあるアメリカ文学を専門にしている人で、特にアフリカ系アメリカ人女性作家に詳しいらしいのですが、少なくとも、詩に「きんきら」や「目玉」や「赤ちゃん」などの言葉をつかう人が、飜訳などすべきではありません。詩に魂をこめたダンバーに失礼でしょう。
南北戦争の後のあの悲惨な状況下での話です。考えてもみて下さい。大学に行って学問をしたい、医者になりたい、弁護士になって困っている人たちの手助けをしたいと考えたかも知れない人たちが、来る日も来る日も炎天下の農園で綿摘みを、あるいは地底で石炭掘りをしなければならないとしたら。反動勢力の敷いたカラー・ラインは、奴隷としてアフリカからつれてこられた子孫たちにとって厳しいもので、ミシシッピ生まれの作家リチャード・ライトは図書館で黒人は本も貸しもらえなくて、白人の名前で本を借りなければならなかった経験を自伝のなかに記しています。白人と対等に、などと張り合えば、忽ちリンチされてしまいます。
「おばけだぞう」と脅したらぎゅっとしがみついてくる我が子を見ながら、その成長を願わない親などいるでしょうか。大きくならないで、このままこの胸元で子供のままでいられたらと願う親がどこにいるでしょう。仮定法の過去は現在の事実の反対を仮定していう表現形式ですが、現実が厳しすぎるからこそ、その表現が真に迫ってくるのでしょう。
Little brown baby wif spa’klin’ eyesに「輝く瞳(め)をした愛しい吾が子よ」という日本語訳がつけられる翻訳論特論でありたいと思っています。
「日本語支援教育専修」と私
統合・法人化という名のリストラ政策の渦中で「日本語支援教育専修」が大学の生き残り策の1つの要素になり得るにしても、言語をもっと大きな視点で捉えようとする目指す方向性のなかで自分の位置を何とか見つけ出せるにしても、また、入学する人たちが意欲のある優れた人たちであるにしても、現実はなかなか厳しいものがあります。どさくさの統合や法人化の中で、新しい組織も充分に機能しているとは思えませんし、やった分の評価がなされているとは到底思えないからです。学生にとって、あるいは学校にとっていいと思える意見を出せば、その分だけすることが増えている現実があり、それがきっちりと評価されていないと思えるからです。医学部との兼任という立場でかかわっているのですが、今でも多い授業に2コマが増えた、というのが実状です。今回行なった入学試験にしても休みの日に長時間木花キャンパスに居なければなりませんでした。その上、規定では夜間開講もしなければならないとのことです。きちんとした評価もなされず、評価や手当も配慮されないようでは、長期的に見て、決していい成果が望めるとは思いません。
それに、「アフリカに文学があることを知らない」、「アフリカは貧しいから助けてあげる」、「日本はODAなどでアフリカに援助している」、そんな程度の人たちが入って来るとすれば、実際の授業は生易しいものではないでしょう。
近い将来に「日本語支援教育専修」の修了生が、JICAや国際交流基金から派遣されるとするなら、2年間は、学ぶ人たちにとっても、講義を担当する私たちにとっても、極めて短かい年月と言わざるを得ません。現状の中で何が出来るのかを考えながら、意識改革や日本語支援に必要な専門的な理論武装をして行かなければならないと思います。
そう考えて、夏休みの初め頃から、英文資料のスキャナでの取り込みを始めています。
1 Ngugi, “From the Corridors of Silence,” originally published in The Weekend Guardian (October 21-22, 1989), p. 3., and later included in Moving the Centre (Heinemann, 1993), pp. 102-108.
執筆年
2005年
収録・公開
日本語支援教育研究報告書