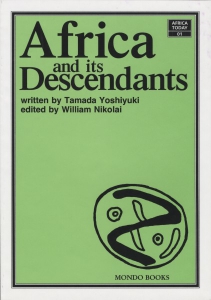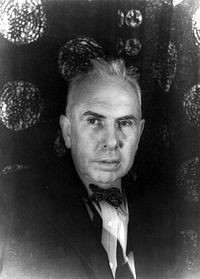つれづれに:『緋文字』
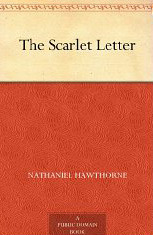
アメリカ関連で、→「アメリカ文学」と→『アメリカの悲劇』の続きで、今回は『緋文字』である。→「採用試験」と→「大学院入試」の読むべき本のリストの中から最初に『アメリカの悲劇』を選んだのは一番分厚かったからだが、次になぜ『緋文字』を選んだかはわからない。3ケ月かかって『アメリカの悲劇』を読み終えたとき、物理的にこのまま続けても一生に何冊読めるのか、と考えた。分からない言葉に出会う度に辞書を引く、その行為自体の方向性が基本的に間違っているのではないか?赤ん坊が言葉を覚えるのは、母親が言う言葉を想像して、想像してそのうちに会得するのだ。読む場合も同じことが言えるのではないか?最初はわからなくても、想像して読むうちに理解できるようになる、そんな風に思えた。
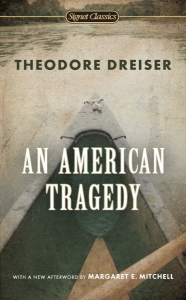
Theodore Dreiser, An American Tragedy
3ケ月ほとんど読む毎日だったので、『緋文字』をかばんに入れ、寝袋を持って→「山陰」周りで津和野に行くことにした。芭蕉の『奥の細道』の「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。‥‥予もいづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、漂白の思ひやまず」の影響もあって、その頃、思い立って出かけることが多くなっていた。
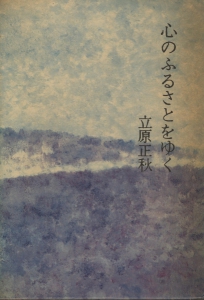
姫路から姫新線に乗ったのは初めてだった。岡山の津山と島根の津和野に行ってみたいと思っていた。新聞の連載小説を読んだ立原正秋の『心のふるさとを行く』(↑)に書かれていたのを見たときである。津山と津和野に2泊しただけだったが、帰ってから吹っ切れたように残りを辞書なしで一気に読み終えた。『シスターキャリー』に次いで、『緋文字』は辞書なしで読んだ2冊目の本になった。文字が目に馴染んで来始めていたような気もする。

津山城
『緋文字』の著者はナサニエル・ホーソンである。1850年の出版だが、舞台は17世紀半ばニューイングランド、現在のアメリカ北東部のボストンで、宗教的規律が厳しい清教徒の多かった時代に生きたある女性の話である。読んだのが半世紀前なので、ニューイングランドの話は暗いなあ、入植して最初に造ったのが刑務所とは大変な社会だなあ、そんな印象しか残っていない。ウェブで調べていると、「そうだった気がする」という感じもして来た。
主人公の夫は数年前に家を出てから再び姿を現さなかったので、死んだと思われていた。その間に、人々に尊敬されている若い牧師と恋仲となり子供を産んだ。厳しい清教徒の社会で婚外子は許されず、公衆の面前で罰せられた。村の広場の処刑台の上に立たされて、上衣の胸に姦婦(adulteress)の頭文字Aを着けられることになったのである。厳しい宗教的制裁にもめげずに、女性は娘を逞しく育てていく。牧師は父親を名乗り出ると言ったが、主人公に止められる。医師として村に戻っ夫は2人の関係を見抜き、執拗に2人を付け回し、執念深く追い詰める。牧師は広場の処刑台に立って、胸に焼きつけた胸のAの文字を見せ、父親を名乗ったあと、女性の腕の中で死んでゆく。物語の概要である。

南北戦争からトランプまでの→「南北戦争のあと:政治篇」、→「経済篇1」、→「経済篇2」、→「ソウル」、→「トランプ2」、→「トランプ3」とは時代が重ならないが、入植者がそこの住んでいた人たちを蹴散らして造っていった移民社会を理解する手掛かりになる。特に、「トランプ3」に引用したある記事が指摘していた「移動しながら住んでいた先住民から広大な土地を奪い、追放と虐殺を繰り返し、19世紀末には先住民をほぼ全滅させた」セトラーコロニアリズムとプアホワイトの心性を探る基軸になる。

『心のふるさとを行く』を読んで津山と津和野に行ったあとも、篠山、鎌倉、倉敷、高山、嵯峨野に出かけた。作家の他の作品を読んだあとにも、大和高田の→「栄山寺八角堂」に行き、奈良西大寺の→「伎藝天」とも会って来た。作家の主な舞台になっていた→「鎌倉」の街と湘南海岸(→「海岸道路」、→「湘南」)を歩き、江ノ島電鉄(→「江之電と『天国と地獄』」)にも乗ってきた。勢いでそのまま神保町の古本屋街にも行ってみたが、作品はほとんど手に入れていたので目ぼしい成果はなかった。明石より西に住んでいたので、姫路から新幹線を利用したと思う。