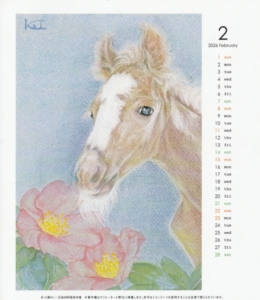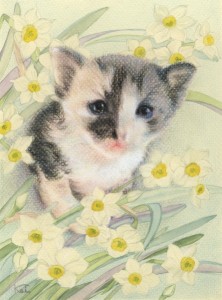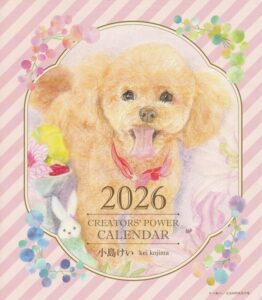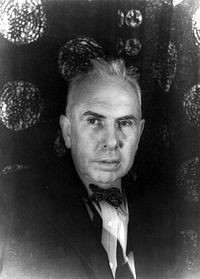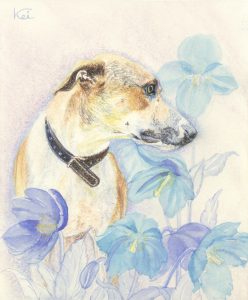「つれづれに」一覧です
「『つれづれに』一覧」→(2024年~2018年)、それ以降は→「過去のつれづれ」(2018年~2007年)、→「過去ログ(2006年度)」、→「過去ログ(2005年度)」
このブログ以前(2018年~2005年)の分はホームページにリンクしています。
2026年2月
→「つれづれに:アメリカの悲劇』(2026年2月8日)
→「つれづれに:アメリカ文学」(2026年2月6日)
→「つれづれに:トランプ3」(2026年2月6日)
→「つれづれに:2月も5日目に」(2026年2月5日)
→「つれづれに:2月も4日目に」(2026年2月4日)
→「つれづれに:2月も3日目に」(2026年2月3日)
→「つれづれに:2月も2日目に」(2026年2月2日)
→「つれづれに:2月に入り」(2026年2月1日)
2026年1月
→「つれづれに:トランプ2」(2026年1月30日)
→「つれづれに:トランプ1」(2026年1月29日)
→「つれづれに:ソウル」(2026年1月28日)
→「つれづれに:南北戦争のあと:経済篇2」(2026年1月24日)
→「つれづれに:南北戦争のあと:経済篇1」(2026年1月19日)
→「つれづれに:南北戦争のあと:政治篇」(2026年1月17日)
→「つれづれに:2026年1月半ば」(2026年1月16日)
2025年12月
→「つれづれに:畑12月」(2025年12月25日)
2025年11月
→「つれづれに:畑11月」(2025年11月10日)
2025年10月
→「つれづれに:日常」(2025年10月29日)
→「つれづれに:10月も半ばを過ぎて」(2025年10月18日)
2025年8月
→「つれづれに:久しぶりに」(2025年8月30日)
2025年5月
→「つれづれに:比較編年史1950⑤南アフリカ」(2025年5月23日)
→「つれづれに:比較編年史1950④アフリカ」(2025年5月21日)
→「つれづれに:比較編年史1950③アメリカ」(2025年5月19日)
→「つれづれに:比較編年史1950②日本」
→「つれづれに:比較編年史1950①私」(2025年5月14日)
→「つれづれに:比較編年史1949⑦ケニア」(2025年5月12日)
→「つれづれに:比較編年史1949⑥コンゴ」(2025年5月11日)
→「つれづれに:比較編年史1949⑤南アフリカ」(2025年5月7日)
→「つれづれに:④1949アフリカ」(2025年5月5日)
→「つれづれに:③1949アメリカ」(2025年5月4日)
→「つれづれに:比較編年史②1949日本」(2025年5月2日)
2025年4月
→「つれづれに:比較編年史①1949私 」(2025年4月30日)
→「つれづれに:マッサージ」(2025年4月29日)
→「つれづれに:畑4月下旬」(2025年4月28日)
→「つれづれに:永谷園俳句」(2025年4月26日)
→「つれづれに:ブログ再開」(2025年4月25日)
2025年2月
→「つれづれに:半ばを過ぎても」(2025年2月10日)
→「つれづれに:半ばを過ぎ」(2025年2月5日)
2025年1月
→「つれづれに:半ば」(2025年1月26日)
→「つれづれに:インタビュー」(2025年1月13日)
→「つれづれに:構想は」(2025年1月10日)
2024年12月
→「つれづれに:しばらく」(2024年12月28日)
→「つれづれに:宣教師」(2024年12月18日)
→「つれづれに:英語雑記ー生得的」(2024年12月17日)
→「つれづれに:晴れが続き」(2024年12月9日)
→「つれづれに:月曜日」(2024年12月3日)
→「つれづれに:山茶花」(2024年12月2日)
2024年11月
→「つれづれに:日曜日」
→「つれづれに:歩く」(2024年11月24日)
→「つれづれに:瓢箪南瓜」(2024年11月23日)
→「つれづれに:探検家」(2024年11月22日)
→「つれづれに:陽の光」(2024年11月21日)
→「つれづれに:白浜行き」(2024年11月20日)
→「つれづれに:グレートジンバブエ」(2024年11月16日)
→「つれづれに:ルーツ」(2024年11月12日)
→「つれづれに:ハイビスカス」(2024年11月10日)
→「つれづれに:『アフリカのための闘い』」(2024年11月8日)
→「つれづれに:立冬」(2024年11月7日)
→「つれづれに:エジプト文明」(2024年11月6日)
→「つれづれに:アフリカシリーズ」(2024年11月5日)
→「つれづれに:陽が出て」(2024年11月2日)
→「つれづれに:1980年頃」(2024年11月1日)
2024年10月
→「つれづれに:アフリカ人」(2024年10月30日)
→「つれづれに:柿干せど」(2024年10月23日)
→「つれづれに:アフリカ小史」(2024年10月17日)
→「つれづれに:最後の疫病」(2024年10月16日)
→「つれづれに:ナイス・ピープル」(2024年10月15日)
→「つれづれに:タボ・ムベキ」(2024年10月14日)
→「つれづれに:HIV人工説詳細」(2024年10月13日)
→「つれづれに:エイズ検査」(2024年10月12日)
→「つれづれに:性のあり方」(2024年10月11日)
→「つれづれに:エイズの起源」(2024年10月10日)
→「つれづれに:ニューアフリカン」(2024年10月9日)
→「つれづれに:アフリカ人に聞け」(2024年10月8日)
→「つれづれに:アフリカ」(2024年10月6日)
→「つれづれに:HIV人工説」(2024年10月4日)
→「つれづれに:10月1日」(2024年10月3日)
2024年9月
→「つれづれに:秋立ちぬ」(2024年9月24日)
→「つれづれに:大統領選」(2024年9月23日)
→「つれづれに:製薬会社」(2024年9月21日)
→「つれづれに:多剤療法」(2024年9月15日)
→「つれづれに:彼岸花」(2024年9月14日)
→「つれづれに:医師の苦悩」(2024年9月13日)
→「つれづれに:国際エイズ会議」(2024年9月12日)
→「つれづれに:CDC」(2024年9月11日)
→「つれづれに:エイズ発見の歴史」(2024年9月5日)
→「つれづれに:HIV増幅のメカニズム」(2024年9月4日)
→「つれづれに:免疫の仕組み」(2024年9月3日)
→「つれづれに:血液」(2024年9月2日)
→「つれづれに:台風一過」(2024年9月1日)
2024年8月
→「つれづれに:ウィルス」(2024年8月31日)
→「つれづれに:エイズ」(2024年8月30日)
→「つれづれに:台風10号続報」(2024年8月29日)
→「つれづれに:台風10号」(2024年8月28日)
→「つれづれに:コンゴと南アフリカ」(2024年8月27日)
→「つれづれに:マンデラの釈放」(2024年8月24日)
→「つれづれに:捏ち上げ」(2024年8月23日)
→「つれづれに:ウラン」(2024年8月22日)
→「つれづれに:自己意識」(2024年8月21日)
→「つれづれに:作家」(2024年8月16日)
→「つれづれに:武力闘争」(2024年8月14日)
→「つれづれに:アフリカ人女性」(2024年8月13日)
→「つれづれに:若い力」(2024年8月12日)
→「つれづれに:セシル・ローズ」(2024年8月4日)
→「つれづれに:暑中の畑模様」(2024年8月3日)
→「つれづれに:8月」(2024年8月2日)
2024年7月
→「つれづれに:百日紅」(2024年7月30日)
→「つれづれに:ヒュー・マセケラ」(2024年7月29日)
→「つれづれに:ラント金鉱」(2024年7月28日)
→「つれづれに:一大搾取機構」(2024年7月27日)
→「つれづれに:金とダイヤモンド」(2024年7月25日)
→「つれづれに:イギリス人」(2024年7月24日)
→「つれづれに:オランダ人」(2024年7月23日)
→「つれづれに:大西洋」(2024年7月22日)
→「つれづれに:どくだみ」(2024年7月21日)
→「つれづれに:7月も半ばを過ぎ」(2024年7月20日)
2024年6月
→「つれづれに:20代オーバーワーク」(2024年6月20日)
→「つれづれに:50代オーバーワーク」(2024年6月19日)
→「つれづれに:オーバーワーク」(2024年6月18日)
→「つれづれに:腸腰筋」(2024年6月17日)
2024年5月
→「つれづれに:関門橋」(2024年5月20日)
→「つれづれに:混沌」(2024年5月19日)
→「つれづれに:デヴィドスン」(2024年5月18日)
→「つれづれに:ニエレレ」(2024年5月17日)
→「つれづれに:モブツの悪業」(2024年5月16日)
→「つれづれに:カビラ」(2024年5月15日)
→「つれづれに:紛争」(2024年5月14日)
→「つれづれに:いのち」(2024年5月13日)
→「つれづれに:銃創」(2024年5月12日)
→「つれづれに:エボラ・コンゴ関連」(2024年5月11日)
→「つれづれに:診療所」(2024年5月11日)
→「つれづれに:エイズハイウエィ」(2024年5月10日)
→「つれづれに:『悪夢』」」(2024年5月9日)
→「つれづれに:深い傷跡」(2024年5月8日)
→「つれづれに:残忍」(2024年5月7日)
→「つれづれに:レオポルド2世」(2024年5月6日)
→「つれづれに:国連軍」(2024年5月5日)
→「つれづれに:コンゴ動乱」(2024年5月4日)
→「つれづれに:ノアとのら」(2024年5月3日)
→「つれづれに:ペンタゴン」(2024年5月2日)
→「つれづれに:コンゴあれこれ」(2024年5月1日)
→2024年4月「つれづれに」一覧
→2024年3月「つれづれに」一覧
→2024年2月「つれづれに」一覧]
→2024年1月「つれづれに」一覧
→2023年12月「つれづれに」一覧
→2023年11月「つれづれに」一覧
2023年10月
→「つれづれに:畝1号」(2023年10月15日)
→「つれづれに:秋」(2023年10月8日)
→「つれづれに:気温も下がり」(2023年10月7日)
2023年9月
→「つれづれに:挨拶」(2023年9月23日)
→「つれづれに:葛」(2023年9月21日)
→「つれづれに:枇杷」(2023年9月14日)
→「つれづれに:彼岸花を」(2023年9月11日)
→「つれづれに:畑を始め‥‥」(2023年9月2日)
→「つれづれに:9月になって」(2023年9月1日)
2023年8月
→「つれづれに:秋立ちぬ」(2023年8月21日)
→「つれづれに:原言語」(2023年8月5日)
→「つれづれに:送稿」(2023年8月3日)
2023年7月
→「つれづれに:絵を描く」(2023年7月28日)
→「つれづれに:水仙郷襖絵」(2023年7月27日)
→「つれづれに:フィクション」(2023年7月26日)
→「つれづれに:青島→白浜」(2023年7月25日)
→「つれづれに:青島と少年」(2023年7月24日)
→「つれづれに:青島」(2023年7月23日)
→「つれづれに:白浜に2」(2023年7月22日)
→「つれづれに:白浜に」(2023年7月21日)
→「つれづれに:今日もまた」(2023年7月20日)
→「つれづれに:今日も歩けた」(2023年7月19日)
→「つれづれに:暑い最中(さなか)に」(2023年7月18日)
→「つれづれに:暑中」(2023年7月17日)
→「つれづれに:街まで自転車で」(2023年7月16日)
→「つれづれに:最近の歩くコース」(2023年7月9日)
→「つれづれに:自転車で」(2023年7月8日)
→「つれづれに:歩くコースまとめ」(2023年7月6日)
→「つれづれに:南瓜の柵完成」(2023年7月4日、翌日更新)
→「つれづれに:南瓜の柵に苦戦中」(2023年7月1日)
2023年6月
→「つれづれに:脱稿」(2023年6月26日)
→「つれづれに:脱稿間近」(2023年6月25日)
2023年5月
→「つれづれに:水平方向と鉛直方向」(2023年5月18日)
→「つれづれに:端午の節句」(2023年5月7日)
→「つれづれに:出席をとる?」(2023年5月5日)
2023年4月
→「つれづれに:教える?」(2023年4月30日)
→「つれづれに:旧暦のこと」(2023年4月23日)
2023年3月
→「つれづれに:さくら満開」(2023年3月30日)
→「つれづれに:畑を再開しました」(2023年3月10日)
2023年2月
→「つれづれに:日常を少しずつ」(2023年2月25日)
→「つれづれに:2023初めまして」(2023年2月23日)
2022年12月
→「つれづれに:2022顛末記」(2022年12月31日)
→「つれづれに:かき顛末記③西条柿」(2022年12月18日)
→「つれづれに:かき顛末記②過去の『つれづれに』」(2022年12月17日)
→「つれづれに:かき顛末記」(2022年12月7日)
→「つれづれに:のど顛末記」(2022年12月1日)
2022年11月
→「つれづれに:日常」(2022年11月2日)
→「つれづれに:ケニア1860」(2022年11月1日)
2022年10月
→「つれづれに:コンゴ1860」(2022年10月31日)
→「つれづれに:『つれづれに』」(2022年10月30日)
→「つれづれに:ボイラー」(2022年10月27日)
→「つれづれに:ガーナ1860」(2022年10月25日)
→「つれづれに:ジンバブエ1860」(2022年10月24日)
→「つれづれに:南アフリカ1860」(2022年10月23日)
→「つれづれに:日1860」(2022年10月22日)
→「つれづれに:米1860」(2022年10月21日)
→「つれづれに:地下鉄道」(2022年10月20日)
→「つれづれに:畑も始めたが」(2022年10月19日)
→「つれづれに:叛逆の系譜」(2022年10月18日)
→「つれづれに:奴隷体験記」(2022年10月17日)
→「つれづれに:年老いたライリー」(2022年10月16日)
→「つれづれに:そっとお行きよ」(2022年10月15日)
→「つれづれに:モーゼ?」(2022年10月14日)
→「つれづれに:深い河?」(2022年10月13日)
→「つれづれに:ジェリコの戦い」(2022年10月12日)
→「つれづれに:畑再開」(2022年10月11日)
→「つれづれに:すすきにこすもす」(2022年10月10日)
→「つれづれに:白鷺」(2022年10月9日)
→「つれづれに:堀切ですすき」(2022年10月日)
→「つれづれに:下り行け、モーゼ」(2022年10月7日)
→「つれづれに:深い河」(2022年10月6日)
→「つれづれに:ブラックミュージック」(2022年10月5日)
→「つれづれに:慈しむ心」(2022年10月4日)
→「つれづれに:寛容」(2022年10月3日)
→「つれづれに:黒人史の栄光」(2022年10月2日)
→「つれづれに:アフロアメリカ史を」(2022年10月1日)
2022年9月
→「つれづれに:ブログ再開」(2022年9月30日)
→「つれづれに:山頭火と彼岸花」(2022年9月22日)
→「つれづれに:既卒組」(2022年9月21日)
→「つれづれに:台風一過続報」(2022年9月20日)
→「つれづれに:台風一過」(2022年9月19日)
→「つれづれに:個展」(2022年9月18日)
→「つれづれに:台風14号」(2022年9月17日)
→「つれづれに:註釈書1」(2022年9月16日)
→「つれづれに:雑誌記事3」(2022年9月15日)
→「つれづれに:南アフリカから」(2022年9月14日)
→「つれづれに:雑誌記事2」(2022年9月13日)
→「つれづれに:雑誌記事」(2022年9月12日)
→「つれづれに:仕上げ」(2022年9月11日)
→「つれづれに:夏の花2」(2022年9月10日)
→「つれづれに:夏の花」(2022年9月9日)
→「つれづれに:暑い日々」(2022年9月8日)
→「つれづれに:黒人研究の会、その後」(2022年9月7日)
→「つれづれに:市立大学」(2022年9月6日)
→「つれづれに:しゅうさく」(2022年9月5日)
→「つれづれに:畑と節気」(2022年9月4日)
→「つれづれに:春の花5」(2022年9月3日)
→「つれづれに:春の花4」(2022年9月2日)
→「つれづれに:春の花3」(2022年9月1日)
2022年8月
→「つれづれに:春の花2」(2022年8月31日)
→「つれづれに:ほぼ初めての春の花」(2022年8月30日)
→「つれづれに:花を描く」(2022年8月29日)
→「つれづれに:装画第1号」(2022年8月28日)
→「つれづれに:歯医者さん」(2022年8月27日)
→「つれづれに:海外事情研究会」(2022年8月26日)
→「つれづれに:アパルトヘイト否!」(2022年8月25日)
→「つれづれに:非常勤」(2022年8月24日)
→「つれづれに:秋桜(こすもす)」(2022年8月23日)
→「つれづれに:英語科」(2022年8月22日)
→「つれづれに:同僚」(2022年8月21日)
→「つれづれに:一般教養と授業」(2022年8月20日)
→「つれづれに:ラ・グーマ記念大会」(2022年8月19日)
→「つれづれに:黒人研究の会シンポジウム」(2022年8月18日)
→「つれづれに:自転車で」(2022年8月17日)
→「つれづれに:初めての郵便物」(2022年8月16日)
→「つれづれに:借家に」(2022年8月15日)
→「つれづれに:宮崎へ」(2022年8月14日)
→「つれづれに:横浜から」(2022年8月13日)
→「つれづれに:お別れ」(2022年8月12日)
→「つれづれに:再び広島から」(2022年8月11日)
→「つれづれに:宮崎に」(2022年8月10日)
→「つれづれに:広島から」(2022年8月9日)
→「つれづれに:工大教授会」(2022年8月8日)
→「つれづれに:遠い夜明け」(2022年8月7日)
→「つれづれに:こむらど委員会」(2022年8月6日)
→「つれづれに:MLAのあと」(2022年8月5日)
→「つれづれに:MLA」(2022年8月4日)
→「つれづれに:サンフランシスコ2」(2022年8月3日)
→「つれづれに:ハワイ」(2022年8月2日)
→「つれづれに:エイブラハムさん2」(2022年8月1日)
2022年7月
→「つれづれに:エイブラハムさん1」(2022年7月31日)
→「つれづれに:UCLA」(2022年7月30日)
→「つれづれに:ゴンドワナ」(2022年7月29日)
→「つれづれに:ラ・グーマ」(2022年7月28日)
→「つれづれに:ミシシッピ」(2022年7月27日)
→「つれづれに:嘱託講師」(2022年7月26日)
→「つれづれに:二つ目の大学」(2022年7月25日)
→「つれづれに:女子短大」(2022年7月24日)
→「つれづれに:黒人研究の会総会」(2022年7月23日)
→「つれづれに:ライトシンポジウム」(2022年7月22日)
→「つれづれに:アメリカ文学会」(2022年7月21日)
→「つれづれに:横浜」(2022年7月20日)
→「つれづれに:横浜」(2022年7月20日)
→「つれづれに:二つの学院大学」(2022年7月19日)
→「つれづれに:紀要」(2022年7月18日)
→「つれづれに:『アーカンソー物語』」(2022年7月17日)
→「つれづれに:『ウィアーザワールド』」 (2022年7月16日)
→「つれづれに:『アフリカシリーズ』」(2022年7月15日)
→「つれづれに:本田さん」(2022年7月14日)
→「つれづれに:『ルーツ』」(2022年7月13日)
→「つれづれに:LL教室」(2022年7月12日)
→「つれづれに:大阪工大非常勤」(2022年7月11日)
→「つれづれに:大学院入試3」(2022年7月10日)
→「つれづれに:修了と退職」(2022年7月9日)
→「つれづれに:修論あれこれ」(2022年7月8日)
→「つれづれに:ゼミ」(2022年7月7日)
→「つれづれに:余震」(2022年7月6日)
→「つれづれに:揺れ」(2022年7月5日)
→「つれづれに:手入れ」(2022年7月4日)
→「つれづれに:体の悲鳴」(2022年7月3日)
→「つれづれに:魚の棚」(2022年7月2日)
→「つれづれに:明石城」(2022年7月1日)
2022年6月
→「つれづれに:言語表現学会」(2022年6月30日)
→「つれづれに:黒人研究の会」(2022年6月29日)
→「つれづれに:あのう……」(2022年6月28日)
→「つれづれに:米麹」(2022年6月27日)
→「つれづれに:珈琲」(2022年6月26日)
→「つれづれに:ラ・ガーディアで」(2022年6月25日)
→「つれづれに:ハーレム」(2022年6月24日)
→「つれづれに:ハーレム分館」(2022年6月23日)
→「つれづれに:古本屋」(2022年6月22日)
→「つれづれに:ニューヨーク」(2022年6月21日)
→「つれづれに:シカゴ」(2022年6月20日)
→「つれづれに:サンフランシスコ」(2022年6月19日)
→「つれづれに:修士論文」(2022年6月18日)
→「つれづれに:中朝霧丘」(2022年6月17日)
→「つれづれに:明石」(2022年6月16日)
→「つれづれに:キャンパスライフ2」(2022年6月15日)
→「つれづれに:ゼミ選択」(2022年6月14日)
→「つれづれに:大学院大学」(2022年6月13日)
→「つれづれに:院生初日」(2022年6月12日)
→「つれづれに:分かれ目」(2022年6月11日)
→「つれづれに:大学院入試2」(2022年6月10日)
→「つれづれに:雪合戦」(2022年6月9日)
→「つれづれに:辞書を引け」(2022年6月8日)
→「つれづれに:英語版方丈記」(2022年6月6日)
→「つれづれに:受験英語」(2022年6月5日)
→「つれづれに:反体制ーグギさんの場合3」(2022年6月4日)
→「つれづれに:反体制ーグギさんの場合2」(2022年6月3日)
→「つれづれに:反体制ーグギさんの場合1」(2022年6月2日)
→「つれづれに:修学旅行」(2022年6月1日)
2022年5月
→「つれづれに:ホームルーム2」(2022年5月31日)
→「つれづれに:顧問」(2022年5月30日)
→「つれづれに:金芝河さん5」(2022年5月29日)
→「つれづれに:金芝河さん4」(2022年5月28日)
→「つれづれに:金芝河さん3」(2022年5月27日)
→「つれづれに:金芝河さん2」(2022年5月26日)
→「つれづれに:金芝河さん1」(2022年5月25日)
→「つれづれに:ホームルーム」(2022年5月24日)
→「つれづれに:学年の方針」(2022年5月23日)
→「つれづれに:担任」(2022年5月22日)
→「つれづれに:教室で」(2022年5月21日)
→「つれづれに:会議」(2022年5月20日)
→「つれづれに:懇親会」(2022年5月19日)
→「つれづれに:新採用一年目」(2022年5月18日)
→「つれづれに:新任研修」(2022年5月17日)
→「つれづれに:県大会」(2022年5月16日)
→「つれづれに:初めての授業」(2022年5月15日)
→「つれづれに:3ケ月早めに」(2022年5月14日)
→「つれづれに:街でばったり」(2022年5月13日)
→「つれづれに:生野峠」(2022年5月12日)
→「つれづれに:阿蘇に自転車で」(2022年5月11日)
→「つれづれに:大学院入試」(2022年5月10日)
→「つれづれに:面接」(2022年5月9日)
→「つれづれに:採用試験」(2022年5月8日)
→「つれづれに:英作文2」(2022年5月7日)
→「つれづれに:山陰」(2022年5月6日)
→「つれづれに:購読」(2022年5月5日)
→「つれづれに:教育実習」(2022年5月4日)
→「つれづれに:教員免許」(2022年5月3日)
→「つれづれに:教員採用試験」(2022年5月2日)
2022年4月
→「つれづれに:百万円」(2022年4月30日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路ー春2」(2022年4月29日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路ー春1」(2022年4月28日)
→「つれづれに:栄山寺八角堂」(2022年4月27日)
→「つれづれに:関門海峡」(2022年4月26日)
→「つれづれに:臼杵」(2022年4月25日)
→「つれづれに:薊」(2022年4月24日)
→「つれづれに:伎藝天」(2022年4月23日)
→「つれづれに:家庭教師4」(2022年4月22日)
→「つれづれに:家庭教師3」(2022年4月21日)
→「つれづれに:花菖蒲」(2022年4月20日)
→「つれづれに:髭と下駄」(2022年4月19日)
→「つれづれに:古本屋」(2022年4月18日)
→「つれづれに:家庭教師2」(2022年4月17日)
→「つれづれに:イリス」(2022年4月16日)
→「つれづれに:コーチ」(2022年4月15日)
→「つれづれに:藤とポピー」(2022年4月13日)
→「つれづれに:家庭教師1」(2022年4月10日)
→「つれづれに:一般教養」(2022年4月8日)
→「つれづれに:英会話」(2022年4月7日)
→「つれづれに:紫木蓮」(2022年4月6日)
→「つれづれに:ロシア語」(2022年4月5日)
→「つれづれに:第2外国語」(2022年4月4日)
→「つれづれに:英作文」(2022年4月2日)
→「つれづれに:引っ越しのあと」(2022年4月1日)
2022年3月
→「つれづれに:植木市と牡丹」(2022年3月31日)
→「つれづれに:牛乳配達」(2022年3月30日)
→「つれづれに:運動クラブ」(2022年3月29日)
→「つれづれに:夜間課程」(2022年3月28日)
→「つれづれに:大学入学」(2022年3月27日)
→「つれづれに:諦めの形」(2022年3月26日)
→「つれづれに:畑の春模様」(2022年3月19日)
→「つれづれに:作州」(2022年3月14日)
→「つれづれに:白木蓮」(2022年3月12日)
→「つれづれに:丸坊主」(2022年3月5日)
→「つれづれに:世界で一つのカレンダー」(2022年3月4日)
→「つれづれに:藪椿」(2022年3月2日)
→「つれづれに:木花俯瞰図」(2022年3月1日)
2022年2月
→「つれづれに:田植え準備」(2022年2月18日)
→「つれづれに:大学6:無意識の『常識』6」(2022年2月17日)
→「つれづれに:大学5:無意識の『常識』5」(2022年2月8日)
→「つれづれに:歩くコース追伸1」(2022年2月6日)
→「つれづれに: 大学4:無意識の『常識』4」(2022年2月5日)
→「つれづれに:大学3:無意識の「常識」3」(2月1日)
2022年1月
→「つれづれに:大学2:無意識の「常識」2」(1月28日)
→「つれづれに:大学1:無意識の「常識」1」(1月25日)
→「つれづれに:高等学校3」(1月21日)
→「つれづれに:高等学校2」(1月19日)
→「つれづれに:高等学校1」(1月17日)
→「つれづれに:諦観」(1月15日)
→「2021年11月Zoomシンポジウム最終報告」(1月13日)
→「つれづれに:歩くコース4木崎浜5」(1月11日)
→「つれづれに:歩くコース4木崎浜4」(1月9日)
→「つれづれに:歩くコース4木崎浜3」(1月7日)
→「つれづれに:歩くコース4木崎浜2」(1月5日)
→「アフリカ史再考④:大陸に生きる(1)牧畜生活:ケニアのポコト人」(1月3日)
→「シンポジウム「アフリカとエイズ」6『ナイスピープル』と『最後の疫病』」(1月1日)
2021年12月
→「2021年11月シンポジウム最終報告:概要」(2021年12月30日)
→「2021年11月シンポジウム最終報告:案内」(2021年12月30日)
→「2021年11月シンポジウム最終報告:HIV/AIDSから社会問題を炙り出す」(2021年12月30日)
→「2021年11月シンポジウム最終報告:はじめに」(2021年12月30日)
→「シンポジウム『アフリカとエイズ』5:アフリカとエイズ」(2021年12月30日)
→「シンポジウム「アフリカとエイズ」4:ケニアの歴史4」(2021年12月28日)
→「つれづれに:歩くコース4木崎浜1」(2021年12月26日)
→「シンポジウム『アフリカとエイズ』3:ケニアの歴史3」(2021年12月24日)
→「つれづれに:歩くコース3」(2021年12月22日)2021年
→「つれづれに:シンポジウム『アフリカとエイズ』2」(2021年12月20日)
→「アフリカ史再考③:ナイルの谷」(2021年12月18日)
→「アフリカ史再考:②『アフリカシリーズ』」(2021年12月16日)
→「アフリカ史再考:①アフリカ史再考のすすめ」(2021年12月14日)
→「つれづれに:シンポジウム『アフリカとエイズ』1」(2021年12月12日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路補足③」(2021年12月9日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路補足②」(2021年12月2日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路補足①」(2021年12月1日)
2021年11月
→「つれづれに:戦後?①」(2021年11月24日)
→「つれづれに:アメリカ?」(2021年11月18日)
→「堀切峠下海岸道路?」(2021年11月15日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路④」(2021年11月7日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路③」(2021年11月6日)
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路②」(2021年11月1日)
2021年10月
→「つれづれに:堀切峠下海岸道路①」(2021年10月31日)
→「つれづれに:山頭火の世界⑤ー防府③」(2021年10月日)
→「つれづれに:山頭火の世界④ー防府②」(2021年10月28日)
→「つれづれに:西条柿6個」(2021年10月23日)
→「つれづれに: 葛」(2021年10月18日)
→「つれづれに:烏瓜2」(2021年10月8日)
→「つれづれに: 通草7」(2021年10月3日)
→「つれづれに:通草6」(2021年10月2日)
→「つれづれに: 通草5」(2021年10月1日)
2021年9月
→「つれづれに: 通草4」(2021年9月30日)
→「つれづれに: 通草3」(2021年9月28日)
→「つれづれに:通草2」(2021年9月27日)
→「つれづれに:通草1」(2021年9月26日)
→「つれづれに: 烏瓜」(2021年9月23日)
→「つれづれに: 歴史をどう見るか」(2021年9月11日)
→「つれづれに:歩くコース2の⑤」(2021年9月10日)
→「つれづれに:歩くコース2の④」(2021年9月9日)
→「つれづれに:大根の芽も」(2021年9月6日)
2021年8月
→「つれづれに:歩くコース2の③」(2021年8月22日)
→「つれづれに: 歩くコース2の②」(2021年8月15日)
→「つれづれに:超早場米」(2021年8月12日)
→「つれづれに:台風一過<②/a>(2021年8月11日)
→「つれづれに:台風一過」(2021年8月10日)
→「つれづれに:台風9号」(2021年8月8日)
2021年7月
→「つれづれに: 歩くコース2の①」(2021年7月30日)
→「つれづれに:山頭火の世界③ー防府①」(2021年7月29日)
→「つれづれに: 南瓜の花が・・・」(2021年7月28日)
→「つれづれに:歩くコース1の⑨」(2021年7月27日)
→「つれづれに:山頭火の世界②ー山頭火の生涯①(2021年7月25日)」(2021年7月25日)
→「歩くコース1の⑧・・・」(2021年7月24日)
→「つれづれに: 山頭火の世界①:なんで山頭火?(2021年7月22日)」(2021年7月22日)
→「つれづれに: 歩くコース1の⑦・・・」(2021年7月21日)
→「つれづれに: 歩くコース1の⑥・・・」(2021年7月20日)
→「つれづれに: 歩くコース1の⑤・・・」(2021年7月18日)
→「つれづれに:南瓜が・・・」(2021年7月14日)
→「つれづれに: 歩くコース1の④・・・」(2021年7月11日)
→「つれづれに: 歩くコース1の③・・・」(2021年7月9日)
→「つれづれに: 歩くコース1の②・・・」(2021年7月7日)
→「つれづれに: 歩くコース1の①・・・」(2021年7月5日)
→「つれづれに: 血液とリンパの流れが・・・」(2021年7月4日)
2021年6月
→「つれづれに: 歩くコースは・・・」(2021年6月30日)
→「つれづれに: 歩き始めたのは・・・」(2021年6月26日)
→「つれづれに: 竹取の翁、苦戦中・・・」(2021年6月23日)
→「つれづれに:南瓜に勢いが」(2021年6月6日)
2021年5月
→「少し停滞気味です」(2021年5月25日)
2021年4月
→「一年が経ちました:近況報告です」(2021/4/17)
2020年
→「授業が始まって大丈夫かなあ」(2020/4/7)
→「つれづれに ひよとめじろが来ています」(2020年2月10日)
2019年
→「2019年の後期が始まりました。」(2019年10月8日)
「連休も終わり、授業再開です。」(2019/5/8)
→「授業も一巡、本格的に。」(2019/4/15)
→「2019年、4月です。」(2019年4月11日)
→「もう2019年の3月です」(2019年3月13日)
2018年
→「雨の一日でした。」(2018年3月5日)