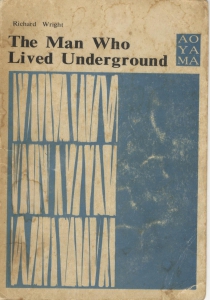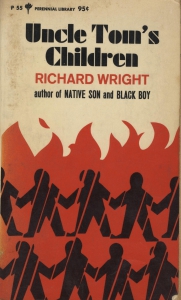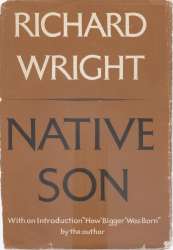つれづれに:修論あれこれ(2022年7月8日)
HP→「ノアと三太」にも載せてあります。
つれづれに:修論あれこれ

修士論文の提出がぎりぎりになってしまった。入学してすぐにテーマと読む作品も決め、夏にはアメリカに資料探しに行ってめぼしい資料は手に入れ(→「ニューヨーク」、→「古本屋」、→「ハーレム分館」、→「ハーレム」、6月21~24日)、戻ってからはずっと書き続けていた。しかし、提出日前日は徹夜になり、当日大学には、事故を心配してタクシーで2時間ほどかけて行くことになってしまった。1982年の1月31日の夕方のことで、仕上がった修士論文は “Richard Wright and His World” である。
青山書店大学用教科書
修士論文では、中編「地下に潜む男」(↑、"The Man Who Lived Underground," 1944)を軸に、中編以前の3作品とそれ以降の3作品を分析して、ライトがアメリカ社会に蔓延(はびこ)る白人の人種主義に対する抗議一辺倒から、より普遍的なテーマを求めて推移していったことを論証した。(→「リチャード・ライトの世界」、2019年5月20日)
一次資料の7編に加えて、二次資料の伝記や新聞や雑誌の書評やアメリカ人の書いた博士論文なども含めて、読む量が半端ではなかった。7編はじっくりメモも取りながら何回も読んだが、それぞれ大変だった。短編集『アンクル・トムの子供たち』(↑、Uncle Tom’s Children, 1940)の子供や死後出版『ひでえ日だ』(Lawd Today, 1963年)の青年の会話の「黒人英語」に手こずってしまった。『アメリカの息子』(↓、Native Son, 1940)は大冊でもわくわくしながら一気に読めたが、同じくらいの大作『アウトサイダー』(The Outsider, 1953)と『長い夢』(The Long Dream, 1958)は、少々観念的過ぎて、読むのにも難儀した。
伝記はライトの作品よりも更に分厚く読むだけでも大変だったが、ファーブル(Michel Fabre)さんの『リチャード・ライトの未完の探求』(The Unfinished Quest of Richard Wright, 1973)には、気持ちの上でも実際的にも一番お世話になった。その時点で、将来直接お会いする機会があるとは夢にも思っていなかったが。(→「リチャード・ライト死後25周年シンポジウム」、2019年3月13日)しかし、この修士論文を納得いく形で書けたのは、ファーブルさん(↓)のお陰である。

ワープロもパソコンもない時代である。神戸の高架下で手動のタイプライター(↓)をたぶん一万五千円で買って、ゼミの発表の時に使った記憶がある。初めはそのタイプライターと白の修正液を使っていたが、途中からはちょうど出始めた電動タイプライターを買って修士論文を仕上げた。白の修正テープも役に立った。

買った当初はキーを見ないで打ついわゆるブラインドタッチもやってはみたが、いまだに出来ないままである。締め切り間際にはずっと座ってキーを叩いていたが、それでもぎりぎりだった。二人目の子供が生まれたのが十月の金木犀の香る時期で、母親代わりをさせてもらったおかげで、二時間おきにミルクを飲ませながら、タイプを打つことになった。もちろん子供が覚えているわけもないが、電動タイプライター(↓)のぎこちないリズムが子守歌になっていたかも知れない。
次は、修了と退職、か。大学院の修了と高校の退職が重なった頃の話である。