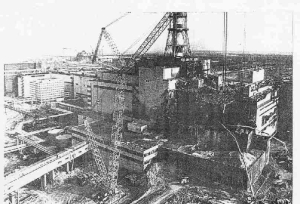つれづれに:探検家

中国でも韓国でも日本でも、アフリカの国々でも、人が集まり富が蓄積されるようになると諍(いさか)いを繰り返して来た。そして、殺し合いをする。中国で敗者を見せしめにするために刑罰として与えた骨殺ぎの刑は、極めて残酷である。斬首(ざんしゅ)刑はたくさんの人が見ている前で、首切り人が大きな刀で首を落とす。今の日本で、眼の前で人が殺される光景を見ることはそう多くない。しかし、この500年余りのアングロサクソン系の侵略では、ヨーロッパ人はアフリカ人から土地を奪い課税して絞り取り続けた。たくさんの人が魂を蹂躙(じゅうりん)され、辱(はずかし)めを受けた。そして、殺された。飢餓(きが、↓)に貧困は日常である。民族紛争、地域紛争では武器製造を基幹産業にする国々から武器を送られ、同胞が資源を巡って殺し合いをする。子ども兵が育てられて、殺し合いに参加する。昔の諍(いさか)いの時代が霞(かす)んでしまうほど、過酷な時代になってしまった。開発や援助と言いながら、多国籍企業貿易と資本投資で制度的に搾取し続ける資本主義社会では、先進国と手を結ぶ少数のエリートが搾り取る側に回る。遣(や)る瀬無い思いが募(つの)る。

1980年代前半のエチオピア飢餓キャンペーンで使われた写真
奴隷貿易で荒稼ぎした莫大な資本が蓄積されて産業革命が可能になり、それまでの社会が根底から覆(くつがえ)されてしまった。生産と消費の規模が格段に増加して、社会自体が拡大し、肥大する一方である。資本主義は、拡大しないと生き残れないシステムなので、このまま突っ走るしかない。制御不能の原子力爆弾で凄惨(せいさん)な光景をみても、原子力発電所(↓)の破壊威力を目(ま)の当たりにしても、核兵器も原子力発電所も諦めきれない。それどころか、危険極まりない老朽化した原子力発電所を法律を変えてでも再稼働し、発展途上国に原子力発電所を輸出しようとしている。核開発も軍需産業でも、関わって働く人たちを養う巨大産業にもなっている。核も、元々は拡大し続ける資本主義社会を維持するために開発された武器である。侵略者は狡猾(こうかつ)で、ありとあらゆる手段を利用して、その侵略を正当化するのに努力も惜しまなかった。侵略した相手に自分たちの言葉をしゃべらせ、自分たちの侵略がより容易(たやす)くするために利用して来た。今や英語は国際語である。白人優位・黒人蔑視の意識は、世界のすみずみにまで浸透している。前回のグレート・ジンバブエも、白人優位・黒人蔑視を具体化したものの一つに過ぎない。探検家もその一つだろう。

九電原発
「アフリカシリーズ」の冒頭で、バズル・デヴィドスン(Basil Davidson, 1914–2010)はヨーロッパ人に発見された当初に偏見の対象になったジンバブエの遺跡の他に、探検家の例をあげている。デヴィドスンは先ず奴隷貿易について前置きする。
「アフリカ最大の不幸は16世紀初めに始まります。ヨーロッパ人が次々と入ってくるようになったのです。目当ては奴隷でした。西アフリカの海岸にはヨーロッパ7か国が50近くも城砦を築き、そこを奴隷貿易の拠点としました。奴隷貿易はヨーロッパ人のアメリカ大陸進出と深い関係があります。新大陸発見後、彼らはそこに根を下ろし、鉱山や大農園をどんどんと開発しましたが、労働力が足りませんでした。そこで目をつけたのがアフリカ大陸だったのです。何とも恐ろしい話です。何千万という黒人が女子供まで有無を言わせず、力ずくで連れ去られたのです。しかも、です。問題は膨大な人間が奪われただけではないんです。400年にも渡って、アフリカ大陸を支えて来た農民や職人など、大事な働き手が、毎年何万、何十万という単位で売り飛ばされていったのです。それがどれほどアフリカを荒廃させたか、計り知れません。奴隷貿易は19世紀半ばまで続きます。少なく見積もっても1500万の人間が新大陸に運ばれました。途中で死んだ数は、その3倍とも5倍とも言います。奴隷船の船長はできるだけ多く運ぼうとしました。身動きできないほどびっしり詰め込んだ者もいます。アフリカの王や首長の中には、奴隷貿易が自分たちの社会を破壊すると抗議をしたものもいます。しかし、その抗議は利益に目の眩(くら)んだヨーロッパ列強に圧(お)し潰(つぶ)されました。奴隷として大量に売買されるにつれ、黒人は人間以下と見做(な)されていきます。人種差別の根源です。ここガーナのケープ・コーストの城砦(↓)には礼拝堂が建っています。その下は嘗(かつ)て奴隷倉庫でした。1度に1500人もの奴隷が送り込まれ、船積みを待っていたのです。奴隷貿易の最盛期には聖職者もこれに反対はしませんでした」

そして、この時期から来るようになった新しい人たち、宣教師と探検家について話し始める。

「ヨーロッパで奴隷貿易反対の声が強くなったのは18世紀末からです。この頃になると、アフリカには全く新しい人々がやって来るようになります。マンゴ・パーク、リチャード・バートンといった探検家です。かれらは未踏の奥地をめざしました。19世紀はまさにアフリカ探検の世紀となります。しかし、ヘンリー・スタンリーのようにアフリカ侵略をめざしあ人は別として、まさか自分たちが切り拓いた道が、間もなく別の目的で使われ、50年もしないうちにアフリカ大陸を変えてしまうとは夢にも思わなかったでしょう。

まあ、何とも残念な話ですが、こうした探検家はほんの僅(わず)かの例外を除いて、みんな黄金だの、象牙だの、地理上の謎を解き明かすことしか頭にありませんでした。アフリカ人の生活や文化には関心を持たなかったのです。ただ、デビッド・リビングストン(David Livingston, 1813-1873)などは例外と言えるかも知れません。リビングストンは伝導者からアフリカ人の生活や環境に関心を寄せる探検家に変わっていきました。

1852年、伝導ルートを求めて奥地に入り、ザンベジ川を発見すると、そこから大西洋に到達、次いでザンベジ川を下り、インド洋まで出ようとします。1855年、旅の途中で、彼は世界有数の滝を発見、当時のイギリス女王の名を取ってビクトリアの滝と名付けます。滝の下流では、激しい流れや鰐(わに)や河馬(かば)など、アフリカならではの障害にぶつかり、舟を岸に上げて川を迂回(うかい)しています。

現在、ビクトリアの滝の脇には滝を見下ろすようにしてリビングストンの銅像が建っています。「デビッド・リビングストン博士、1855年、この滝を発見」しかし、です。この滝は元々現地の言葉で「音を立てる煙」と呼ばれていました。リビングストンも土地の人に教えられて、ここまで見物に来たようです。現に、リビングストンは心の広い人でしたから、自分を案内してくれたこの親切なアフリカ人のことをちゃんと日記に書いています。でも、あの銅像を建てた人には、現地の黒人がリビングストンを案内したなど、無視して当然でした。それが白人の一般の考えだったのです。

ビクトリアの滝発見の報せは、彼が属していたロンドンの伝導教会にも届きます。しかし教会の人は、それを苦々しい思いで聞いたようです。彼らにはその発見は、伝導の務めを怠っているとしか見えませんでした。大事なのはアフリカ人をキリスト教徒にすることだったのです。リビングストンはこういう心の狭さに嫌気がさし、伝導教会を辞めます。自分の使命は未開の土地を切り拓くことにある、そうすれば文明の2つの先駆者、キリスト教と商業があとに続く。そう考えたのです。その通りでした。間もなく、色んな国から大ぜいの人々が次々とやって来るようになりました。異教の地に神の福音を伝えるためでした」

産業社会になったヨーロッパ社会は更なる生産のための安い原材料と製品を売り捌くための市場を求めてアフリカやアジアの植民地化を始めた。侵略の前の下見をしたのが探検家と宣教師である。ヨーロッパの金持ちたちは冒険心にはやる探検家を雇ってアフリカを探らせた。宣教師も金持ち層に協力した。デヴィドスンがあげるヨーロッパの探検家を批判するのは、本人の意識とは別に、結果的にヨーロッパ諸国の金持ちが目論(もくろ)む商業主義・資本主義をに加担して、多くの人が大変な目に遭(あ)ったからである。ただ、本人が自覚しているかどうかにかかわらず、結果が問題だ。その行為がもたらす結果がたくさんの人に被害を与えるなら別問題である。

伝導教会の伝導所
探検も冒険も本人の自由で、何の問題もない。結婚してからずっと後に、妻から大学のとき友だちと穴もぐりしてたよ、狭所恐怖症なのによう行くよね、服もびしょぬれで、中が崩れて死にそうになるし、若いからもったんやろね、と聞かされたことがある。大学で入っていた洞窟探検同好会とは別行動で友人の出身地の高知の地図にない洞窟に2人で行ったときの話らしい。スポンサーもないし、人に迷惑もかけていなし、問題なしだろう。しかし、スポンサーがついたらどうか?探検家として教科書にも載(の)っている間宮林蔵(↓、1775-1844)は江戸幕府の役人だった。今でいう国家公務員だから、国がスポンサー?という気もするが、職務を果たし、作った地図が後世の役に立ったから教科書にも載り、探検家と言われるんだろう。蝦夷(えぞ)地・樺太探検に役に立ったということだろう。しかし、厳密に言えば、江戸幕府の薩摩藩が琉球王国を滅ぼしたのは、明らかに領土拡大を狙(ねら)った侵略行為である。蝦夷地開発も同じだ。元々、ツングースの侵略で追われた縄文人の末裔(まつえい)が逃げのびた地が沖縄と北海道である。1万年以上、日本列島に平和に暮らしていた縄文人の末裔(まつえい)である。

そういう意味で言えば、蝦夷地も琉球王国も元の持主アイヌの人や琉球の人に返還すべきである。1980年代に黒人研究の会で、間宮林蔵のお孫さんと知り合いになった。アメリカに行った時には泊めてもらい、奥さんや奥さんの妹さんやお母さんに大変世話になった。マミヤさんは→「ニューヨーク」市(↓)から北に電車で1時間ほどの閑静な街の小さな大学の教授で、日本語は話せなかった。身近なところに教科書に載る人物のお孫さんがいたんや、と感心した。

国がスポンサーの話では、私にも関わりがある。私の専任が決まったのは、原子力村の1員だった人の推薦があったからである。見ず知らずの私を取るために教授会で奮闘したと聞く。国にすり寄る研究者が研究費が欲しくて原子力村に群がっていた。原子力の安全神話を強化するためだった。しかし、チェルノブイリ(↓)の歴史に学ばず、フクシマが現実の問題となった。御用学者は、それでも安全だと言い張って再稼働に協力している。歴史から学ぶという概念が欠落しているのだろう。痛し痒(かゆ)しである。
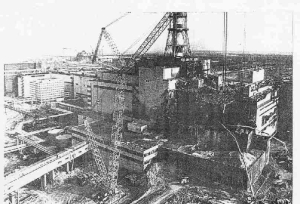
最近では、兵器製造に関わる基礎研究での助成金は大学の人には身近な問題である。国立大では、特に地方大学(↓)では運営交付金が毎年減らされ続けて研究費不足は常態化している。それに付け込んで、国が理系の研究者に向けて助成金募集をかけたのである。大学では教育、研究、社会貢献が問われる。最近は外部の批判を気にして評価も厳しくなり、研究者には甘い誘いである。工学部にも知り合いがいるので、人ごとでもない。組合員の同僚も、募集に強く反対していたし、学内の掲示板に貼られた研究資金募集の広告も見た。観方次第だが、結構身近に問題はころがっている、そんな感じがしている。
次回は、宣教師である。








 先週の曇り空の白浜
先週の曇り空の白浜