つれづれに:デヴィドスン(2024年5月18日)
つれづれに:デヴィドスン

やはり、デヴィドスンである。欧米相手におまえら、恥を知れと啖呵(たんか)を切ったのはニエレレだが、言い分は至極まっとうである。それ以上に正論を展開してみせたのがデヴィドスンで、やけに楽観的で、前向きである。「ザイールの艱難(かんなん)、アフリカ的解決に誘(いざな)う」のタイトルをつけている。賄賂(わいろ)が横行し、経済は破綻(はたん)、政府軍と反政府軍の戦闘が常態化し、道路はがたがた、欧米の禿鷹(はげたか)すら投資を諦め、不幸をもたらした張本人アメリカが声高に米国式民主主義を叫ぶなかで、その混乱した状態が今日のアフリカ問題の解決に繋(つな)がる糸口になると説いている。
デビッドソンはベルギーの植民地勢力がコンゴの人たちを追い出し、豊かな富だけでなく、自尊心を奪い、自己責任なども侵害したことを重要視している。つまり、意思決定の力がヨーロッパ人の手に渡ってしまったことが大惨事をもたらす最大の原因だと捉(とら)えたわけである。1960年の独立は、この意思決定の力を取り戻すいい機会だったが、政府の支配構造が外国の利益を優先するアフリカ人職員の手に渡っただけ、つまり、独立はまやかしだったというわけである。過去10年か10数年の間、アフリカの広い地域で、このまやかしの独立に対する本当の反対運動が沸き起こっているが、中央政府と官僚から権力移行して地方自治をめざすこの運動こそが本当の民主主義を求める運動だと力説し、ザイールの事例がよい見本だと結論づけている。
「カビラはアフリカ人の自尊心にとってという点ではよい知らせで、本当に とてもいい知らせです。奇抜な観方かも知れませんが、その観方は二つの強い見込みに基づいています。一つは、外部の主要な勢力ももはや、また別の騒乱と荒廃を経たのちにこの地域で得られるものがもはや何もないということです。冷戦の残酷な狂乱は過ぎ去り、すべての処置も終わりました。もう一つの見込みは、ザイールと呼ばれるこの国はもはや安全な搾取源として存在していないということです。つまり、ザイールの多くの人々は、ついに自分たちの利益を自分自身で管理することが出来るかもしれないという可能性が見えてきたのです。一世紀前、それよりも数十年前にこの地で始まった無益な歳月は、終わりに近づいているのかもしれないのです」
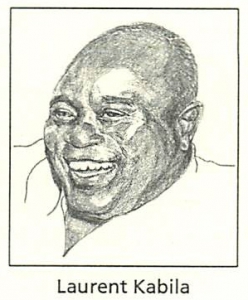
デビッドソンの見解は楽天的である。地方重視の、効率的な民主主義に向けた運動が、すでにエリトリアで見られるように印象的な結果を示し始めているとも言っている。独立過程を散々邪魔しておいて、独立後の混乱に乗じて「アフリカ人には自治の能力がない」と恥ずかしげもなくほざいた欧米の輩(やから)には、「カビラの政府がザイールで仕事が出来るかどうかの証拠をもっと見つけるのは可能です」と前置きして、文章を終えている。
「実際上、ザイールの問題は見かけより厄介でないとわかるかも知れません。そうであるとしたら、それはモブツ独裁制のひどい堕落と全くの不適格さ故に、長い間見捨てられた人々が出来る限り自分たちのことは自分たちでやれる体制が許されてきたからでしょう。結局、もし、カビラが逃げ延びていた間じゅう、地方の人々が自分たちのことを自分たちでやっていなければ、一体誰が、広大なキブ州の切り盛りをやってきたと言うのでしょうか」
そして、ベルリンの壁の崩壊や欧米の都合でマンデラが逮捕時と同じ法律で無条件に釈放されたとは言え、アフリカ人の大統領が誕生した南アフリカとの連携の夢まで披露している。
「カビラが成功すれば、より大きな社会変化とより広範囲の経済協力に希望を見いだせるかもしれません。というのも、九つの国と境を接するザイールは、モブツ支配の下で巨大な経済的の空洞をつくり出していたからです。コンゴが機能的に働けば、サハラ以南のアフリカの大部分のビジネスのための中心となるインフランストラクチュア(基幹施設)が供給される可能性があります。また、国を横断する鉄道と道路が出来れば、キンシャサとケープタウン、マプートとルアンダ、ナイロビとブラザヴィルといった東西、南北の経済の中心地間を結ぶ決定的な交易網になり得ます。もし、ダイヤモンドから銅まであるコンゴの鉱物資源を再びうまく採掘できれば、国が豊かになる可能性もあります。ニエレレが指摘するように『もしカビラの下で、カビラの言うコンゴ民主共和国での理想が、地理的な面だけでなく、あらゆる面で統合が可能であり、潜在的な富を現実の富に変えることが出来るのであれば、タボ・ムベキ(南アフリカ大統領代行、↓)が『アフリカ・ルネッサンス』を提唱する南アフリカとともに、新生コンゴは指導的役割を果たす国になり得ると思います』」

デヴィドスンに触れると、マルコム・リトゥルが常々言っていた「金髪で青い目をしたのがみな悪魔だと思っているのか?」という言葉をいつも思い出す。イギリス英語なので、私には少し読みづらい面もあるが、いつも心に響いて来る。やっぱり、デヴィドスンである。大好きなソルボンヌのファーブルさんがニューヨークの古本屋からデヴィドスンの古本を送ってくれたことがあるが、パリに来たら紹介するよというメッセージだった気がする。ハラレに行って以来、パリの学会で発表するよりも、もっと身近なところですることがあるやろと自分に言い聞かせ、日々を見つめることを優先したが、もう一度同じような局面があっても、同じ選択をする気がする。

ソルボンヌ前で、1992