シンポジウム「アフリカとエイズ」3:ケニアの歴史3(2021年12月24日)
2021年Zoomシンポジウム3
「アングロ・サクソン侵略の系譜―アフリカとエイズ」(11月27日土曜日)
「ケニアの小説から垣間見えるアフリカとエイズ」3:
ケニアの歴史(3)イギリス人の到来と独立・ケニヤッタ時代
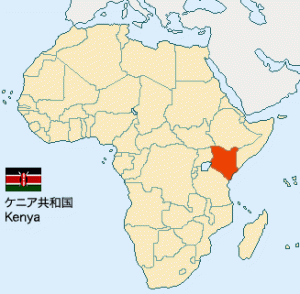
今回はケニアの歴史の3回目、ポルトガル人の後に来たイギリス人がケニア社会を根底から変えてしまったという話である。
ポルトガルはアフリカの東海岸で略奪をして、一部を破壊はしたが、社会の基本構造を変えるほどの影響を与えたわけではなかった。しかし、後から来たイギリスは、ケニア社会を根本から変えてしまった。結果的に、キルワ虐殺はヨーロッパ侵略の始まりに過ぎなかったのである。
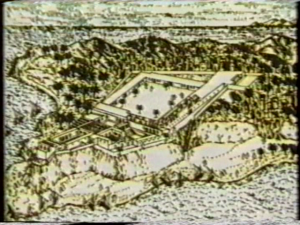
キルワの復元図
アフリカ西海岸で直接金を買い始めたポルトガルは、インドへの海上ルートも発見してベニスの都市国家から東インドとの香辛料貿易の支配権を奪いたいと望んでいた。そのためにも栄えていた東アフリカとの貿易は不可欠で、取引の交渉をしたが計画は頓挫した。商品が粗悪だったためである。ならば力ずくでということになり、武力で東アフリカの貿易を独占しようと決めた。キルワ虐殺はその一環だったのである。
前回、前々回のシンポジウムでポルトガルとスペインの植民地支配について寺尾智史さんが発表で再三指摘していた通り、ポルトガルとスペインは植民地支配に向いてなかったようだが、後から来たイギリスは植民地支配に長けていた。貴族社会が支えた王朝で永年培った、自分は働かずにたくさんの人を働かせて上前をはねる、徹底的に管理して骨の髄までしゃぶり尽くすという特技をいかんなく発揮しているわけである。→「2021年Zoomシンポジウム:第二次世界大戦直後の体制の再構築」(続モンド通信27、2021年2月20日)、→「2018シンポジウム」(blogには2018年の報告を載せていないが、報告書の印刷物は出来ているで、連絡をもらえれば、PDFでの送付も可、である。)

2018シンポジウム案内ポスター
南アフリカケープ州からのイギリス人入植者が最初に狙ったのはホワイトハイランドという現在の首都ナイロビである。赤道に近く、標高約1800メートルの高地にあるが、快適で過ごし易く、代々多数派のギクユ人が平和に暮らしていた。一番いい場所を力づくで奪い、豊かな文化を持つ人たちの制度を利用して、植民地支配を徹底した。他のアフリカ諸国でも同様だが、イギリスは発達した社会制度を持つ国を植民地化している。遅れを取ったフランスが植民地化した国が、サハラ砂漠も含めて土地は広大ながら、社会制度が未発達の地域だったのとは対照的である。従って、地元の制度を利用しても利点がないのでフランスは直接支配、同化政策を取った。イギリスはケニアの一番過ごし易い土地を奪い、高度な文化を持つ人たちの制度を借用して、着実に植民地支配を続けたのである。

ナイロビ市内を望む
ケニア社会の基本構造を変え得たのは、イギリス人の侵略性と狡猾さゆえだが、キリスト教と貴族社会下の制度を持ち込んだもの大きい。それに時期、である。つまり、奴隷貿易で蓄えた資本で産業革命を起こし、資本主義を加速度的に発展させて、農業中心の社会から産業社会に変えていた最盛期だったのである。すでに経済規模もそれ以前とは比べようもないほど拡張していた。産業化に必要だったのは、更なる生産のための安い原材料と安価な労働力である。必然的に植民地争奪戦は熾烈を極め、ヨーロッパに近いアフリカ大陸の植民地化が一気に加速した。すでに南アフリカで安価な労働力を無尽蔵に生み出す南部一帯を巻き込む一大搾取機構を構築していたイギリスがケニアに進出して来たのだから、ケニアでも南アフリカと同様の制度を導入したのは当然である。課税してケニア人を貨幣経済に放り込んで大量の安価な労働力を生み出し、産業社会に必要だった原材料や豊かな生活のための農産物を安く作らせた。紅茶もその一つである。

ケープ植民地相だったセシル・ローズ
宮崎に来る前に住んでいた明石の家に、当時非常勤でいっしょだったイギリス人のジョンとケニア人のムアンギが来たことがあった。居間で紅茶を淹れている時に「これがイギリス流の紅茶の淹れ方」とジョンが言うと、「イギリスの紅茶やなくて、ケニアの紅茶やで」とムアンギがぼそぼそ反論していたのを思い出す。ジョンにとって「イギリスの紅茶」が当たり前だが、ムアンギにはイギリスに作らされて来たものという意識が強く働いているようだった。次回は一党独裁時代の話をするつもりだが、ムアンギは二人目の独裁者モイ大統領の時代に日本に留学し、同郷で亡命中の作家グギさんの世話をして、ケニアに戻れなくなったと聞く。ムアンギといっしょにいる時、植民地時代や専制政治の身近な影を何度か感じたことがあった。侵略された経験のない国にいるので、どうもその意識が欠落しているらしい。

ムアンギといっしょにしたシンポジウム(大阪工大、1988年)
「変革の嵐」(The Wind of Change)が吹き荒れてケニアも独立したが、アフリカ諸国の独立は第二次大戦で殺し合った宗主国の総体的な力が低下したからである。決して、アフリカ諸国の力が上がったわけではない。独立時の宗主国の狡猾な戦略については、前回のシンポジウムでガーナとコンゴを例にあげた。→「アングロ・サクソン侵略の系譜25: 体制再構築時の『先進国』の狡猾な戦略:ガーナとコンゴの場合」(続モンド通信28、2021年3月20日)
ケニアでも独立への胎動は大戦前に始まっている。1942年にギクユ人、エンブ人、メルー人、カンバ人が秘密裏に独立闘争を開始、例によってメディアを巧みに使ってイギリスは闘争をマウマウと蔑み、武力で抑え込みに躍起になったが、闘っていた人たちは闘いの本質を知っていた。デヴィドスンが映像に収めた戦士の一人は「マウマウは独立の力だ。あれなしでは土地も自由も教育も得られなかった。」(「アフリカシリーズ第7回 湧き上がる独立運動」)とインタビューに応じている。

戦士の一人
1953年にジョモ・ケニヤッタが、1956年に指導者デダン・キマジが逮捕されて戦いは激化、1952年10月から1959年12月まで国内は緊急事態下に置かれた。長く険しい闘いを経て1963年に独立、ケニヤッタが初代首相に就任した。

捕らわれたデダン・キマジ
しかし、ケニヤッタは共に闘った人たちを平然と裏切って、欧米諸国や日本と手を結んでしまった。1966年に前副大統領ルオの長老ジャラモギ・オギンガ・オディンガが結成した左翼野党ケニア人民同盟(KPU)を1969年に禁止、事実上のケニヤッタの一党独裁政治が始まった。独立から僅か数年の間にケニヤッタが変節したからだが、変節の背景はケニヤッタが率いたケニア・アフリカ人民族同盟(KANU, Kenya African National Union)の変容にあった。KANUは様々な階級からなる大衆運動で、主導権は、帝国主義と手を携える将来像を描く上流の小市民階級と、国民的資本主義を夢見る中流の小市民階級と、ある種の社会主義をめざす下流の小市民階級との三派にあったが、1964年にケニア・アフリカ人民主同盟(KADU, Kenya African Democratic Union)がKANUに加わったことで、上流の小市民階級の力が圧倒的に増した。外国資本を後ろ盾に、数の力で、ケニヤッタは誰憚ることなく、自分たちの想い描いた将来像を実行に移し始めた。外国資本の番犬となったケニア政府は、植民地時代の国家機構をそのまま受け継ぎ、政治、経済、文化や言語を支配したというわけである。選挙・投票という「民主主義」と数の力を最大限に駆使しての完全勝利だった。

ジョモ・ケニヤッタ
そして、1978年にケニヤッタが死んだあとも、副大統領のダニエル・アラップ・モイが大統領になり、一党独裁政治は維持・強化されていった。
次回は、モイ時代・キバキ時代 ・現連立政権時代である。