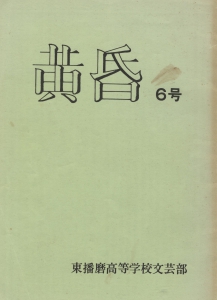露とくとく
概要
教員3年目、兵庫県立東播磨高等学校文芸部の部員から頼まれて書いたものです。高校の教員になって3年目、担任をした文芸部の加納文代さんから頼まれて、同僚の2人とともにこの原稿を書きました。
馴染めず反発しか覚えなかった高校時代を再現するような新設高校に、今度は教員として行くことになりました。受験勉強も出来ずに外国学部の夜間課程に通った僕が、受験のためにと英語の成績で分けられたクラスの担任をするという、皮肉な事態となりました。
家庭にも、学校にも、地域社会にもすっかり希望を失なっていた僕は、生きても30くらいまでだろうと感じて、生き(死に)急いでいました。出口も見えず、生きる命題も見つからないまま、遮二無二自分を追い込みながら突っ走った日々だったように思いますが、もう一度その時点に戻ったら、きっと同じことをしただろうと思います。
教員になる前の写真は全部燃やしてありませんが、載せた写真は、竣工直前、非常勤講師とし女子バスケット部の人たちといっしょに淡路島の県大会に行った時に撮ったものです。3年目の写真はありません。
本文
露とくとく 誠に浮世 すすがばや
去年の春も、もう終わり頃だったか、吉野の桜の花を見に出かけた時であった。上千本の、奥の、西行庵の近くの夕暮れの、うす暗がりの中で、この芭蕉翁の句に出会ったのは………。
春は、僕にとって、いつも哀しい季節だった。春の頃には、なぜか、かなしいことが続いた。入学やら、卒業やら、花見やら、世の喧噪は、僕には、いつも、縁のないものだった。
冬は、寒くて、つらいこともあったが、そのつらさが、かえって、かろうじて、生きるバネとなった。寒い冬の夜に、暖房具を使わないで、過ごしたこともある。指が冷たくて、かじかんで動かなくなると、木刀を振りまわし、かけまわっては、体を暖め、又、机に向った。そんな寒さが去って、春めいてくると、なぜか、又、わけなく、ものがなしかった。
旅に病んで 夢は枯野をかけめぐる
この句に、最初に出会ったのは、多分、中学校の頃ではなかったかと思う。文字の意味も何もわからなかった。高校になって、古典の時間に、奥の細道をやる頃になると、単行本を買ってきて、読むようになった。光陰は百代の過客にして、行き交ふ年も、又、旅人なり……あまりの句調のよさに、得意顔に覚えたりもした。しかし、本当にその句が切実なものになったのは、十九歳の春ではなかったか……。意味もわからない。背景もさほど知らない。その人がどんな時代に生きて、どんな生活をしたか、想像の域を出ることはない。ただ、感覚が残っている。感覚だけが伝わってくる……そんな気がした。ずっと、ずっと遠いことのようにも思えるし、きのうのことのようにも思われる。
十七から二十一くらいまでの期間は、僕には悪夢の歳月であった。おそらく自分の持つ価値観が、大きく移っていった時代だった。そんな大げさなものではないかも知れないが、それが過ぎた頃には、たしかに自分が、それまでの自分とは違うものになっていた。
(過ぎ去ってしまえば何ともないことでも、その時、本人には、それこそ、生死にかかわることもあるらしい。)
悪夢。
ぼくは、それまで、世に絶対的なものがあると信じて、疑ったことがなかった。そのことを考えたこともなかった。だからこそ、生きるということを疑ったこともなかったし、生きるからこそ、生きなければならないという命題があった。すべて思う通り生きられるはずもなかったが、それでも、思いどおりにゆかないときには、それこそ、事あるごとに後悔をし、自分を責めた。笑われるかもいしれないが。
一日、六時間も寝た日には、ああ惰眠をむさぼって、自分は何となさけない人間だと本気で思った。大阪の街に出て、人の多さと、建物の大きさに驚いて、自分の非力を嘆いて、涙した。笑われるかも知れない。しかし、僕は本気だった。
何がきっかけだったかは知らない。そんな自分が、本当に…絶対的なものを信じているのか…もしかりに、あるとしても、わからないものをあると信じる自分が果たして、本当に、自分なのか・・・そんなことを思い出してから、心の中のすべてが、がらがらと音をたてて、くずれはじめた。
一瞬には、くずれなかった。長い歳月が必要だった。悪夢の連続であった。夜すら、ねむれなかった。ちょうど、大学入試や、家のごたごたが重なった。が、それどころではなかった。自分の存在がわからない…くる日も、くる日も、同じことを考えた。生きる命題が見つからない…そんな言葉に換えた……生きる命題が、見つからない…
旅が、身近かなものになった。下駄ばきに寝袋で出かけるようになった。駅のベンチに寝た。道端に寝た。草花が目に入ってくるようもなった。
山陰に出かけたときのことだった。前日、松江止まりの列車にのって、駅に降り立ったのが、夜の十一時すぎだった。駅のあたりをぶらぶらしながら、その日は、駅のベンチに寝た。翌朝、修学旅行にゆくらしい中学生の声におこされた。別にこれといったあてもなかったが、入ってきた鈍行列車に乗った。益田まで、十時間以上かかったろうか。秋だった。山陰独特の、どんよりした空だった。目の前の景色が、どこまでいっても、かわらなかった。しかし、退屈だとは思わなかった。時の流れが、わからなかった。
そんな頃だったと思う。毎日、毎日、寝床の中の暗やみで、悪夢をみた。ねられぬことを、心底つらいと思った。ある夜いつものように、ねむられないまま、あかりを消して、何時間も疲れた体を海老のようにかがめながら、同じことをくり返しくり返し考えていた。いまにも砕けそうな体とは、うらはらに、とがった神経だけが、なぜか、冴え渡っていた。
頭の中を、一つの思いが去来した。
なぜ、その句が浮かんできたのか、わからない………
旅に病んで 夢は枯野をかけめぐる
……浮かんでは消え、浮かんでは消えていった……知らずに泣いていた。
意識すればするほど、涙が止まらなかった。部屋には、他に誰もいないのに、なぜか、声が出せなかった。
今、僕は高校で英語の教員をしている。くる日も、くる日も、人に疲れながら、精一杯、精力的に、それこそ魂を削りながら、がたがたの体を引きずりながら……
三十の坂を、のぼりだした。
執筆年
1978年
収録・公開
同高校文芸部「黄昏」 6号 (1978年)32-34頁。
リンク・ダウンロード