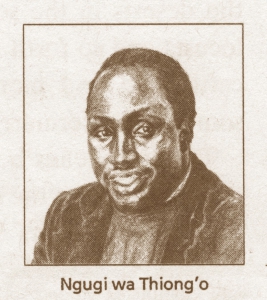サイラス・ムアンギ「グギの革命的後段(メタ)言語学1 『ジャンバ・ネネ・ナ・シボ・ケンガンギ』の中の諺」(翻訳)
概要
サイラス・ムアンギさんとは、1982年か83年か(84年か)に初めにお会いして以来ですから20年以上のつき合いになります。最初は、黒人研究の会でお会いしたように思いますが、86年か87年頃、僕もムアンギさんも定職のない非常勤講師として大阪工業大学でご一緒しました。その後、僕は宮崎に、ムアンギさんは四国は香川県善通寺の四国学院大学に決まって、現在に至っています。
普段はなかなか英語をしゃべる相手がいないので「英語の相手をしてよ」と頼んでも「ここは、日本やから」と英語をしゃべろうとしなかったのに、88年に大阪工大のESS部員の付き添いでハリウッドにいたムアンギさんを訪ねた時は、「ここはアメリカやから」と英語をしゃべっていました。
88年には、黒人研究の会のシンポジウム「アパルトヘイトを巡って」でご一緒しました。(<書いたもの>のなかに「アレックス・ラ・グーマとアパルトヘイト」と「アパルトヘイトを巡って(シンポジウム)」として掲載しています。)
89年には、来日中の南アフリカの作家ミリアム・トラーディさんを宮崎にという話しがムアンギさんからあり、お引き受けしました。(<書いたもの>のなかに「ミリアムさんを宮崎に迎えて」と「ミリアム・トラーディさんの宮崎講演(講演記録)」として掲載しています)
昨年の宮崎大学の大学祭のシンポジウム「アフリカと医療」でも、またご一緒できました。(現在、シンポジウムの記録をまとめています。近々公開予定です。)
ナイロビ大学を卒業後文部省に勤務、その後京都大学に坂本龍馬の研究に来られたそうですが、体制とたたかうグギさんと親しくしてケニアに帰れなくなったようです。
政治学者ですが、グギさんの文学にも造詣が深く、この文章はグギさんが亡命後に書いた作品の作品論で、僕が翻訳することになりました。ムアンギさんは、日本語の読み書きも堪能で、日本語訳についてのやりとりが何回かあって、この雑誌で活字になりました。
母国語のギクユ語に加えて、英語とスワヒリ語と日本語の4ヶ国語を使っておられます。二人の間でのやりとりは主に英語でやっていますが、最近はメイルでは日本語も使っています。意図は伝わっていると、思っていますが。たぶん、伝わっていると思います。
グギさんは1938年生まれ、ムアンギさんは1946年生まれ、ちなみに僕は1949年生まれです。
本文(写真作業中)
言葉を選べば読者が決まり、自ら階級が決まる
グギを中傷する人達がよく繰り返すあやまりの一つに、ギクユ語で書くようになってから、グギは民族的な狂信的排外主義に逆戻りしてしまった、というのがある。グギがどのようなイデオロギーを持ち合わせているかを知っている人たちには、そんないいがかりはいかにも馬鹿げていて、空しいものである。もし、1987年11月、来日した際にショインカが行った賢明とも思えない主張がなければ、ここであえてそのことを取り上げる価値などないだろう。ショインカは、自分の言語であるヨルバ語でものを書くことは石器時代に逆戻りするにも等しい、と述べた。
ウォレ・ショインカには1986年のノーベル文学賞受賞という事実があるから、軽薄な連中は、誰もが日本語でものを書く国でショインカが主張した明らかな一貫性のなさに気付かないで、ショインカの言動に魅せられて信じ込んでしまいそうである。石器時代から離れるために、日本人は自分たちの言語を捨てて英語を採用しろ、とまさかショインカが提案したわけではないだろうが、それでは日本語で書くこととヨルバ語で書くことが一体どう違うのか。
ショインカが語るのを聞いた日本人の中でショインカが自分の言語を低く見ていることを気にした人はそう多くはいなかっただろう。実際は、ショインカの発言が、アフリカの言語は劣っているという傲慢な見方をする連中を喜ばせ、元気づけた可能性がある。これから先、ヨルバ語に関する、広く言えば、他のアフリカの言語に関するショインカの立場が、グギを攻撃するのに使われるのを耳にすることもありそうである。というのも、ショインカ流の論理で言えば、ギクユ語とスワヒリ語でしか作品を書かないと誓い、1986年からそのことを実行しているグギが、文字通り石器時代の洞窟人間になってしまうからである。
従って、グギが敢えてギクユ語で書こうとしている意味合いをより深く考え、グギを貶めようとする連中の馬鹿げた主張を暴き出すのは、尚更のこと重要である。しかし、グギが文学的な表現のための言葉としてギクユ語を使うことに触れる前に、私にはショインカを中傷する意図など全くないことをはっきりさせておく必要がある。ナイジェリア内だけではなく、貪欲な政治屋どもが自分たちに反対する人々を抑圧している私たちの大陸、アフリカのどこにおいても、正義のために、そして暴君に対してショインカが勇敢に闘っている点に関して、私はショインカを高く評価している。私が言いたいのは、不運にも、アフリカの言語でものを書くという点に関してショインカが行なった論評が、アフリカを低く見ている連中の非道な策略に利用される可能性がある、ということである。
イギリスの雑誌「マルキシズム・ツゥディ」1982年9月号のインタビューで、グギは次のように述べている。
もし、私がギクユ語で (他のアフリカの言葉でも同じことが言えるのですが) 書けば、私は農民と労働者を読者に持つことになります。つまり、ある読者を選べば、自ずから階級が決まるということなのです。従って、「黒い膚、白い仮面」の中で、言葉を選べば、世界が決まる、とファノンが述べた言葉を私は拡大して使っているというわけなのです。
グギは、又、どのようにして1976年に、ギクユ語で書こうと決意したかについて振り返っている。1976年に故郷のカーメレーゾ村では、農民と労働者が、カーメレーゾコミュニティ教育文化センターをつくった。そして、人々は劇場を作る必要があったので、そのためにグギが劇を書くことになった。自分たちの言葉を使わずに、一体どうして劇を書いたり、脚本作リが出来るというのだろうか、とグギはつくづく考えた。これが私の人生の『大転機であり、実際、ギクユ語で書くという意思の一部がカーメレーゾの人々と共に働くという経験の源泉になっていったと言わなければなりません、とグギは言う。グギ・ワ・メリーエと一緒に書いた劇「ガアヒカ・デンダ」 (結婚? 私の勝手よっ!」) によって、結果的にグギは拘禁されることになった。しかし、拘禁されても、挑戦的な行為として当局を不快がらせていた言葉で書くというグギの決意は高まるばかりであった。その厳しい獄中の状況でさえ、グギの創作能力を衰えさせるどころか、逆に、いいように手なずけ{やろうとする看守たちの企みをものの見事に打ち砕く結果を生んだ。文芸雑誌「クナピピ」(1983年5巻1号) の別のインタビューでは、グギは次のように言う。
獄中の状況の厳しさから、全く正反対のもの、つまりケニアの言葉で何かを成し遂げるという凄まじいまでの決意が生み出されました。その本 (『十字架の悪魔』)のもう一つの局面はその基調がもう少し明るい感じのものなのですが、かと言って決して軽いものではありません。風刺的な要素がより支配的です。もし人が、おぞましい境遇の中で生活していれば、あるユーモアの感覚を、時として風刺的ユーモアの感覚を培い、現実を見る能力を身につける必要があります。もし、厳しい状況で生活する時には、その厳しさによって壊されてしまう可能性があるのです。しかし、もし見かけだけでもにこにこしていられる仮面を着けることが出来れば、それが別の精神的な支えにもなり得るのです。
このグギの挑戦的な姿勢から『シャイタアニ・モザラバイネ』(『十字架の悪魔』) が生まれた。この紙面で説明し切れないほど色々な意味合いでの傑作であるが、ここで一つだけ取り上げておきたいことがある。それは、女性を勇気づけようとするグギの意識的なねらいだ。
女性は社会で、より厳しく抑圧されているので、自分たちの自信の解放を始めるに当たって、自らへの抑圧の強さをまず知る必要がある。
1980年8月16日付のケニアの日刊紙「ザ・スタンダード」の編集者あての感動的な手紙の中で、ワンジェラ・カリオキ・カロービアというケニア女性は、グギのギクユ語小説『シャイタアニ・モザラバイネ』が「出現しつつあるケニア、アフリカ人女性の可能性に献げられたすばらしい、歴史的な里程標であり・・・・・・この国の美しい娘たちへの時宜にかなった、本当はもっと早く言うべきであったのですが、信頼と愛と希望の表明です」と述べている。その評は「抑圧され、闘い続けている人々のために」書こうと決意したグギに対するまさにぴったりの賛辞である。グギは「マルキシィズム・ツゥデイ」のインタビューの中で、どうしてそれほどまでに女性の運命に深い関心を示すのかを次のように語る。
女性は私の作品の中でいつも重要な役割を果たしています。このことは、ある意味で反帝国主義闘争でケニアの農民女性が占めてきた重要な位置を反映しています。ケニアの女性は、現に大抵のアフリカ諸国と同じように、しばしば2重にも、それ以上にも搾取され、虐げられています。まず、農民と労働者の一員として、国内ブルジョアジーと帝国主義者に抑圧されています。しかし、農民女性は女性としても抑圧されているのです。というのも、前資本主義的、前植民地主義的時代以来、男性に仕えるものとして女性を見る後進国で、封建的な要素がなお残存しているからです。ですから、女性が2重の意味で自己を認識しなければならない、というのが重要なテーマになるのです。
『ジャンバ・ネネ・ナ・シボ・ケンガンギ』に使われているギクユ語の諺の反女性的意味合いに対するグギの鋭い粛正
グギの女性を高く評価する姿勢は『シャイタアニ・モザラバイネ』で終わりはしなかった。又、更に、女性解放にグギが深く共感を抱いていることに賛辞が送られたのはケニア内ばかりではなかった。事実、ナイジェリアの女優兼劇作家エリザベス・オズ・オシィシィオマは、英訳だがその作品にとても魅せられて『世俗的策略の王国』というタイトルでその改作劇の脚本を書いた。
子供向けのギクユ語3巻本『ジャンバ・ネネ・ナ・シボ・ケンガンギ』の第3巻で、グギは、男性優位の伝統的排外主義的要素が未だ残存しているギクユの諺を意識的に一部修正している。5ペイジでは、ロヘニ将軍が、平和や調停に対する若者の限りない許容性に舌を巻く。そのシリーズの青年主人公ジャンバ・ネネはマウマウの指導者ロヘニ将軍の所ヘシボ・ケンガンギを殺しに行く許可を求めにやって来る。(シボ・ケンガンギの名前の意味はワニ首長) つまり、ジャンバ・ネネの母親を苦しめ死に追いやった残忍な植民地主義者の手先。ワニ首長がジャンバの母親ワーショを殺す理由は、明らかに母親がゲリラの息子がどこに隠れているかをどうしても言わなかったからである。ジャンバ・ネネはワニ首長を殺そうと決意するには至ったものの、心の中では相当悩んでおり、この地に相互の信頼や愛や平和がやって来るすばらしい時代を切に望んでいる。「ムァナケ・ネ・キェーニョ・ケァ・ガイ」というギグユの諺を使ってロヘニ将軍が考えることを促しているのは、自分の母親のそんな不幸や死別と直面しながらも、ジャンバ・ネネのような若者の中に決して尽きることのない楽観的な見方が存在するからである。もともと「ムァナケ・ネ・キェーニョ・ケァ・ガイ」という形で諺にあるのだが、その形では、若者は神のものである (つまり、若い男性は神の一部分である) という意味である。言いたいのは、若い男性は神の一部で、本質的に神のものであり、何か敬うべきもの、ということである。元来、その諺は割礼を受けた青年は女性と未だ割礼を受けていない男性から大いに尊敬されるという事実から来ている。しかし、元の形でグギがその諺を使えば、暗黙の男性中心主義を大目に見ることになってしまうだろう。そうすれば、伝統的、現代ギクユ杜会の女性を苦しめる諸悪を正そうとグギが情熱的に係わっていることと矛盾を起こしてしまう。ワニ首長のような登場人物に元の性差別的な意味でその諺を使えばぴったりするだろう、というのも、ワニ首長が下劣な抑庄者や反動者として描かれるように意図されているからだ。その人物を創作したグギがワニという名前を与えたのもその理由からで、ギクユの考え方では、ワニは憎しみ、恐れ、強い反感の対象である。
しかしながら、ロヘニ将軍のような人物が伝統的な形でその諺を使うのは本質的に合っていない、なぜなら将軍が女性を軽蔑することになってしまうからで、解放戦争の指導者には適しくはない。もし本物の指導者なら、女性を劣等視するような反動的な考えを持つべきでない。ロヘニ (その名前は”稲妻”と訳し、その人物が稲妻のように素速く抑圧者に打撃を与えるという含意がある) 将軍は、従って、「ウェーゼ・ネグオ・キェーニョ・ケァ・ガイ」と言う。「青年は神の片割れであり、若さこそ神の心である」という意味である。ムァナケ (若い男) ではなく、ウェーゼ (若者) という表現なら、その諺の中に性的差別はないし、その本の読者は男性にも女性にもその諺が当てはまるのがわかるだろう。
6ペイジで再び、ロヘニ将軍がジャンバ・ネネにケンガンギ首長を殺すまで追跡する許可を与える時に、どんなにケンガンギ首長が固く護衛されていても、ジャンバ・ネネはきっと職務を遂行するだろうと確信を持つ、と言うのは、諺にあるように「ケレミ・ウェーゼ・ネ・ケガリョーレ」(青年は問題に懸命に取り組む前に諦めたりはしないものである)からだ。ここでも又、性に関係のない言葉、男性、女性のどちらの青年をも意味する若者 (ウェーゼ) であり、元来の「ケレマ・アロメ・ネ・ケガリョーレ」という諺の中に実際に表われる言葉の代わりに使われている。アロメは男という意味で、従って、グギの革命的登場人物ロヘニ将軍によって使われるものとしては不適である。
革命的後段 (メタ) 言語学
後段(メタ)言語学とは、ある特定の文化における、言語と、他の特徴との間の関係を研究するものである。又、メタ言語学は、言語構造が如何に意味と関連を持つかに関心があり、表現と話し言葉に付随する仕草を考察する。諺のような言語の側面を丹念に調べ、それらを時事的な解放の要素を含む使い方にまで高めることによって、虐げられた人々、闘っている人々、特に2重にも何重にも苦しんでいる女性のために、グギはギクユ語に関しての革命的な役割を果たしつつある。その意味では、「哲学者はただ単に世界を解釈してきただけであり、肝心なのは、世界を変えることである」というのがお気に入りのマルキストの原則の一つに従ってグギは行動していることになる。ギクユ語でグギが最も関心をはらっているのは単なるメタ言語学ではなく、革命的メタ言語学なのである。(つづく)
執筆年
1988年
収録・公開
「ゴンドワナ」11号34-38ペイジ