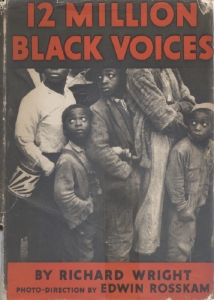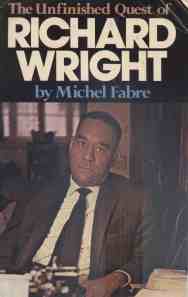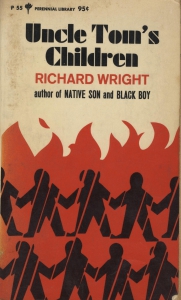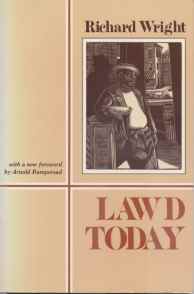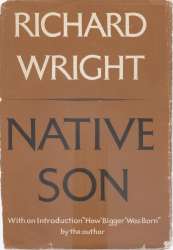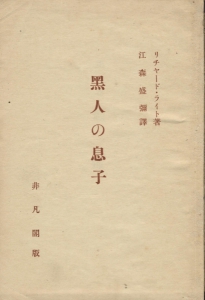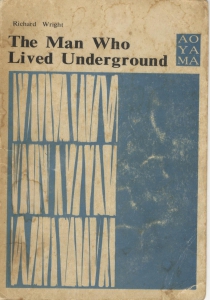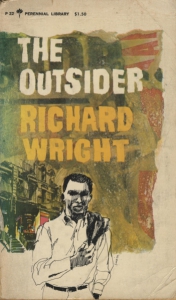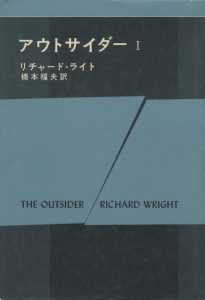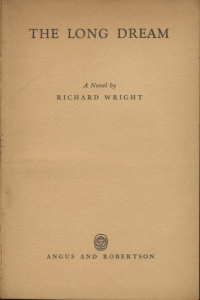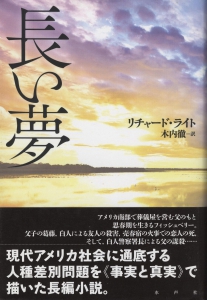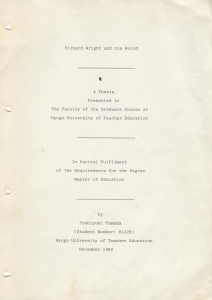1 私の絵画館:パンダ(小島けい)
2 ジャカランダのある風景(小島けい)
3 ほんやく雑記⑤:オハイオ州デイトン(玉田吉行)
**************
1 私の絵画館:「パンダ」(小島けい)
少し前、上野動物園のシャンシャンが2歳の誕生日をむかえたと話題になっていましたが。
私がこのパンダの絵を描いたのは2009年<花のカレンダー>を全国発売していただいた時です。
花の絵に加えパンダの絵も描いて送って下さい、と言われました。それまでパンダをきちんと見たこともありませんでしたが、慌てて2枚のパンダを描きました。
そのうちの一枚、この絵が<カレンダーにもれなく3枚入るパンダトレカ>となりました。青空を背景とするもう一枚の絵も私は好きでしたが、他のクリエイターさんたちと重なっていないからでしょうか、こちらが私のトレカとして選ばれました。
大好きな笹の葉のなかで小枝にのって遊んでいるパンダの子供を、想像して描きました。無邪気でのんびりした様子が、今も愛らしいなあ・・・と思います。
(「2019年小島けいカレンダー「私の散歩道ー犬、猫ときどき馬」6月に収載)
**************
2 ジャカランダのある風景(小島けい)
* この花のことを以前<花のエッセイコンクール>に書いたことがありました。
+++++
5月の終わり頃から6月にかけて、私の住む住宅地でも、空に向かって高くのびた枝にうす紫色の美しい花が咲きます。ジャカランダです。
”昨日今日明日、変わりゆく私”と谷村新司がねばっこくも魅惑的に歌う「三都物語」を聞くと、ああ、あの花だ、といつも思います。一本の木なのに、白・薄紫・紫と三色の花が同時に咲く。この花を、アフリカのジンバブエでは「昨日今日明日」と呼びます。
ジンバブエの首都はハラレは、色鮮やかな花々が咲き乱れる南半球の街です。
「昨日今日明日」のように、宮崎においてもさりげなく咲く花も多いのですが、ひときわ印象に残っているのは、大きな街路樹としていたる所に植えられていた「ジャカランダ」です。
花が心に残るのは、その花とともに出逢った人々が忘れられない時のように思います。私にとってのジャカランダも、素朴なショナの人たちとの出逢いと重なります。
アフリカで暮らす。それだけを目的に、私たちは白人の老婆から家を借りました。五百坪ほどの家には、庭番のゲイリーと大きな番犬のデインがいました。ゲイリーは背の高いショナ人で、犬のエサ代よりも安い給料で雇われていました。けれど敬虔なクリスチャンである彼は、不平は言わず、誠実で正直でした。


ゲイリーと私たちが親しくなった頃、八月の冬休みを利用して、田舎から家族がやって来ました。ガレージの裏のベッドも何もない部屋で、彼らは家族が一緒に暮らすことのできる貴重な日々を、遠慮がちに楽しんでいました。
奥さんのフローレンスはほっそりとした美人です。私はモデルを頼み、毎日絵を描きました。十四歳の娘と十歳の息子は、同年齢のウォルター・メリティーそして末っ子のメイビィと、朝早くから日が暮れるまで遊び続けました。

庭は広い芝生で、真ん中に特別大きな木がありました。ジャカランダです。五人は遊び疲れるとその木陰の椅子で、時には木の枝でひと休みします。そこが遊びの本拠地でした。
肌の色も言葉も違う五人の子供たちが、どっしりと枝を広げたジャカランダの下で、まるで兄弟のように笑いころげ走り回る。それは、外の世界の白人と黒人の格差・対立などを忘れさせるほど、平和で美しい光景でした。
ジャカランダのある風景で、今一つ忘れられない場面があります。ウォルターとメリティーの通うルカリロ小学校を訪問した時のことです。
ルカリロ小学校
吹き渡る風で乾いた土がむき出しの丘に、小学校はありました。資金不足のため、屋根や床のない校舎もあり、むろん門や塀もない。ただ二本の若いジャカランダの木が、アーチのように入り口あたりに立っていました。その薄紫の花のずっとむこうに小さな校舎。と、そこから全生徒職員がいっせいに、私たちめがけて駆け出してきます。その後の握手ぜめ。私たちは、村を訪れた初めての外国人でした。
アフリカでの生活は予期せぬことの連続でしたが、ショナの人たちとのいい出逢い、珍しい花々との出逢いに恵まれた日々でもありました。
そして、ジャカランダの花が街を薄紫に染める頃、私たちはその街を去りました。
宮崎市在住・装画家(四十九歳)
**************
2 ほんやく雑記⑤:オハイオ州デイトン 玉田吉行
概要
ほんやく雑記の5回目で、オハイオ州デイトン出身の詩人ポール・ダンバー(Paul Laurence Dunbar, 1872–1906)の“Little Brown Baby”という詩を取り上げます。表現の仕方と、時代背景の理解の大切さについて書きました。
「ほんやく雑記」の連載(「モンド通信」)用に2016年に書きましたが、編集洩れしたようですので、今回の「続モンド通信」に掲載しています。「ほんやく雑記」は「モンド通信」が発行されなくなってたち切れになりましたが、近いうちに「続モンド通信」で再開しようと思っています。
本文
ほんやく雑記の5回目です。
前回はアレックス・ラ・グーマの『夜の彷徨』(A Walk in the Night)の舞台になったケープタウンの第6区を取り上げ、ほんやくをする人の気持ちの大切さについて書きましたが、今回はオハイオ州デイトン出身の詩人ポール・ダンバー(Paul Laurence Dunbar, 1872–1906)の“Little Brown Baby”という詩を取り上げます。表現の仕方と、時代背景の理解の大切さについて書きたいと思います。(写真:ポール・ダンバー)
わが子と戯れる父親について詠んだ短かい詩は、次のように始まります。
輝く瞳の愛しいわが子よ、
こっちに来て、パパのお膝にお座り。
閣下、何をしておられたのでありますか?お砂のパイでもお作りでしたか?
涎掛けを見てごらん、パパと同じくらい汚れているね。
お口を見てごらん、きっと、糖蜜だろうね。
マリア、こっちに来て、この子の手を拭いてやってくれないか。
蜜蜂が来て、この子を食べちゃいそうだから、
ねばねばして、甘いからね!
Little brown baby wif spa’klin’ eyes,
Come to you’ pappy an’ set on his knee.
What you been doin’, suh – makin’ san’ pies?
Look at dat bib – you’s ez du’ty ez me.
Look at dat mouth – dat’s merlasses, I bet;
Come hyeah, Maria, an’ wipe off his han’s.
Bees gwine to ketch you an’ eat you up yit,
Bein’ so sticky an’ sweet goodness lan’s!
そのあと父親は、一日じゅうも笑みも絶やさない可愛いわが子を見つめながら、突然からかい始めます。「パパはお前なんか知らない、きっといたずらっ子だと思うよ」「戸口からこの子を砂場に投げちゃおう」「この辺りに、いたずらっこなんて要らないから」「この子をお化けにやっちゃおう」「お化けよ、お化け、戸口から入っておいで」「ここに悪い子がいるから、食べてもいいよ」「父さんも母さんも、もうこんな子は要らないから」「頭から爪先まで飲み込んじゃって下さい」と脅された子供は、ぎゅっと父親にしがみついてきます。そして、最終連です。
ほらほら、やっぱり、ぎゅっとしがみついて来ると思ったよ。
お化よ、もう帰っておくれ、もうこの子はあげないないから。
もちろん、迷子でもないし、いたずらっ子でもないよ。
父さんを許してくれるいい子で、遊び相手で、喜び。
さあ、ベッドに行って、お休み。
お前が、いつも平穏無事で、こうして素敵なままでいられたらどんなにいいだろうね。
お前がこのまま私の胸の中で、子供のままでいられたらどんなにいいだろうね。
輝く瞳の愛しいわが子よ!
Dah, now, I t’ought dat you’d hub me up close.
Go back, ol’ buggah, you sha’n’t have dis boy.
He ain’t no tramp, ner no straggler, of co’se;
He’s pappy’s pa’dner an’ playmate an’ joy.
Come to you’ pallet now – go to yo’ res’;
Wisht you could allus know ease an’ cleah skies;
Wisht you could stay jes’ a chile on my breas’
Little brown baby wif spa’klin’ eyes!
アフリカ系アメリカ人の言葉(いわゆる「黒人英語」)で書かれたこの詩はなかなか難しいですし、仕事帰りの父親が小さなわが子と戯れる様子は微笑ましいのですが、最後の仮定法の二行に来ると、ちょっとほろっとしてしまいます。
ダンバーは早くから詩を書いて白人の編集者に認められて国際的に有名になったそうですが、33歳の若さで亡くなっています。ダンバーの生きた頃は、アフリカ系アメリカ人には厳しい時代でした。奴隷貿易で大儲けをした南部の荘園主と、奴隷貿易で蓄積した資本で産業革命を起こしてのし上がった産業資本家が、奴隷制をめぐって南北戦争で殺し合い、法的に奴隷制は廃止されたものの、経済力の拮抗する対立の最終決着はつかず、結局アフリカ系アメリカ人は奴隷から小作人に名前が変わっただけ、苦しい生活は変わりませんでした。1890年代に入ると「奴隷解放」によって自由を夢見て南部から北部へどっと人が押し寄せますが、安価な単純労働しか求められないアフリカ系アメリカ人には厳しい現実は元のまま。特に本来なら知的労働者になるべき人たちには特に厳しい時代です。
小作人(a sharecropper)、Twelve Million Black Voicesから↓
炎天下の綿摘み作業、Twelve Million Black Voicesから↓
Richard Wright’s Twelve Million Black Voices (1941)
merlassesは砂糖黍の絞り滓、口のまわりをべとべとにして汚くしているのは、長くて汚い仕事から戻って来た俺といっしょ、今は俺の胸の中で何とか平穏にいてもらえるが、大きくなって仕事があっても安い辛い仕事ばかり、カラーラインを越えようものなら、白人のリンチ。このまま、俺の胸の中にいてくれたらなあ、という切なる父親の願いに、ほろっとしてしまいます。人種差別反対を声高に唱えるより、「現在事実の反対の仮定」を意味する「仮定過去」を最後に二つ並べた表現の妙は、心にじんと迫ります。
アメリカ文学会の会誌か何かでLittle brown baby wif spa’klin’ eyes が「きんきら目玉の小さな褐色の赤ちゃん」とほんやくされているのを見かけて違和感を覚えたことがあります。「きんきら」「目玉」「赤ちゃん」は論外ですが、それより「褐色の」が気になりました。
次回は「ほんやく雑記(6)イリノイ州シカゴ」です。(宮崎大学教員)
執筆年
2016年(「モンド通信」の連載洩れです。)
ダウンロード
2016年7月用ほんやく雑記5(pdf 286KB)