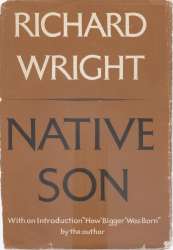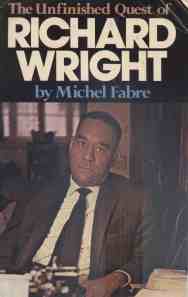Richard wright, “The Man Who Lived Underground”の擬声語表現
概要
「リチャード・ライト作『地下にひそむ男』―出版の経緯に触れてー」でテーマや視点に焦点をあてて書いた作品論を、今回はテーマや視点に、表現をからめて考えてみました。英語を母国語とするライトが、言葉に対してここで分析するように感じていたかどうかはわかりませんが、少なくとも読み手にはそう感じられるほど、ライトの表現力や文章の持つ力は、僕には圧倒的でした。少しでもそういった表現力をからめた視点からライトの作品を評価してみたいと思ったのが書いた動機です。
擬声語に関しての引用は、都合のいいところだけ使ったように思います。決して数字に裏付けされたものではなく、語感や字感など、感性的に述べたきらいがあります。擬声語に対するこだわりは、やがて、南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマの作品を読む際にも役立つことになります。
言語表現研究は、修士号を取った兵庫教育大学大学院の学生と教官ではじめた国語・英語の共同学会で、今は学部生も加わっているようです。
「言語表現研究」 2号 1-14ペイジ
本文
Richard Wright (1908-1960) の中編小説 “The Man Who Lived Underground” に於ける幾つかの場面で用いられた擬声語表現を分析、鑑賞することにより、この<地下作品>の評価をはかりたいというのが本論のねらいである。尚、ここで用いる擬声語 (Onomatopoeia, echo-words) とは、自然音そのままではなくそれを模したarticulate soundsを指し1、本論ではO.E.D. に於いて [Imitative.] の表記がある語を中心に取り上げるものとする。
1944年にCross-Section誌に収載されたこの作品は、死後出版されたEight Menの中にも再録されているが、1956年には既に、ハックスリー、トルストイ、モーパッサン、サロヤンの小説と並んでQuintet – 5 of the World’s Greatest Short Novels の中に取りとげられる程の評価を得ている。1973年にM. Fabreによって伝記The Unfinished Quest of Richard Wright が出版されてからは、この小説が従来の人種問題を中心にしたテーマを一歩踏み越えようとした最初の作品として、或いは、後続の黒人作家エリスン (Ralph Ellison, 1914- ) 等に少なからず影響を及ぼした作品として、頓に再評価されるようになってきた。それらの評価は、作品中に提示された人種問題の枠を越えた、より広い、より深いテーマの重みや、主人公の<地下生活>を通して、人種によって差別された黒人こそが日常性の中で見失いがちな物事の本質に、いち早く気付き得る有利な地点に、装っているのだと暗に仄めかしたライトの視点の鋭さに負うところが大きい。現に殆んどの批評家がテーマや視点に対する評価に終始している。しかし、私達はそれらのテーマの重みや視点の鋭さが、実は作者の言葉による表現によって裏打ちされていることを見逃してはいないだろうか。又、ある囚人の実話に基づいて書かれた探偵小説からヒントを得たライトが2、自らの想像力や視点に従ってストーリーを虚構したように、ライト自らが選択した言葉によってその表現が生み出されたことを見過ごしてはいないだろうか。ストーリー自体は、無実の罪を押し着せられた主人公が偶然逃げ込んだ下水溝での体験を経た後、警察に自首して出るのであるが、その時には既に真犯人は捕えられており、逆に警官に気狂い扱いされた挙旬、結局は元の下水溝に葬り去られてしまうという割り切れない感じのするものである。にもかかわらず、作品が読者を終始引き付けて止まないのは、主人公が相手に気づかれない有利な立場から垣間見る様々の「現実の裏面」のスリリングな展開に支えられていることにもよるが、音や色に関する鮮やかな表現、分詞構文や中間話法を用いた簡潔な表現、夢の箇所に於ける句読点抜きの表現等、数々の表現技巧に負うところが大きいことを忘れてはならない。それらを念頭に置いた上で、本論では、工夫された表現技法のうち、以下の3つの場面で用いられた擬声語表現を取り上げ、分析、鑑賞してみたいと思う。(1) 主人公が官憲からの逃亡中に、マンホールの蓋が下水に吹き上げられる異様な光景を見て地下に潜む妙案を思いつき、首尾よく下水溝に降り立つ場面……<地下世界へ> (2) 艦人公が地下での数奇な体験を経た後、地上の人々に自らの発見を語るために、同じマンホールから再び地上に戻る場面……<再び地上世界へ> (3) 自らの地下体験を証明する為に警官達をマンホールに案内するが、警官の一人によって下水溝に葬り去られてしまう場面……<再び地下世界へ>
3つの場面を敢えて取り上げるのは、そこに擬声語表現が普通以上に多く、或いは効果的に用いられているからであるが、それ以上に、3つの場面に共通して、マンホールの蓋によって発せられた音が含まれており、その音が主調音の如く作品全体に響き渡っているように思われるからである。尚、その音は作品中4度用いられている- (1) の場面で2度 (1度は名詞の “clang”、もう1度は動詞の “clang”)、 (2) の場面で1度 (名詞の “clang”)、(3) の場面で1度 (名詞の “clank”)。マンホールの蓋に、或いはその音を表現した語 “clang,” “clank” にこだわるのは、その蓋が虚偽、死臭に満ちた地上世界と、日常では気付き得なかった新しい自己を再発見するきっかけになった地下世界を隔てる役目をしているだけでなく、主テーマに係わる何か重要な象徴的意味合いを示唆しており、その音がその象徴的意味合いを聴覚によって鮮やかに読者の耳に印象づける役割を果たしていると考えられるからである。以下、 “clang,” “clank” を軸にしながら3つの場面を見ていきたいと思う。
<地下世界へ>主人公と思しき男がある玄関先に潜んでいる時、パトカーのサイレンが鳴った。男が「隠れなくては……」と思った時、路上の異様な光景が彼の目に飛び込んで来た。それに続く件が次のように書かれている。
…Then a sudden movement in the street caught his attention. A throng of tiny columns of water snaked into the air from the perforations of a manhole cover. The columns stopped abruptly, as though the perforations had become clogged; a grey spout of sewer water jutted up from underground and lifted the circular metal cover, juggled it for a moment, then let it fall with a clang.
He hatched a tentative plan: he would wait until the siren sounded far off, then he would go out….3
下水に押し上げられたマンホールの蓋は、雨に濡れた路上に勢いよく音を立てて落ちたのだが、作者はその音を “clang” で表現したのである。いや、厳密に言えば、 “clang” で表現される場面を設定したという方が正しいのかも知れない。いずれにしろ、マンホールの蓋と道路間の接触音が “clang” で表現されたわけだが、まずその語について検討してみたい。O.E.D. によれば “clang” は次のように解説されている。
Clang (klAN), sb.
- A loud resonant ringing sound; orig., as in Latin, that of a trumpet, and so still in literary use; but now, most characteristically, the ringing sound of metal when struck, as in 'the clang of arms’; sometimes also the sound of a large bell.(下線は筆者)
下線部が示すように “clang” によって示される音の特徴の1つは、その音が大きい、騒々しいということである。Otto Jespersen は “Sound Symbolism” のMovementの項でl-combinationで始まる言葉の多くが “loud sound” を示す特徴があることを指摘しているが4、このcl- [kl] に、もう少し分析的解釈を加えてみたい。破裂音 (Plosives) は「吹き鳴らされた音や打ち鳴らされた音、或は物の衝突・摩擦等による音を表はす場合が多」5く、そのうち k [k] を含む無声音は「概ね澄んだ軽快な音色」を示す。又、l [l] を含む流音 (Liquids) は「耳に感ずるところ楽音的・諧音的」であり、「積極的には静止に逆ふ動揺・流動・飛翔等の運動を、消極的には粘滑の感を表出」する。つまり、その2つの組み合わせcl- [kl] は、この場合、下水に吹き上げられたマンホールの蓋が道路上に落ちた際に発した澄んだ軽快な金属音を表わしたことになる。次に語尾の -ng [N] について少し検討を加えたい。鼻音 (Nasals) は継続的な感じを示すが、中でも特に [N] は物の響きに関して見い出され「轟く餘音を表はすに適切」である。cl- が示す音の特徴が大きいという点にあれば、この -ng の示す音の特徴は響く余音という点にある。以上のことを総合すると、“clang”の一語はマンホールの蓋が道路に落ちた際に澄んだ大きな金属音を発したことと同時に、その音が軽快に余音を残しながら響いたことを示したことになる。裏を返せば、作者は大きさと響く余音を象徴する “clang” をこの冒頭の場面に持って来たわけだが、その音によって作者は一体どんな効果をねらったのか。或いは、何故その音を持ち出したのか。そのあたりの情況を詳しく知る為に本文に立ち戻ることにしよう。庭先に潜む男がパトカーの音に驚いたことは既に少し述べたが、冒頭から、男が路上の異様な光景に気付くまでの本文は以下のようになっている。
I’ve got to hide, he told himself. His chest heaved as he waited crouching in a dark corner of the vestibule. He was tired of running and dodging. Either he had to find a place to hide, or had to surrender. A police car swished by through the rain, its siren rising sharply. They’re looking for me all over…. He crept to the door and squinted through the fogged plate-glass. He stiffened as the siren rose and died in the distance. Yes, he had to hide, but where? He gritted his teeth. Then a sudden movement… (58)
本文からは男の姓名も素性もわからないが、その男が警察に追われて逃げていること、そして逃げ回ることにもう辟易して、隠れ場所が見つからなければ自首をするしかないと考えながら潜んでいることがわかる。又、パトカーのサイレンの音を聞いて「奴らが俺を探し回っている」と考えて、とっさに動き出したり、そのサイレンの音に体を強張らせたり、或いはパトカーの音で「隠れなければ……」と動き出したりしたことにより、その男がどこへ逃げたらよいのかわからない荷立ちから歯ぎしりをする程追いつめられている様子が窺える。今し方汚水の噴き出した下水溝に逃れることを思い付き、敢えてパトカーが頻繁に行き交う道路に出て、その計画を実行したことを考え合わせれば、如何に男が追いつめられていたかは充分に想像がつく。男がそれ程までに追いつめられていたからこそ、又あせりを感じ、苛立ちを覚えていたからこそ、マンホールの蓋がそのあせりや苛立ちを瞬時忘れさせる程大きい “clang” の音でなくてはならなかったのである。或いは又、男がもうどこにも逃げ場がないと考える程追いつめられた極限に近い状態にいたからこそ、マンホールの蓋の音があたかも男を地下に誘っていると錯覚してもおかしくない程、響く余音を “clang” に持たせる必要があったのである。事実、作者は動詞を用いないで名詞を持ち出し “with a clang” と文尾に “clang” を置いている。“clang” を文尾に置くことでその響きに余音の効果を持たせようとしている。又、その “clang” で文を切り、行を改めたのも、一呼吸置くことによってその余音の効果をより高めようとしたためではなかったか。この“clang” に関しては、もう一つ見逃せない作者の工夫がある。それはパトカーの音を表わした “swish” との対照的な組み合わせである。その音が男のあせりを誘ったことは既に述べたが、ここでその音について考えたい。O.E.D. によれば “swish” は次の如く記されている。
Swish (swiS), int. or adv. and sb. 1 [Imitative.]
- int. or adv. Expressive of the sound made by the kind of movement defined in B. 1; with a swish. Also reduplicated swish, swish.
B.sb.
- A hissing sound like that produced by a switch or similar slender object moved rapidly through the air or an object moving swiftly in contact with water; movement accompanied by such sound.
Swish (swiS), v. [Imitative. Cf. prec]
- intr. To move with a swish (see prec. B. 1); to make the sound expressed by ‘swish.’ (下線は筆者)
下線に示されたように “swish” の音の特徴の一つはその動きがすばやいことである。この場合、パトカーが疾走したからこそ男のあせりを誘ったと言える。逆に言えば、男のあせりを誘う為に、この場面でパトカーを疾走させたとも言えるだろう。もう少し分析的解釈を試みたい。s, shを含む摩擦音 (Fricatives) は「物の軋み・衝突・摩擦等によって発せられる音を写すに適してゐる」が、この s [s], sh [S] の両音は路上を走るパトカーのタイヤと雨に濡れた道路間に生じる摩擦音シュ、或いはシュッという音を写している。又、母音が象徴する形状の大小、明暗の度、距離の遠近等については「小 (明・近) から大 (暗・遠) に向ふ順序は [c] [o] [u] の序列は別として…… [i] [e] [ε] [A] [a] [u] [o] [c] (又は……[a:] [c:] [u:])」であり、その中でも特に[i] [i:]は微小・鋭敏・急速等を象徴する。更にswi- (スウィッ) の音は、日本語のヒョッ、ニュッ等に似て、「出し抜けに生じる」変化を感じさせる。それらを総合すると “swish” の一語はswi- でバトカーの音が出し抜けに聞こえたことを、[i] でその音が近くで、速く、鋭く響いたことを、[s], [∫] で雨の降る道路を疾走するパトカーのタイヤと道路間の摩擦音を同時に言い当てたことになる。パトカーが速く走れば、その音の聞こえる時間が短いのは当たり前だが、その時間の短さが、実は“clang” と対照的なのである。又、大きく余音を残したことを “clang” が示すのだからその音が長く聞こえたのは当然だが、パトカーの音の短さがよけいに “clang” の響く余音に効果を与えているのである。これに似た組み合わせがこの小説の最後の場面にも出てくるのだが (“clank” と “swish”)、前作Native Son の冒頭にもこの組み合わせが用いられているのは一見の価値がある。本文を掲げてみる。
Brrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinng!
An alarm clock clanged in the dark and silent room. A bed spring creaked. A woman’s voice sang out impatiently:
‘Bigger, shut that thing off!’
A surly grunt sounded above the tinny ring of metal. Naked feet swished dryly across the planks in the wooden floor and the clang ceased abruptly.6
目覚まし時計の鳴る動作を動詞 “clang” で、その音を名詞 “clang” で言い換えたわけだが、その音の大きさ、けたたましさは少年が時計を止める為に素早く走った際に発せられた“swish” の鋭い、短い音との対照的な使い方によって倍加されている。
以上のように考えると、この “clang” が主人公を地下世界へ誘う響きであると同時に、主テーマ<地下>の物語の実質上の幕開けのかねの音 (金属音) を象徴していると思えてくるのである。
地下に逃れる妙案を思い付いた男は機を窺ってマンホールに近づく。その時、又パトカーのサイレンの音が聞こえて、まるでそのサイレンの音にせかされているかのように慌てて取手伝いに下水の中に降り立つ。それからブレーキの音がして見上げるマンホールに白い顔が見えた。続く件が次のように描かれている。
‘How did this damn thing get off?’ he heard a policeman asked. He saw the steel cover move slowly until the whole looked like a quarter moon turned black. ‘Give me a hand here,’ someone asked. The cover clanged into place, muffling the sights and sounds of the upper world. (59)
マンホールの蓋が元の位置に戻される動作に伴なって発せられた音が、やはり人きく余音を残して響いたわけだが、先の名詞 “clang” と響き方が微妙に異なるように思われる。その理由は2つ。一つは、男が音を聞いた場所が前回は地上であったのに対し、今回はマンホールの中であったこと、もう1つは、前回はマンホールの蓋が下水によって噴き上げられてそれが落ちる際に発した音であったのに対し、今回は警官によって蓋が元の位置に戻される動作中に発せられた音だったことである。会話から察するに、警官の1人が、おそらく蓋を見ながら、こ奴 (“this damn thing”) と忌々しげに言いながら、蓋を元の位置に収めたに違いない。敢えて “clang” を動詞で用いたのはその動詞を強調したかったからであろう。その忌々しさが余音となったわけで、下水の中でその音を聞いた男の耳には、マンホールによるエコーとその忌々しさの余音が重なって響いたのではなかったか。先の“clang” が地下への誘いの響きであるとすれば、この “clang” の動作に伴なった音は、地下生活の始まりのかねの響きを持っていたと言える。その響きが、彼を地下に追いやる原因となった警官によるものであったとは何とも皮肉なことなのではあるが。
先に、パトカーの発した “swish” の音で男があせりを誘われたと書いたが、男を地下世界に急かせたのは、やはりパトカーのサイレンの音であった。その辺を検討してみたい、男がマンホールを覗いた時、パトカーのサイレンの音が聞こえて来たが、その音については本文では “The siren seemed to hoot directly above him” と描かれている。その音が“hoot” と聞こえるように思えたことを示しているわけだが、この “hoot" は先に記したように、母音の中では最も暗くて、遠くて、大きなものを象徴する [u:] と瞬間的なものを表わすのに適した破裂音 [t] の組み合わさったもので、[u:] によってそのサイレンが暗闇の遠くからだんだんと大きくなりながら男に迫って来る感じを、[t] によってその音が男の耳に瞬間的に鋭く響いた感じを示している。その音には、行動を始めたが、尚、意を決し兼ねる主人公に行動開始を急き立てる鋭さが感じられる。興味深いのは、この “hoot” [hu:t] が先の “swish” [swiS] と、high back vowel [u:]とhigh front vowel [i]とで著しい対比をなしていることである。近くで鋭く響いた [swiS] と遠くの暗闇から大きく迫って来た [hu:t] の響きによって男があたかも遠近・大小・緩急にわたって脅かされているかの錯覚にさえ陥るのである。
結局、その “hoot” と聞こえたサイレンの音に急かされるようにして、男はとっさにマンホールの縁に手をかけ、中に入って行くわけだが、中に入った時、サイレンの音が、又違った風に聞こえて来た。本文では “・・・the siren seemed to howl at the very rim of the manhole." となっている。“hoot” [hu:t] が “howl” [haul] に変わったわけだが、通常なら “animate” なものに使用されるはずの “howl” が擬人的に “inanimate” なパトカーのサイレンの音を表現するのに用いられている。あたかもマンホールの縁で、逃げる主人公に追手の犬が低い唸り声をあげて今にも飛びかかろうとしている感さえ抱かせる。追われる立場にいる主人公の心理状態を象徴する “howl” の使い方である。
唸るように響くサイレンの音に急きたてられたかのように、取手から両手を離した男は、下水の烈しい流れに足を掬われ壁に頭を打ちつける。壁の裂け目に指を立て、必死の思いで立ち上がり、辛うじて彼は事無きを得るが、その時、今度は車の止まる音が聞こえて来た。それが本文では “He heard a prolonged scream of brakes and the siren broke off. Oh,God! They had found him!” (59) と書かれている。そのブレーキの音 “scream” はscr- [skr] によってタィヤと道路間の摩擦とその動きを、[i:] によってその音が近くで短く響いたことを、更に鼻音m [m] によってその音が継続的な余音を残して響いたことを示している。マンホールの蓋が道路上に吹き飛ばされているのを目撃した警官が慌てて急ブレーキを踏んだのであろう。車はタイヤから烈しい軋り音を立てて鋭く余音を残しながら急停止した。そんな情景をこの一語 “scream” が的確に写したことになる。それから先述の如く警官によって蓋が閉められるのたが、蓋によって地上と遮断された彼の耳には、地上からの音が今までとはまるで違った風に聞こえて来た。その様子が以下のように書かれている。
… His lips parted as a car swept past along the wet pavement overhead, its heavy rumble soon dying out, like the hum of a plane speeding through a dense cloud. He had never thought that cars could sound like that; everything seemed strange and unreal under here. He stood in darkness for a long time, knee-deep in rustling water, musing. (59)
車の響きを表現した “rumble” は2つの流音 [r] [l] によって流動する感じを、有声破裂音 [b] でタイヤと道路間の摩擦で生じた濁った噪音を、更に鼻音 [m] で継続的な余音を一語で表わしており、それを雲間に轟く飛行機の音 [hVm] に譬えたのである。逆に言えば、雲間に轟く飛行機の音にまがう程、地下の流れに立つ主人公の耳には地上の音が異常な躁音に聞こえたということである。これまでの “swish,” “hoot,” “howl,” “scream” が総て澄んだ無声音で表わされたのとは極めて対照的である。つまり金属板一枚の隔たりを直接音・間接音の違いで表現し分けたのである。そればかりか、2つの流音を含む “rumble” と “rustle” は有声音 [rVmbl]・無声音 [rVsl] の対立をなして、遠くで鈍く聞こえる車の音、近くではっきり聞こえる下水の音という遠近感を抱かせる。“swish” と “clang” の組み合わせが “clang” の響きに効果を与えたように、“rumble” と “rustle” の組み合わせは、地上の濁った噪音、地下の澄んだ快音という響きに、より効果を与えている。マンホールをはじめて覗いた時の場面が “…He went to the center of the street and stooped and peered into the hole, but could see nothing. Water rustled in the black depths. ” (58) と記されているが、今回も又、前回と同じように表現された下水の流れ “rustle” は、めまぐるしく変化して表現された “swish,” “hoot,” “howl,” “scream,” “rumble” という一連のパトカーの音と変化・不変化、或いは動と静という著しい対比を見せていることに気付くとき、人間の地上世界の喧噪がますます鈍く、濁ったものに思えて来る。そしてマンホールの蓋によって地上世界と遮断された地下世界の静寂が主人公の五感を把えるとき、読者は<地下世界>にひき込まれて行く自分に気付くのである。尚、先に少し触れたのではあるが、“clang,” “rustle” の両語共、変化して表現されたパトカーの音の間に2語ずつさしはさまれただけでなく “clang” は名詞と動詞に、“rustle” は動詞と形容詞にそれぞれ使い分けられているのも見逃せない作者の工夫ではなかろうか。
<再び地上世界へ>地下の下水溝を通じて、相手に気づかれない有利な地点から地上世界の現実の裏面を垣間見る中で、男は自らの本当の姿に気付く。様々な体験を通して得た新しい発見を地上世界の人々に告げたいという衝動にかられた主人公は、もう一度地上に戻る決意をして、同じマンホールのところまで戻って来る。取手伝いに入口まで辿り着き肩で少し蓋を押し開く。それに続く場面は次のごとくである。
…A crash of sound came to him as he looked into a hot glare of sunshine through which blurred shapes moved….A heavy car rumbled past overhead, jarring the pavement, warning him to stay in his world of dark light, knocking the cover back into place with an imperious clang. (88-89)
今までの静かな地下の様子とは極めて対照的な “crash” である。O.E.D.によると “crash” は次のように解説されている。
Crash (krA∫), sb1 [f. CRASH v.]
- The loud and sudden sound as of a hard body or number of bodies broken by violent percussion, as by being dashed to the ground or against each other; also transferred to the sound of thunder, loud music, etc. (It is often impossible to separate the sound from the action as exemplified in sense 2.)
- The breaking to pieces of any heavy hard body or bodies by violent percussion; the shock of such bodies striking and smashing each other. (下線は筆者)
下線部が示すように、特徴はその音が大きく、突然響くことである。この場合、破裂音c [k] と摩擦音sh [∫] には、今までの静寂を一撃で打ち破る瞬間的な、大きな響きが含まれている。突然の轟音に圧倒されて、彼は一旦下水に叩き落されるのだが、その時男の耳に人って来た地上の音は、やはり金属板一枚隔てた間接音、つまり有声音を含む [rVmbl] と [dJa:] で表現されている。やはりO.E.D. によれば、“jar” の音の特徴の一つは “harsh”或いは “inharmonious” であるから、地上の音が地下の静けさとは対照的な濁った噪音であったことがわかる。その意味では、この “crash” は特に地上と地下の音の違いをはっきりさせる役目も果たしていたことになる。“crash” の音が如何に凄まじかったかは、3度目の “clang” が一度目の時と同様に “with” を伴なった名詞の形で文尾に置かれていることからも窺える。下水に叩きつけられた主人公には、頭上から響く金属音が、再び地上に戻る決心をした彼への地上世界からの尊大な (“imperious”) 警告の鐘のように響いたに違いない。
<再び地下世界へ>結局、主人公はうまく地上に戻るのだが、皮肉にも、自らの体験を証明する為に、こともあろうに自分を地下に追い遣ったと同じ警官達を連れて、又、同じマンホールの所へ戻って来る。そして警官のうちの一人の手にする銃に撃たれて、塵芥の如く社会の排泄溝である下水溝に葬り去られてしまう。その最後近くの光景が以下のように描かれている。
As though in a deep dream, he heard a metallic clank; they had replaced the manhole cover, shutting out forever the sound of wind and rain. From overhead came the muffled roar of a powerful motor and the swish of a speeding car. (102)
先に3度用いられた蓋の昔が総て、何らかの余音を残し、それぞれ何か大切なものを象徴する -ng [N] を語尾に持つ “clang” であったのに対し、この蓋の音は「突然的で後に響を残さぬ瞬間的な」感じを示す破裂音を含む –nk [Nk] を語尾に持つ “clank” である。cl- からその音が大きかったことが考えられるが、その大きな金属音かどうしてマンホール内で余音を残して響かなかったのか。それは、警官が蓋をそっと置いたからである。2度目の “clang” の場面では警官は忌々しげに蓋を閉めたと思われるのに、なぜ今回はそっと蓋を置いたのか。おそらくそれは警官の感じた後めたさの故であろう。既に真犯人を捕えていた警官達にとって、自首して来た男は、もはや必要ではなかったばかりか、拷問の末告白書にサインさせたことをばらされるかも知れない厄介者でしかなかったのである。「地下」のことを口走る男を消す為に、マンホールの所までついては来たが、いざ葬り去ってみると後ろめたさが残る。同僚の何故やったのかの質問に “I had to.” とか “You’ve got to shoot his kind, They’d wreck things.” とかの官憲の御都合主義を振りかざしてみても、やっぱり後ろめたさが残る。だからこそ、人には気付かれないようにと、そっと「くさいもの」に蓋をしたのである。
最後に地上の音を表わした “roar” と “swish” について一考したい。O.E.D.の “roar” の項には以下の説明が付されている。
Roar (rōəɹ), sb. 1
- A full, deep, prolonged cry uttered by a lion or other large beast; a loud and deep sound uttered by one or more persons, esp. as an expression of pain or anger.
- transf. The loud sound of cannon, thunder, a storm, the sea, or other inanimate agents.
“Roar" の特徴の一つは、その音が大きいということである。対語的に用いられた小さな鋭い “swish" がその大きさを倍加している。塵芥の如く下水に流し去られる男の耳に、大きな “roar" と小さな “swish" が交錯して聞こえたのであろうが、薄れ行く意識の中では、"swish" の音でその効果を倍加された “roar" は、O.E.D. の1の項が示すように、まるで誰かが苦しみか怒りの為に叫び声をあげているように聞こえたかも知れない。鋭い “swish" の一語は、冒頭の場面での “swish," “clang" の組み合わせでもそうであったように、"clank" の大きな音を一層引き立たせている。1度目の “clang" が地下への誘いの響きを、2度目の “clang" が地下生活の始まりの響きを、3度目の “clang" が地上世界からの警鐘の響きをそれぞれ感じさせるとすれば、余音を響かせなかった瞬間的、刹那的なこの"clank" には、やはり世の人々に自らの新発見を告げ得なかったという主人公の挫折の響きが感じられる。実に、物語は “swlsh," “clang" に始まり、"clank," “swish" に終ったのである。
一般に擬声語は、小児語や日常語、俗語や方言によく見られたり、最近では漫画等にもよく用いられたりするように、形態上必ずしも進んだ段階のものとは考えられていないが、この作品で見る限り、聴覚に訴える擬声語は、確かに簡潔で、鮮明で、ある場合には読者に緊張感や不安感を抱かせる程、効果的な言葉であった。その点ではBloomfieldの"Symbolic forms have a connotation of somehow illustrating the meaning more immediately than do ordinary speech forms." 7という指摘や佐久間博士の「他の概念的な抽象的なまた叙述的な言葉をもつてしたのでは適切に表現し得ないところのものを端的にいひあらはして、心持にしつくりはまり、いはゆる『ピンと來る』という趣を生じる」8という説明は当を得ている。擬声語は、理性的というよりは感覚的で、間接的というよりは直接的で、より鮮明なものを表現するのに適していると言える。又、ドンドン、カチカチ等の重複形の多い日本語に比べて、英語では “swish," “clack" 等の単音節のものが多いとされるが、ライトは実にその英語の特徴を心得、擬声語を効果的に用いることによって冗長を省き、読者の聴覚に直接的に訴えかけようとしたのであった。この作品では、主テーマに係わるマンホールの蓋の音 “clang," “clank" を軸にして、幾重にも対比表現を織り交ぜながら、鮮明に、強烈に読者の心に迫ろうとしている。
<註>
1 乾亮一、「擬声語雑記」(『市河博士還暦祝賀論文集』第二輯、研究社、1947年)、1ペイジ。
2 Michel Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright (New York: William Morrow, 1973), pp. 574-575.
3 Richard Wright, “The Man Who Lived Underground,” in Cross-Section, ed. Edwin Seaver (New York: L. B. Fisher, 1944), p. 58; all subsequent page references to this work will appear in parentheses in this paper.
4 Otto Jesperen, “Sound Symbolism,” Language (1922, rpt. New York: Norton, 1964), pp. 399-400.
5 音声学関係の記述に関しては、「擬声語雑記」と “Sound Symbolism” に負うところが大きい。
6 Richard Wright, Native son (New York: Harper & Brothers, 1940), p. 3
7 Leonard Bloomfield, Language (1933; rpt. London: George Allen & Unwin, 1979), p. 156
8 佐久間鼎、『日本語の理論的研究』(三省堂、1943年)、18-19ペイジ。
本稿は、黒人研究の会1983年7月例会に於いて口頭発表したものを加筆・訂正したものである。
執筆年
1983年
収録・公開
「言語表現研究」 2号 1-14ペイジ
ダウンロード
Richard wright, “The Man Who Lived Underground”の擬声語表現(106KB)