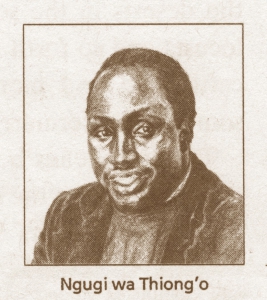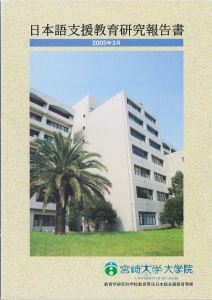概要
1992年に家族でジンバブエに行き、首都のハラレで2ヶ月半を過ごしました。帰国後、暫くは何も書けませんでしたが、半年後に何とか思いを書きとめて1冊の本にまとめました。
まだ本の形では出版がかなっていませんが、その抜粋を「ごんどわな」(横浜:門土社)に「ジンバブエ大学① アレックス」(2000)、「ジンバブエ大学② ツォゾさん」(2000)、「ショナ人とことば」(2001)と題して寄せています。
出版を前提に、今回は元の原稿に少し手を入れ、抜粋をこの雑誌に寄せることにしました。雑誌では2段組の縦書きですが、ここでは横書きに改め、少し写真を入れました。
本文(写真作業中)
ジンバブエ
1992年に家族と一緒にジンバブエの首都ハラレで暮らした2ヶ月半をまとめた滞在記の一部です。文部省の在外研究員としてジンバブエ大学に通いました。
アフリカについて考えるようになったのは偶々です。85年にリチャード・ライト国際シンポジウムがあり、ミシシッピ州立大学に行ったのですが、その時の発表者の一人、ケント州立大学英語科教授の伯谷嘉信さんから87年の会議での発表の誘いを受け、南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマについて発表することになりました。その頃から南アフリカの歴史についても考えるようになり、出来れば家族とある一定の期間アフリカで住んでみないと気が引けるなあ、と思うようなりました。
在外研究に行ける可能性が高かった1991年に文部省に申請の書類を出した時は、ラ・グーマの生まれ育ったケープ・タウンに行ってみたいと考えていました。しかし、申請した時点では、日本政府は、表向きは一応反アパルトヘイトを標榜して南アフリカとの文化・教育の交流の禁止措置を取っていましたので、国家公務員の南アフリカ行きは認められませんでした。結局は、「国内が独立に向けての混乱期でもあるので今回は遠慮して」、「しかし、折角の機会でもあるので、せめて『遠い夜明け』のロケ地となった南アフリカとは地続きの隣国ジンバブエの赤茶けた大地を見に行こう」、と自分に言い聞かせて、ジンバブエ大学に行くことにしました。しかし、知り合いがいたわけではありません。ジンバブエ大使館とジンバブエ大学に問い合せる一方、知り合いの紹介で、ハラレ在住の吉國恒雄さんに手紙を書きました。吉國さんは、アメリカの大学とジンバブエ大学でアフリカ史を学んだあと、現地採用でハラレの日本国大使館に勤務されていた方です。「恐ろしく不動産事情が悪いので、最悪の場合はホテル住まいになるかも知れません。」という手紙をもらっていましたが、ある日、家が見つかりましたので、という国際電話がありました。82歳の老婆がスイスに出かける間、家具付きで貸して下さるというのです。1ヵ月約10万円の家賃でした。宮崎を離れる10日ほど前のことです。
ハラレ第一日目
ハラレの空はからりと晴れていました。
ロンドンのヒースロー空港を真夜中に出た英国航空機は、およそ10時間後、ジンバブエの首都ハラレに着きました。92年7月21日のことです。日本では猛暑の季節ですが、南半球では真冬でした。海抜千500メートルの高原地帯にあり、雨期と乾期のあるサバンナ気候で、1年中過ごし易いところです。すんなり税関を通過し、待合室で吉國さんの奥さんの出迎えを受けました。2日前に車の盗難に遭ったという奥さんの話を聞きながら、私たちを乗せた車は独立記念のアーチをくぐり、ハラレの中心街を抜けて、これからの2ヵ月半を暮らす、アレクサンドラ・パーク地区フリートウッドロード22番地に到着しました。
500坪近くもある広い所で、オランダ風の建物がたっていました。南西の隅に車庫と「庭師」用の小さな建物があり、その建物の北側には野菜園がありました。庭には、パパイヤとマンゴウがたくさんの実をつけ、ジャカランダの大木が2本あり、北側にはハイビスカスの生垣がありました。
ハラレでの借家
道を隔ててアレクサンドラ・パーク小学校があり、ジンバブエ大学の建物も見えます。「この家の持ち主のおばあさんが雇っておられるゲイリーです。給料はおばあさんからもらうそうです。普段のゲイリーの仕事は、庭の手入れと、犬の世話かな。おばあさんがいる時は、買物や銀行にも行かされているようね。少しくらいなら手伝ってくれるでしょう。何かあったら、頼んでみて下さい。」と奥さんから紹介されたのが、ガリカーイ・モヨさんで、190センチ近くはある、すらりとしたショナ人でした。
体長が1メートル50センチほどの犬もいました。前脚が悪そうでしたが、デインと呼ばれる番犬のようです。ゲイリーがいたからでしょう、初めての私たちにも吠えませんでした。
ゲイリーとデイン
南の棟には、寝室が3つと風呂と台所、西側の棟には食堂と居間がありました。居間は20畳ほどで、応接セットに机とテレビが置いてあります。スイッチを入れたらぶんという音がして、映像が出るまでに少し時間がかかりました。
ダブルベッドのある12畳ほどの東の部屋を長男と私が、真ん中の6畳くらいの部屋を長女が、西側の7畳ほどを妻が使うことにしました。見かけとは違って、全体に陽当たりも風通しも良くないようでした。長女の入った部屋は犬が使っていたようで、臭いもひどく、ぎしぎしと大きな音をたて、寝心地が悪そうでした。どの部屋も照明器具がお粗末で、全体に暗い感じです。3方が広い窓の12畳くらいの台所には、冷蔵庫と4つ続きの電熱器があり、湯も出るようでした。故障したトースターと芝刈り機に似た掃除機もあります。電源を入れて試してみましたが、1円玉も吸いこまず役に立ちそうにありません。願ってもない邸宅を世話してもらっておきながら、文句ばかり、我ながら浅ましく思いました。便利で快適な日本の生活に浸りきっているようです。
夕方、吉國さんが食事に招待して下さいました。お宅は、同じ地区内の2キロほど北東にあり、手入れの行き届いた庭のある閑静なお住まいでした。久しぶりの家庭料理を味わいながら、子供たちはゲームを楽しみ、私たちは吉國さん夫妻のお話をうかがいました。ハラレでは、1年を通じて北東から南西の方角に概ね風が吹くようで、白人入植者は東側に水源地を確保したあと、南西の方角にアフリカ人の居住区(ロケイション)を造ったそうです。工業地帯をその間に置いて、緩衝地帯にしたと言います。なるほど、アフリカ人は風上には置かないということか。待てよ、どこかで似たような話を聞いたことがあるぞ。ジョハネスバーグ近郊のアフリカ人居住区ソウェトだ。 SOUTH WEST TOWNSHIPのそれぞれの頭2文字を取った地名です。ジョハネスバーグの南西にあり、55年のソフィアタウン強制撤去の後に自然発生的に生まれたといわれる地域です。金鉱のボタ山が、緩衝地帯になっています。そう遠くないハラレが、ソウェトのモデルだったのか。
遠く離れたアフリカの歴史などは、ややもすれば歴史の方から人の生活を捉えがちですが、実態は、いいものを食べたい、いい家に住みたいというようなごく一般的な欲望が、結果的に歴史を作ったのではないか。吉國さんと話している時、ふとそんな思いに捕らわれました。
こうして、ハラレの第1日目が終わりました。
突然の訪問者
暮らし始めると、予期せぬ事態が起きるものです。
第2日目、「誰か玄関に来てるよ」という長男の声に起こされました。8時過ぎです。朝早くから誰だろう、そう考えながら玄関を開けると、すらっとしたショナ人らしき女の人が立っていました。突然のことで事態がよく飲みこめませんでしたが、育ち盛りの男の子が3人いるんです、今度来る人に雇ってもらえるから今日来るようにとここのおばあさんから言われました、と言っているようでした。取り敢えず10ドルを手渡して、引き取ってもらいましたが、吉國さんに相談するしかなさそうです。
翌3日目の朝、昨日よりも早い時間です。
「玄関で何か言ってるよ」という長男の声で戸を開けると、今度は中年の品の悪そうな白人女性です。車を置いてもらおうと中に入れたらエンストしてしまった、夫に連絡を取りたいから、電話を貸してほしいという事情のようでした。夫に連絡がつきましたと言い、車に乗り込んで帰って行きました。さては、おばあさんの偵察隊?
次は8日目、7月28日のことです。
10時過ぎにYAMAHAのバイクに乗ったおじさんが突然やって来ました。電気代を払わないと明日から薪の生活になるぞ、明日からでも電気を切るぞと脅しているようです。市役所か郵便局で、明日までに200ドルを払え、24時間は待ってやる、そうでないと、薪の生活だとにやにや笑っています。
翌日、無事払い込んで郵便局で言われたように、市役所に電話をして、支払いを済ませた旨を告げると、その領収書を持って明日来るようにとの返事、何のために行くのかと尋ねたら、来られるでしょうの一言で電話は切れてしまいました。
翌朝、市役所に係の人を尋ねて受け取りを見せたら、「いいですよ」の一言、何がいいものか。こっちは電話をかけるのも大変なのに……大体、支所の係の者が一本電話を入れれば済むことじゃないか。あとから吉國さんに確かめたところによると、ジンバブエでは電気を引く際にはディポジット(保証金)が必要で、電気を切った時には、払い込んだお金は戻ってくるとのことでした。おばあさんは電気を引く際に、保障金を払わなかったようです。支払いなどに関するデータは、すべてコンピューターに入力されるとのことでしたが、入力するコンピューター自体の性能がよくないので、半年後とか、1年後に突然こういった事態が起こり得るのだそうです。ともかく、電気を切られる事態だけは免れたようでした。
今度は、生活にも慣れ始めた8月15日です。
朝早く、突然大きなトラックが進入してきました。作業服を着た2人の青年が、ゲイリーと何やらショナ語で大声の会話を交わしています。ゲイリーの説明によると、家具のレンタル会社が、契約が切れたので、食堂のダイニング・セットを引き取りに来たようです。しかし、突然椅子と食卓を持って帰ると言われても……。何回かのやり取りの末、何とか私たちがこの家を離れる次の日に、改めて引き取りに来てもらうことに落ち着きました。「独り暮らしだから、普段あそこは使ってなかったんでしょう。家を人に貸すことになって、ダイニングセットくらいは入れておかないとでも思ったんでしょうね。古き良き植民地時代にいい思いをしたローデシアばあさんの一種の見栄ですな」と吉國さんが説明して下さいましたが、何とも中途半端な契約をしたものです。
小学校
4日目、アレクサンドラ・パーク小学校に行きました。中学2年生の長女と小学校4年生の長男を受け入れてもらうためです。9月から始まる3学期の最初の1ヵ月しか学校には通えませんし、英語もわかりませんが、2人には又とはない貴重な機会を最大限に生かして欲しいと考えていました。
校長は、私たちより少し若そうなショナ人で、黙って事情を聞いたあと、本当に2人分のお金をお支払いになりますかと何回も念を押します。3学期分に1人当たり、授業料など約500ドルが必要だそうで、1万2500百円ほどです。貴重な経験が出来ると思えば、高くはありません。
「何とか空きがありますから、お姉さんは7年生に、弟さんの方は3年生に入ってもらいましょう、この手紙を持って教育省に行き、許可証を貰ってからもう1度学校に来て下さい」と言う校長から手紙をもらいましたが、「あそこの小学校の教員で700, 800から1000ドル、校長でも1500百ドルの月給はもらってないでしょう」という吉國さんの話を聞いた時、校長が念を押した理由に気づきました。実際に学校に通うためには、授業料などの他に経費も必要で、わずか1ヵ月のために大金を払ってまで子供を学校に通わせる理由が、校長には見当がつかなかったのでしょう。吉國さんの話によれば、80年の独立以来、無償だった小学校が、2年前から有償になっているようでした。白人地区に住むアフリカ人の子供を同じ学校に通わせたくないための措置だそうで、植民地時代の良き思い出を捨てきれない反動勢力の巻き返しといったところでしょうか。制服が買えないで学校に行けないアフリカ人も多いと聞くのに、1学期に500ドルも一体誰が払えるというのでしょうか。
そういった事情があるにしろ、校長も好意的な感じでしたし、まだ決まったわけではありませんが、先ずは一安心、週明けに教育省に行けば手続きも、予想していたよりは簡単に済みそうな感じでしたが、そうは行きませんでした。
月曜日の朝、教育省に行きました。建物に入ると、長い人の列、入場者は手荷物検査を受けていて、なかなか順番がまわって来ません。小学校の入学の許可証をもらうだけなのに手荷物まで検査されるとは。
受け付けで指示された部屋に行き、一から事情を説明すると、分かったから次の人のところへ行けということです。今度は女性で、また、一から説明です。少し時間はかかりましたが、やはり分かりましたと言い、教育省の便箋にタイプを打って書類を作ってくれました。正式な許可証のようです。これを持って移民局に行って下さいと言います。書類を見ると、移民局長から出されている貴殿の在外研究員許可証に従って、小学校への入学許可を認めると書いてありました。さて、次は移民局です。何人もの人に場所を尋ねて、移民局に辿り着くと、また長蛇の列で、1時間以上待たされました。やっと順番が来て、また一からの説明です。
「以下のものを揃えて来て下さい。
一、それぞれの子供に対する校長からの推薦状2通、
一、子供のレントゲン撮影の公立病院での証明書2通、
- 親の承諾書1通、
一、保証人の推薦状1通、
一、外国通貨で経費を支払える証明書1通、
一、登録費1人151ドル2名分302ドル。
よろしいですか。はい、次の方」
それで終わりでした。病院を探しだし、子供たちを連れてレントゲンの撮影に行かなければならないと思うだけで気が滅入ってきます。
その夜はただ疲れ果てて、何もせずに寝てしまいました。その後2日間は学校に出向く気が起こりませんでしたが、3日後に意を決して妻と2人で、再び校長を訪ねました。今までの経緯を話し、移民局からたくさんの提出物を求められたが、来たばかりの私たちには子供を病院に連れて行くのも大変です、校長の裁量で何とかなりませんか、わずか1ヵ月のことでもあるし、お金はきちんとお支払いしますからと目を見据えながら訴えました。これから先の手続きの煩わしさを考えたら、もし効めがあるものなら少々の寄付金を出してもいいとさえ思ったほどです。その思いが通じたのか、しばらく考えたあと、校長は「分かりました、移民局は無視しましょう。学校から手紙を出しますから、その手紙が着いたら、郵便局で経費を支払い、領収書を持って学校へ来て下さい。そのからもう一度、学校から手紙を出します。そのあとは、PTA会費を払ったらそれで完了です。それでどうですか」と言います。それなら、最初からそのように取りはからってくれればよかったのに……。
自転車
小学校の次は、足の確保です。
教育省に出かけた日に、電話で申しこんで初めてタクシーに乗りました。「公共運輸施設はほぼ無いとお考え下さい。タクシーは当てにならないし……」と聞いていましたが、充分に利用出来そうです。窓ガラスの1部が壊れていたり、ドアの把手がないこともありますが、ショナ人の運転手も人が良さそうですし、料金も格段に安いようです。車中心の白人街には、小売店はなく、広い市街地にショッピング・センターが点在しているだけです。買物にも大学にも、自転車は必要なようです。
4日目、街まで自転車を買いに行きました。マニカ・サイクルという店のフロアには、玩具や遊具と一緒に自転車が並べられており、1台1500ドル前後の値札がついていました。事情を説明すると、それなら中古車がいいでしょう、帰る時には引き取りますよと店主が薦めます。結局、中古自転車を2台買うことにしました。1台2万円足らず、性能はあまりよくなさそうでしたが、2ヵ月半、何とか持ちこたえてくれますようにと祈るしかありませんでした。
ジンバブエ大学
次は大学です。日本経由の手紙を、吉國さんの奥さんが届けて下さったのは、4日目の朝です。
「前略
92年1月27日付けの貴殿の手紙が今日私の机に届きましたので、あなたがジンバブエに来られるための手配をする時間が十分にないように思われます。どの国の場合もそうですが、外国人が入国する際には、手続きに時間がかかります。
従いまして、貴殿の計画を新しく練りなおして下さるようお手紙を差し上げている次第です。敬具
7月7日 英語科科長代行トンプソン・ツォゾォ」
既に受け取っていた「貴殿の当大学での在外研究を歓迎いたします」という英語科からの手紙を信じて日本でも手続きを済ませてやってきたわけです。無事に税関を通り抜け、既に家を借りて生活を始めています。まさかそんな手紙が日本に送られ、その手紙が転送されていようとは夢にも思いませんでした。
「予期せぬ事態」も次々と起こるし、小学校、教育省、移民局、市役所や銀行にも足を運ばねばならず、大学に出かけたのは2週目の半ばを過ぎてからで、直接、T・K・Tsodzoと書かれた部屋の戸を叩きました。授業中なのか、部屋の中に数人の学生の姿が見えます。人懐っこいアフリカ人の顔が現われました。この人がツォゾォさんに違いない。私の名前を告げると、一瞬困惑の表情が浮かぶ。きっと、7月7日に書いた手紙を思い出したのでしょう。
ツォゾォ氏は学生に何やら指示を与えてから部屋を出て、ついて来て下さいと言う。廊下を少し歩いて行くと、そこは英語科の部屋でした。事務員の若い3人のアフリカ人女性に紹介を済ませたあと、ツォゾォさんは、さあどうぞと別室に私を招じ入れてくれました。狭い部屋です。ドアには科長室と書かれていました。教育省や移民局などで鍛えられて、少しは英語に慣れてきていたせいか、ツォゾォさんの陽気な冗舌に誘われてでしょうか、私の方も言葉が滑らかに出てきました。2時間ほど話をしましたが、例の手紙を意に介している様子はありませんでしたし、手紙の遅れを詫びる言葉もありませんでした。
「来れば誰でも大歓迎ですよ」
辛うじて、大学の方も一段落したようです。
白人街
アレクサンドラ・パークは白人街で、アメリカ映画「遠い夜明け」の世界です。幅の広い道路に大きな街路樹、プールやテニスコート付きの広い家……借りた家にはプールやテニスコートはありませんでしたが、両隣にはプールが、南側の家には、夜間照明つきのテニスコートがありました。
泥棒にも3分の理と言いますが、白人街に住むアフリカ人が仮に盗みを働いたとしても、アフリカ人に五分の理があると感じました。ある場合には、9分の理すらあると思えるほど、持てる白人と持たざるアフリカ人との格差が大きく見えました。
基本的に、車中心の街で車に乗るのは白人、歩くのはアフリカ人です。80年の独立以降、白人街の家1軒分にも相当するベンツを乗り回すアフリカ人もいます。しかし、それは体制側にいる一握りの「白人化」したアフリカ人で、大半のアフリカ人には車は無論のこと、自転車を持つ余裕もありません。「ここは車(金持ち)が歩行者(貧乏人)をけ散らして走るのが普通ですから……」という吉國さんの手紙の内容は、まさにその通りでした。うっかり歩行者優先などと思っていると、大変な目に遭ってしまいます。車が最優先なのです。歩行者用の青信号の短かいこと、青になったとたんにもう点滅が始まっていると思えるほどでした。老人や身体の不自由な人は、到底信号は渡れません。乗用車に限らず、車は猛スピードを上げて走ります。広い道路を渡るのも命懸けだと最初は思いましたが、慣れるとそれほどの緊張感を持たずに道路を渡れるようになります。
歩く方も、知恵を絞ります。少し広い空き地には、蜘蛛の巣のように小道が出来ています。長い距離を少しでも縮めるためです。
ほとんどの白人は家の中に入るまで車を降りようとはしません。門まで来ると、クラクションを鳴らします。その音ですぐに庭師が走り出てきて、門の鍵を開けるのです。車を車庫に入れている間に庭師が鍵を閉めて、車庫に急ぎます。荷物があれば庭師が家の中に運びこみます。スーパーでも、買物の重い荷物を運ぶのは店員のアフリカ人で、白人は当然のように表情も変えず、わずかなチップを渡すだけです。
鍵の国
入居の日に、吉國さんの奥さんから、鍵の束といっしょに陶器の食器から銀のスプーンに至るまでの調度品の明細が書かれている用紙の分厚い束を渡されました。家主にしてみれば、独立以来風向きも変わって住みづらくなってきた今、家を貸して大金も欲しい、かといって我が家の宝ものを盗まれるのもかなわない、そんな心の葛藤に苦しんだ末に、この明細書を書いたのでしょう。家にある品物はどれも古くて趣味の悪いものばかりです。保証金2000ドルを取っていても、おばあさんの目には、日本はよほど未開で、野蛮な国と映っているようです。
鍵の束は、重いものでした。普段出入りする門、玄関、居間、台所の鍵の他にも何本かの鍵がついていて、その一つ一つが大きいのです。鍵を使って、まず玄関に入ります。ドアにはチェーンロックと鍵穴の上下に2つ止め金がついている4重式です。2畳ほどの空間に、電話台が置いてあり、左は寝室と風呂、トイレ、正面は食堂、右手は居間に通じていますが、すべての戸に鍵穴があるのです。どのドアも、内と外の両側から鍵がかけられるようになっていました。机にはどの抽出にも鍵がかかっています。台所では、冷蔵庫にまで鍵がついていました。
家の中だけではありません。街のいたるところ、鍵、鍵、鍵です。レストランのトイレではトイレットペーパーにまで鍵がかかっていました。兼好法師ではありませんが、この鍵なからましかば、と溜息が出てきました。
大学では、ツォゾォさんも大きな鍵の束を持っていました。机の鍵を開けて、抽出の中からビデオテープを取り出した時には、ビデオテープが貴重品であるのを肌で感じました。窓の鉄格子と鍵を束ねる大きな金の輪には、最後まで馴染めませんでした。
ある日、台所の戸棚を開けて、またびっくりです。透明のナイロン袋に入った30個ほどはあると思われる鍵の山が見つかったのです。台所の違う箇所にも、居間の机の引き戸の中にも、同じような鍵が入っていました。使いふるしなのか、予備の鍵なのかは分かりませんでしたが、一度にそんなにたくさんの鍵を見た経験がなかったので、何か見てはならない暗部を覗き見る思いでした。
鍵だけではありません。一番大きな寝室の厚板ガラスの一枚を除いて、すべての窓に鉄製の格子が取り付けられていたのです。監獄のようなものでなく、花柄の模様が多かったのですが、確かに格子です。外からの侵入者を防げるかも知れませんが、中からも出られません。警察とは別に、その地区全体で私設のガードマンも雇っているようですし、玄関には「24時間警備会社と契約中」の掲示もあります。敷地内には見張り役の「庭師」や「番犬」もいますし、大きな塀もあります。生き垣の下には金網も張ってあるし、あちらにもこちらにも鍵がかけられています。それでも窓には格子です。私には白い花柄の鉄格子が、穏やかな言葉を操りながら、残虐な侵略行為を朝飯前にやってのけたイギリス人入植者の分身に思えてなりませんでした。
1日24時間扱き使われて「130ドル」では、車を盗もうと思っても不思議ではありません。うまく捌ければ、何年分ものお金にもなります。自転車なら更に盗み易く、鍵など掛かっていても、担いでいけばいいのです。自転車を停めて、ちょっとよそ見をして振り向くと、自転車がなくなっていた、といっても冗談ではないほどの状況でした。大学でも状況は同じで、廊下や部屋の中まで自転車を持ち込む光景を何度も見かけました。私も買物に行ったときは、標識の鉄柱か店の横の鉄柵か金網に、大学では階段の鉄の手摺りか鉄の支柱にチェーンロックをかけましたが、わびしい思いが先に立ちました。門には電灯もブザーもありません。必要性がないからです。危険なので夜間外出は差し控えますし、仮に出掛けても客が来ても、門の前でクラクションを鳴らせば、誰かが呼べるのです。車の中にいる限りは安全なのですから。
門の前で、アフリカ人が口笛を吹く光景をよく見かけました。ブザーがないから、広い敷地内の片隅にいる「庭師」や家の中の「メイド」を呼び出していたのです。垣根越しの会話もよく見かけました。縁者でも恋人でも、中に入れてはもらえないようでした。口笛で合図を送って呼び出せても、門をはさんでの会話が許されるだけとは切ない限りです。
そんな中で生活していると、生い茂る街路樹や聳える大木は、初期の入植者たちが、理不尽な侵略で荒んだ心とアフリカ人への恐怖心を和らげるために植え付けたのではないかと思えてなりませんでした。
(たまだ・よしゆき、宮崎大学医学部英語科教員)
執筆年
2005年
収録・公開
mon-monde 創刊号 14~24ペイジ