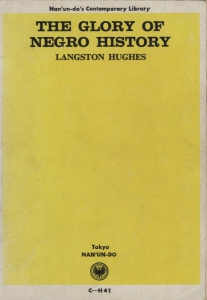つれづれに:1980年頃

「アフリカシリーズ」が放映されたのは1983年である。大学も小説のために探したので、まさかアングロサクソン系の侵略の系譜を辿(たど)ることになるとは思わなかったが、その過程で1980年頃に歴史の流れに大きな変化があるのを感じた。「アフリカシリーズ」も、その大きな流れの中にあったと思う。バズル・デヴィドスン(Basil Davidson)がタイムズの記者をしていた時期に、アフリカ大陸を駆け巡りながら考えていたことをまとめ始めた頃のビデオ映像である。イギリスで出た45分8巻の英語版ビデオシリーズをNHKが編集し、日本語の吹き替えで放映されている。編集と日本語を担当したのは国立大の教員で、「黒人研究の会」での評判はよくなかった。学生の時のゼミの教員が同僚と始めたアフリカとアフリカ系アメリカの研究をしている人たちの小さな集まりで、会誌の発行と月例会が主な活動だった。編集を担当した人は、私が入会したときに退会していた。

1980年頃の流れの変化に気づいたのは、南アフリカの歴史の全体像がぼんやりと見え始めた頃だったと思う。きっかけは、武力闘争を続けていたアフリカ民族会議の本部にアパルトヘイト政権後の相談に出かける人たちが出始めたという話を聞いた時である。最初はなんでやろ?と思っただけだったが、その疑問が頭から離れず、何かにつけて考えるようになった。
そうかあ?アメリカが遣りたい放題し難(にく)うなってきたからやったんか?
あるとき、ふとそう感じた。そう言えば、第2次大戦後はアメリカの一人舞台やったなあ。30数年経って、その構図が変わって来たんや。「アフリカシリーズ」の結論は、アフリカから絞ってきた富、今はそれを返す時に来ています、それには先進国側の経済的な譲歩が必要です、だった。デヴィドソンは、戦後アメリカ主導で再構築された、多国籍企業による資本投資と貿易の体制の詳細を、映像で見せてくれていた。特に、独立後にアメリカが公然としゃしゃり出たコンゴでは、民衆からアメリカの民主主義的に選ばれた首相のルムンバが、アメリカが立てた若き日の精悍な将校モブツに殺される生々しい映像は衝撃的だった。危機を感じたルムンバが出動を要請した欧米が資金を拠出する国連軍に見守られながらである。1995年のエボラ出血熱騒動で映像に現れたモブツは、まだ独裁政権を続けていた肥った老人(↓)だった。

東側諸国も関係してると意識したのは、1970年代に宗主国ポルトガルと闘ったアンゴラとモザンビークが独立後社会主義路線を取ったことを知ったからである。1992年に行ったジンバブエも、社会主義路線を取っていた。ハラレ空港で、グレートジンバブエ(↓)行きのプロペラ機の写真を子どもたちがカメラを構えたとき、突然兵士が現れて撮影を止められた。知り合ったショナ人の子どもさんが通う田舎の小学校の校長室に案内されたとき、正面に大統領ムガベの大きな写真が飾られていた。ハラレのスーパーに行ったら、まったく品物がない棚がいくつもあった。日本では見かけない光景だった。ジンバブエは宗主国イギリスとも東側の中国やソ連とも国交があるので、意識しないと社会主義路線だと気づかないくらいである。

1990年くらいから15年間ほど、学生や留学生や教員といっしょに週に一度体育館でバスケットボールの試合(↓)をしていた。中国の留学生が多かった。中国では体育館が使えないと言っていた。中国は産業化の最中だったので、工学部と医学部が同じレベルだと聞いた。工学部博士課程の国費留学生が、中国の状態を資本主義と呼んでもらっても、共産主義と呼んでもらってもどっちでもいいです、と言っていた。1972年に日中の国交が回復したあたりから、西側諸国の企業や投資家が進出し、市場も開放されて、西側の車や家電製品や日用品が大量に出回っていたからである。もちろん、コンピューターやスマートフォンも、西側と競いながら普及させていった。少なくとも、中国人留学生が共産主義の国から来ていると普段意識することはなかった。

シャープヴィルの虐殺(↓)で非暴力を捨てて武力闘争を始めたとき、アパルトヘイト政権は欧米と日本の支援のもと軍事力、警察力を総動員してアフリカ人勢力を抑え込んだ。1964年にリボニアの裁判でマンデラなどが終身刑を言い渡されたときには、指導者層は殺されるか、投獄されるか、亡命するかしかなかった。地上から指導者が消えた。そのとき、正式に外交官扱いでその人たちを受け入れたのが、ソ連とキューバである。もちろん、武器の供給も両国が主体だ。武器の製造は自国の産業を潤(うるお)す。第2次大戦では核兵器も使われたのだから、重火器や戦闘機などの規模や質も格段に上がり、軍需産業は利潤の高い重要な産業になっていたのである。

多国籍企業による資本投資と貿易の体制を再構築したアメリカは大戦で疲弊した宗主国を尻目に大手を振って、鉱物資源の豊かなコンゴと南アフリカの経済競争に参入した。南アフリカには、おまけに入植者が築き上げた安価なアフリカ人労働者を無尽蔵に使える短期契約労働システムまでついている。IT産業や家電製造に必要なレアメタルや金やダイヤモンドを安く掘り出して手に入れていたのである。もし、東側諸国にから武器を供与されているANCが、最先端の近代兵器を備える白人の軍隊と正面衝突すれば、南アフリカは廃土と化す。余り汁を吸い続けるアメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本などのアパルトヘイト政権の盟友は、搾り取る主体をなくしてしまうのである。だからこそ、1980年代に入ると、アメリカやヨーロッパ諸国はザンビアのANC本部にアパルトヘイト政権後の相談に行き始めたのである。そして、1980年代の後半には、ベルリンの壁が崩れて東側も自由経済に向けて舵取りを余儀なくされた。経済レベルの低い国の人たちは、当然、豊かな西側諸国にどっと流れてゆく。東ドイツの人たちが西ドイツにながれるのは、貧しい田舎から仕事のある都会に人が流れるのと同じ原理だろう。

ヨハネスブルグ近くの金鉱山
1990年にはマンデラたちは投獄された時と同じ法律のまま無条件で釈放された。そして、4年後、マンデラが大統領になり、アフリカ人政権が誕生した。白人政府が、アフリカ人政権と引き換えに、アメリカや日本と協力して搾取構造を死守したのである。1980年頃の流れの変化は、まさにこの帰結のための予兆だった。

1990年2月12日に釈放された時のマンデラ夫妻のBBC映像
次回はアフリカシリーズである。