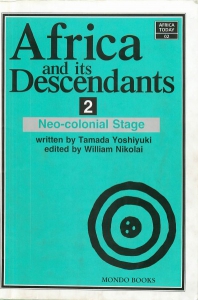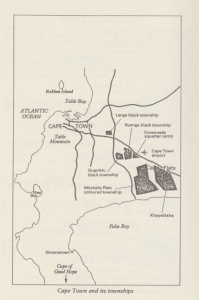アフリカとその末裔たち 2 (1) 戦後再構築された制度⑧経済的依存
『アフリカとその末裔たち2』
アフリカ大陸に変革の風が吹き荒れたとき、欧米の指導者は直接の政治支配をこれ以上は続けられないと悟り、より容易く、より効率的に第三世界から搾取し続けるにはどうすればよいか、また中国で起きたような社会主義化を防ぐにはどうすればいいのかを考え始めました。植民地支配に代わる新しい形の支配形態を新植民地主義と呼び、エンクルマは大きな脅威と考えました。その実態について次のように述べています。
クワメ・エンクルマ(小島けい画)
開発途上国の問題で外国からの干渉をやめさせるためには、名目が何であるにしても、新植民地主義を研究して理解し、公表して積極的に対抗する必要があります。新植民地主義者が使う手口は巧妙で変化に富んでいるからです。その人たちは経済分野だけでなく、政治、宗教、イデオロギーや文化の領域までも操作します。
アジアやアフリカ、カリブ海地域や中南米の元植民地地域の戦闘的な人たちと向かい合うようになって、帝国主義は単に戦略を変えました。帝国主義は何のためらいもなく、国旗も、嫌われていた植民地官僚もなしで済ませます。つまり、旧植民地に独立を与え、開発のための「援助」がそれに続くというわけです。しかし、そのような言葉を装って、以前はあからさまな植民地支配で達成していた目標を、今度は数え切れないほどたくさんの方法を考え出して達成するのです。それは、「自由」について語りながら同時に植民地主義を恒久化しようとするそういった現代的な企みの総体で、
今では新植民地主義として知られるようになりました。
新植民地主義者の先頭に立ったのは、中南米で長い間その力を行使してきたアメリカ合衆国です。アメリカは当初は手探りで、ヨーロッパ大陸の大半の国が戦争でアメリカに借金をした第二次大戦後は確かな足取りで、ヨーロッパに対抗しました。それ以来、ペンタゴン(米国国防総省)は方法論的には完璧に、細かい配慮まで配りながらその支配力を強化し始め、その具体的な例が世界の至る所で見受けられるようになりました。」
[『新植民地主義:帝国主義の最終段階』(NEO-COLONIALISM: The Last Stage of Imperialism, 1965)]
新植民地主義(NEO-COLONIALISM)
アフリカ諸国に与えた独立はアメリカには脅威ではありませんでしたが、共産主義の影響による社会主義化だけは容認出来ませんでした。アメリカ資本はラテンアメリカの場合ほどアフリカに興味はなかったものの、アフリカに対するアメリカの投資は著しく拡大して行きました。第二次世界大戦の後、資本は多国籍化されました。ヨーロッパの経済は大戦によって崩壊して全体的な力が低下し、アメリカの大企業が国境を越えて著しく成長して拡大しました。多国籍企業の多くは、アメリカの企業です。
大戦以来、第三世界でのアメリカの政策は、旧植民地列強と競い合うなかでアメリカの経済的な影響力を増加させました。自国を大事に思うアフリカ人に対する支援は、影響力を持つための戦略の一部でした。アメリカは将来のアフリカ人指導者に対する奨学金や自国を大事に思うアフリカ人に対する経済援助という形を取りました。その狙いは、独立後に親米派の指導者を養成することでした。
アメリカは独立を認められたアフリカ人政権に援助をしましたが、それはひとえに経済分野で旧植民地列強に取って代わり、共産主義の影響を防ぐためでした。アメリカはアフリカでのヨーロッパの役割を引き継ぎ始めました。
多くのアフリカ諸国が独立を認められ、自分たちの国旗を手にしましたが、同時に、経済の依存関係を継続させました。労働力の植民地分配方式は引き継がれ、主要な経済分野は外国人によって支配されました。生産物の多くは輸出品として売られ、その輸出品の大半は石油、銅、綿、珈琲、カカオ、落花生のような加工していない原料でした。アフリカの輸出の5分の4以上は、ヨーロッパ諸国向けでした。アフリカの輸入品の4分の3は、そういった国からでした。西ヨーロッパが依然として優勢でしたが、アメリカ合衆国と日本もまた、主要な貿易相手国でした。アフリカ諸国間内では、ほとんど貿易は行なわれませんでした。
アフリカの原材料の取引で暴利を貪ったのは大手の民間会社で、商取引の機密は固く守られました。多国籍企業が近代産業の技術開発を統制しました。多国籍企業は多くの国で産業を私有化し、製造分野を殆んど独占しました。しばしば民間会社は、経済の分野で支配的な地位を保持しました。独立騒動で、旧宗主国以外の資本にも門戸が開かれました。アメリカ合衆国は資本を増やし、日本と西ドイツもアフリカ資源の新しい争奪戦に加わりました。
1960年、南アフリカのアパルトヘイト体制に対抗してパンアフリカニスト会議(PAC)のメンバーが積極行動に出たとき、警察は無差別に発砲してあのシャープヴィルの虐殺の悲劇をまねきました。国連が非難決議をして経済制裁を始めたとき、日本と西ドイツはその機に乗じて第二次世界大戦で途切れていた通商条約を再締結しました。日本の場合、八幡製鉄(現在の新日鉄)が翌年に5年の長期契約を結んでいます。見返りに白人政府は居住地に関する限り白人並みに扱うという名誉白人の称号を日本人に与えて貿易の便宜をはかりました。その辺りを境目に日本は高度経済成長期に入り、南アフリカは指導者を失なって長い暗黒時代に入りました。南アフリカの人たちはこの時の日本政府の対応を裏切り行為と捉えています。以降、現地の安い労働力を使って生産したトヨタや日産などの工業製品を売りつけ、ウランや金やダイヤモンドやレアメタルなどの原材料を輸入して莫大な利益を得てきています。
ソブクエを筆頭に警察署に向かうデモ隊:ベンジャミン・ポグルンド『ロバート・ソブクウェとアパルトヘイト これ以上美しく死ねるだろうか』より
大企業が輸出用に加工する農産物もあります。自動車だけでなく、ラジオや冷蔵庫などの組み立て工場が多くのアフリカ諸国で見られるようになりました。その組み立て工場は、安いアフリカの労働力を利用するために、現地につくられています。
今日、殆んどすべての西側先進諸国は、何らかの形でアフリカに投資しています。(宮崎大学医学部教員)