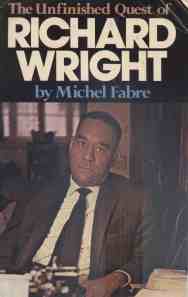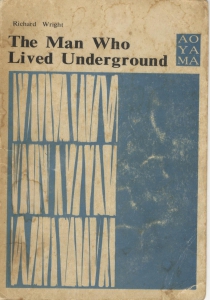ほんやく雑記(6)イリノイ州シカゴ
概要
ほんやく雑記の6回目で、リチャード・ライトの「地下に潜む男」の擬声語表現について書きたいと思います。(6)で「地下に潜む男」を読むようになった経緯、(7)で「地下に潜む男」が掲載された雑誌「クロスセクション」(CROSS SECION)、(8)で作品の中の擬声語表現に取り上げるようになった経緯、(9)で作品の中の擬声語表現、について書いています。今回は「地下に潜む男」を読むようになった経緯、です。
本文
ほんやく雑記の6回目です。
前回は詩人ポール・ダンバーの詩「愛しいわが子よ」の表現の仕方と、時代背景の理解の大切さについて書きましたが、今回はイリノイ州シカゴが舞台の「地下に潜む男」の擬声語表現について書きたいと思います。(写真1:リチャード・ライト)
「地下に潜む男」(“The Man Who Lived Underground”)はアフリカ系アメリカ人作家リチャード・ライト(Richard Wright、1908-1960) が書いた中編小説で、1944年に「クロスセクション誌(Cross-Section)に収載されています。死後出版された『八人の男』(Eight Men, 1966; 晶文社、1969年)にも再録されていますが、1956年には既に、ハックスリー(Aldous Leonard Huxley, 1894-1963)、トルストイ(Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828-1910)、モーパッサン(Henri René Albert Guy de Maupassant, 1850-1893)、サロヤン(William Saroyan, 1908-198)の小説と並んで Quintet – 5 of the World’s Greatest Short Novelsの中に取りあげられる程の評価を得ています。
1973年に ミッシェル・ファーブル氏(Michel Fabre)の伝記『リチャード・ライトの未完の探求』(The Unfinished Quest of Richard Wright、写真2)が出版されてからは、この小説が従来の人種問題から脱皮しようとした試みとして注目され、後続のアフリカ系アメリカ人作家ラルフ・エリスン (Ralph Ellison, 1914-1994) などにも少なからず影響を及ぼした作品として再評価されました。
物語は、無実の罪を押し着せられた主人公が偶然に逃げ込んだ下水溝での様々な体験を経て警察に自首した時には既に真犯人は捕えられており、逆に警官に気狂い扱いされた挙旬、最後は元の下水溝に葬り去られてしまうという割り切れないものですが、作品が評価されたのは、主人公の<地下生活>を通して人種によって差別されたアフリカ系アメリカ人こそが日常性の中で見失いがちな物事の本質に気付き得る有利な立場にいるという点を描き出そうとした視点や、主人公が相手に気づかれない有利な立場から垣間見る様々の「現実の裏面」のスリリングな展開や、音や色に関する鮮やかな表現に負うところが大きいと思います。今回は中でも音に関する擬声語表現をほんやくと絡めて書こうと思います。
「地下に潜む男」を読んだのは大学の英語の時間で、たぶん青山書店から出たテキスト(写真3)で、だったと思います。大学に入ったのは学生運動が国家権力にぺちゃんこにされた翌年の1971年で、浪人しても受験の準備が出来ないまま結局はうやむやに心の折り合いをつけて、家から通える神戸市外国語大学のえせ夜間学生になりました。
えせは、神戸市役所や検察庁などの仕事を終えてから授業に出る前向きな「同級生」に比べて、という意味です。検察庁の「同級生」は「神戸の経済を二度失敗した」末に入学したそうですが、「ワシ、今日はやばいねん、昨日取り調べたやーさんに狙われるかも知れへんから」と帰り道に言っていました。高校も定時制(4年間)だった「同級生」は住友金属で働く好青年で、何百万か貯めて着実に生活している風に見えました。若くに人生を諦めてしまって大学の空間を余生としか考えていない身には、ずいぶんと希望に満ちた大人に見えました。もちろん、僕と同じようなえせ夜間学生で、定職は持たず、昼間の運動部に混ざって活動しているものもいましたが。
学費は年間12000円(昼間は18000円)、月に1000円、定期代も国鉄(現在のJR)と阪急(電鉄)を合わせても1500円ほど、朝早くに1時間ほど配っていた牛乳配達が月に5000円ほど、学費はそれで充分にまかなえていたように思います。もっとも自分から進んでやった牛乳配達ではなく、母親がやっていたのを見兼ねてやるようになっただけでしたが。
入学した年、中央以外では学生運動の残り火が燻っていたようで、神戸大でも神戸外大でもヘルメットを被った学生が拡声器を持って「われわれは・・・・」と、がなり立てていました。僕には入学式も無意味なので通常なら出ることはないのですが、一浪したあとよほど気持ちが縮こまっていたようで、つい入学式に出てしまいました。奇妙な入学式で、図書館の階段教室で始まって学長という人が挨拶を始めたとたん、合唱部とおぼしき人たちが初めて聞く校歌らしき歌を歌い始め、違うサイドでは拡声器を持った学生が「われわれは・・・・」とまくし立て始めていました。座っている学生は僕のようにへえーと感心しているものもいれば、四方に野次を飛ばしているものもいました。
その後、授業はなく毎日のようにクラス討議なるものが強要され、ある日学生がバリケードをして学舎を封鎖しました。しばらくして機動隊が突入して「正常化」されたようでした。70年安保の学生運動では国家体制の再構築というような理想論が取りざたされたようですが、覚えている限り、マイクから聞こえて来て耳に残っているのは、たしか、学生食堂のメシが不味いから大学当局と交渉して勝利を勝ちとろう、そんな内容だったと思います。中央では負けたので、地方では部分闘争をということだったんでしょうか。
昼間のバスケット部といっしょに練習をしていましたが、運動部はバリケードが張られているときも、中に入れて練習もやっていました。マネージャーの女子学生も、ヘルメットを被って封鎖に参加している学生の一人で、後に退学したようなことを聞きました。
学生側についた七人の教員は、最後まで学生側についていたようです。後にゼミの担当者になった教授もその中の一人です。十年ほどかかって仕上げた翻訳原稿を投げ入れられた火炎瓶で焼かれたそうですが、また同じ年月をかけて翻訳出版したという話も聞きました。その担当者の追悼文が僕の記事の第一号です。→「がまぐちの貯金が二円くらいになりました-貫名美隆先生を悼んで-」(「ゴンドワナ」3号8-9ペイジ)→「がまぐちの貯金が二円くらいになりました」
第二次大戦前の神戸外事専門学校が戦後の制度改革で神戸市外国語大学になったそうで、教員の中には今までやらなかった分野を専門にする人たちもいたようです。小西友七という人の黒人英語などもそんな分野の一つで、他にも西洋のバイアスがかかっていないアフリカ系アメリカやアフリカの名前を学内ではよく見かけたように思います。
おそらくそんな流れの中で、英語の時間にアフリカ系アメリカ人作家リチャード・ライトの「地下に潜む男」の教科書を読むことになったのだと思います。
続きは、次回に。
次回は「ほんやく雑記(7)イリノイ州シカゴ2」です。(宮崎大学教員)
執筆年
2016年
収録・公開
「ほんやく雑記⑥『 イリノイ州シカゴ 』」(「モンド通信」No. 96、2016年8月3日)
ダウンロード
2016年8月用ほんやく雑記6(pdf 469KB)