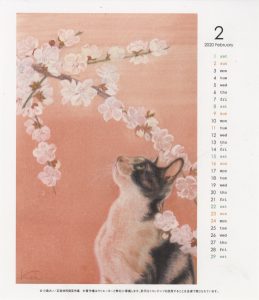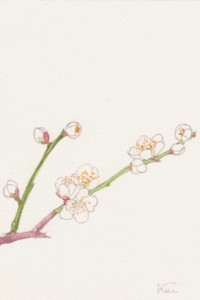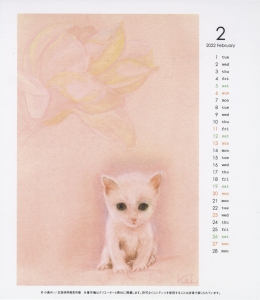昨日ほど風はなく、きれいに晴れていたので気持ちよく散歩が出来た。天気ニュースでは上が9度下が零度とあったが、昼間は陽ざしのお陰て体感温度は高めの感じだった。歩くコースの紹介を始めたのが6月の末だから、もう半年以上が過ぎたことになる。→「歩くコースは・・・」(2021年6月30日)今回は歩くコースの追伸1、木花駅と道路工事についてである。何日か前に歩くコース1→「歩くコース1の①」(2021年7月5日)を散歩しているときに、帰り路で木花駅の外壁を塗り直している場面に遭遇した。その日は「そんなに痛んでないのになあ」と思いながら通り過ぎたが、次の日になぜ塗り直したかが判明した。巨人のキャンプ入りだったのである。→「歩くコース1の⑧」(2021年7月24日)
昔から野球に関心が向かなかったのでそれほど影響はないが、人と車が多くなるのは少し鬱陶しい。県道を渡るときに待たされることも多くなる。10年ほど前に、医学生の交換留学制度でタイとアメリカから医師を招待して症例報告(ケーススタディ)や病院での臨床実習(ベッドサイドティーチング)をやってもらった時に、いつも通りに半年以上も前に普段使っている宮崎観光ホテルの予約しようとしたが既に満室だと言われた。メディア関係の人たちが宿を押さえていたからだそうである。イチローが来たと言われる年は、特にひどかった。

今回はコロナの第6波で感染者が急激に増えている最中である。キャンプ誘致は仕方がないにしても、有観客には「宮崎の首長たちは、住民たちに自助の新型コロナ対策を訴えまくってるけど、プロ野球のキャンプは認めて、県外からどっさり人を入れるんだから、めちゃくちゃな県だよ。民度の低い県だから仕方ないけどね。」、「無観客を支持しなかった河野知事。キャンプクラスターで増えまくったらどう責任をとるか?が楽しみだし、これが原因で落選となってもおかしくない。武井氏や戸敷氏に続くかね?子供たちには午前授業、学級閉鎖、部活停止とかしといてこれはあんまり。県民には我慢を、だけどキャンプは有観客。>矛盾だらけですよね、子供達の大切なものをこれ以上奪わないでいただきたい。県民に不要不急の外出ヲ控えろって言ってるのに有観客ってどういう考えなんだ?宮崎県知事の考えは?」(Yahooのコメント)などの反対意見も多い。もちろん、「えっ!キャンプは有観客なん?うーっわ!行きたい!無観客やろなって思ってたから行く予定してなかったけど、これから宿探しして宮崎行く段取りする!」と言う人たちもいる。何が正しいのか誰にもわからないようだし、先行きもまだ見えそうにないが、自分の身は自分で守るしかないようである。
歩くコースの途中の道の工事中が続いているが、舗装済みの個所も増えて来たとところを見ると、全面開通の日もそう遠くはないらしい。

元々木花駅は東側に正面入り口があり、西側からはプラットホームには上がれず、踏切を渡って細い道を通り駅入り口まで行って列車の乗り降りをしていた。サンマリーン球場が出来た後、整備が進められた。駅からの道は立ち退き交渉がうまく行かなかったのか、ことのほか時間がかかっていたように感じた。駅から県道までの道が開通したあと、東口駅前のロータリーと東西の自転車置き場など、次々と工事が進んだ。学園木花台から南の県道への道路の工事が済めば、その付近一帯の整備工事も完了しそうである。

西口にはバス停とタクシー乗り場、東口にもタクシー乗り場が出来ている。大学の統合後、宮崎駅から清武経由大学病院行きのバスがタウンセンターまで延長されていたが、駅の整備に伴って更に一部が駅の西口まで延長された。宮崎駅から木花経由のバスも大学病院まで延長されている。一時間に一本あるかないかのダイヤだから、通学通勤に使うと料金も高いし、よく待たされる。しかし、列車もそうだが、利用できるのと出来ないとでは大きな違いがある。大学に来た三十数年前に比べれば、利用できる店も増えたし、駅も整備され、VISAカードが使える店が増えて、だいぶ住みやすくなった。