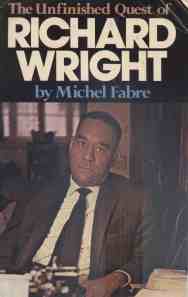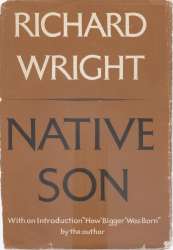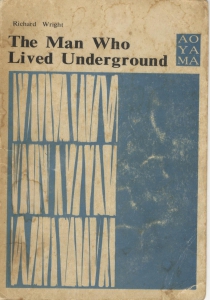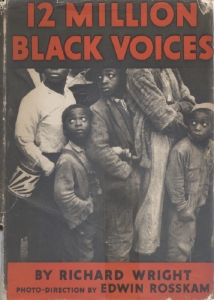概要
ほんやく雑記の8回目で、前回の書いた「地下に潜む男」が掲載された雑誌「クロスセクション」(CROSS SECTION)を手に入れた経緯、に引き続いて、作品の中の擬声語表現を取り上げるようになった経緯について書いています。
『リチャード・ライトの未完の探求』
本文
ほんやく雑記の8回目です。
今回は先ず、なぜ擬声語表現なのか、です。(写真:ミシシッピの会議でのファーブルさん)ライトの伝記『リチャード・ライトの未完の探求』(The Unfinished Quest of Richard Wright, 1973)を読んだときに、本を読みながら感じた思いと、自分のレベルも知りたくてファーブルさんに手紙を書きましたが、そのときに日本語訳して手紙に入れました。
僕はずっと書こうと思って生きて来た人間ですから、文学の研究そのものも作品論や作家論にも極めて懐疑的です。人の好みや受け取り方も人それぞれですし、そもそも字や語に対する感覚などは努力して何とかなるものでもありません。努力は誰でもやりますが、絵が描ける、ダンスが踊れるなどと同じで、語感や文章に対する感性などは努力でなんとかなるものでもありません。
必要性もあって、好きだった人に聞いたリストを元にアメリカの小説を読み始めました。最初に読んだのはセオドア・ドライサー(Theodore Herman Albert Dreiser)の『アメリカの悲劇』(An American Tragedy, 1925)、タイトルだけ聞いて図書館から借りてきたハードカバーはなんと1026ページもの大作で、辞書を引きながら読むのに2か月ほどかかりました。(このとき、辞書などひいとったら本なんか読まれへんと身に染みました。)それから、ナサニエル・ホーソン(Nathaniel Hawthorne)の『緋文字』(The Scarlet Letter, 1850)、ウィリアム・フォークナー(William Cuthbert Faulkner)の『八月の光』(Light in August, 1932)を読みました。どれもアメリカ文学では有名で、フォークナーなどは1949年度にノーベル文学賞を受賞しています。1985年にライトの死後25周年を記念して国際会議がミシシッピ州のオクスフォードにあるミシシッピ州立大学でありましたが、集まったのは1500人ほど、前年にあったフォークナーの会議に集まったのが一万人だったそうですから、オクスフォードで過ごしたフォークナーは、アメリカ人好みの作家なのでしょう。
読まなくては、という思いで読んだせいもあったかも知れませんが、どの本もまったくおもしろくありませんでした。その反動もあったのでしょうか。『アンクル・トムの子供たち』(Uncle Tom’s Children, 1938)、『アメリカの息子』(Native Son, 1940)、『ブラック・ボーイ』(Black Boy, 1945)など、ライトの本は鮮烈でした。ことに『アメリカの息子』はからだがばりばりでいうことをきかなかったのに、興奮して震えながら二日ほどで一気に読んだ記憶が鮮明に残っています。
『アメリカの息子』
僕の好きなファーブルさん(ライトの伝記『リチャード・ライトの未完の探求』の著者で、本を読んで感激し、自分の書いたものを英訳して送った翌年にミシシッピの会議でお会いし、7年後にジンバブエの帰りに家族といっしょにパリの自宅にお邪魔しました。ソルボンヌ大学や街並みを案内して下さり、訪ねて来られた同僚の世界的に有名な経済学者といっしょに子供たちとトランプをして下さいました。)が「地下に潜む男」を高く評価しておられた影響もありますが、「地下に潜む男」もなかなかの作品でした。(ハックスリー、トルストイ、モーパッサン、サロヤンの小説と並んでQuintet-5 of the World’s Greatest Short Novelsの中に取りあげられています。)
もちろん、ファーブルさんがおっしゃったように、この中編小説が従来の人種問題を中心にしたテーマを一歩踏み越えようとしている作品として、或いはエリスン(Ralph Ellison, 1914-)を筆頭にする後続の作家に少なからず影響を及ぼした作品として評価されるようになったのは確かですし、そういった評価が、作品の中に示された人種問題の枠を越えたより深いテーマの重みや、差別される黒人こそが日常性の中で見失いがちな物事の本質にいち早く気付き得る有利な地点に立っているというライトの視点の鋭さに負うところが大きいのですが、それらがライトの紬ぎ出した言葉による表現によって裏打ちされていることも忘れてはいけないと思います。作品をぞくぞくしながら読んだのは、その時は意識してなかったと思いますが、言葉や表現にも魅せられていたのでしょう。
次回はそういった表現の中でも、作品の中の主要な場面で使われた擬声語表現について書きたいと思います。
日本語訳→“Some Onomatopoeic Expressions in ‘The Man Who Lived Underground’ by Richard Wright”
次回は「ほんやく雑記(9)イリノイ州シカゴ4」です。(宮崎大学教員)
「モンド通信」は途切れましたが、「続モンド通信」に連載を再開するつもりです。
→「『続モンド通信』について」(2018年12月29日)
執筆年
2016年
ダウンロード
2017年5月用ほんやく雑記8(pdf 343KB)