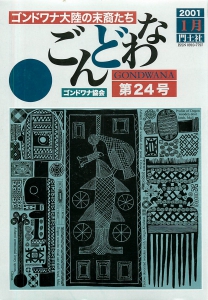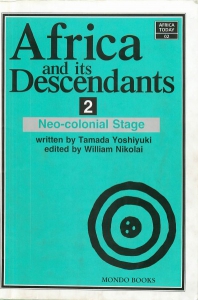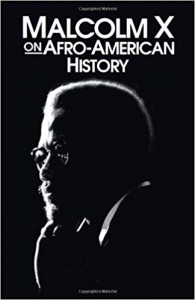概要(作業中)
2003年11月23日(日)に宮崎大学医学部すずかけ祭で開催されたシンポジウム「アフリカと医療」で行なった講演の記録で、国際保健医療研究会の葛岡桜さんがして下さったテープ起こしの原稿に手を加えたものです。テープ起こしの原稿を見ながら、我ながらあまりの日本語のひどさに悲しくなりました。美しい日本語の会会員などと称していることに後ろめたさも感じました。そして、普段の話し言葉も、話し方も考えなくてはと思いました。これからは、美しい日本語の会準会員を名乗ります。
当日は、時間の関係で、当初予定していた内容を変更して話をしました。当日の内容に手を加えたものがこの「アフリカのエイズ問題―制度と文学」で、その前に、事前に配られたパンフレットの表紙とその内容を載せました。
予定していた原稿につきましては、ずいぶんと遅くなりましたが、手直しのうえ「アフリカとエイズと文学」と題して、近々ホームペイジに掲載の予定です。
ご一緒した山本さんとムアンギさんの話は、ホームペイジには掲載できませんでした。
(パンフレットの表紙)
|
第28回すずかけ祭医学展 宮崎大学医学部 シンポジウム「アフリカと医療」 ~世界で一番いのちの短い国~
●国際医療ボランティア・派遣医師 山本敏晴 「世界で一番いのちの短い国」 …本当に意味のある国際協力とは?…
●四国学院大学社会学部教員 Cyrus Mwangi 「アフリカにおけるエイズとセクシュアリティ」
●宮崎大学医学部英語科教員 玉田吉行 「アフリカのエイズ問題―制度と文学」
日時 2003年11月23日(日)1時~4時 主催 宮崎大学医学部国際保健医療研究会・英語科 場所 宮崎大学医学部臨床講義棟205教室
主な対象者; 発展途上国での医療活動やボランティア活動などに従事することも含め、その分野に深い関心のある医療関係者、医療系学生、将来そういう分野で活動したいと考える中学生や高校生、および、国際保健活動に関心のある方々。◆
|
本文(写真作業中)
アフリカのエイズ問題―制度と文学 玉 田 吉 行
玉田と申します。よろしくお願いします。旧宮崎大学と旧宮崎医科大学が(10月に)統合して、こちらは清武キャンパス、向こうは木花キャンパスと呼ばれています。実際には(統合後の最初の授業が始まるのは)4月からなんですが、(今は)こちらの方で英語を担当しています。4月からはさっきお話にありましたように、アフリカ文化論とか、南アフリカ概論とかの名前で、(木花キャンパスの方でも、主題教養科目の)授業を担当する予定です。
今回のシンポジウムは、わりと準備していたんです。一応、こういうタイトル(『アフリカのエイズ問題―制度と文学』)で、初めに少し挨拶をして、それからアフリカのエイズの現状を少しお話してと、本当はそういうつもりでした。
病気でもそうですが、(たとえば)喉が痛いとか、それは(それで)原因があるわけです。西洋医学の場合だと、対症療法で熱を下げましょうとか、薬を与えましょうとか、まあ、そういうことになるわけですが。本当は、免疫力があれば、病気にならない確率が高いわけで、「ちゃんと良く寝ましょう」、「規則正しい生活をしましょう」、「むちゃくちゃ飲まないようにしましょう」、そういうことが一番大事だと思うんですが、そのためにはやっぱり何が原因かというのを知らなければなりませんし、出てきた症状から、病気の場合だと、診断しなければいけません。
実際に、エイズの惨状は、今日ムアンギさんがお話されましたように、大陸が滅びるかもしれないという可能性を含んでいるほどだと、ぼくは思っているんですが。それは、HIVだけが原因というわけではなくて、それを生み出した原因というのはもっと大きな所にあると思うからです。
ぼくは、たまたま読んだアフリカ系アメリカ人の作家リチャード・ライトの祖先が奴隷貿易で連れてこられたという縁で、アフリカに辿り着きました。その人はアメリカから追われるような形パリに渡った人で、常に「自分は何か?」を問い続けていました。生まれながらにして、肌の色が黒いというだけで疎外されていましたから。同じような意味で、ぼく自身もいつも「自分は何か?」を問い続けていました。生まれてくるとわけのわからない親でしたし、子供もたくさんいて貧乏だったですし、大学入試はすべって行く所はないし、学校へ行っても腹が立つし、地域社会にも腹が立つし。そんな状況でしたから、自分の居場所というか、つまり疎外された状況のなかで、自分はいったい何ができるんだろうか?とか、どうしたらいいんだろう?とか、そんな事ばかり考えていました。リチャード・ライトがアフリカの問題を取り上げていたのがきっかけで、僕自身も自然にアフリカについて考えるようになりました。
ですが、そこで考えて、(ぼくはここの英語の授業でもアフリカの話をずっとしてきたんですが。ここに来て16年になります。その前の5年間も含めますと、20年以上にもなりますが。)最後にたどり着いた地点は、山本さんとか、ムアンギさんとはだいぶ違うとは思うんですが、なんかため息しか出ないというか、希望的な観測が全くもてないというか。それもありますし、それから実際に長いあいだ授業をしていますと、この部屋でもそうですが半分以上寝ている中で授業が行われていますし、(学生は)あまり来ません。ほかの大学でもそうですが。以前いました大阪工業大学とかだと、授業の一番初めに出席をとって、ぱっと見上げたら前半分全部いないんですよね。それで、おかしいなぁと思って、出席を後からとるようにしたら、最初あまり来なくて、終わりの方に(たくさん)来ましたね。(非常勤としてご一緒した)ムアンギさんは、アルファベットで名前書けない奴にどないして単位だすねん、とぼやいてましたね。大阪工大は、(偏差値でいうと)関関同立(関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学)の次くらいだと言われている大学です。(ムアンギさんも僕も)ひどいところで授業をやっていたわけです。ここでも実際に授業をやってみますと、(学生は)授業には来ませんし、(来ても)半分くらいは寝ていますし。今、(その時の学生が)二人くらい(会場に)来ているんですが、その学年のときの話です。ぼくは一年間一生懸命話をしてきて、(それでも大体半分くらいは寝てましたけど)すごく頑張って(まとめの話を)やりだしたのに、ふと見ましたら前の方で漫画を読んで、パンを食べている学生がいるんです。腹が立って、こんなやつは絶対に医者にしたらあかんと思って、授業やめて出てきたんです。医学部でさえそうですから、別に医学部でなくてもいろんなところでそんな状況があるのが実際のようです。授業中に夢中になって携帯電話をしている人もいますし、すこし進歩的な話をしたら寝てしまいますし。ま、そういうのが現状のようです。
どちらかと言いますと、(授業で)アフリカのことをしながら日本にいて、その狭間に立って、その希望を託すべき、有能な若者と実際に授業をやりながら、その合間に立ってみますと、いろんなことが見えてきて、やっぱり最終的に、授業の最後で「いや申し訳ない、もうため息しか出ない」という感じになってしまうんです。でも(そのような状況でも)20年間ずっと話し続けてきたのは、そこにしか希望はないんじゃないかなと思っているからなんです。ですから、今日もそうですが、やる事に対しては、やはり準備もしますし、それなりにやります。ですが、人のためにやっていますと、例えば、「なんで授業に出てこれんのや?」とか、「なんで寝てしまうねん?」と思うかもしれないんですが、でもその人がいつかこの話を思い出して、医者になったときに、ああ、あんなことをいってたなと思ってくれること…まぁこれは実際にあるんですが…そのほうが一番大事で、ひょっとしたらそういう希望があるのかもしれません。でも、実際にはそんなに希望があるわけでもないし、だけどやっぱり喋り続けないといけない、みたいな(感じです)。そういう狭間で、ぼくは毎日少しずつ…。あ、もちろんこのシンポジウムはなかなか大変で。最初、授業でアフリカの話をしていたときに、山本さんの本(『世界で一番いのちの短い国』)を課題図書で紹介しました。一年生の石崎さんが、私知ってるよ、みたいな感じで。すぐメールを打って山本さんに「講演をお願いします」と頼んでみたら、山本さんからすぐ返事が来て、「それじゃ玉田先生に相談してみてください」、と(いうことになりました)。それで(講演が実現しましたので)、今日はぼくとムアンギさんは二人とも、付け足しみたいなものです。国際保健医療ですから、山本さんの話に関連して話をするので、ムアンギさんも来ませんかみたいな感じで電話したわけです。で、はじめの話では、前半、半分以上(山本さんに)やってもらって、ムアンギさんとぼくとで残りの時間を分けるつもりだったんですが、もうほとんど終わりであと(残り時間が)5分くらいしかない。(一同笑)で、一応ぼくがここで今言いましたように、普段考えてきて授業の中で言っているような話をした後、実際に1992年にジンバブエに行ってみて、「ほー、やっぱり同じやった」みたいな話をして(と考えていました)。
実際には、ぼくらは大学にいる(知的な欲求を満たしやすい環境にいる)わけですから、ほかの人の事(実際には行けない外国のことなど)を知るために、例えば、山本さんの話を聞いたり、ムアンギさんの話を聞いたり、そういう部分も大事ですが、制度(についてだけ)じゃなくて、実際に生活している人のことを書いているとか、文化(について書いてる)とか、そういうものを読めればそれにこしたことはないと思います。例えばエイズの話でも、1991年に、エイズが問題になり始めた時期のケニアの混乱した状況を描いた小説をゲテリアという作家が書いています
ぼくは今、(本学の)2年生で授業をやっているんですが、実際に授業やっていましても、2年生は忙しいからと、あんまり来ませんし。授業では、そんな深刻な問題を話していても、半分くらい寝ていますけど。
そういう風な本の内容をみてみますと、例えばケニアの場合など、実際に今日お話しましたように、植民地(支配)で、それから新植民地(支配)で、その侵略は今も続いてるんですが。ですから、極端に言いますと、日本のように、中産階級がいるわけではなくて、一握りの貴族と西洋の人たちが手を結んで長い事(新植民地体制を)引きずってるわけで。で、ごく一部ですよね、その(支配階級に属している)人たちは。その人たち以外はほとんど全て貧乏人で。そういう構図の中でHIVにこの人達もたくさん感染しているんです。いっぱい。その小説は、『ナイス・ピープル』というタイトルですが、こっちの方の人たち…治すものの側(の人口)がものすごく減ってきてるわけで。こっち側(支配される側)の方は、そこにムアンギさんが持っていらっしゃいますが、メジャー・ムアンギという人が書いている本 [『最後の疫病』(2000年)] では、そのHIVに関して、一般的な人たちが西洋文明を、受け入れるか – つまり、HIVは精液や血液で感染しますから、原因がわかっているはずですよね、だけど実際には抑えられないみたいな、それのせめぎ合いみたいなところが書いてあるわけです。その中で、どういう風な感じで人間の尊厳を保つかみたいな、そういう部分も書いてあるわけです。
僕自身はもともと、文学を志して、30ぐらいで高校(の教員)を辞めて、それから書いたり読んだりするには大学しかないって思って、5年間ほど(通算にしたら9年位)浪人してるんですが。ですから、ここが初めて(の大学)で、それ以来で、16年目になります。そういう感じで生きてきました。
文学は、生き死にの問題が優先される場合…戦争をやっているときには文学は(直接には)役に立たないかもしれませんが、やっぱりものすごく大きな役割を持っています。根本的なことになるんですが、人間が人間に何か教えられるかと言うのは、非常に疑問で。その事を一年間ほど考えて、棒に振ったことがあります。結論は、やっぱり分からないというか。例えば今授業で先生をやっていますけど…何年か前に生まれてきて、先に少しだけ多く覚えて、それを言ってるだけですから。そういうことを考えていましたから、中学や高校では、こいつ何言ってんねん、そんなもん教科書に書いてあるやないか、といつも腹立てていたんです。だけど、そういう側面はどうしてもあるように思えますので、人のために教えてやるというのは、少し違うかな、と思っています。そんなことを考えながら、もんもんと授業をやっているんです。
ですから、ここで一番いいたかったのは、やっぱり、そのアフリカの問題を授業の中で取り上げているのも、大学の時代がやっぱり大事(な時期)だと考えているからだ、ということです。なぜかと言いますと、知的な欲求は、(今は物が豊かで、なんか無理やり勉強やらされて、その中でそがれてる部分もものすごい多いと思うんですが)本来は、何か知りたいとか、何かやってみたいというところから始まります。知的な欲求が、人間にはすごくあると思うんです。だから、そういう欲求を満たすには、(大学に)入ってきて、その中でいろいろ話を聞いて……。そのときに、人生が方向付けられる事があるかもしれないですし。ですから、そういう意味では、ぼくは大学入ってきた人たちに、できるだけ、「今まで持ってきた価値観は大丈夫か?」みたいな揺さぶりのための材料として、アフリカの事をずっと話したりしてきたんですが。ぼくがその中でよくするのは、14、15世紀ぐらいから、中国から持ち帰った火薬を武器に、西洋社会が銃(武器)を作って、それから侵略を始めたという話です。当初は、東アフリカを略奪したりしていましたが、もっと恒久的に略奪しつづける方法はないかと考え出して、結局は片方(の手)に聖書、もう一方に銃を持って侵略を始めたんです。南アフリカなんか、オランダ人に侵略されたんですが。1972年にマジシ・クネーネいう南アフリカの詩人が来て、多分あのときだと、日本の文学者の野間宏とか針生一郎とか、その辺の人に案内してもらったと思うんですが。その人がオランダの出島を見て、「日本人てえらいなぁ」と言ったそうです。実際に、南アフリカはオランダ人に侵略されましたからね、「(オランダ人を出島に閉じこめた)日本人はえらいなあ」という意味でしょうが、そういうことを、ぼくは雑誌で読んだことがあります。実際に、南アフリカはそういう形で侵略されていったんですよね。そのうちに、今度は人間を売買し始めて、ものすごく片一方(西洋)は富んだわけで、その資本で、今度はもっと儲ける方法を考え(始め)たのです。つまり、奴隷貿易は、大きな損失(リスク)もありますよね。(逃亡とか反乱とかの)リスクを伴いますから。だからもっと効率よく儲ける方法、つまり今まで手でやっていたことを機械でやるようになって。ものすごくたくさん作って、それを売り始めたわけです。売るための材料をもっと手に入れるために、植民地化を始めます。その勢いはとても大きかったわけです。そのときにあつかましく、たくさんの植民地を取ったのは、英語をしゃべっていたアングロ・サクソン系の人達です。特に文明のあったケニア、ガーナや、ナイジェリア、南アフリカ、ジンバブエなど。とにかく、文化の発達していた所ばかり狙ってたわけです。その人達は自分の言葉を押し付けました。押しつけられた国は数多く、(今も経済的に結びつきが強い)Common Wealth countriesは、確か51か52あると思いますが。その人達は、(国として)英語をしゃべるようになってるわけです。ですからジンバブエに行った時もそうでしたが – ジンバブエはショナ人がほとんどなんですが – それが、キャンパス内で(ショナ人同士が)英語でしゃべっているのです。みんながそうなんです。自分の子供に母国語のショナ語を教えないで、英語を教えている人が増えているようです。名前もAlexや、そんな名前ばっかりです。そういう傾向は顕著で、インドもそうらしいです。小田実さんがインドで行われている英語支配は、だいたい形を変えた侵略じゃないかのかねとあるインドの友人に尋ねたら、何を言ってる、侵略そのものだ、と言い返されたと言ってましたが。そんな状況になっているようです。
いまさっき、山本さんがシェラレオネ(の平均寿命が)34歳とおっしゃったんですが、何日か前、インターネットで調べてみましたら、ジンバブエの場合、36.5歳でした。1995年の記事ですが、イギリスのインディペンダントという新聞を授業で読んだことがあります。その記事は、2010年くらいまでには平均寿命が55歳くらいから40歳くらいに落ち込むだろうと予測していました。 55歳(という元の数字)が、そんなに高くないとぼくは思いますけれども。ここ(提示したグラフ)でみてもらったら分かりますが、ムアンギさんのケニアも、南アフリカも、45歳ぐらいです。日本は80歳こえていますから、このあたりのところは、(原因が)絶対あると思います。そういうふうなことを考えると、形態は変わっても(侵略は)ずっと続いているのです。
実際に知的なものを考えて世の中をなんとかしていかないといけないという大学生でさえも、知的な好奇心が薄い(人も多い)ですし。それから、政治とか、社会的なことをあんまり考えません。今ぼくがお話したようなことが、その侵略の延長だとしますと、アメリカなんかずーっとそれを続けているわけです。その国が国連を無視して、イラクを侵略した事を、ぼくらは止めることもできなかったわけです。そういうふうなことに対して、そういうことを考えもしないと言いますか。その辺りのところに対してぼくはどういう風に話しかけたらいいのか。すごく、とまどいながら。それでもやっぱり言わないといけないな – そういうところで過ごしていますね。
南アフリカに関して言いますと、ジンバブエで…ジンバブエに行って、家を借りました。今言いましたように(ジンバブエには)貴族と貧乏人しかいませんから、ほとんど借家はないんですが。でも、たまたまみつけてもらって。10万円の家賃ですと言われて、行きましたら、500坪ですよ、これくらい。ちゃんとガーデン・ボーイ付きでした。知り合って、いろいろ話を聞きましたら、その人の給料は4千円くらい(ひと月ね)。子供たちも(その人の子供たちと)一緒に遊んだのですが、遊びに使ったボールがひとつ5千円くらいでした。実際はそんな中で生活をしていて、その人の田舎のほうに行ったんですが、(写真をうつしながら)こういうところに住んでいて、ジンバブエに関しての新聞にあったように。大体、田舎のでは女性が農作業と、それから老人や子供の世話をしてるんですが。HIVで、みんな倒れていくんです。
ヨーロッパ人がやって来たときにどんな侵略の形態を取ったかと言いますと、つまりアフリカ人の土地を奪って課税したんです。課税されて、その現金を払わなければなりませんから、みんな出稼ぎに出ざるを得ませんでした。たいていは鉱山か、農場か、白人の家か、工場か。たいがいそれは短期契約…つまり(労働単価の)一番安いパートタイムです。男ばっかり集めてコンパウンドという、まぁ、日本で言うたこ部屋ですね。そこに売春婦が入りますから、そこで感染します。こんどは、1年に2回ほど田舎に帰って、奥さんにうつすんです。アフリカの場合、特にそれが極めて多いのです。英語では「マイグラント・レイバー」、いわゆる季節労働とか、出稼ぎ労働とかいわれます。そういうシステムがあるわけです。それは今さっきも言いましたが、実際に、ぱっと略奪するのではなくて、永遠に略奪し続けるというか。だって、奴隷みたいに、大の大人が24時間中拘束されて、ひと月4千円ですよ。今(写真に映っている)ここで子供達が遊んでいましたが、ここはスイスのおばあさんが持ってるところで、そこの人達(ショナの人たち)は子供が遊びにきても、ぼくらがたまたまいたので子供たちもいましたけど、普通はそこに入れてもらえなくて。家族とほとんど一年離れて(暮らしているんです)。(田舎に)帰ったら、家も大きく土地もあるんですが。だから、そういう状態ですよね。それは、いってみれば奴隷と一緒じゃないですか。経済の配分は、システムは……。それが基礎なんです。あまりそういうことは言われないんですが、安価な労働力によって、人が生産したものを掠め取ってるわけです。実際に例えば、ここ(臨床講義室)の電力でも、そうですよね。南アフリカとか、ナミビアとかその辺りの安い労働力で、(ウランが)掘られて運ばれ、(日本では)安い電力が供給されているわけです。そういうことを考えてきますと、ぼくらは、完璧に加害者なわけです。そのことを山本さんも、ムアンギさんも言われてましたが。それが問題なのです。何が問題かというと、(たいていの人が)その事にも気が付いていないことなんです。
そんなことを考えてみますと、自分の自己存在も肯定できるのかなと思います。やっぱり生きる自信が持てないと思いながら。(授業で)そんな話をすると半分くらい寝てしまいます。もう、ひどいのになると、授業終わった後、あー、なんてあくびして。あーもう(受験勉強で詰め込んだ)英語も忘れてしまった、なんて言って。授業終わった直後に言われますと、さすがに、がっくりときますが。でも、現実なんですよね。
アパルトヘイトがあったときに、(ヨハネスブルグの)日本人学校に(取材に)行って、(朝日テレビの)「ニュースステーション」がインタビューをして、日本人学校の校長は(管理職だから)、「いやー、もう危険だから、(安全確保のために、もっと)フェンスを高くしないと」、と言ったんですが。せめて、「将来を託す子供達だから、知らない所に来てぼくらにできないことをやってもらいたい」くらいは言ってもらいたいですよね。企業の特派員の子供達が大きな顔をして、「あの人達とは生活が違うから雇ってあげなくちゃいけないですよね」と言うんです。「せっかく一緒に友達になったんだから、もう帰りたくない」くらいは、せめて(その子供たちに)言って欲しいですよね。
良く分かりませんが、現状がどうであれ、受験勉強で疲れて、何もものを考えないようになって大学入ってきたとしても、例えばぼくらみたいに授業する立場の人間が、「もうしゃーないから」といって諦めてしまう、そうなったら終わりじゃないですか。そう思っているんです。しかし、今の状況でぼくらが何かが言えるかといったら、いやー、あまり自信がなくて、何かぶつぶつ言いながら、「ぼくは英語嫌いです」とか、「外国人が苦手です」とか言いながら、最後にぼそっとと「いやー、ため息しか出ない」としかいえないんです。ですが、人のためだけにやっているわけではありませんので、ぼくは、最初にも言いましたが、自分が読んだり書いたりする空間を求めて大学にも来ましたし、授業をもつことで実際に生活もしているわけですから、その責任として、やっぱり、それでもきちっと準備をして、ぶつぶつ言いながらでも、しゃべりかけないといけないと思っています。とくに、医者になる人が多いですので、ぼくは、「医者になる人が風邪をひいていてどうする?」と、いつもそれだけは言うんです。(高校の教員をやっていたときにもあったのですが)ここ(宮崎)の人なんかもそうですが、自分はたばこを吸いながら、「お前たち、たばこ吸うな」、なんて生徒指導でやっている人がいますけど、そんなの(元々)信用できるわけがありませんから。医者(の場合で)もそうだと思うんです。だから、今はどうか分かりませんけど、いつか気が付いて、(患者の)いのちを預かるときになって、山本さんもお話されましたように、勉強するのは大事だということを思い出して、自分のために考えてもらえればいいなぁ、と思います。
今回、たまたまこういう形でやったわけなんですが、アンケートの中にもお書き下されば、今日お話できなかったこととか、興味がおありの方に、ホームペイジとか或いは印刷物とかを通して、連絡が取れると思います。
もう13年にもなりますが、アパルトヘイトが廃止される前の年に、この下の105(臨床講義室)で、南アフリカの作家をお呼びして講演会をしたとき、またやったらどうだって言われたんですが。もし、機会があれれば、誰かをお呼びしてまたやろうかな、と思っています。予定していた事が充分にはできなかったんですが、わざわざ足を運んで下さって、有り難うございました。
執筆年
2004年
収録・公開
出版(私製)