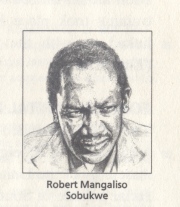概要
松山市内で弁護士をされている薦田伸夫さんが誘って下さった「アサンテ・サーナ!(スワヒリ語でありがとう)自由」という催しの一環として、1989年7月1日に、愛媛県の松山東雲学園百周年記念館で講演した「アパルトヘイトの歴史と現状」をもとにしてまとめたものです。その催しでは、他に、アパルトヘイト否! 国際美術展・写真展、エチオピア子供絵画展、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ等の資料展示、「源の助バンド」によるレゲエのコンサート、「アモク!」の映画会が、主に一日、二日の両日にわたって行なわれました。
本文
アパルトヘイトの歴史と現状
ズールー人か「ズールー族」か?
南アフリカは南半球にある、日本から遙かに離れた遠い国なのですが、いろいろな意味で、日本と深く係わっています。
日本にいる外国人の方から、近ごろよく苦情を聞きます。先日も、新聞の投書欄で次のような記事を見つけました.熊本県の九歳になる女の子のものです。
わたしは、今まで、いろいろなさべつをされてきました。でも、いちばんいやだと思ったことは「外人」といわれることです。かみの毛の色がちがったり、名前が長かったり、そういった少しのちがいで「外人」という言葉をみなが口にするのです。
わたしは「外人」という言葉があったってかまいません、怖、も、それを、いじめたり、からかったり、さべつとして使われるのは、大へんかなしいものです。
宮崎で知り合ったスウェーデンの女性は、日本入は興味本位で、なぜ?なぜ?と聞きたがり、ひどい人になると、なぜ金髪なのか、なぜ目が青いのか、と本気で質問する、と憤慨していました。どうして、日本では小さいころから、家庭で、世の中にはいろんな人がいることを教えないの、この頃よく言われている「国際化」っていったい何なの、と悲しそうに言っていました。これは、単に「ガイジン」という言葉だけの問題では決してないのです。その言葉の背後にひそむ、ものの考え方や、そんな言葉を生み出す、ものの見方こそ、本当は大切なのです。
新聞やテレビなどでよく見かける「族」という言葉についても同じことが言えます。「最強の部族と讃えられるマサイ族」とか、「最近南アフリカでは部族問の対立が激しくなって・・・」とかの「族」ですが、新聞やテレビだけでなく辞書などでも「族」が使われています.特に、文化人類学や言語学ではその傾向が強く、学者の中には、そんなことは言葉の問題にすぎないと言う人もいます、でも、果たしてそうでしょうか。
南アフリカのズールー人の中で自分たちのことをズールー「族」と呼ぶ人は、まずいないと思います。「部族」が、「未開で、野蛮な」という軽蔑的な意味を含んだ、西洋人の作った言葉だと知っているからです。
アフリカは発見されたのか?
アフリカの歴史と西洋人のアフリカ観
伝統的な西洋の歴史では、アフリカやアメリカはヨーロッパ人によって「発見された」とされていますが、今日ではそんなこととを本気で信じる人はいないでしょう。第二次世界大戦後の考古学や歴史学の研究で、アフリカにもヨーロッパに勝るとも劣らない文明が幾つもあったこと、アフリカ文明がヨーロッハ文明に多大な影響を及ぼしたこと、18世紀後半までは、社会的、経済的に見て、ヨーロッバよりも優れていた地域がアフリカには多くあったことなどが明らかにされています。
何年か前、NHK海外ドキュメンタリーシリーズで、イギリス人歴史家バズゥル・デヴィドゥスンがレポーター役の、イギリスMBTV製作「アフリカ8回シリーズ」という番組が放映されたことがあります.その一部を引用しながら、アフリカの歴史と西洋人のアフリカ観について、少し触れたいと思います。
14世紀、15世紀頃の東アフリカの海岸地域は、遠くインドや中国とイスラム世界、それにアフリカ内部を結ぶ黄金の交易路として非常に栄えていました。文化水準も高く、交易を結んだポルトガル人は品物が粗悪だという理由で、貿易を断わられたりしています。そんな中にキルワという街がありましたが、その島は、ある日廃墟となります。その出来事について、デヴィドゥスンは次のように語ります。

バズゥル・デヴィドゥスン
・・・その年バスコ・ダ・ガマが率いる小さなポルトガル船三隻が、歴史上初めて、喜望峰を回りインド洋へと入ってきました.ここにヨーロッパ人の侵略が始まります。ポルトガルヘ戻ったガマは旅先で目にしたものを報告しました。そして、七年後の1505年、今度は前より大きな武装した船団が水.平線に姿を現わしたのです。それに同行したドイツ人ハンス・マイルは、彼が目撃したことをこう書いています。
ダル・メーダ提督は軍人14人と6隻のカラブル船を率いてここへ来た提督は大砲の用意をするように全船に命令した。7月24日木曜未明、全員ボートに乗り上陸、そのまま宮殿へ直行し、抵抗するものはすべて殺した。同行した神父たちが宮殿に十字架を降ろすと、ダル・メーダ提督は祈りを捧げた。それから全員で街の一切の商品と食料を掠奪し始めた。2日後、提督は街に火を付けた。
(「第4回、黄金の交易路」)
キルワのこの虐殺事件あたりを境に、東アフリカ一帯の交易網はずたずたにされるばかりか、アフリカはヨーロッパ人の飽くなき侵略の餌食となります。と同時に、それまであったアフリカ人とヨーロッパ人、黒人と白人の対等な関係は崩れ去り、奴隷貿易や植民地政策を正当化しようとする西洋中心の考え方が捏造されていきます、同シリーズに、19世紀の思想家や探険家について紹介した次のような箇所があります。
……ドイツの高名な哲学者フリードリッヒ・ヘーゲルもこの点では同じでした。ヘーゲルはアフリカを訪れたこともなく、アフリカ人についてもそれほど知らなかったはずですが、1813年こう言っています。
「アフリカは幼児の土地である。自我の意識に照らしだされた、歴史のない、夜の闇に閉ざされた土地である。歴史とは無縁の土地なのである。」
へーゲルだけではありません。こうした見方は広く行き渡っていたのです。アフリカ探険家で、風習や吾語もかなり研究していたイギリス人リチャード・バートンでさえ、こう言っています。
「黒人の研究は、未発達の精神の研究にほかならない。黒人は文明人に近づこうとしている野蛮人、というより文明人が退化したもののように見える。無知蒙曚、大人になり切れず堕落する、幼稚な人種に属しているらしい。」
やはり、有名な探険家サミュエル・ベイカーは、ナイルの水源を求めてアフリカの奥地を歩き、こう書いています。
「アフリカの未開人の人間性は、非常に未熟で、まさに野獣同然、ただ貧欲で恩知らずで自分本位なだけだ。」(「第1回、最初の光り、ナイルの谷」)
何ともひどいことを言ったものですが、その後の歴史を見れば、それも充分に納得がいきます。奴隷貿易による莫大な富の集積によって産業革命は促進され、さばききれないほど多くの製品が生み出されます。そして、余った製品を売りさばく市場としての、アフリカ争奪戦が始まり、徐々に資本は集中していきます。帝国主義国家による植民地支配が確立し、やがて第一次世界大戦、第二次世界大戦へと向かいます。二つの大戦、いわゆる「先進国」の殺し合いによって国力が低下したお陰で、アフリカ諸国の大半は、名目上一応、独立は果たすものの、戦後の国力の回復に従って、再び搾取される構造が復活します。ヨーロッパ列強にアメリカや日本も本格的に加わった形での、新植民地支配です。そのような状況を考えるとき、「アフリカシリーズ」の締め括りにデヴィドゥスンが提言した次の言葉は、傾聴に値するでしょう。
奴隷貿易時代から植民地時代を通じて、アフリカの富を搾り取ってきた「先進国」は、形こそ違え今もそれを続けています。アフリカに飢えている人々がいる今、私は難しいことを承知で、これはもうこの辺で改めるべきだと考えます。今までアフリカから搾り取ってきた富、今はそれを返すときに来ているのです。(「第8回、植民地支配の残したもの」)

南アフリカは、今だに植民地支配の続く、アフリカ大陸最後の「白い牙城」です。日本とも非常に深く係わっている限り、知る知らないとに係わらず「南アフリカ」の問題は、私たちの問題でもあります。そして、何よりも大切なのは、南アフリカの提起する問題は、実は、私たちの心の問題なのです。そういう視点から南アフリカの歴史を見ていきたいと思います。
南アフリカか「南アフリカ共和国」か?
南アフリカの歴史
オランダ人の到来
最初に南アフリカに立ち寄ったヨーロッパ人はポルトガルの航海者達ですが、移り住んだのはオランダ人でした。1652年に、オランダの東インド会社のヤン・ファンリーベック一行は、南アフリカ南端のケープに上陸します。本国と植民地インドネシアとの問に、船に食料や水を補給できる中継基地を築くためでした。そして、現在南アフリカ第二の大都市となっているケープタウンがつくられます。植民地でなく、あくまで安定した補給基地を求めた東インド会社が「入植者」を認めたために、「宗教改革」で国を追われていた「新教徒」たちがヨーロッパから続々と流れてきます。「入植者」はオランダ人農民が中心で、オランダ語で「農民」という意味の「ボーア」と呼ばれます。そして後に、「アフリカに根ざした白八-という意味の「アフリカーナー」を名乗るようになります。現在、「アフリカーナーは南オランダのオランダ語を根幹とした一種の混成語「アフリカーンス語」を使っていますが、その言葉は英語と並んで公用語とされています。
ヨーロッバ人が移住を開始したとき、ケープ地帯には既に、狩りをして暮らしているサン人と牧畜を営んでいたコイコイ人が住んでいました、移住者たちはサン人を「ブッシュマン」、コイコイ入を「ホッテントット」と蔑み、戦争をしかけました。コイコイ人は屈伏し、広大な土地と家畜を奪われ、より抵抗を示したサン人は、大多数が虐殺されます。
女性不足から、移住者はコイコイ人や、労働力として輸入されたマレー人たちと結婚して、今日の「ケープカラード」と呼ばれる混血の人たちが生まれます。大体、18世紀末までに、先住のアフリカ人コサ人などと武力衝突を繰り返しながら、移住者たちは現在のケープ州東端にあるイーストロンドンあたりにまで達します。しかし、ケープ地方の支配を完成させるのは、後から乗り込んでくるイギリス人達でした。
イギリス人支配・アフリカ人制圧
市場争奪戦での激しい競争相毛フランスのケープ進出がアジアとの貿易を脅かすことを懸念したイギリスは、1795年大軍を送り込んでオランダ人を降伏させ、ケープを占領します、一度ケープをオランダ人の手にかえすものの、ケープの重要性を再認識したイギリスは1805年に植民地政府を樹立し、様々な政策を推し進めます。もはや奴隷を必要としなくなっていたイギリスは、1833年奴隷解放令を出しますが、これは奴隷に労働力を依存していたボーアに大きな打撃となりました。イギリスの支配を不満とするボーアは翌年、家財道具一式を牛車に乗せ、大挙して内陸部に向けて大移動、いわゆるグレート・トレックを開始します。その人たちは内陸部を経て、翌年には、一部はインド洋岸のナタール地与に、他は現在のジンバブウェとの圏境辺りに達しました。しかし、ナタールには強大なズールー王国があり、当然、ボーアはその人たちと衝突することになります。1838年12月16日、ズールー軍とボーアは、コモ川流域で決定的な戦いをします。この時、コモ川は牛車で円陣を組んだボーアに殺された三千人のズールー兵の血で真っ赤に染まったと言われます。それが、ブラッド・リバーの戦いですが、アフリカーナーにとってその日は勝利の記念日として、いまも国祭日となっていますが、アフリカ人にとっては、屈辱を記念し、解放を誓う日となっています,
戦いには勝ちましたが、ナタール州はボーアのものとはならず、1834年イギリスに併合されてしまいます。
ケープ州でコサ人と衝突したボーアは、こうしてナタール州でズールー人と戦います。ナタールをイギリスに併合されたボーアは再び内陸に移動し、トランスバール州でンデベレ人と、オレンジ白由州ではソト人とぶつかります。イギリスに追われた形のボーアが行く先々で、先住のアフリカ人を次々と痛めつけてゆくわけです。
アフリカ人は、ボーアに痛めつけられただけではありません。その後、ナタール併合を果たしたイギリスに、コサ人が居住地区のシスカイとトランスカイを、ソト人がバソトランドを、ズールー入がズールーランドを、次々に併合されてしまいます。ズールー人が「イサンドルワナ」の戦いでイギリス軍を壊滅させたことは有名ですが、アフリカ人たちは、結局、近代兵器の前に屈してしまいます。1854年頃には、南アフリカは4つの州に分割され、イギリスが海岸線の恵まれた地域ケーブ州とナタール州を領有し、ボーアに内陸部のオレンジ自由州とトランスバール州での自治権を認める形で、一応は落ち着きます。

しかし、1867年にダイアモンドが、1886年には金が、それぞれボーアの自治領内で発見されたことによって、様相は一変します。
イギリス人とボーアは金とダイアモンドの利権をめぐって争いました。それがアングロ・ボーア戦争です。結局、またイギリス人の勝利に終わりますが、この戦いでイギリスは今後の植民地支配に、ボーアとの共存が不可避であることを悟ります。そして1910年、イギリスの自治領として南アフリカ連邦が誕生しました。
イギリス本国は南アフリカに移住した白人に全権を委譲したわけですが、その時以来、その人たちには帰るべき本国がなくなります。後に、大半のアフリカ諸国は独立を果たしますが、南アフリカは、独立時に白人に帰るべき本国がないという点で、ほかのアフリカ諸国とは少し違う道を歩むことになります。
イギリス連邦の成立・リザーブの設定
当初からイギリス人とボーアは絶えず抗争を繰り返しますが、アフリカ人を搾取するという点では利害が一致しました、両者の協力体制は、常に多数派の黒人の脅威にさらされていた少数派にとっては、必然の結果であったと言えます、
手を組んだ白人側は、アフリカ人搾取を基盤に体制固めをはかってゆきます。1913年、原住民土地法を制定します。それまで実際に行なわれていた慣習を法制化したものです。その内容は、「リザーブ」なるものを設定して、入口の七パーセントに及ぶアフリカ人を全国土の僅か7.3パーセントからなるリザーブに住まわせるというものでした。カラード人口の多いケープ州は例外とされましたが、白人はリザーブ内で、黒人はリザーブ外での土地売買を禁止されました。リザーブは大体が散在する不毛の土地でしたから、つまり、早い話が、手を組んだ白人が黒人から奪った土地を自分達のものだと法律で決めてしまったわけです。
その後、ケープ州の例外がはずされ、リザーブが13.7パーセントに広げられた形で、その法律は1936年に原住民信託土地法と名前を変えて今日まで生きています。
リサーブは、後にバンツースタン(1972年まで)、そしてホームランドと呼ばれるようになりますが、これがアパルトヘイト体制の基本となります。
農場では引き続きボーアがアフリカ人をこき使いますが、鉱山でも大規模な形でアフリカ人労働者が搾取されます。フォアマンと呼ばれる管理者には、労働争議の恐れの少ないヨーロッパ人が雇われたうえ、白人の突き上げで、アフリカ入は熟練技術を教えられない状態に置かれました。つまり、それはアフリカ人の賃金が極力抑えられたことに他なりません。コンパウンドと呼ばれるタコ部屋に押し込められ、季節労働昔としての厳しい労働を強いられたアフリカ人は、信じられないほどの低賃金で働かされました。
アフリカ人の抵抗・ANCの誕生
勿論、アフリカ人はただ黙っていたわけではありません。1882年12月には、百人のアフリカ人労働者がキンバリーで賃上げを要求してストライキを行なっています。1920年代の初めにはかなり大規模なストライキが敢行されますが、ことごとく力で制圧されます。
1912年、アフリカ人の土地権利の擁護と政治的権利を求めて、抵抗組織南アフリカ原住民民族会議が結成されます。1925年に名前がアフリカ民族会議と改められ、ANCと呼ばれますが、様々な人種グループから成る民主的で平等な統合国家実現をめざす、最も伝統的な抵抗組織となります。
当初は、イギリス本国に代表を派遣して誓願したり、大衆に直接呼びかけたりしますが、やがて大規模なデモやストライキなどを組織して大衆を動かすようになっていきます。
国民党政権の誕生
抵抗運動が高まるなか、アフリカ入労働者の犠牲のもとに、南アフリカの工業化は進んでいきます。ことに、製造部門は第二次世界大戦中に飛躍的な伸びを示します。国内産業を軍需産業に切り替えなければならなかったイギリスやアメリカが、連合国側についた南アフリカにも消費物資を求めたからでした。より多くのアフリカ人労働者を必要とした国内産業は、賃金の引き上げによってアフリカ人労働者を獲得しようとしましたが、安価なアフリカ人労働者に依存していた白人の農場経営者や鉱山所有者の反対にあい、逆に安定したアフリカ人の安価な労働力を保証する、国に規制された労働力市場を要求されました。アフリカ人労働者にその地位を脅かされつつあった白人の賃金労働者も、鉱山資本の拡大によって貧弱化していたボーアも、いわゆるプア・ホワイト層は人種差別を前面に掲げ、白人の特権を保証することをうたう国民党に傾いていきます。第二次大戦でナチスドイツに傾倒した国民党の掲げる人種差別主義こそが、社会の低辺層に沈みつつある自分達を救ってくれる唯一の道だと信じたからです。1948年の白人だけの選挙では、国民党が第一党となり、ここにアパルトヘイト政権が誕生します。
アパルトヘイト政策
アパルトヘイトは「分けること」という意味のアフリカーンス語で、「白人とアフリカ人が完全に分かれて生活し、それぞれの特性を発展させる」という未来図を描く国民党の政治スローガンです。しかし、白人杜会の繁栄がアフリカ人労働力の基礎の上に成り立っているかぎり、完全な分離は不可能であるのは明らかです。
アパルトヘイトは、小さなアパルトヘイトいわゆるプティ・アパルトヘイトと大きなアパルトヘイトいわゆるグランド・アパルトヘイトに分かれます。
プティ・アパルトヘイトは、ホテルやバスなどにおける白人と白人以外の人々との差別政策であり、グランド・アパルトヘイトは少数派の白人が大部分の上地を占有し、多数派のアフリカ人を散在する不毛の地に隔離することによって市民権を奪い、アフリカ人の安価な労働力を確保しようとする政策です。「白人地域」で働くアフリカ人は、「パス」の所有を義務づけられ、携帯しない場合や記載事項に不備な点が認められる場合は、罰金、懲役、強制労働を強いられるほか、エスニック・グループ別に割り当てられた「ホームランド」に強制的に送還されます。1965年から75年までの10年問に、年平均50万人の人が逮捕されたといいます。(パス法は86年7月に廃止されましたが、かわって全国一律の新たな身分証明書が交付されています。)また、労働許可証も必要とされ、仮に許可証があっても、余剰労働力として、政府の一方的な方針で強制送還される場合もあります.「遠い夜明け」でケーブタウン郊外のクロスローヅという「不法居住区」が強制的に撤去される凄まじいシーンがありましたが、あれは余剰労働力を取り払うためになされたものです。政府側のラジオ放送では、衛生上の見地から、という名口でしたが。
アパルトヘイト体制とは、つまり、少数の白人が大部分の土地を占有し、残りの散在する不毛の土地にアフリカ人を締め出したうえ、その労働力だけは利用して、南アフリカの豊かな富を独り占めにする国家形態です。しかも、その体制を守るための、自分たちに都合のよい法律を制定し、体制を維持するためには武力行使をも辞さないというファシズム体制なのです。
国民党が政権をとるまでは、現に法律はあったものの、締めつけはさほど強くなかったようで、たとえば、ケープタウン生まれの「カラード」作家アレックス・ラ・グーマは、小さい頃、黒人と同じ街に住んでいたといいます。集団地域法はあっても、実際にはそれほど厳密に実施されていなかった地域もあったということです。(本誌8号24ペイジ)

アレックス・ラ・グーマ(小島けい画)
しかし、国民党が政権の座についてからは事態がにわかに厳しくなります。
会議運動・反逆裁判
次々と法律がつくられ、アパルトヘイト体制が強化されるにつれて、アフリカ人の抵抗運動も次第に高まっていきました。五十年代初めには、ANCを中心に、ガンジーに率いられたインドにならって「不服従運動」が展開されますが、厳しく弾圧されて運動は中止せざるを得なくなります。
しかしすぐ後に、アフリカ人は今度は白人、インド人、カラードと連帯して会議運動を展開します。そして、1955年、ヨハネスブルグ近郊のクリップタウンに様々な人種グループの代表が集まって国民会議が開かれ、自由憲章(フリーダム・チャーター)が採択されます。
解放後の、国の展望を示したもので、次のような書き出しで始まります。
自由憲章
われわれ、南アフリカの人民は、すべてのわが国土と世界に宣言する、
南アフリカは、黒人と白人を問わず、そこに住むすべての人々に属し、如何なる政府も、全人民の意志に基づかない限り、その権威を正当に主張することは出来ない、と。
自由憲章白体は短いものですが、人種の平等、少数派の尊重、基本的人権の確立、アパルトヘイトの廃止、土地の再配分などをうたっており、その後の解放闘争の指針となります。
会議運動の高まりに対して、政府は弾圧を強化、1956年12月に、闘争の指導者156名を一斉に逮捕し、全員を反逆罪で起訴します。いわゆる反逆裁判事件ですが、政府は、結局、反逆罪を立証しえず、16日後に全員を保釈し、61年3月までに全員に無罪を言い渡さざるをえませんでした。
大変な事態であったはずですが、ネルソン・マンデラを初めとする指導者層は、一堂に会せたことをむしろ感謝して、刑務所内で討議や勉強会を開いたといわれます。経済的に苦しく、広い国内を自由に動き回れる余裕のないひとが大部分だったからです。当時、ケープタウンの左翼系週刊紙「ニュー・エイジ」の記者をしていた先述のアレックス・ラ・グーマは、ヨハネスブルグに赴いたあと「皆それぞれに大変だが不平をこぼすものは誰一人としていない」という記事で、裁判での指導者たちの息吹を伝えたほどでした。(本誌9号29ペイジ)
この運動で示された多人種統合国家の実現がANCの基本的な路線ですが、58五年に、白人の手を借りないアフリカ人だけによるたたかいを掲げたパン・アフリカニスト会議(PAC)が、ロバート・ソブクウェに率いられて、ANCと袂を分かちます。
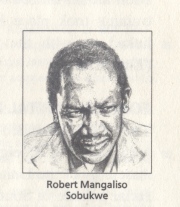
ロバート・ソブクウェ(小島けい画)
アフリカ人自身による政府をめざすソブクウェたちの考え方は、「遠い夜明け」で紹介されたスティーヴ・ビコをはじめとする若い人たちに引き継がれていきますが、理由が何であれ、この解放運動の分裂は、南アフリカの歴史にとっては大変悲しいことでした。
ソヴクウェは、60年3月に、ヨハネスブルク近郊のオルランドで、自らのパスを焼き捨て裸足で警察本部の中に入っていったと言われます。
シャープヴィル事件・共和国宣言・武力闘争開始
ソブクウェが消えた一時間後、PACの呼びかけで、パス法の廃止、最低賃金の引き上げの要求を掲げたデモが、やはりヨハネスブルク近郊のシャープヴィルで行われました。
それに対し、警察側の連絡ミスなどもあったようですが、最終的には無防備なデモ隊に警察が無差別に発砲する、という事態になりました。当局は即死者69名、負傷者百86名と発表しましたが、目撃者の証言によれば犠牲者の数は実際にはもっと多かったと言われます。当時、報道規制は敷かれていませんでしたから、この事件はショッキングな「虐殺事件」としてただちに世界中に伝えられ、非難の声が高まりました。そして、今回の中国「天安門事件」のように、非難の声は制裁へと動きます。

シャープヴィル虐殺事件
ますます激化する黒人の抵抗に対して、政府は非常事態宣言を発令して弾圧に乗り出す一方、経済制裁に動きだした各国に使節を送り友好関係の継続を訴えました。
この時、日本政府は、国際世論に反して「国交の再開と大使館の新設」を約束し、翌年の一月には通商条約を結びました。白人政府はこれに対して四月の議会で、日本人を「居住地に関する限り白人なみに扱う」ことを表明します。よく言われる「名誉白人」ですが、1920年、30年代に既に使われていたその称号は、貿易関係が親密になっていくにつれて実を伴う「不名誉な」称号となっていきます。
六十年四月に、ANCとPACが禁止されますが、アフリカ人の抵抗は根強く、フルウールト首相暗殺未遂事件などもあって、弾圧はさらに強化されていきます。
そんななか、61年5月31日、政府は白人の一方的意志により、英連邦を離脱、共和国を宣言します。地下解放戦線はマンデラを総書記にしてゼネストで対抗しますが、力で押し切られてしまいます。したがって、この暴挙に反対する人は「南アフリカ共和国」とは言わないのです。
白人のこうした異常なまでの弾圧に、ANCは五十年来の非暴力の道を捨てて、武力闘争部門「民族の槍」を創設し、61年12二月、遂に武力闘争を開始します。
ネルソン・マンデラと破壊活動法・リボニアの裁判
ネルソン・マンデラは、1918年にテンブ人の首長の長男としてトランスカイに生まれました。52年には、現ANC議長のオリバー・タンボと一緒にヨハネスブルグで弁護士事務所を開設していました。既に、解放運動のただなかにいたわけです。ANCが禁止されたあとも、果敢に地下活動を続けますが、62年8月に逮捕され、5年間の禁固刑を言い渡されてロベン島に送り込まれてしまいます。裁判では、白人が一方的に決めた法律に従う義務は自分になく、刑期終了後も不正がなくなるまで戦うことを言明します。

激しくなる一方の破壊活動の脅威から、政府は62年6月に一般法修正令、俗にいう破壊活動法を成立させていました。その法律は常識を越えて市民さえ容易に巻き込む厳しいものでした。
しかし、破壊活動法を強行し、マンデラを逮捕・監禁しても、破壊活動の火は鎮まりませんでした。追い詰められた政府は、63年5月にさらに法を改悪、再修正して、名目上一期を90日として、破壊活動に少しでも係わりがあると思える個人を、逮捕状・裁判なしに拘禁できる「90日無裁判拘禁法」を成立させ、指導者層を追い込んでいきます。拘禁された者には、1日、23時間半に及ぶ孤独拘禁を初め、様々な精神的・肉体的拷問が加えられました。
63年7月、ヨハネスブルグ近郊にあるリボニアにあった「民族の槍」の司令部が急襲され、ウォルター・シスルをはじめとするANCの指導者が大量に逮捕されます。そして、追訴されたマンデラとともに裁判にかけられ、ここに「リボニアの裁判」が始まります。マンデラは被告席から自らの弁護を行ないますが、5時間にわたるその弁護を次の格調高い一節で締め括りました。
……今まで述べてきたように私はこれまでの人生すべてをアフリカの人々の闘いに捧げてきました。私は白人支配とずっと闘ってきました。そして黒人支配とも闘ってきました。すべての人々が協調して、平等に機会を与えられて共存する民主的で自由な社会を私は理想としてきました。それは私がそのために生き、成し遂げたいと願う理想です。しかしながら、もし必要とあらば、私はその理想のために死ぬ覚悟ができています。
世論を懸念した政府は、極刑は下さずに八名全員に終身刑を言い渡し、マンデラを含む七名をそのままロベン島に送り込みました。(82年、マンデラはケープタウン郊外のボールズムーア刑務所に移されますが、88年7月に獄中で70歳の誕生日を迎えました。8月には「肺結核」のマンデラが民間施設に移送され「経過良好」と新聞が伝えました)
こうして、解放運動の指導者は、国外逃亡を強いられるか、拘禁されるか、抹殺されるかの壊滅状態に追い込まれ、大衆は指導者を失なって、南アフリカは暗黒の時代に突入していきます。
*50年代、60年代については、南アフリカ問題の草分け的な役割を果たした野間寛二郎氏の『差別と叛逆の原点」(理論社、1969年)に詳しく書かれています。
クリス・メンゲス『監督、ショーン・スロボ脚本のイギリス映画「ワールド・アバート」は、この頃の「実話に基づいた」ものですが、モデルとなったルース・ファーストは「90日」の白人女性第一号の犠牲者でした。
南アフリカが暗黒時代に入る同じ頃、日本では東京オリンビックが開かれ、高度経済成長の時代が始まります。
黒人意識運動・スティーヴ・ビコ
暗黒の時代に、それでもなお、次の新しい世代が生まれます。「遠い夜明け」で一部紹介されたあのスティーヴン・ビコに率いられる学生たちを中心にした世代です。

スティーヴン・ビコ(小島けい画)
ビコは1946年にケープ州東部のキングウィリアムズタウンで生まれました。ナタール大学医学部の学生時代に運動の指導者となり、のちに、白人の手を借りない黒入だけによる「ブラック・コミュニティ・ブログラム」を推進していきます。
ビコはまず何よりも、自己意識の変革を訴えます。白人のもとに働きに出るために両親が不在のまま、惨めなλラム街で幼少時代を過ごす子どもたちが、やがて白人居住区に出るようになると、いやでも白人社会との格差を思い知らされる。白人の教育を受け、白人の価値観に飼い慣らされ続けるなかで、知らず知らずのうちに肌の色に起因すると思われる劣等感を抱くようになる。したがって、黒人は、人間性を取り戻すために、白人とは係わりなく、まず自分自身の価値体系を確立し、自分の生き方を自分で決める必要かある……つまり、何よりも自己意識の変革の尊さを説いたわけです。そして、「プログラム」に従って、一九七四年にザネンピロ・コミュニティ・ヘルス・クリニックを創設して、自ら実践をしてみせます。すべてのものが白人の価値体系下にあった当時の状況の中で、黒人自身の手によって、白人に影響されることのない自立の方向性を具体化し、実践に移し得たのは画期的なことでした。法廷においても、理路整然と黒人自身の自己変革の必要性を説きました。76年の裁判では、黒人・白人の武装した警官の立ち並ぶなかで「警察当局のために働いているアフリカ人をどう思うか」と尋ねられた時「その人たちは裏切り者です」と厳然と言い切りました。
その頃にはすでに、その指導力をかわれてビコは国外でも高い評価を受けるようになっていました。しかし、その存在があまりにも大きくなり過ぎたために官憲の手によって獄中で葬り去られてしまいます。1977年9月12日のことでした。
そのビコの存在が、しかし、社会や親たちに希望を見い出せなくなっていた若者たちを立ち上がらせる大きな力となります。
ソウェト蜂起
1970年代のアフリカ人の抵抗運動は73年の労働者の広範囲にわたるストライキで始まりました。ストライキの波はナミビアの鉱山ストライキやダーバンでのゼネストヘと波及して翌年まで続きます。厳しい弾圧にもかかわらず、ストライキの参加者は2年問で20万人にも及び、ストライキの数も246に達しました。
75年の隣国モザンビークとアンゴラの独立やアンゴラ内戦に介入した南アフリカ正規軍の敗戦・撤退の知らせは国内のアフリカ人たちを勇気づけます。そんな意気揚がる情勢のなか、ビコの裁判から六週間のちの76年6月、自らの意志で、自らが決定して、ソウェトの高校生たちが立ち上がります。アフリカーンス語の強制的な導入などによる当局の「文化の押しつけ」を拒否して、高校生がデモ行進を始めたのです。ベン・バルカ監督の、モロッコ・ギニア・セネガル合作映画「アモク!」でも強烈に描き出されていましたが、希望を挫かれてもぐり酒屋に逃避する親たちを叱咤して、警官隊と対峙し、銃弾に立ち向かっていったのです。警官隊の発砲により多数の死傷者をみますが、抗議と連帯のデモは各地の黒人居住地区に広がります。この一連の事件はソウェト蜂起と呼ばれ、「ソウェト以後」という言葉で表現される新しい世代が解放運動の流れを大きく変えていくことになります。88年5月に開設されたANC東京事務所の代表ジェリー・マツィーラ氏も、当時ソウェトで教員をしていたその世代のひとりです。
575人の死者、数千人の負傷者と公式発表されましたが、実際の犠牲者はそれ以上であったと言われます。
ソウェト蜂起以後「民族の槍」によるゲリラ活動が活発化し、破壊活動は激しくなります。国際世論の非難が高まりANCへの支援が強まったこと、ソウェト事件での亡命者によってゲリラ要員が大幅に増えたこと、モザンビークとアンゴラの独立でゲリラ活動の拠点ができたことなどが要因でした。
外からは世界の経済制裁の波と「民族の槍」の破壊活動など国内外の様々な運動が強まるなか、78年9月、首相のピーター・ボタが登場します。
ボタ政権
フォルスター政権失脚の後を受けて登場したボタは、「適応か死か」を賭けて「アパルトヘイト体制の手直し」のポーズを見せる一方、軍事体制を強めながら強攻策を打ち出して、少数派白人の体制死守をはかってきました。
強まる世界の非難に対して、政府は84年に、前政権の導入できなかった白人・カラード・インド系からなる3人種体制を発足させます。ねらいは、カラード・インド系と黒人を分裂させることによって白人単独支配の安定をはかる、いわゆる分断支配でした。しかし、事態が政府の思惑通りに進んでいないのは、カラードとインド系の投票率の低さからも窺えます。85年に「背徳法」「異人種問結婚禁止法」、86年には「パス法」、などの法律を廃止しますが、すべてアパルトヘイト体制の根幹は変えずに「手直し」による「改革」によって世論の非難をかわしながら、あくまで多数派の黒人を国政から締め出すことを優先させようとするものです。
ボタは次々と見せかけの懐柔策を繰り出す一方、白人権益擁護のため、体制死守のために軍事予算を拡張しながら、警察国家から軍事国家への国家体制の脱皮をはかります。
81年末に南アフリカ軍は、激しくなる「民族の槍」の破壊活動への報復手段としてモザンビーク首都マプートのANC拠点を襲撃しますが、ソ連・キューバなどの東側諸国への接近を懸念するアメリカ大統領ロナルド・レーガンは政府軍の襲撃に暗黙の了解を与えていたといわれ、この時からレーガン政権の「建設的関与」政策が始まります。さらに白人政権は、ゲリラ活動を支援する周辺諸国に圧力をかけ、82年にはスワジランドと、84年にはモザンビークと不可侵条約を締結することに成功しました。
ボタ政権が人種「改革」を進めていた83年5月に、あらゆる人種、様々な団体が参加した南アフリカ史上最大の政治運動組織統一民主戦線(UDF)が結成されます。カラード・オランダ改革派の牧師アラン・ブーサックを発起人にして約600の団体が参加したUDFの運動は、五十年代にマンデラたちによって展開された会議運動の再来であり、組織と数の力だけではなく、現実に労働組合を中心にして大衆が動員されたために、白人政権の脅威となりました。
過去においても常にそうであったように、白人政権はUDFの弾圧を開始し、85年には指導者16名を逮捕して反逆罪で起訴しました。そして、88年2月には、他16団体とともにUDF自体を活動禁止処分にしてしまいます。
*UDFやボタ政権については、八十年代前半に共同通信社の記者としてヨハネスブルクに駐在して広範な取材活動をした伊高浩昭氏の『南アフリカの内側』(サイマル出版会、1985年)を参照されるとよいと思います。
アパルトヘイト体制を支えるもの
理不尽なアパルトヘイト体制が半世紀以上にもわたって生き続けているのは、その体制によって多大な恩恵を受ける人々がいるからです。また、アフリカ人による抵抗という中からの突き上げにあっても、経済制裁という外からの締めつけを受けても、なりふり構わず体制を死守しようとするのは、現在の搾取構造を維持することによって、南アフリカが生み出す豊かな富を、その人たちが独り占めにできるからなのです。
体制内の白人の生活水準がいかに高いかは、「遠い夜明け」や「ワールド・アパート」などでも少し紹介されましたが、商用でヨハネスブルクを訪れた日本人のある記事を見てみましょう。

映画「遠い夜明け」のパンフレット
500坪(1650平方メートル)の敷地に10メートルのプール、3つの浴室のついた120坪(396平方メートル)の建物、それにバーベキュー用の中庭がついている。読者は家賃はいくらだと思われるか。日本では手が出ないし見当がつかないと言われるだろう。
南アフリカ、ジョバーグ(商業都市ヨハネスバーグの現地名)でのお話である。場所は都心から車で30分の住宅地。月の家賃は日本円にして5万円である。このくらいで中級という。では高級の基準となると……最低でも1000坪(3300平方メートル)はあるだろう……。
某日本商社の支店長宅に招かれた。白人高級住宅地の真ん中、敷地面積2600百坪(8580平方メートル)、4面のテニスコート、15メートルのプールと6台駐車できる車庫、建物は250坪(825平方メートル)大木の植わったすばらしいこの庭園つきのこの豪邸が日本円で2600万円。では億の家はどのくらいの大きさか。たまたま、1億2000万という家を尋ねた。敷地1万2000坪(39万6000平方メートル)で、プールやテニスコート、それに建物、庭園は想像がつくだろう。また馬屋がついている。金持ちの条件には馬は欠かせないのかもしれないが欧米型だろうが、その馬を世話する人が4人は必要なので、その人たちの家、そして馬の運動場。なにしろ、日本の金持ちと規模を異にする。(88年12月24日付け「宮崎日日新聞」、江田祐典氏の「南ア豊かな白人社会」り抜粋、原文のまま)
その「豊かな白人社会」を内側からしっかりと支えているのは、強力な警察力と軍事力です。84年から85年の統計によれば、警察を含める軍事費は国家予算の20パーセント近くに及ぶといわれています。また、63年、77年に国連で決議された対南アフリカヘの兵器輸出禁止措置に対抗して、白人政権は国内の軍需産業を発展させ、兵器類を自国で賄うことによって軍事力の強化をはかってきました。そして今では、軍需産業は重要な国内産業の一つとなり、82年のアメリカ政府の統計によれば、その生産高は世界の第10位に達している、ということです。兵器輸入国から輸出国へと完全に脱皮したことになります。
さらに、75年には核実験が行なわれた、ともいわれます。現政権は潜在的な核兵器保有国と見なされており、黒人との最終的な対決の場面で追い詰められれば、核兵器が使用される可能性もある、とさえ考えられています。
しかし、いくら強力な力によって内側から支えられていると言っても、アフリカ人による屈強な内圧や経済制裁の外圧を白人政権が単独で受け止められるわけがありません。実は、外側からのもっと大きな力によって支えられているのです。その力とは、イギリス、フランス、西ドイツやアメリカ、日本などのいわゆる「工業先進国」で、強固な搾取構造を持つ内側の「豊かな白人社会」と協力して、貿易や産業投資によって莫大な利益を得ています。その構図は、さながら多国籍企業による「植民地」の様相を呈しています。南アフリカがアフリカ大陸に残る最後の「白い牙城」と言われる所以もここにあります。
国連の経済制裁決議に反して、「工業先進国」が白人政権と貿易を止めないのは、主として南アフリカが産出する豊かな鉱物資源、特にクロム、マンガン、モリブデン、バナジウムなどの希少金属から多くの利益を得ているからで、それらの希少金属は「先進国」の先端技術(ハイテク)産業や軍需産業には不可欠なものです。日本などのように鉱物資源の乏しい国では、より依存度が高くなり、その結果、貿易の関係もより親密になるというわけです。
各国が競って南アフリカに産業投資するのは、無尽蔵で、安価なアフリカ人の労働力を利用して莫大な利益が得られるからです。日本のように、国から直接投資を禁じられても、現地法人を作って巧妙に法の網の目を潜ってまで経済を優先させるのは、その利益がそれほど大きいからに他なりません。
*日本企業と南アフリカについては、北沢洋子さんの『日本企業の海外進出』(日本評論社、1982年)が参考になると思います。
アパルトヘイト体制を外側から支えているのは、貿易や産業投資などの経済的な要因ばかりではありません。ほかに、政治的、軍事的な側面も見逃せない要素となっています。
西側諸国は南アフリカの社会主義化を恐れています。経済制裁の強化によって白人政権がソ連やキューバなどと急接近することもそうですが、武力闘争を経て政権交代が行なわれた場合に黒人政権が社会主義路線を取ることを何よりも恐れるのです。アパルトヘイト体制の崩壊以上の間題とも考えられています。埋蔵量、生産高ともにアメリカに次いで2位を誇るウランをはじめ、豊かな鉱物資源を持つ南アフリカが社会主義国家になれば、現在の東西の力のバランスは崩れます。アフリカには社会主義体制を目指す国も少なくはなく、現にモザンビーク、アンゴラ、ジンバブウェなどの周辺国が社会主義路線を打ち出しているため、その懸念は大きく、レーガンが「建設的関与」政策を掲げて南アフリカに介入したのもそのためでした。
南アフリカは軍事戦略上でも重要な役割を担っています。インド洋と大西洋を結ぶ喜望峰まわりの航路を西側諸国の商船が通過し、中東原油や戦略鉱物資源が多量に運ばれているからです。白人政権はその戦略上の重要性を盾に、ナミビアの独立問題など様々な局面で西側諸国に難題を吹きかけています。
また、白人政権は最近、イスラエル、韓国、台湾、チリ、アルゼンチン、ブラジルなどとの関係を密にしていますが、それらの諸国との政治的、軍事的な協力関係も、アパルトヘイト体制を支える一つの力となっています。
このように、アパルトヘイト体制は、内側からは強力な警察力・軍事力で、外側からは経済的、政治的、軍事的な利益に与る国々によって支えられてきたのです。
革命の前夜
しかし、現政権は行き詰まっています。国内では、UDFなどを力で封じようとしていますが、アフリカ人の解放運動の火は鎮まりません。ANCの都市部でのゲリラ活動、労働組合による大規模な乳トライキの多発、飢えによるバンツースタンからの黒人の大量都市流入などの「黒人問題」に加えて、白人社会の分裂にも頭を悩まされています。白人極右翼勢力は政府の「懐柔策」さえ「裏切り」と捉え、反発の色を増しています。また、アパルトヘイト体制ではもはや立ちいかないと判断する財界のリベラル派は、85年にザンビアで、87年にはセネガルで、政府の反対をおしてANCと直接交渉を行ないました。
国外でも、様々な動きが白人政権を追い詰めています。85年10月、アメリカは、経済制裁を渋るレーガンの拒否権を覆して、「反アパルトヘイト包括法」を成立させています。
金の国際価値の暴落や相次ぐ外国資本の撤退などによって、国内は経済不況と社会不安に見舞われています。
88年11月に、アンゴラ、キューバ、南アフリカ、アメリカによるアンゴラ包括和平交渉の最終会談がコンゴで行なわれ、ナミビアの独立に向けて事態が動きだしました。ナミビアが独立を果たせば、南部アフリカに残される問題は南アフリカ黒人の解放だけに絞られることになります。
折しも、89年1月、ボタ大統領(84年9月から執権大統領)は脳卒中で倒れ、憲法・開発企画相ヘウニスが代行に就任します。
89年5月には、ボタ外相がローマでアメリカのべーカー国務長官にアパルトヘイト廃止を約束した、と報じられました。
7月には、大統領ボタが初めて獄中のネルソン・マンデラと面談し、政府との対話を要請したマンデラの声明を当局が公表した、と報じられています。9月の選挙での勇退を表明しているボタ大統領が、黒人指導者層との交渉に向けての下地作りをすることで、勇退の切り札を探っているのではないか、と言われました。
8月には、主導権争いに敗れたピーター・ボタが15日付けで大統領を辞任し、与党国民党の党首デ・クラーク国民教育相が大統領代行に就任します。九月に総選挙を待たず失脚同様に追い込まれたボタに代わって登場したデ・クラークは、改革推進に積極的に取り組む姿勢を見せていると言われています。
九月六日に行なわれた人種別3院政議会総選挙の白人議会選挙では「改革路線」を掲げる与党国民党が過半数93議席(改選前120)を維持したものの、アパルトヘイト廃止派の左派民主党が33議席(改選前19)、固守派の右派保守党が39議席(改選前22)とどちらも票を伸ばし、左右分極化の進む白人社会の状況が浮き彫りになりました。
その選挙に抗議して、六日間にわたって在宅ストが行なわれ、黒人労働者たち300万人が参加したと言われます。8日には、ケープタウン郊外の抗議デモでの白人警官のデモ隊への横暴さに耐え兼ねた同僚警官が内部告発を行なったというニュースが、民放で流れました。
また、カラード、インド両議会の投票率は前回の84年と同様に低調で、政府の目論む分断支配への黒人たちの抵抗の強さが改めて示されました。
白人政府が流血の惨事を避けて、黒人の指導者とどう折り合って連合政権を作っていくかが、おそらく今後の最大の課題となるでしょう。現時点での見通しが必ずしも明るいとは言えませんか、黒人解放の前夜に向けて歴史が流れているのはもはや何びとも否定できないでしょう。
日本人は名誉白人か
アパルトヘイトと日本
1928年、南アフリカがアジア人に対して「酒類販売取締法」を実施した際に日本人だけを優遇したのが「名誉白人」の原型と言われています。当時、既に両国間の貿易関係はそれほど密になっていたということです。先述のラ・グーマが書いた、1950年代のケープタウン第6区(カラード居住区)を舞台にした小説『夜の彷徨』(1962)の中にも「はるばる日本からやってきたセルロイドの人形」とあり、日本の商品が出回っていたことが窺えます。つまり、日本は南アフリカにとって、優遇措置を取らざるを得ないほど重要な、繊維や雑貨などの輸入元だった、というわけです。
その後、両国間の貿易関係は第二次大戦によって途絶えますが、60年代に入って復活します。60年に国交の再開と大使館の新設を約束した日本が、翌61年に正式に通商条約を結んだからです。その見返りとして、1961年にケープタウンの白人だけの議会において、居住地に関する限り南アフリカ在住の日本人は白人並みに扱う、という声明が出されます。アフリカ諸国の独立、シャープヴィル事件後の各国の経済制裁への動きなどに脅かされていた白人政府が、イギリス連邦離脱による経済的空白をドイツと日本で埋めたいと願った経済優先の窮余の策でした。
日本は、南アフリカのその要請に「見事に」応え、貿易相手国として実質的な両国間の絆を深めていきます。人権の問題には目をつぶり、経済制裁という世界の流れに逆行してでも、自国の経済政策を優先させたわけです。
*1988年4月7日付け「朝日新聞」、藤田みどりさんの「南アのアパルトヘイト奇妙な日本人の白人幻想」に明治、大正時代の日本と南アフリカの関係が少し紹介されています。
大量逮捕によって指導者を失ない「暗黒時代」に入っていった南アフリカと東京オリンピックをはずみに「経済高度成長時代」に入っていった日本。
1987年、東京のメーデーの集会で、「私が逮捕されて警察に連行されたときに乗せられたのはニッサン車でした」と語った統一民主戦線(UDF)の指導者アラン・ブーサック師と同じ壇上に並んで座っていたニッサン代表。
それらのことは、決して歴史の偶然から生まれたわけではないのです。
国際世論を気遣って、日本政府は国連の南アフリカヘの制裁決議に従って、表面上は国交を制限したり、直接投資や教育・文化・スポーツの交流、航空機の日本乗り入れを禁止しています。
しかし、現実には、第3国を通じての投資が行なわれていると言われていますし、外務省の要請を振り切って84年に南アフリカでの試合に参加したプロゴルファーの青木功は、何もなかったかのように大手を振ってテレビのブラウン管に登場しています。
87年11月に、モーリシャス沖で起きた台北発南アフリカ航空機の墜落事故では、ケープタウンでの試合に出場予定の日本のプロレスラーが遭難し、政府の「スポーツの交流禁止」措置が、残念ながら、有名無実である実態があらためて明らかにされました。また、同乗していた漁船員やビジネスマンの存在によって、貿易や観光が日本と南アフリカの間で如何に日常的に行なわれているかがクローズアップされる結果となりました。
経済最優先の日本政府の外交政策は、88年には、日本が南アフリカの最大貿易相手国となるという必然の結果を生みました。同年12月5日には、国連総会で、アフリカ諸国が中心になって提案された「南アの人種差別体制に対する包括的かつ強制的制裁」決議案が採択され、その中で日本は「対南ア貿易を増やしている国々、とりわけ最近南アの最大の貿易相手国となった日本に対し、対南ア貿易関係を断絶するよう呼びかける」と名指しで非難されることになります。
南アフリカとの関係だけに限ったわけではありませんが、名指しで非難されても経済最優先の路線を走る日本の政界や財界の南アフリカ白人政府との繋がりは想像以上に強いものがあります。
84年に40数人の自民党議員によって日本・南アフリカ友好議員連盟が結成されたことはよく知られています。二階堂進が会長、今回の総裁選挙に出馬した石原慎太郎が幹事長で、竹下登も名を連ねていました。女性問題で辞任した山下徳夫に代わって官房長官になった森山真弓は、当時、外務省の政務次官でした。反アパルトヘイトの立場を取る政府の方針に反する活動をしていると非難されて渋々脱会したと言われます。石原慎太郎の言う「南アは西側の政治戦略に欠かせない国。人種問題への批判とは別に友好関係を結ぶことは大切だ」という論理は、自民党の本音として生きている、と言われています。その本根は、87年4月の中曽根・タンボ会談でも垣間見られました。
20日に当時の中曽根首相がANCタンボ議長と会談した、また、同日、倉成外相が外務省でタンボ議長と会談し白人政権を介さずに40万ドル(約5700万円)をANCに援助することやANCの東京連絡事務所の設置を認める考えを示した、というのです.結果的にはそのことによって、翌年の5月にANCの東京事務所が開設され、代表としてジェリー・マツィーラ氏が赴任してくるのですが、何とも奇妙な話です。貿易によって甘い汁を分かちあってきた日本政府が、こともあろうに、白人政府を介さずに援助する、しかも、日本が海外のNGO(非政府組織)に援助するのは初めてというおまけまでついていました。今すぐにではないにしても、やがては誕生する黒人政府への布石のつもり、なのでしょう。近い将来に黒人政権ができたとき、「私たちもあなたがたに援助した」と言うつもりなのでしようか。

オリバー・タンボ
「もし日本が、全黒人の憤激をひきおこしている南アフリカの人種差別にひきつづき協力するならば、日本はアフリヵの全人民から離反する危険に直面していることを指摘しておきたい」というタンボ氏の手紙が『差別と叛逆の原点』のまえがきに紹介されたのは1969年のことです。あとがきには、62年にタンザニアのモシで開かれた第3回アジア・アフリカ人民連帯会議で、南アフリカ代表から目本代表に特別会見の申し入れがあったことが記されています。アジアの一員でありながら国連の経済制裁決議を無視して白人政権との関係を密にしている日本政府をどう思うか、政府を黙認するのは抑圧への加担ではないか、という内容だったようですが、その団長がタンボ氏でした。四半世紀も前のことです。87年の来日の際に、「27年の逃亡生活、故郷のケープ州に帰りたいと思わないか」と問われて、「帰り……たくない。今は闘いの最中だ。闘いを続けることが私の仕事だから」と答えています。62年に同僚のネルソン・マンデラが逮捕されて以来、ANC議長代行の立場を取り続けるタンボ氏。姑息な日本の政治家連中と会見しながら、いったいどのような思いを抱いたのでしょうか。
財界も破廉恥という点では政界に負けてはいません。88年2月、南アフリカとの係わりの深い大手企業が結成する「南部アフリカ貿易懇話会」が、「南アフリカ黒入の生活向上のため」に設立した「日本基金」の50万ドルを贈るために、南アフリカの黒人を呼んだと言われます。
招かれたのは、南アフリカ国内の反アパルトヘイト黒人支援民問組織「カギソ(平和)基金」の事務局長アハマト・ダンゴル氏ですが、ダンゴル氏は自分を招いた「南部アフリカ貿易懇話会」の事務局長が、南アフリカ航空の相談役牧浦利夫だと知って、金も受け取らずに帰国したといいます。「日本・南アフリカ友好議員連盟」を発足させた張本人と目される人物、日本と南アフリカとの貿易推進の黒幕ともいわれる牧浦利夫は、南アフリカの黒人が「有り難く金を受け取る」とでも考えたのでしょうか。
半年後の8月に、カナダのブロック大学で行なわれた南アフリカの二人の作家アレックス・ラ・グーマとベシー・ヘッドの記念大会で、私はダンゴル氏とお会いしました。トロントで開かれたコモンウェルス外務大臣会議での「南アフリカの検閲制度に関するフォーラム」で発言されたダンゴル氏が、飛び入りで記念大会に参加し、大会に花を添えられたからです。発表後、すぐに帰られたので、挨拶しか交わせなかったのですが、日本からの参加者を見ながら、半年前の出来事を振り返ってどう思われた……か。その時、私はダンゴル氏の来日のことは知りませんでした。
*最近の南アフリカの動向、白人政権と日本の政財界との関係については、アフリカ行動委員会を中心に反アパルトヘイト運動を推進している楠原彰氏の『アパルトヘイトと日本』(亜紀書房、一九八八年)をお薦めします。また、88年7月4目付け「朝日新聞」所収、堀江浩一郎氏の「返還したい『名誉白人』称号 現地での南ア制裁めぐる論議と対日観」での南アフリカの邦人社会への提案も、現状では不可能に近いようですが、示唆的だと思います。
私たちは今……
「アパルトヘイトの歴史と現状」はいろいろなことを私たちに教えてくれます。
「アパルトヘイトの歴史」は、西洋人たちによる侵略の歴史でした。如何に聖書で理論武装し、その行為を正当化しようとも、殺戮の歴史に変わりはないのです。強者が弱者を意のままにするという、まさに弱肉強食の世界でした。悲しいことに、その歴史は今も続いています。
現代の文明は、大部分、その搾取構造の上に発展し、その犠牲の上に繁栄してきました。知ると知らないとにかかわらず、ある意味では、私たち日本人もその延長上に居ます。そして、抑圧の側に立っているのです。
そのような厳しい抑圧のなかでも、アフリカ大陸は数多くの偉大な人物を生み出してきました。
ネルソン・マンデラは、死の恐怖のなかで、一国を相手に答弁し、「……すべての人々が協調して、平等に機会を与えられて共存する民主的で自由な社会を理想としてきました……もし必要とあらば、私はその理想のために死ぬ覚悟ができています」と言いました。そして、62年以来、今だ獄中にいます。
ロバート・ソブクウェは、自らパスを焼き捨て、警察本部に入っていきました。
アレックス・ラ・グーマは、世界に現状を知ってほしい、後の世の若い人たちに歴史を記録したいと、数々の物語を残しました。
スティーヴ・ビコは、指導者を奪われて希望を見失なっていた人々に、「生活の厳しさにただ諦めて身を任せていないで、希望を育み、自らの人間性を培うべきだ」と自己の変革の必要性を説きました。自らは獄中の露と消えましたが、ビコの魂は、今もなお多くの人々に引き継がれています。8月に来日し宮崎でも講演された南アフリカ在住の黒人女性作家ミリアム・トラーディさんも、ビコに心動かされた一人です。発禁などの処分を受けながらも南アフリカ国内で小説を書き続けるトラーディさんの心の中に、ビコの考えや精神は大きな拠り所として生き続けています。
その人たちは例外なく歴史をよく理解していました。そして、追い詰められても、誰ひとりとして最後まで侵略者とは化しませんでした。
厳しい抑圧の中でさえ、南アフリカの人たちはなんとか自分たちの文化を継承し続けてきました。アパルトヘイト体制をもってしても、黒人たちの文化までは根こそぎにはできなかったのです。
ダンゴル氏は、先述の記念大会で、国内の現状を次のように述べました。
アパルトヘイトの闘いが21世紀まで続くならば、その闘いを支えるのは一般大衆の文化的な慣習でしょう。
文化は私たちに残された最後の領域です、というのも国が他のすべてのものを閉ざしているからです。
演劇のグループは非常に盛んで、タウンシップ内にたくさんのグループがあります。もし、政府に活動を禁止されても、少し形を変えたり、また違った名前で、どこか別の所に再び姿を現わします。
発禁処分を受けた文学はパンフレットや地下出版、ビデオや録音テープの形で国内に出回ります。
トラーディさんは、宮崎の講演で、「母国語のソト語で書き始められたそうですが、字も書けない人たちのためにどういうことをお考えでしょうか」と聞かれて、次のように答えました。
私たちには、いわゆる口承文学と呼ばれるものがあって、それは引き継がれてきています。たとえば、もし南アフリカに関する映画などをご覧になれば、何千もの大衆が動員されているのがおわかりになるでしょう。非常に豊かな口承の歴史がありますから、起ったことを人々に伝えることが出来たのです。私たちは、口承の文学を代々継承させてきました。そして、こういった種類の情報伝達の構造は体制に破壊されてはいません。たとえば、詩人がいますが、その人たちはタウンシップではとても活躍していて、詩を通して、いつも言葉を伝えます。詩人たちは、誰かを埋葬したり、誰かが結婚したりするような儀式で、殆んどすべての儀式で詩をうたいます。詩人たちによって言葉が伝達され、口承の文学を通して政治的情報が伝えられているということがお分りになると思います。
現に南アフリカ国内に踏み留まって作家活動を続けておられる二人の発言には千金の重みがあり、その迫力がひしひしと伝わってきました。
厳しい抑圧のなかでも自分たちの文化を守り続けてきた南アフリカの人たちと較べて、私たち日本人はどんな文化を守ってきたのでしょうか。
「高度経済成長」を遂げたと言われている日本人ですが、果たして自分たちの誇れる文化を守り続けて来たと言えるのでしょうか。
2年前に、南アフリカを現地取材したテレビ報道番組「ニュースステーション」の中で、ヨハネスブルグにある日本人学校で開かれたパーティーの模様が紹介されていました。日本人学校の校長が、招待した白人達(白人の子供を抱いた黒人の「メイド」もいましたが)に、日本の文化をお楽しみ下さいと挨拶し、子供達がKendoを披露し、「美しい」着物を着た奥様方がお茶を接待していましたが、その「文化」を日本人の文化だと思った人はいないでしょう。
「アパルトヘイトについては・・・・」という質問には皆一様に「お答えできません」という「美しい」奥様方の背後には、人権の問題に目をつぶっても経済の最優先を、という「企業の論理」が見え隠れしていました。
「企業の論理」は、「アパルトヘイトの歴史と現状」が教えてくれた「弱肉強食」の世界とまさに同じです。
宮崎の土呂久、熊本の水俣、若狭の原発など、「企業の論理」や「弱肉強食」の世界が如何に身のまわりに横行していることでしょうか。「辺境の地」に公害をまき散らして企業利益を優先する「企業の論理」にたくさんの人々が苦しめられています。その「弱肉強食」の世界と、ヨーロッパ人が南アフリカを侵略し、人々を苦しめ続けている構図にどのような違いがあるのでしょうか。
私は戦後しばらくして兵庫県の高砂市に生まれ、加古川市で育ったのですが、走ってよく出かけるようになった学生時代には、すっかり高砂の海は汚れていました。三菱製紙や鐘淵化学などたくさんの企業が海岸線に立ち並んでいたからです。風のある日には、海から何キロも離れた家のあたりまで煤煙のにおいが漂ってくるのです。
高校生のときだったと思いますが、真夏のある日、思いたって友人と「あの辺に砂浜があったなあ」と言いながら泳ぎに出かけたことがあります。砂浜は確かこの辺だったかなあ、とコンクリートの堤坊をよじ登ってみたら、目の前に広がるのは無残に埋め立てられつつある神戸製鋼所の工事現場でした。あるはずのところに、海のなかった驚きは、今も暗く、詫びしい心象風景として心のなかに残っています。
ある頃から、夜中でも南の方の空が明かるくなる時が度々ありました。公害の規制の激しい昼間を避けて、夜中の間に煙突から煙を出すんだよ、と住友金属に勤めながら夜学に通うクラスメイトが教えてくれました。
日本では、70年安保闘争、大学紛争が繰り広げられようとし、南アフリカでは、ビコを中心とする学生たちが立ち上がろうとしていた時期でした。
都会中心の社会は電力の消費を増大させ、「辺境の地」に原発と核の脅威をもたらしています。
車や先端技術によって得た「便利さ」や、消費文明によってもたらされた「豊かさ」と引き替えに、私たちが失なったもの失ないつつあるものは、とてつもなく大きく、この辺りで、自分たちの傲りに気づいてなんとかしなければ、手遅れになるかもしれません。
「アパルトヘイト」の問題も、私たちに、自分と社会とを問い直させてくれる大きな問題の一つなのです。
現実の問題として、日本と南アフリカが貿易という太いパイプで繋がっている限り、楠原彰さんの言うように「アップルタイザーを飲まない……婚約者にデ・ビアーズ(De Beers)社のダイヤモンドなんか贈らない。ケープ・ワインを飲まない。南アに進出している企業の製品をボイコットする……」(『アパルトヘイトと日本』)など、身近な、やれるところからやってみるのは大切なことです。
そのためには、まず南アフリカの本当の歴史と現状を知ると同時に、自分自身で何が正しいかを判断できる視点を持つことが何よりも必要でしょう。
その上で、改めて「アパルトヘイトの歴史と現状」が提起している問題をそれぞれ自分の問題として受けとめ、問い直してみたいと考えます。自分のまわりの身近なところを大切にして生きていくことが、自分を大切に、ひいてはひとを大切にすることにつながると思うからです。
そうすることが、自分たちの文化を、自分たちの大切なものを、やがては次の世代へと引き継いでいくことにもなると思うのです。
「アサンテ.サーナ!自由」に参加して
本稿は「アサンテ・サーナ!(スワヒリ語でありがとう)自由」と題する催しの一環として、1989年7月1日に、愛媛県の松山東雲学園百周年記念館でお話させていただいた講演「アパルトヘイトの歴史と現状」をもとにしてまとめたものです。
その催しでは、他に、アパルトヘイト否! 国際美術展・写真展、エチオピア子供絵画展、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ等の資料展示、「源の助バンド」
によるレゲエのコンサート、「アモク!」の映画会が、主に一日、二日の両日にわたって行なわれました。
今回の講演は、松山市内で弁護上をしておられる薦田伸夫さんからお誘いをいただいたのですが、実は、本誌「ゴンドワナ」の取り持つ縁で実現したものです。
以前お世話になった薦田さんから草薙・薦田法律事務所の事務所だより「水平線」
が届き、僕の方からは時折「ゴンドワナ」をお送りしていました。
4月の半ばに「アパルトヘイトの話を」というお電話があったとき、門外漢の僕がと思いましたが、去年から授業でも南アフリカのことをやっているし、この機会にひとつまとめさせていただけたら、と考えてお引き受けすることにしました。催しは予想していたよりも好評のうちに終わったとのことですが、周到な準備をされ、いろいろな人が協力された成果だと思います、薦田さん、北村親雄さん、会場のお世話をしてくださった山内弥生さんをはじめたくさんの方々にお祝いとお礼を申し上げます。
講演に出かける直前、宮崎大学農学部の学生都築扶美さんは、パンフレットを見ながら「会場の松山東雲学園は私の母校です。城山の中腹にあるきれいな所ですよ,と教えてくれました。
講演を聞いて下さった温泉郡川内町安國寺の住職浅野泰巌さんは、私も同じ落第生、落第したので、世を裏から見ることができ、アパルトヘイトにも関心を持つようになったという意の丁寧なお手紙を下さいました。
様々な機会に「ひと」と巡り会えるのは有り難いことだと思います。
「ボランティアで手伝ってくれた愛大(愛媛大学)の学生が、あの時運んだ絵、重たかったなあ、何か髭はやした人がアパルトヘイトの話しとったなあ、といつか思い出してくれるのが大事やねん」という北村さんの言葉と「松山と宮崎は海を隔てて、隣の県みたいなもんやから、これに懲りずにこれからもよろしく。少しでも僕らが世の中変えていかなあかんから……という薦田さんのさりげない言葉が印象的でした。
89年9月下旬、宮崎にて。
(宮崎医科大学講師・アフリカ文学)
南アフリカ小史 (1989年9月現在)
1652 東インド会社、ケープに中継基地を建設。
1795 イギリスの第一次ケープ占領。
1806 イギリス、ケープ植民地政府樹立。
1833 イギリス、ケープで奴隷を解放。
1835 グレート・トレック(ボーア人の内陸大移動)開始。
1838 ブラッド・リバーの戦い(ズールー人対ボーア人)。
1867 キンバリーでダイアモンドを発見。
1880 第一次アングロ=ボーア戦争(~81)。
1886 ヴィトヴァータースランドで金を発見。
1899 第二次アングロ・ボーア戦争(~1902)。
1910 南アフリカ連邦成立。
1912 南アフリカ原住民民族会議〔後に、アフリカ民族会識(ANC)と改名〕結成。
1913 「原住民土地法」制定(リザーブの設定)。
1921 南アフリカ共産党結成。
1936 「原住民代表法」・「原住民信託土地法」制定。
1948 国民党マラン内閣成立(アパルトヘイト体制強化)。
1949 「雑婚禁止法」制定。
1950「共産主義弾圧法」制定。南アフリカ共産党禁止。「住民登録法」,「集団地域法」
制定。
1955 クリップタウンの人民会議で自由憲章を採沢。
1956 「反逆罪裁判」事件開始(~61)。
1958 パン・アフリカニスト会議(PAC)結成。
1960 シャープヴィルの虐殺。ANC,PAC禁止。
1961 共和国宣言。ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)創設,ANC武力闘争を開始。
1962 ネルソン・マンデラ逮捕。
1963 リボニア裁判開始(~64)。
1967 「反テロリズム法」制定。
1976 ソウェト蜂起。
1977 スティーヴ・ビコ獄中死。ANC、ゲリラ闘争を開始。ピーター・ボタ首相政権発足。
1982 統一民主戦線(UDF)結成。スワジランドと不可侵条約締結。
1984 ボタ、執権大統領に就任。三人種体制発足。モザンビークと不可侵条約締結。
1985 「背徳法」廃止。「異人種間結婚禁止法」廃止。
1986 「パス法」廃止。
1987 オリバー・タンボANC議長来日し,首相と会見。
1988 ANC東京事務所開設(5月)。国連総会で,対南アフリカ貿易に関する日本非難の決議を採沢(12月)。
1989 南アフリカ外相、米国務長官にアパノレトヘイト廃止を約束(5月)。マンデラと初会談のボタ大統領、マンデラの声明を発表(7月)。ボタ辞任(8月)。デ・クラーク、大統領に就任(9月)。
執筆年
1988年
収録・公開
「ゴンドワナ」 14号 10-33ペイジ
ダウンロード
アパルトヘイトの歴史と現状(116KB)