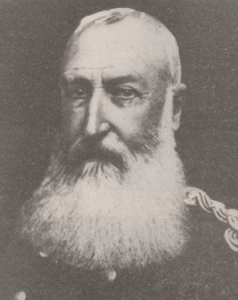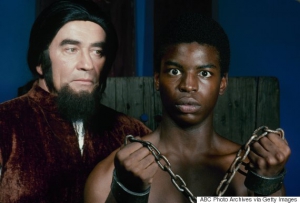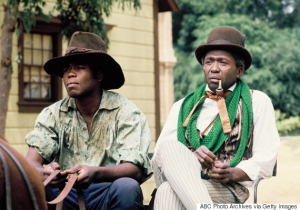日程のお知らせ
来週24日(水)は金曜日の振替で授業なし、再来週31日(水)が3との合同授業2コマ続きです。
用語の日程と要領
31日(水):15章のチェック(説明→例題→病態の解説→練習問題→Pronunciation of Terms225題の順で丁寧に見るのが大切。)
11月7日(水)筆記試験(Pronunciation of Termsのdefinitionにterminologyと日本語を答える、CDで配った演習の要領で。)
例
問題Pertaining to the acetabulum / ( ) /( )
答えPertaining to the acetabulum / (acetabular) /(寛骨臼の)
10月10日
4・5回目の後半のクラスとの合同授業でした。あなたらと獣医の人たちの分の準備でこの2,3日、結構大変でした。寝不足気味で早うねないともたん気もするけど、ブログは書いとかんとあとで苦しみそう。何とか書いときます。
CNNの聞き取りと15章のチェックをするつもりで行ったけど、予定変更。次回はどっちもやろ。
1コマ目は佐保くんの発表と用語。2コマ目は新聞記事。
佐保くんは英語でコンゴの紹介をやってくれました。充分にわかる発表でした。紹介してくれた箇所については、映像でも見てもらうつもりです。
用語は専門用語の発音チェックと15章のPronunciation of Termsと骨の発音のチェックをやりました。初めてやったんで、発音の細かいチェックなどでわりと時間を食いました。
新聞記事は名倉くんが英文を読んでくれて、質問に答える形で。さっと要約してもらえたらよかったけど、ポイントを質問に答えてもらう形でやりました。そう難しい文章でもないと思うけど、政治や歴史背景がないとわかりにくい例として読んでもらいました。最後の方に日本語訳を貼っとくんで、細かいところは自分でチェックしぃや。何カ所か難しいところもあるで。
次回は、今日出来なかった①CNNの聞き取りと②コメントの続き、③CNNの聞き取りと④15章のチェックと⑤ERX1。時間があれば、Outbreak, 1976年の一回目のエボラ騒動の映像、それに独立・コンゴ動乱→植民地時代(レオポルド2世の個人の植民地「コンゴ自由国」)→ベルリン会議・植民地分割の映像も。
ブログに入れない人は、入れた人に教えてもらいや。
配ったプリント:ERIX6のtranscription(B5で6枚、CDは週末に作って参考ファイルに置いとくんで、実際に使われている用語をチェックしぃや。)
やっと何とか書けたねえ。また、再来週に。
たま
新聞記事の日本語訳
“Ebola virus returns Zaire into world’s spotlight”
Reuter (sic) in The Daily Yomiuri (May 16, 1995)
The Ebola virus outbreak in Zaire has refocused attention on the vast nation of 40 million people in the heart of Africa that has lurched from one crisis to another since independence from Belgium in 1963 (sic).
ザイールでエボラウィルスが発生して、1963年(原文のまま)のベルギーからの独立以来、数々の危機に揺れ動いて来た中部にあるアフリカ4000万人の広大な国に再び注目が集まりました。
The virus, for which there is no known cure or vaccine, has killed at least 64 people.
治療薬もワクチンも知られていないウィルスは少なくとも64人の死者を出しました。
Many Zaireans are openly angry at the government of President Mobutu Sese Seko, who has ruled unchallenged for most of the past 30 years and, according to critics, salted a way (sic) a personal fortune estimated in billions of dollars.
批評家によれば、多くのザイール人が過去30年間無投票で当選し、不正にためこんだ個人の資産が数十億ドルにのぼるといわれるモブツ・セセ・セコ大統領の政府に公然と腹を立てています。
Opposition commentators and independent journalists blame the frequency of epidemics and lack of resources to deal with them on corruption and mismanagement of the wealth of a country blessed with just about every strategic mineral known to man.
反対派の批評家やフリーのジャーナリストは、流行病が頻繁に起こるのも、取り扱う資源が不足するのも、既知のあらゆる戦略的に重要な鉱物資源に恵まれている国の富の管理ミスと賄賂のせいだと指摘しています。
“Mismanagement of public resources that leads to poor management of the environment create opportunistic factors for the birth and spread of epidemics," lamented an editorial in the opposition newspaper Le Palmares.
「環境の管理不備に繋がる、公共資源の管理ミスが日和見的な要因を作り出して、流行病を発生させたり、広げたりしている。」と反対派の新聞ル・パルメール(Le Palmares)の社説は嘆いています。
“Health facilities are in a deplorable state. We have been heading for disaster for a long time," Lambaert Mende, spokesman for Zaire’s chief opposition leader Etienue Tshisekedi said.
「医療関係施設は悲惨な状況です。私たちは長い間、大災害が起きてもおかしくない方向に向かって進んできました。」とザイールの野党指導者エティニュエ・ツィセケディ(Etinue Tshisekedi)のスポークスマン、ランバエルト・メンデ(Lambaert Mende)は言いました。
Corruption has eaten deep into the fabric of Zairean society and government and even quarantine measures announced to keep the Ebola virus from the capital of five million people are being undermined by bribery, Kinshasa city officials say.
賄賂はザイールの社会と政府に深く染み込んでおり、500万人が住む首都をエボラウィルスから守るために発令された隔離手段でさえも賄賂がきく有様です、とキンシャサ市職員が言います。
Public workers are owed several months salary and bribery has become a way of life.
公務員は何ヶ月分もの給料を払ってもらえず、賄賂は生活の一手段となってしまっています。
The virus is stretching Zaire’s decrepit medical services, already hard pressed, to cope with the scourge of AIDS, which has hit Zaire harder than most countries.
ウィルスはザイールの老朽化した医療機関に広がっており、医療機関はたいていの国よりも激しくザイールを襲っているエイズ禍の対応追われています。
Zaire’s political problems began early: Katanga, which today is the mineral-rich province of Shaba, made a disastrous attempt at secession, 11 days after independence from Belgium. It was forced back after three years of bloody conflict.
ザイールの政治の問題は早くに始まりました。鉱物の豊かな現シャバ州であるカタンガ州はベルギーから独立した11日後に、不幸な結果に終わった分離工作が謀られました。その分離工作は血まみれの闘争の3年後に強行されました。
The second largest country in sub-Saharan Africa. Zaire has rich farm and watered by the Zaire river, formerly River Congo.
サハラ以南のアフリカで2番目に大きい国ザイールには豊かな農場があり、旧コンゴ川のザイールの川から水の恵みを得ています。
The country is blessed with some of the best copper deposits in the world but the engine of its economy, the state mining collosus Gecamines, has virtually ground to a halt."
その国は世界でも有数の銅の埋蔵量を誇っていますが、経済のエンジンである国営巨大鉱山会社ゲカマイン(Gecamines)は、事実上操業を停止しています。
Copper production dropped from a peak of 500,000 tons to under 50,000 tons in 1994. Cobalt production slumped too.
1994年には、銅の製造量は最盛期の50万トンから5万トン以下にまで落ち込みました。コバルトの製造量も同じようにひどく落ちみました。
The government has dissolved three core companies in the Gecamines group and not said what will become of the state company, which generates over 70 percent of its hard currency.
政府はゲカマイン(Gecamines)グループの中の3つの中心会社を解散させ、硬貨の70パーセント以上を製造する国営会社の先行きについては言及していません。
The World Bank, International Monetary Fund and creditors led by former colonial power Belgium abandoned Zaire long ago.
世界銀行も国際通貨基金も旧宗主国ベルギーが仲立ちをする債権者たちも、ザイールをずっと以)前に見捨てています。
With inflation running close to five digits, the government has periodically reverted to printing mountains of worthless money.
インフレ率が5桁近くなりつつあるインフレで、政府は定期的に価値のない紙幣を山のように印刷するようになっています。
The capital Kinshasa is still recovering from waves of looting by unpaid soldiers in 1991 that forced France and Belgium to send troops to evacuate Europeans.
首都キンシャサは、ヨーロッパ人を退去させるための軍隊派遣をフランスとベルギーに強いた、給料を払ってもらえない兵士たちによる1991年の数々の略奪行為から何とか立ち直ろうとしているところです。
The United States, which propped up Mobutu during the Cold War as a bulwark against communism in Africa, has been at the forefront of pressure for democracy in Zaire.
アメリカは、冷戦の間アフリカで共産主義に抗する防波堤としてモブツを支援してきましたが、今は最前線に立って、ザイールでの民主主義を求めて圧力をかけています。