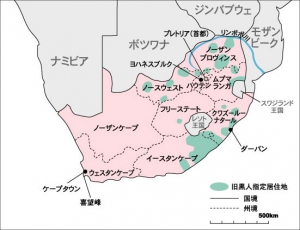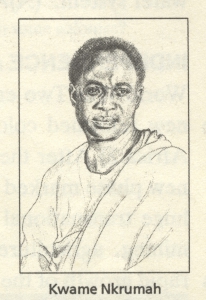つれづれに:10月も半ばを過ぎて

10月 秋立ちぬ(サンダンス) (3号)

9月 (ぴのことジョバ)青い街(3) (2号)
10月も半ばを過ぎている。今回もカレンダーを更新できずに、2ヶ月分を載せることになった。吉祥寺にいる娘は寒いのが苦手、こっちと代わって、こっちも代わってほしいと母と娘で遣り取りしている。3年続きで、10月の半ばを過ぎてもまだ日中の最高気温が30以上である。しかし、昨日から北東の風が吹いて雨も降り、少し気温が下がり始めている。月曜日くらいからは、下が22℃くらいになるらしい。植物は暑さ寒さに対応する幅があるようで、例年通りしっかりと柿(↓)も色付き始めて、芒もあちらこちらで見かけるようになっている。

先週は熱中症気味でやられたかなと思ったが、早めに対策したので、何とか持ち直した。先々週に、暑い最中に長時間自転車に乗ったのがじんわりときいていたらしい。出来るだけ外出は控えましょう、は人ごとではなかったわけである。

この時期になって、瓢箪南瓜(↑)の実がつき始めた。今年はわりと早い時期に竹の柵(↓、解体作業中)を拵えて肥料も入れたが、それがよくなかったらしい。最初の頃は葉っぱばかりが繁り、花が咲いても実をつけなかったり、途中で変色して消えてしまったり。1本の蔓に7~8個はなるものらしいから、70、80個はなってもおかしくないのに、今のところ十数個である。南瓜は肥料なしの方がたくさん実がなるものらしい。

9月末と10月の半ばに、小説は投稿した。最近はウェブで投稿できるので原稿用紙を綴じて、郵送するという手間が省ける。ただ、相手次第なので、先行きは相変わらず見えない。教授選といっしょで候補者には投票権がない。相手任せである。次回は3月末に2つ出す予定で、どちらも400字で250枚と300枚らしい。1つは3日ほど前から書き始めている。100枚ほど書いたところだ。先の見えない旅路が続く。考えれば、小説を書きたいと思って大学の職を探したくらいだから、やりたいことがやれているので、有難い話である。
 赴任当時の旧宮崎医科大学(ホームページより)
赴任当時の旧宮崎医科大学(ホームページより)
きのう、長崎のオムロプリントから2026年のカレンダーの見本が送られて来た。いつも専属の人が表紙や各月の構成や色合を考えてくれる。今年も、なかなかの出来栄えである。有難い。表紙と8月は、注文をして下さった東京の方の愛犬である。お気に入りのうさちゃんの人形がかわいい。名前がりりーちゃんなので、百合の花が豪華である。僕はいつものように、花屋を巡って材料の調達係だった。写真ではなく、生きた花を見ながら描いているので、勢いもある。毎年、最後は寝不足になるので、来年は個展が終わったら準備を始めようと言っている。恒例行事である。

リリーちゃんと百合:2026カレンダー表紙