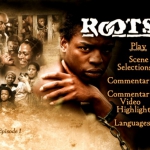自己意識と侵略の歴史
概要
この五百年ほどのアングロサクソンを中心にした侵略の歴史の意識の問題に焦点を当てて書いたものです。
理不尽な侵略行為を正当化するために白人優位・黒人蔑視の意識を植え付けて来ましたが、意識の問題に正面から取り組んだアメリカ公民権運動の指導者の一人マルコム・リトルと、アパルトへイトと闘ったスティーブ・ビコを引き合いに、意識の問題について書きました。
アパルトヘイト反対運動の一環として依頼されて話した講演「アフリカを考える—アフリカ」(南九州大学大学祭、海外事情研究部主催)や宮崎市タチカワ・デンタルクリニックの勉強会での話をまとめたものです。
本文
白人優位・黒人蔑視
奴隷貿易に始まる西洋諸国の侵略によって、支配する側とされる側の経済的な不均衡が生じましたが、同時に、白人優位・黒人蔑視という副産物が生まれました。支配する側が自らの侵略を正当化するために、懸命の努力をしたからです。支配力が強化され、その格差が大きくなるにつれて、白人優位・黒人蔑視の風潮は強まっていきました。したがって黒人社会は、支配権を白人から奪い返す闘いだけでなく、黒人自身の心の中に巣食った白人優位の考え方を払しょくするという二重の闘いを強いられました。アメリカ映画「遠い夜明け」で広く知られるようになったスティーヴ・ビコは、ある裁判で黒人意識運動の概念について質問されたとき、その「二重の闘い」に言い及んで、次のように述べています。
基本的に「黒人意識」が言っているのは黒人とその社会についてであり、黒人が国内で二つの力に屈していると、私は考えています。まず何よりも黒人は、制度化された政治機構や、何かをしようとすることを制限する様々な法律や、苛酷な労働条件、安い賃金、非常に厳しい生活条件、貧しい教育などの外的な世界に苦しめられています。すべて、黒人には外因的なものです。二番目に、これが最も重要であると考えますが、黒人は心のなかに、自分自身である状態の疎外感を抱いてしまって、自らを否定しています。明らかに、ホワイトという意味をすべて善と結びつける、言い換えれば、黒人は善をホワイトと関連させ、善をホワイトと同一視するからです。すべて生活から生まれたもので、子供の頃から育ったものです。[I Write What I Like (New York: Harper & Row, 1986), p. 100.神野明他訳の日本語訳『俺は書きたいことを書く』(現代企画室、 一九八八年)が出ています]
南アフリカを本当の意味で変革していくためには、先ず何よりも黒人ひとりひとりが、厳しい現状に諦観を抱くことなく、自らの挫折感とたたかい、自分自身の人間性を取り戻すべきだと、ビコは説きました。自己を同定するために自分たちの歴史や文化に誇りを持ち、次の世代に語り伝えようと呼びかけました。そして、経済的な自立のための計画を立てて、実行に移しました。
白人支配の体制に闘いを挑む前に、先ず自己意識の変革をと唱えたのは、もちろんビコだけではありません。ビコに大きな影響を及ぼしたアメリカ公民権運動の指導者の一人、マルコムXも同じようなことを言い、経済的に自立するための企画を試みました。マルコムはあらゆる機会を利用して、黒人自身の自己意識の変革の必要性を説きました。暗殺される直前の一九六五年一月二十四日の集会では、アメリカ黒人の歴史についての話をしています。奴隷船でアフリカから連れて来られる以前に、アフリカにいかに豊かな文化があったか、いかに自分たちの祖先が優れた人々であったか、又、いかに巧妙な手段を使って白人たちが黒人に白人優位の考え方を植えつけてきたか、そして今、自分たちが何をしなければならないのかなどを語りました。マルコムは、翌月に予定されていた「黒人歴史週間」やアメリカ黒人の呼び方「ニグロ」の欺瞞性を厳しくただして、次のように言っています。
なかでも、特に質の悪いごまかしは、白人が私たちにニグロという名前をつけて、ニグロと呼ぶことです。そして、私たちが自分のことをニグロと呼べば、結局はそのごまかしに自分が引っ掛かっていることになってしまうのです。……私たちは、科学的にみれば、白人によって産み出されました。誰かが自分のことをニグロと言っているのを聞く時はいつでも、その人は、西洋の文明の、いや西洋文明だけではなく、西洋の犯罪の産物なのです。西洋では、人からニグロと呼ばれたり、自らがニグロと呼んだりしていますが、ニグロ自体が反西洋文明を証明するのに使える有力な証拠なのです。ニグロと呼ばれる主な理由は、そう呼べば私たちの本当の正体が何なのかが分からなくなるからです。正体が何か分からない、どこから来たのか分からない、何があなたのものなのかが分からないからです。自分のことをニグロと呼ぶかぎり、あなた自身のものは何もない。言葉もあなたのものではありません。どんな言葉に対しても、もちろん英語に対しても何の権利も主張できないのです。[『マルコムX、アメリカ黒人の歴史を語る』 Malcolm X on Afro-American History (New York: Pathfinder, 1967), p. 15]
そして、ニグロが、人類をコーカソイド、モンゴロイド、ニグロイドと分類した「いわゆる文化人類学」の用語に由来しており、アフリカ・アジア侵略を正当化し、白人優位の考えを浸透させようとする西洋列強の手先にしか過ぎなかった文化人類学者のでっち上げであるとマルコムは断言しました。もちろん、マルコムはニグロという言葉の問題だけを言ったのではありません。むしろ、ニグロという言葉、つまり、その現象を生んだ背後にひそむ、侵略を正当化しようとする白人社会の総体的な意志や利欲、白人優位・黒人蔑視の考え方を指摘し、そのことに気づくための自己意識の変革の大切さを語ったのです。
ビコもマルコムと同じように、白人優位の思想から生み出された「ノン・ホワイト」という言葉を拒みました。植民地支配の道具に使われた宗教や教育など、白人から押しつけられたものを拒否し、自分自身の意識変革から出発しようとしました。死を覚悟して銃弾に立ち向かった一九七六年のソウェト蜂起は、アフリカーンス語教育を押しつける体制側ヘのたたかいであると同時に、自己意識の変革を通して、長年の抑圧によって蝕まれた心から白人優位の考えを洗い流し、自らの人間性を取り戻そうとする、若者たちの二重のたたかいでもあったのです。
マルコムは三十九歳、ビコは三十歳の若さで体制の犠牲になって、二度と還らぬ人となりました。しかし、二人の問いかけは、西洋中心社会から今だに抜け出られないでいる現在の私たち自身の問題でもあるのです。
従来の白人優位の考え方を根本的に見直して、アフリカを考える試みが、アフリカ人だけでなく、色々な国の人たちによってもなされています。今回は「スウェーデンのアフリカ・グループ」が出版した『アフリカの闘い』The Struggle for Africa (London: Zed Press, 1983)と、数年前にNHKで放映された、イギリスの歴史家バズゥル・デヴィドスンが語るイギリスMBTV制作「アフリカ八回シリーズ」を軸に、ルネッサンス以降の西洋諸国によるアフリカ侵略の歴史について考えてみたいと思います。
奴隷貿易
デヴィドスンは、ルネッサンス以前のヨーロッパ絵画を紹介し、白人優位・黒人蔑視の風潮を「比較的、近代の病なのです」と指摘しながら、つぎのように語ります。
八世紀、十九世紀のヨーロッパ人は、祖先の知識を受け継ごうとはしなかったようです。それ以前のヨーロッパ人は、例えば西アフリカに、中世ヨーロッパにひけをとらない立派な王国がいくつもあることをよく知っていました。しかも、そうした王国を訪れた貿易商人や外交官の報告には、人種的な優越感をにおわせる態度は全く見られません。人種差別というのは、比較的、近代の病なのです。この違いを何よりよく語っているのは、ルネッサンスまでのヨーロッパ絵画です。ここには、黒人と白人が対等に描かれています。非常に未熟な人間という後の世の言葉を思わせるものはありません。美術の世界だけではありません。中世では、広く一般に、黒人は白人と対等に受け入れられていました。「アフリカシリーズ 第一回 最初の光 ナイルの谷」
西アフリカにヨーロッパ人が来るようになるのは十五世紀の半ば頃からですが、最初は貢ぎ物と引き換えに、国王たちが許可を与えるという形で交易が始まりました。当時のヨーロッパ人は、その頃の王の権威や宮廷の華やかさを伝える記録を多く残しています。そのような王国の一つ、ベニン王国を千六百年頃に訪れたオランダ人は次のように書いています。
都は三十の大通りが碁盤の目に交錯している。どの大通りも真っすぐで、大層広い。家は整然と並び、鏡のように磨きたてられている。清潔さという点では、ここの人たちは、オランダ人に少しもひけをとらない。立派な法律や警察組織もあり、住民は交易にきた外国人に極めて友好的であった。「アフリカシリーズ 第三回 王と都市」
ヨーロッパは八世紀から十五世紀にかけて、急速な社会の発展を遂げますが、それでも、かなりの発達段階に達していた近隣のアフリカ諸国には多くの点で劣っていました。たとえば、一四九七年に初めて喜望峰を回って北上したヴァスコ・ダ・ガマは、ペムバ、キルワ、モンバサなどの華やかな都市に目をみはっています。アラビア商人によってアフリカの内陸部やメソポタミヤ、ペルシャ、インド、中国を結ぶ黄金の交易網が張りめぐらされて、二百年に渡る繁栄を続けていたからです。ポルトガル人は東アフリカとの交易をもくろみますが、商品が劣っていたために相手にされませんでした。そこで、ポルトガル人は東海岸の貿易を独占するために掠奪を始めます。キルワの例をあげて、デヴィドソンが語ります。
その年、ヴァスコ・ダ・ガマが率いる小さなポルトガル船三隻が、歴史上初めて喜望峰を回り、インド洋へと入っていきました。ここにヨーロッパ人の侵略が始まります。ポルトガルへ戻ったガマは、旅先で目にしたものを報告しました。そして、七年後の一五○五年、今度は前より大きな武装した船団が水平線に姿を現わしたのです。それに同行したドイツ人ハンス・マイルは、目撃したことをこう書いています。
「ダル・メイダ提督は、軍人十四人と六隻のカラブル船を率いてここに来た。提督は、大砲の用意をするように全船に命令した。七月二十四日木曜未明、全員ボートに乗り上陸、そのまま宮殿へ直行し、抵抗するものはすべて殺した。同行した神父たちが宮殿に十字架を下ろすと、ダル・メイダ提督は祈りを捧げた。それから、全員で街の一切の商品と食料を掠奪し始めた。二日後、提督は街に火をつけた」「アフリカシリーズ 第四回 黄金の交易路」(本誌十四号十一、十二頁参照)
こうしてヨーロッパ人のアフリカ侵略が始まります。ヨーロッパ人のねらいは、主にスパイス、布、金、象牙などでしたが、明らかに理不尽な侵略が出来たのは、火薬を人殺しの道具に使用した狡猾さ、相手にされないなら掠奪してしまえという侵略性、祈りを捧げてから掠奪や殺戮行為をなし得る傲慢さや残虐性などをヨーロッパ人が備えていたからでしょう。マルコムもヨーロッパ人の侵略性や残虐さを指摘し、中国で発明された火薬をヨーロッパ人が人を殺すための道具として使い出してから黒人が戦場で敗北し始めた、と言って、次のように続けます。
中国人は、火薬を平和な目的のために使いました。たしか、マルコ・ポーロだったと思いますが、マルコ・ポーロは火薬を手に入れて、ヨーロッパに持ち帰りました。そして、ヨーロッパ人はすぐにその火薬を人を殺すために使い始めます。ここが違う所です。ヨーロッパ人は、他の人たちが求めないものを必死になって獲ようとするのです。ヨーロッパ人は、殺すことが好きなんです、そう、本当にそうなんです。アジアやアフリカでは、食べ物のために殺します。ヨーロッパでは、楽しみのために殺すのです。そのことに気が付いたことはありませんか。あの人たちは血に飢えているんです、血が好きなんです。自分の血ではなく、他人の血が流れるのを見るのが好きなんです。あの人たちは血に飢えていますが、昔のアジアやアフリカのどの社会でも、獲物を殺すのは、食べ物のためで、楽しみのためではなかったのです……白人が黒人をリンチした話をよく聞きますが、黒人をリンチしながら、白人は刺激を得て、スリルを楽しんでいたんですよ。でも、あなた方も私も、殺すときは、食べ物のためか自分を守るためかのどちらかの必要性があるからなんです。そこのところをよく考えてほしいのです。(『マルコムX、アメリカ黒人の歴史を語る』二十八頁)
当初、ポルトガル人は海路と海岸線を支配しただけでしたが、ポルトガルに続いて、初めはオランダが、次にはイギリスとフランスが参入して、東海岸貿易の支配権をめぐって競争を繰り広げ、次第に本格的な侵略を開始していきます。
西海岸で海賊まがいの行為をしていたポルトガル人は、すでにアフリカ人を奴隷として本国に連れかえっていました。しかし、その規模は小さく、奴隷も権利は認められてはいなかったものの結婚も認められ、一般の貧しい人たちとそう変わらない生活を送っていました。奴隷貿易の性質や重要性を根本的に変えたのは、スペイン人による南アメリカ大陸の侵略です。栄えていたペルー、ボリビア、メキシコなどを武力で制圧したスペイン人の多くは、農民としてその地に留まり、そこに住んでいた人たちを強制的に働かせました。しかし、病気や劣悪な労働条件に耐えられず、強制労働を強いられた人たちの大半が死んでしまいます。鉱山や農場での汚なくて辛い仕事をする労働者を必要としたヨーロッパ人は、その労働力をアフリカに求めました。ヨーロッパ人がアフリカに目を向けたのは、もちろん距離的に近かったこともありますが、当時、アフリカが鉱山技術でヨーロッパよりも優れていたために熟練した鉱山技師が少なからずいたからでもありました。
一五一八年に、スペイン船が初めての積荷を直接アフリカからアメリカに運んだと言われています。それから三百五十年に渡って、アフリカ人が奴隷として西インド諸島や北、南、中央アメリカに売られていきました。奴隷の三分の二は西アフリカから、残りの大部分はコンゴやアンゴラから連れ出されました。デヴィドソンによれば、少なく見積もって千五百万のアフリカ人が売買されたと言います。輸送の途中や、奴隷狩りやそれに伴なう争いや飢きんなどの際に多くのアフリカ人が死んでいますから、おそらく被害者の数は、二千万から、三千万、あるいはそれ以上であったと考えられます。
奴隷貿易は「ヨーロッパで奴隷船に銃や布を積みこんでアフリカに向かう➝アフリカで銃や布を奴隷に換え、奴隷船に積みこんでアメリカに運ぶ➝アメリカで奴隷を売り、綿や砂糖、タバコなどの原材料を積んでヨーロッパに帰る➝ヨーロッパで原材料をさばいて高利を得て、その利益を布や銃の製造にあて、再び布や銃を積みこんでアフリカに向かう」というヨーロッパ、アフリカ、アメリカの三点を結んで行なわれました。いわゆる三角貿易です。一九七七年に全米を沸かしたテレビ映画「ルーツ」は、奴隷貿易の一部を画面に再現しましたが、ニューイングランドのアナポリス港に着いた奴隷船の中で、奴隷を商うアンドルーズ商会の代理人ジョン・カリントンと奴隷船ロード・リゴニア号のデイヴィス船長が交わす次の会話は、三角貿易の内容を端的に示しています。
デイヴィス「ガンビア川の河口で、百四十人の奴隷をロード・リゴニア号に乗船させました」
カリントン「それは、ゆったりとした積み方で。それで……」
デイヴィス「そのうち、港に着いたときの生き残りは九十八人でした」
カリントン「九十八人。そうですか、それじゃ死んだのは三分の一以下ですな。入港した時に、生き残りが半分以下でも、まだかなりの利益があった奴隷商を私は何人も知っておりますよ。おめでとうございます、船長」
デイヴィス「一刻も早く積荷を下ろしたいのですがね」
カリントン「直ちに船を引いて行って、岸壁にお着けしましょう」
デイヴィス「船倉で燃やす硫黄の粉をぜひご用意いただきたい。もう一度、きれいになった船が見たいのです」
カリントン「それは、もう、船長。それから、船長はまた、ロンドンへタバコを運んで行かれることになりますね」
デイヴィス「そして、ロンドンで……」
カリントン「ギニア海岸向けの貿易の品を、それから、またガンビア川に向けて」
デイヴィス「そして、もっとたくさんの奴隷を……」
カリントン「その通りですよ、船長。かくして天は我らにほほ笑みかけ、黄金の三角で点と点を結ぶ。タバコ、貿易の品、奴隷、タバコ、貿易の品など、永遠に限りなく。誰もが得をし、損するもの誰もなし、ですよ」
「誰もが得をし、損するもの誰もなし」の言葉どおり、奴隷船の船長をはじめ、奴隷商や奴隷を使う大農園主が暴利をむさぼりますが、これほど大規模な経済的不均衡が生じたことは、それまでにはおそらくなかったでしょう。奴隷貿易や奴隷制によって生じた偏った経済的不均衡によって、アフリカ社会は甚だしく疲弊し、西洋社会、特にアメリカとイギリスの金持ちは莫大な利益を獲得します。その利益は蓄積されて、やがて産業革命を引き起こす要因となるのです。
奴隷貿易や奴隷制によって生じたのは、経済的不均衡だけではありませんでした。それまであった交易の相手としての平等な関係は消え去り、白人優位・黒人蔑視の考え方が定着していきます。鎖につながれて船に運ばれるとき、あるいはアフリカからアメリカに向かう奴隷船の中で、あるいはアメリカの岸壁での競買で、アフリカ人は家畜並みの扱いを受けました。また、アメリカの農園では、アフリカ人とその子孫は、しばしば人間以下の扱いを受け、時には見るものが目をそむけたくなるような屈辱を味わいました。
奴隷貿易の最盛期に、初めて奴隷船に乗ったデイヴィス船長から、黒人についての質問を受けたスレイター一等航海士の次の話からも、黒人がどのように白人に考えられていたかの一端がうかがえます。
奴らは別の人種なんですよ、船長。人間が狩り用に犬を育てたり、女子供のペット用に育てたりするのに似ていますな。黒人っていう人種は、まあ、おつむの方は弱いんですが、体の方はいたって頑丈なんです。奴ら、奴隷にぴったりなんです。ちょうど、船長がこの船の船長にぴったりなように。自然の摂理ってやつですかな。
奴隷貿易が激しくなるにつれて、ますますその考えは浸透していきました。
奴隷貿易によって苦しみを味わったのは、連れ去られたアフリカ人やその子孫だけではありません。残された人たちもまた、共同体の柱を奪われて深い苦しみを味わったのです。奴隷貿易の被害にあった地域は人的な資源を失なって、急速に疲弊していきます。そして、ヨーロッパから来た安い製品によって、それまでかなり発達していた手工業の技術も衰えていきました。
植民地支配
奴隷貿易によってもたらされた最大の変化は、蓄積された資本によって産業革命が可能になり、資本主義に向けての発達過程が早まったことです。おそらく、欲に目のくらんだデイヴィスもカリントンも、自分たちのやっている奴隷貿易が、後の世にそれほど大きな経済的、社会的変化をもたらすことになろうとは、当時、夢にも思わなかったでしょう。
奴隷貿易やアメリカの鉱山や大農園の奴隷労働から得た多額の利潤を、自国の産業の発展のために投じるようになったヨーロッパの資本家は、徐々に力をつけて、それまで国を動かしていた奴隷商をしのぐようになり、奴隷制を廃止するに至ります。奴隷制よりも儲かる商売を見つけたというわけです。その人たちの関心は、産業のための原材料と労働者の低賃金を保障してくれる安価な食糧を確保することでした。
産業革命が最初に起こったのは、奴隷貿易で一番潤ったイギリスでした。十九世紀前半のことです。それまでは手で作っていたものを機械でつくるわけですから、かなり多くの製品が生産されるようになります。それでも、まだ、製品をさばくための市場の問題は起きていませんでした。しかし、十九世紀後半になって状況は一変します。イギリスに続く他のヨーロッパ諸国とアメリカ合衆国が、関税を引き上げて自国の産業を保護したために産業が巨大化し、余剰生産物を生み出す結果になったからです。つまり、消費者が買える以上の生産が可能になったのです。アメリカとドイツはなお、自国産業の保護政策を取り続けますが、イギリスとフランスは、生産拡大のための新しい市場を探さなければならない段階にまで産業が発達していました。そうした事態を打開してくれるのが、市場と原材料を確保してくれる植民地でした。こうして、ヨーロッパ列強によるいわゆるアフリカにおける植民地争奪戦が始まります。
アフリカ争奪戦はかなり激しいものとなり、戦争の危機さえはらむようになりますが、植民地を搾取するという共通の利害関係と、台頭しつつあった自国内の労働者階級への不安もあって、一八八四年から八五年にかけて、西洋諸国が調停のために話し合いのテーブルにつきます。これがベルリン会議です。ヨーロッパ列強によって「正式に」アフリカが植民地として分割されたわけですが、実際は、すでに行なわれていた植民地争奪戦の結果を確認し合っただけに過ぎませんでした。
一番大きな分け前を取ったのはイギリスで、エジプト、ケニア、ナイジェリア、ゴールド・コースト(現ガーナ共和国)など一番いい場所を確保しました。次いでフランス、ドイツの順で、特に産業化のすすんだその三国で全体の八十%を占めました。残りを、ベルギーとイタリア、それにポルトガルとスペインが分けてアフリカ分割が完了し、本格的な植民地支配が始まります。余剰製品を売りさばく市場を確保し、原材料の価格を思い通りに操作するためには、植民地内のアフリカ人を完全に掌握し、管理しなければなりませんでした。支配の仕方は、その地域社会の発達段階によって異なりますが、中央集権化の進んだ地域では、その統治機構や支配者層をうまく利用しました。これがいわゆる間接統治で、進んだ地域を占領したイギリスは、おおむねこの支配形態を取りました。あまり発達していない地域を支配したフランスなどは、直接統治の形態を取りました。
一部の地域を除いて、各地でアフリカ人による強い抵抗運動がありますが、ヨーロッパ列強は資本と武器の力にまかせて強引にそれらの抵抗運動を鎮圧します。ドイツに支配された南西アフリカのように、大量虐殺に及んだ例も少なくありませんでした。植民地での搾取は苛酷を極め、直接統治によって一千万人以上もの人が殺されたと言うレオポルド二世のベルギー領コンゴの例などは特によく知られています。
多くの植民地では、農園や鉱山での労働者を獲得したり、植民地支配のための資金を得るために、強制労働や人頭税や小屋税などの税金、あるいは輸出用作物の耕作などの方法が取られました。アフリカ人は否応なしに貨幣経済に巻きこまれ、重い税金を払うために、あるいは巷にあふれるヨーロッパ製品を買うために、現金収入の道を求めて村を離れざるを得ませんでした。出稼ぎ労働者の誕生です。ほとんどの場合、短期間の契約労働の形が取られました。熟練した技術を覚えさせずに単純労働に従事させるには短期契約が一番都合がよかったからです。契約期間が切れたら、賃金のベースアップなしに、新たに他のアフリカ人を雇えばいいのです。あり余る出稼ぎ労働者は、低賃金を確保するにはもってこいのシステムでした。出稼ぎ労働者として村の働き手を奪われることで、旧来のアフリカ社会は完全に崩壊していきます。
また、多くの地域では輸出向けの換金作物を強制的に作らされました。セネガルのピーナッツ、ガーナのココア、タンザニアのコーヒーとサイザル麻、モザンビークの綿などです。大体が単一の作物で、以前のように自分たちが食べるのではなく、宗主国の産業用だったのです。土地を休めずに連作を強いられて土壌が疲弊しただけでなく、それまでの自給自足の形態も根本から崩れて、のちの飢餓の要因となります。輸出価格を含め、植民地の経済は、完全に宗主国に支配されるようになりました。
一方、ヨーロッパでは、アフリカ人を幼稚で怠け者で救いようのない野蛮人と決めつけて、さかんに笑い者にしました。そうでもしなければ、国を取り上げて甘い汁を吸うことを正当化できなかったでしょう。ありとあらゆる形で自らの侵略を正当化する試みがなされて、白人優位・黒人蔑視の考え方はしっかりと定着していきました。
新植民地支配
「白人同士が殺し合った」第一次、第二次世界大戦では、アフリカ人も駆りだされ、多くの犠牲者を出しました。しかし、両大戦で白人と共に銃を持って闘ったアフリカ人は「自分たちにもやれる」という自信を持ちました。戦争で荒れ果てた自国の復興に追われる西洋諸国を尻目に、アフリカは独立に向けて静かに動き始めます。
独立の先頭に立ったのは、宗主国のヨーロッパやアメリカに留学したことのある知識階級の若者たちでした。ブラック・アフリカでは、それまで模範的な植民地とされていたゴールド・コースト(現ガーナ共和国)が一九五七年に最初に独立を果たします。イギリスはあらゆる手段で独立を阻止しようとしますが、大衆の圧倒的な支持を得たクワメ・エンクルマの勢いを止めることは出来ませんでした。時代の流れには逆らえず独立を許しますが、元植民地の利権を守るための新たな手口を考え出します。いったん独立を認め、形式的にアフリカ人に政治はやらせるものの、混乱に乗じてやがては軍事介入、実質的な経済力を握ってそれまでの利権を守るというやり方です。これが今も続く新植民地政策です。その意図は、エンクルマの次の自伝の一節からもはっきりと読み取れます。
遺産としてはきびしく、意気沮喪させるものであったが、それは、私と私の同僚が、もとのイギリス総督の官邸であったクリスチャンボルグ城に正式に移ったときに遭遇した象徴的な荒涼さに集約されているように思われた。室から室へと見まわった私たちは、全体の空虚さにおどろいた。とくべつの家具が一つあったほかは、わずか数日まえまで、人びとがここに住み、仕事をしていたことをしめすものは、まったく何一つなかった。ぼろ布一枚、本一冊も、発見できなかった。紙一枚も、なかった。ひじょうに長い年月、植民地行政の中心がここにあったことを思いおこさせるものは、ただ一つもなかった。
この完全な剥奪は、私たちの連続性をよこぎる一本の線のように思えた。私たちが支えを見い出すのを助ける、過去と現在のあいだのあらゆるきずなを断ち切る、という明確な意図があったかのようであった。[クワメ・エンクルマ著野間寛二郎氏訳『アフリカは統一する』(理論社、一九七一年)十四頁。Kwame Nkrumah, Africa Must Unite (1963; Panaf, rep. pp. xiv-xv.)]
結局、エンクルマは、一九六六年にベトナム戦争収拾の協力で極東に出向いている間に、クーデターを起こした軍部に失脚させられてギニアに亡命、六年後、失意のうちに病死するはめに陥りました。
ベルギー領コンゴ(現ザイール)の場合は、もっと悲惨です。一九六〇年、ベルギー政府は、政権をコンゴ人の手に引き継ぐのに、わずか六ヵ月足らずの準備期間しか置きませんでした。ベルギー人管理八千人は総引き上げし、行政の経験者はほとんどなく、三十六人の閣僚のうち大学卒業者がわずかに三人といった状態になります。その結果、独立後一週間もせずに国内は大混乱し、そこにベルギーが軍事介入、コンゴは「自治の能力なし」のレッテルを貼られてたちまち大国の内政干渉の餌食となりました。大国は、鉱物資源の豊かなカタンガ州(シャバ州)での経済利権を確保するために、首相パトリス・ルムンバの排除に取りかかります。危機を察知したルムンバは国連軍の出動を要請しますが、アメリカの援助でクーデターを起こした政府軍のモブツ大佐に捕えられ、国連軍の見守るなか、利権目当てに外国が支援するカタンガ州に送られて、惨殺されてしまいます。
独立は勝ち取っても、経済力を完全に握られては正常な国政が行なえるはずもありません。名前こそ変わったものの、搾取構造は植民地時代とあまり変わらず、「先進国」産業の原材料の供給地としての役割を担わされているのです。しかも、原材料の価格を決めるのは輸出先の「先進国」で、高い関税をかけられるので加工して輸出することも出来ず、結局は原材料のまま売るしかないのが現状です。サイザル麻を作らされているタンザニアの元大統領ニエレレは次のように嘆きます。
第一次五ヵ年計画を準備していた当時、サイザル麻の価格はトン当たり百四十八ポンドの高値でした。これは続くまいと考え、トン九十五ポンドの値を想定して計画を立てました。ところが、七十ポンド以下に暴落です。私たちにはどうしようもありません。
原料生産者は、一体どうしたらいいのか。サイザル麻を作って売るしかありません。その価格が下がったら、もうお手上げです。苦しむのはいつも弱者です。「アフリカシリーズ 第八回 植民地支配の残したもの」
また、カカオが主要輸出品であるガーナのローリングス議長は、怒ります。
ひどい話です。買い手が一方的にカカオの値段を決定する。昔はトン当たり三千五百ポンド。それが、今では千ポンド。奴隷並みに働いて、カカオを差し出している。一方で、輸入品の値段は天井知らずに上がっているが、押しつけられ、慣らされて、今や、買わずにはいられない。「同シリーズ 第八回 植民地支配の残したもの」
第二次大戦後は、再進出の西ドイツと、アメリカ、日本を加えた多国籍企業に経済を握られ、開発援助の名の下に累積債務は増えるばかり、より巧妙かつ複雑になった搾取構造の下で、アフリカ諸国は苦しんでいます。「先進国」の大幅な経済的譲歩がない限り、先の希望は望めそうにありません。その意味では、デヴィドスンのつぎの提言は、傾聴に値するでしょう。
飢えている国の品を安く買いたたき、自分の製品を高く売りつける。こんな関係が続いている限り、アフリカの苦しみは今後も増すばかりでしょう。アフリカ人が本当に必要としているものは何か。私たちは問い直すことを迫られています。
戦争、内乱、飢え、貧困、その中で、今、アフリカは何とか前進しようとしています。それを支えているのは、虐げられた歴史を覆した自信と未来に賭ける夢です。
奴隷貿易時代から植民地時代を通じて、アフリカの富を搾り取って来た先進国は、形こそ違え、今もそれを続けています。アフリカに飢えている人がいる今、私は難しいことを承知で、これはもうこの辺で改めるべきだと考えます。今までアフリカから搾り取ってきた富、今はそれを返す時に来ているのです。(「同シリーズ 第八回 植民地支配の残したもの」本誌十四号十三頁参照)
アフリカを考える
ニューヨークのラ・ガーディア空港か、シカゴのオヘア空港だったかは忘れましたが、もし日本だったら、こんな対応をするのかなあと考えたことがあります。予約の変更か何かで立ち寄ったのだと思いますが、どうも私の至らぬ英語がカウンターの相手には解りかねたと見えて、ちょっとお待ちくださいと言って「言葉」のわかる同僚を奥から連れてきました。しかし、「言葉」のわかるその人は、英語をゆっくりと話すだけで、日本語でサービスをなどという考えは全く念頭にはない様子でした。十年ほど前のことです。
アメリカ国内を旅行するとき、日本人がそこで話されている英語をしゃべるのは当たり前なのかも知れませんが、アメリカ人が日本を訪ねる場合には、必ずしもそうではありません。今では空港のカウンターで日本語がしゃべれなくてもそれほど不自由を感じる人は少ないでしょうし、観光地や地方の駅に行っても、不自由ながらも係員が英語を使ってくれたり、それでも通じないなら英語の話せる人を探してくれたりします。それが、日本を訪れた外国人に対する自発的な好意や親切心から生まれたものなら喜ばしいことなのでしょうが、中国語で話す中国の人に、ベンガル語で語りかけるバングラデシュの人に、果たして同じ対応をするのかと考えるとき、個人を超えた大きな意思のようなもの、黒人蔑視・白人優位にも似た風潮がここにも厳然と生き続けていると感じないわけにはいかないのです。
確かに、国際社会での英語の重要性は増しています。しかし、裏を返せば、イギリスがそれだけ多くの国からたくさんのものを奪い取ったということです。たとえば、八十九年十月にクアラルンプールで開かれたに英連邦首脳会議には、四十九ヶ国が参加していますが、それは、英語を公用語にしている南アフリカを加えた五十ヶ国にも及ぶ国が、かつてイギリスに支配され、搾取されただけでなく、母国語以外の言葉を押しつけられるという蹂躙を受けたことに他なりません。一九八六年にノーベル文学賞を受けたナイジェリアのウォレ・ショインカが八七年に来日した際に「自分の言語であるヨルバ語でものを書くことは石器時代に逆戻りするにも等しい」と発言したことにケニア人のムアンギさんが異議をはさんでいるのは、それまで英語で作品を書いていたグギさんがギクユ語とスワヒリ語でしか書かなくなった意味合いを考えてほしかったからでしょう。また「ショインカが語るのを聞いた日本人の中でショインカが自分の言葉を低く見ていることを気にした人はそう多くはいなかっただろう」という評は、第二次大戦後、特にアメリカの影響をもろに受けて、横文字が氾濫し、まるで英語を話すことが美徳でもあるかのような日本の風潮への厳しい警告ではなかったでしょうか。(サイラス・ムアンギ「グギの革命的後段言語学1」、本誌十一号三十四頁~三十八頁参照)
今回の湾岸戦争で、西側の情報がいかに一方的に流されていたかを痛感した人も少なくないでしょう。その背後には、中東における石油の権益を確保しようと躍起になっている西側諸国の総体的な意思が見え隠れしていました。その点ではアフリカに関しても、同じことが言えます。たとえば、経済的につながりの強いケニアに関する情報は、いまだに美しい自然や野性の王国といったものばかりです。独裁的な恐怖政治のもとで多くの人が亡命を強いられているといった負のイメージはなかなか伝わってきません。しかし、グギさんは、新植民地主義支配の手先であると体制を批判してナイロビ大学を追われ、亡命生活を強いられています。また、ナイロビ大学の卒業生でもあるムアンギさんによれば「私と同世代のナイロビ大学関係者や政治の批判者たちはディテンショナルな刑務所に入れられているか、亡命しているか、殺されたか、これら三つのどれかにあてはまっていると言える程である」とのことです。(本誌十二号二十四頁参照)そこにもやはり、マスメディアを巧みに利用する体制側や貿易によって潤っている大企業や国の大きな意思のようなものが垣間見られます。そのように考えますと、マルコムXやビコが問いかけた自己意識の問題は、本当は、大きな総体的な意思に慣らされてしまって本質を見失いがちになっている現在の私たちの問題なのではないでしょうか。
そういう意味では、アフリカを考えることも、自分を見つめ直したり、自分の立場を考えたりする一つのきっかけになると思えてならないのです。
「アフリカを考える—自己意識と侵略の歴史」は、昨年の十月二十二日の月曜会でお話した「アフリカを考える—アフリカ、そして南アフリカ」と、南九州大学大学祭での海外事情研究部の主催による講演会「アフリカを考える—アフリカ」をもとにして書いたものです。
月曜会は宮崎市とその周辺の歯医者さん有志が、毎日見ている小さな口の中ばかりでなく、他の世界のことも知ろうと月一回集まって開いておられる勉強会で、治療や検診でお世話になっているタチカワ・デンタルクリニックの院長立川俊介さんのご紹介で、今回、お招きにあずかりました。
海外事情研究部は、海外渡航や他大学との交流などの広範な活動をしている創立二十五年目のサークルですが、昨年の統一研究のテーマ「アフリカ」と顧問の宮下和子さんのご縁で、講演が実現しました。
お世話下さった月曜会の立川俊介さんと運営委員の石井千春さん、南九州大学海外事情研究部元部長の富田篤さん、現部長の河野弘志さんや部員の皆さん、色々お気遣い下さった宮下さんをはじめ、お話を聞いて下さった月曜会とタチカワ・デンタルクリニックのスタッフの方々、南九州大学講演会に参加して下さった皆様に深くお礼申し上げます。
一九九一年七月 宮崎にて
執筆年
1991年
収録・公開
「ゴンドワナ」19号(横浜:門土社)10-22ペイジ。