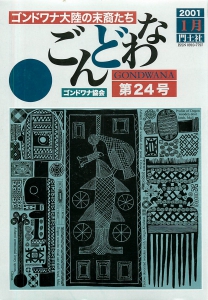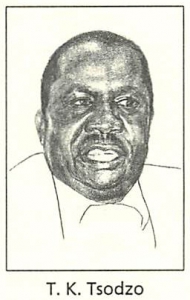概要
ジンバブエ人口の九十数パーセントに及ぶアフリカ人の四分の三を占めるショナ人と母国語のショナ語と英語をめぐる論文である。イギリス系の南アフリカ人によって侵略されたジンバブエでは、1980年に独立後も、西洋人とその人たちと手を組む少数のアフリカ人が大多数のアフリカ人を搾取する構造を維持しており、その支配体制に応じて言語事情も変化している。多数のショナ人は仕事を求めて英語を使うことを余儀なくされているし、知識階級における英語の重要性も増している。そんな立場にいるショナ人と支配者の言葉英語と母国語ショナ語をめぐる文化状況を分析した。
本文(写真作業中)
ショナ人とことば
ジンバブエ大学
ジンバブエに行ってから、八年が経つ。むこうで色んなことがあったはずなのに、記憶は日常の出来事の中に一つ一つ消えてゆく。
しかし、時折り、脈絡もなく、ある光景が思い浮かぶこともある。ジンバブエ大学のキャンパスの光景など、である。
ジンバブエの人口の九十数パーセントはアフリカ人で、その約四分の三がショナ語を話し、残りはンデベレ語を話すという。その二つのアフリカの言葉と英語が公用語である。
ジンバブエ大学は、南アフリカから移り住んだイギリス系の白人が自分たちのために創った大学で、瀟洒な白人居住区マウント・プレザント地区にあり、広大なキャンパスを持つ。日本では30年振りの大旱魃、と報じられていたが、キャンパスの芝生の上では、毎日、スプリンクラーがくるりくるりとまわっていた。
今は学生の大半がアフリカ人で、講義では英語が使われていた。接した学生は殆んどショナ人だったように思う。見せてもらった授業は英語科の授業だったから、ショナ人同士のやりとりがすべて英語でもおかしくはないのだが、問題は、授業が終わった後も、キャンパスではアフリカ人同士が英語を喋っていたことである。たしか、あの人たちはショナ人かンデベレ人だったはずなのに、みんな英語をしゃべっていた、そう言えば、キャンパスでは一切ショナ語を耳にしなかったような気がする……。
学生数が約一万のジンバブエ大学は人口が約一千万の国の唯一の総合大学で、選ばれた人たちの空間だったが、誰もが生活に精一杯のようで、部外者の受け入れが可能だとはとても思えなかった。英語科に問い合わせをした時も、返事の手紙に、カローラの九十年型を手配してもらえないかとあったから、在外研究員といっても、大学の建物を見てきただけで終わりという可能性もあった。それでも、行く前は、アフリカで家族と暮らせるだけでいい、と思っていた。
ツォゾォさん、アレックス
大学では二人のアフリカ人と親しくなった。英語科の教員トンプソン・クンビライ・ツォゾォさんと、学生アレックス・ムチャデイ・ニョタである。二人とも英語のファーストネイムを持つが、生い立ちなどを聞いているうちに、国の歴史的な経緯や二人の立場の違いなどがわかってきた。
西洋人が来たのは1880年代の後半で、目的は金だった。ケープ植民地相セスゥル・ローズは、第二のヴィットバータースラント(現ジョハネスバーグ)を夢見て、私設軍を送りこんだ。豊かな鉱脈は見つからなかったが軍隊は立ち去らずに侵略を始め、後に大量の移住者が流れこむようになる。
西洋人の侵略と戦ったのは、ツォゾォさんたちのお爺さんの世代だろう。お父さんの世代には、既に豊かな土地は取り上げられ、アフリカ人の大半は安価な賃金労働者に仕立て上げられていた。ジンバブエでは、同じ先祖から枝分かれした一族(クラン)の指導者のもとで農耕や牧畜が行なわれており、二人のひいお爺さんの世代までは、白人の脅威は存在しなかったはずである。英語のファーストネームには、侵略者の享受する豊かな生活に対する、親の世代の憧れや、無意識の願いがこめられていたのかも知れない。
定住した白人は、1920年代に南アフリカとの合併を拒み、独自の路線を歩む。西洋の資本、安価なアフリカ人労働力、豊かな鉱物資源などによって、南ローデシア(現ジンバブエ)は第二次大戦を境に一大工業国になっていた。充分に経済力と軍事力をつけた南ローデシアは、六十年代にイギリス政府の意向を無視して独自の路線を進むのだが、アフリカ人の力を知っていた政府は、アフリカ人中産階級を育てる政策をとった。クランの指導者の家系に生まれたツォゾォさんが、南ローデシア大学(現在のジンバブエ大学)に入学したのもその改革によるもので、1968年のことだった。1500人の学生のうち、300人がアフリカ人だったそうである。
1966年にはソ連と中国の支援を受けて独立闘争が始まり、1980年に独立を果たすのだが、独立は経済を欧米や日本に依存する妥協の産物だった。
独立闘争で活躍したツォゾォさんは、独立後、文部省を経て、ジンバブエ大学の教員となり、副学長補佐に昇任している。アレックスは、頭の良い普通の家の子弟で、奨学金をもらいながら大学生活を楽しんでいた。
ツォゾォさんには授業を見せてもらい、出来る限り話を聞いた。アレックスには子供の英語の家庭教師を頼み、学生寮やアフリカ人居住地区や街中に連れて行ってもらった。短かい期間ではあったが、二人を通してのジンバブエの一端を垣間見たように思う。
ゲイリー
ハラレでもう一人のアフリカ人と親しくなった。私たちがスイス人の老婆から借りた家に「ガーデンボーイ」として雇われていたガリカーイ・モヨ、通称ゲイリーである。ゲイリーは、同じ敷地内の小さな部屋に住んでいた。私たちは雇い主ではなかったから、最初から、友だちづきあいとなった。
到着した七月の終わりに、冬休み(北半球とは季節が逆)を利用してゲイリーの家族がやってきて、同じ敷地内に二家族が同居することになった。私たちの子供二人とゲイリーの三人の子供たちは、通じる共通の言葉こそなかったが、存分に楽しんでいた。
金持ちと貧乏人しかいない国の不動産事情は極めて悪いと言われていたので、ホテル住まいも覚悟していたが、運よく月額十万円の家賃で一軒の家を借りることが出来た。敷金などもなく五百坪ほどの敷地の家を、住んでいたままの状態で借りられたのだから、私たちに不満のあるはずもなかった。
一緒に暮らすうちに、ゲイリーの給料が月に四千円余り、一年の大半は家族と離れて暮らし、親子五人が寝泊りする部屋が、ベットもないコンクリート床の二つの小さな部屋だということなどがわかってきた。子供たちが庭で遊ぶ時に使っていたバスケットボールは、一個五千円ほどだった。
ある朝、ゲイリーは「バケツに一杯お湯をもらえませんか」と言ってきたが、その時初めて、「召し使い」の部屋では、トイレの水のシャワーしか使えないことを知ったのである。滞在中に私たちはゲイリーに色々頼み事をしたが、ゲイリーから頼まれたのは、そのバケツ一杯のお湯だけだった。
九月に入るとゲイリーの子供たちのうち二人は田舎に帰っていった。私たちは十月初めの帰国までに二人の小学校を訪ねる計画を立てた。ハラレから百キロほどの所にあるゲイリーの田舎のルカリロ小学校を訪ねたのは、九月の半ばである。運転手つきの車を借りて訪れた小学校では、全校あげての大歓迎を受けた。私たちは村始まって以来の外国人訪問客だったそうである。そこで、その住民の大半と、殆んどすべての小学生がショナ語しか話せず、ゲイリーの家族は、遥かに望む山裾までの広大な土地を持っている事実を知ったのである。ゲイリーも父親も、白人の貨幣経済の渦中に投げこまれ、現金収入を得るために村を離れることを余儀なくされた、典型的な安価なアフリカ人賃金労働者だったのである。
研究室も貰えず、途中でツォゾォさんの昇進人事がなかったら、図書館の利用許可証さえ貰えずじまいになる所だったが、二ヵ月半の短かい期間に、体制側にいるツォゾォさんとアレックスと、搾取される側にいるゲイリーに巡り会えたのは、実に幸運だった。
ことば
アレックスはアメリカ映画の影響で、日本では今も街中にニンジャが走っているのを疑わなかった学生の一人だったが、ある時、経済力のある日本はどうして他の人たちに日本語を話させないのかと聞いたことがあった。
考えてみれば、ほぼ百年の間で、アレックスたちの国の人たちは、侵略者の言葉の英語を日常に使うようになっている。ハラレにいるあいだ、市役所でも銀行でもデパートでも、レストランでもスーパーでも、接したのは殆んどアフリカ人だったが、英語で事足りた。ショナ語で話しかけられたことはない。生活の隅々にまで、英語が浸透していたのである。
ルカリロ小学校の生徒は、英語が苦手だったようである。卒業して街で働き出すときには英語が必要で、必死に言葉を覚えるのだろう。
ゲイリーも日常の生活に支障のない程度の英語を使っていた。その後も手紙の遣り取りをしているが、綴りの間違いはあるものの、意志の疎通には支障がない。
何事も一旦制度化されると、それが一人歩きする場合が多い。元々母国語以外の言葉を覚えるのは面倒で、日本に来る大半の欧米人は、片言以外の日本語を覚えようとしない。それは言葉を使う必然性に乏しいからで、周りにはそういった人がたくさんいる。
ことばが人の文化や生活を伝える手段ならば、昨今の英語の隆盛は、英語を母国語とする人たちの文化的侵略の延長線上にある、と言える。
当初はアメリカの軍事目的でつくられたコンピューターの普及は目覚ましく、使われる言語は圧倒的に英語である。裏を返せば、英語を母国語とする人たちの文化の侵略の度合いがますます高まっているということである。
ショナ人同士が母国語のショナ語を使わずに英語を使いたがる傾向は、その侵略の度合いが、もう抜き差しならない所まできているということだと思う。その現象は、ジンバブエだけでなく世界の至る所にまで及んでいる。
先日も、小田実さんが「まかり通るインド英語支配」というエセイのなかで、家庭内でも子供に英語を話し、欧米国で教育を受けさせるインドの親たちに「それは文化の侵略じゃないのかね」と尋ねたら、「何を言ってる、侵略そのものだ」と言い返されたいう話を記していたが、意識的にその状況に便乗して生きている中産階級層が増えているということだろう。
日本でも英語の第二公用語化の論議が喧しい。国際化に備えての運用能力を高めるためだそうである。そう遠くない将来、ジンバブエのように、都会では意識的に英語が使われ、大学のキャンパスでは、日本人同士が英語を喋るようになっているかも知れない。
執筆年
2001年
収録・公開
「ごんどわな」24号62-65ペイジ