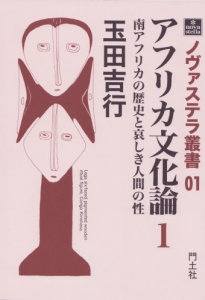概要
日本と深い繋がりのある南アフリカを、南アフリカの歴史を軸に、エイズなどの諸問題を通してすかし見える人間の哀しい性について論じたものです。20年近く英語やアフリカ文化論の授業の中出で取り上げて来たテーマの一つを、南アフリカという題材を通して論じたものでもあります。
本文(写真作業中)
目次、1章(はじめに)、15章(哀しき人間の性)、南アフリカ小史、奥付けを載せています。↓
目次
1章 はじめに 3
2章 「アフリカの蹄」 4
3章 南アフリカ概観 6
4章 アフリカ史のなかで 9
5章 ヨーロッパ人とリザーブ 12
6章 アパルトヘイトと抵抗運動 15
7章 ロバート・マンガリソ・ソブクウェ 19
8章 武力闘争 24
9章 アレックス・ラ・グーマ 26
10章 バンツー・スティーヴン・ビコ 28
11章 セスゥル・エイブラハムズ 30
12章 体制を支えたもの 35
13章 ネルソン・マンデラの釈放 39
14章 エイズと『アフリカの瞳』 43
15章 哀しき人間の性 52
註 57
南アフリカ小史 62
1章(はじめに)
この小冊子は、「アフリカ文化論」「南アフリカ概論」などの授業で話した内容をまとめたものです。
書く空間を求めて辿り着いた宮崎医科大学は旧宮崎大学と統合して宮崎大学となり、今はそこで英語と一般教養の科目などを担当しています。
授業では、折角大学で学ぶ空間を得た人に、価値観や歴史観を問い直してもらえればと考えて、アフリカなどを題材に取り上げています。アフリカ史を辿れば、英語が一番侵略的だった英国の言葉であることも、白人優位・黒人蔑視の思想が都合よく捏造されて来たことも判ります。アフロ・アメリカ史を見れば、今日のアメリカの繁栄が奴隷貿易や奴隷制の上に築き挙げられたことも分かりますし、全てが過去の出来事の羅列ではなく、過去から繋がっている現在の問題であることにも気づきます。
元来、自由な空間で培う素養は大切なものです。素養が価値観や歴史観の基盤でもあり、生き方を決める要素でもあるからです。大学に入学するために大量の知識を詰め込んできた人に、今までの歴史観や考え方そのものを揺さぶるような話をして、「さすがは大学だ」と思ってもらえるような授業がしたいといつも思っています。この小冊子が、自分自身について考えるための一助になれば嬉しい限りです。
1章ではこの小冊子の生まれた経緯を、2章では「アフリカの蹄」の中の問いかけを、3章では南アフリカの地理や言語などの紹介を、4章ではアフリカ史の中での南アフリカを、5章ではヨーロッパ人入植者が打ち立てた搾取機構を、6章ではアパルトヘイト体制とアフリカ人の抵抗運動を、7章では抵抗運動を指導したソブクウェを、8章では武力闘争の経緯を、9章ではアパルトヘイト体制下の作家ラ・グーマを、10章ではカナダで出会った学者エイブラハムズさんを、11章では黒人意識運動の指導者ビコを、12章ではアパルトヘイト体制を支えた実体を、13章ではマンデラの釈放とその後の実状を、14章ではエイズの実態を、15章では人間の性についての正直な思いを綴っています。
最後に、註と南アフリカ小史を載せました。
15章(哀しき人間の性)
哀しき人間の性
長々と南アフリカの歴史を辿って来たわけですが、そこに浮かび上がって来るのは、侵略という行為を通して透かして見える哀しい人間の性です。
最初は、直接侵略に関わったオランダ人、イギリス人入植者においてです。ヨーロッパ人はある日、片手に聖書、もう片方の手に銃を携えて南アフリカに現われました。力ずくでアフリカ人から土地を奪って無産者に仕立て、種々の税を課して、大量の安価な労働力を産み出しました。そして、アフリカ人に金やダイヤを掘らせては巨万の富を築きます。搾取体制を守るために連合国家を作り、反対するものは自分たちの作った法律で罰して「合法的に」排除、抹殺してきたのです。いいものを食べたい、広い土地に住みたいという個々の欲望が集まって総体的な意思となりました。植民地政策は本国を潤し、世論にも支持され続けました。
次にその白人王国に群がり、手を携えて共に甘い汁を吸い続けて来た多くの「先進国」においてです。「先進国」は、これ以上はあからさまな搾取体制を維持出来ないことを悟ると、アパルトヘイト政権に自らが決定した法律を反故にすることを強いて「政治犯」を釈放させ、基本構造を替えない形でアフリカ人政権を誕生させました。
そして、新アフリカ人政権においてです。未曾有のエイズ禍に苦しむ国民に抗HIV薬を供給出来ないと見るや、まだ治験の済んでいない薬を無料で配布したり、安価で販売するという暴挙に出たのです。欧米の製薬会社はエイズまでも食い物にしたわけですが、新政権の担い手の大半は、長く苦しいアパルトヘイトとの闘いを続けて来たはずです。その人たちはどうして、欧米の製薬会社の言いなりになったのでしょうか。エイズに苦しむ同胞をどうして苦しませることが出来たのでしょうか。
最後に、日本人においてです。授業で出会う学生が、「暗黒大陸」や「未開の地」というあからさまな偏見は持たないにしても、多くは「アフリカ人はかわいそう」「アフリカに文学があるとは思わなかった」「日本は、ODAを通じてかわいそうなアフリカに支援してやっている」(註27)と考えています。貿易や投資でアパルトヘイト政権を支えて莫大な利益を得たばかりか、今も形を変えてIT産業に不可欠な希少金属や電力供給に欠かせないウランなどを通して利益を得続けている現実に無関心を装い、積極的に深くを知ろうとはしません。そして、「遠い夜明け」を見ると、たくさんの人が「日本に生まれてよかった」と胸をなで下ろし、私たちに何か出来ることはありませんかと言います。アパルトヘイトの抑圧の中でも、外的要因によって自己否定して自らに見切りをつける人たちに自己意識の大切を説き、自分への希望を捨てず、国に対しても希望を育もうと語りかけたソブクウェやビコの崇高さに比べて、その無知と無関心と傲慢さに虚しさを覚えます。
そんな狭間に立って現実と直面していますとつい悲観的になって、授業の最後に「もう溜め息しか、出ませんね」と呟きましたら、受講生から次のような反論が届きました。
「『人間について考えれば考える程に絶望的になる』『人間の問題の現状について努力することは大切だけれども、ほんの少ししか変わらないか、全く変わらないかのどっちかだろうな。』という考えは十分にわかります。が、それで終わってしまうのはどうでしょうか。もちろん絶望を知ることは大切なことです。絶望と向き合うこと無しでは、何も理解出来ません。しかし、先生は、折角教壇に立てる機会を持つことが出来ているのです。私達生徒に絶望だけ、無力感だけを叩き込むのではなく『行動することで、現状はほんのわずかしか動かない。けれども、そのほんのちょっとが大事なんだ。』という方向も教えたほうが、私には社会や国にとって有益だと思えるのです。こんな考え方は短絡過ぎるでしょうか?」
その学生が指摘する通りです。溜め息をついていても、問題が解決するわけではありません。現状を正しく受け止めたうえで、少しずつでもやれることをして行くしかないでしょう。アフロ・アメリカの小説を理解したいという思いでやり始めて気がついて見れば、妙な空間に踏み入ってしまいました。以来、大学の英語や教養の授業でアフリカやアフロ・アメリカを取り上げて二十年以上になりますが、余りにも出口の見えない現実に、悲観的になり過ぎているようです。
意識や発想を変えて
人が持つ哀しい性と無力を思い知ったうえで、何が出来るかを考えたいと思います。これだけ規模が大きくなった今、世界の構造の枠組みを変えるのは不可能に近く、実質的ではありません。しかし、意識や発想を変えて枠組みの中でやれることをやって、結果的に少しは変わるというのは可能です。
ボツワナのエイズ対策事業に取り組んで成功したアーネスト・ダルコー医師の例は参考になります。
ボツワナは、四三ペイジの表にも示しましたが、極めて絶望的な状況にあった国です。ダルコーさんは医療とビジネスを両立させて、多くのエイズ患者を社会復帰させています。(註28)
三六歳のダルコーさんは、アメリカに生まれ、タンザニアとケニアで過ごしました。ハーバードで医学の資格を、オクスフォードで経営学の修士号を得た後、ニューヨーク市の経営コンサルタント会社マッキンゼー社に就職して、二〇〇一年にエイズ対策事業のためにボツワナに派遣されました。(註29)
派遣された当時、三人に一人がHIVに感染していたと言います。最初の一年間は、「夜明け」という意味の国家プロジェクトMASAの責任者として「一日最低二十二時間」は働いたそうです。感染者数を知るためにモハエ大統領にテレビでエイズ検査を受けるように呼びかけてもらう一方で、医療体制を把握するために国じゅうを隈無く調査しています。その結果、絶対的な医師不足を痛感しました。周辺国に呼びかけ破格の給料を出して数年契約で医師を雇い入れると同時に、国内でも医師を育成し、現場に二千二百人の医師を配置しました。
最大の問題は薬でしたが、アメリカの製薬会社と交渉し、患者の資料を提供する代わりにほぼ無料で薬を確保し、半数以上の患者の治療を可能にしました。
政府の資金では足りませんでしたので、「エイズ撲滅のためのプロジェクト」を展開するマイクロソフト社のビル・ゲイツと掛け合い、一兆円を引き出しています。その薬と豊富な資金を基に、ネットワークシステムを構築します。プロジェクト本部の下に四つの支部を置き、それぞれの支部にコーディネーターを配置、コーディネーターはその下にある多くの拠点病院と連携し、現場の状況に応じて薬を届けるというシステムです。ダルコーさんは学んだ経営学の知識を生かし、ウォルマートの最先端の納品システムを参考にしたと言います。二〇〇〇年に三六歳までに落ち込んでいた平均寿命は上昇に転じ、二〇二五年には五四歳に回復する可能性も出てきたと言われています。(註30)
ダルコーさんは今、エイズ対策を専門に行なうブロードリーチ・ヘルスケア社を設立して、最大のHIV感染国南アフリカのケープタウンでエイズと闘っています。現在、アフリカ十二カ国がダルコーさんのエイズ対策モデルを取り入れていると言います。
ダルコーさんは、永年のアパルトヘイト体制の影が色濃く残っている南アフリカで医師や病院に頼らずにエイズ治療が出来るシステムを開発しました。白人の利用する民間病院に医師が集中し、アフリカ人が利用する公立病院に医師が極端に少ない現状の中でシステムを機能させる必要性に迫られたからです。そのシステムでは、感染者の多い地域で雇い入れられた現地スタッフが、定められたマニュアルに従ってエイズ患者の簡単な診察を行ないます。その診断結果がファックスで出先事務所に送られます。出先事務所では、情報をパソコンに入力してデータベース化され、必要に応じてケープタウンのセンターの医師に相談します。センターでは、医師が情報を総合的に判断し、現地スタッフが患者に薬を届けるのです。医師が現場にいなくても治療が出来、一人の医師がたくさんの患者を治療するという、南アフリカの現状に即した体制です。
そのダルコーさんに、かつて「国境なき医師団」で活動した医師貫戸朋子さんがケープタウンの事務所を訪れてインタビューを試みました。「私たちはエイズとの闘いに勝てますか?」という貫戸さんの質問にダルコーさんは次のように答えました。
「もちろんです。私は不可能なことはないと自分に言いきかせています。四千万人の感染者を救うのは無理だと言う人もいます。でも、然るべき時に然るべき場所で指導力を発揮すれば、実現できます。そもそも私たちは、何故失敗するのでしょうか。それは、私たち自身の中に偏見が潜んでいるからです。その偏見に打ち克つことが出来れば、エイズは克服できるのです。恐れることなく、国民に正しいメッセージを伝えれば、必ず前進できます。一人一人が精一杯呼びかけるのです。明日は、明日こそはエイズを食い止めることが出来るのだ、と。」
インタビューを終えた貫戸さんは、困難に立ち向かっている人たちのために再び現場に立つ意欲をかき立てられたと言います。(註31)
ダルコーさんは、壊滅的な医療体制を考えれば予防を最優先すべきだと主張して欧米の製薬会社が目を向けなかったエイズ患者を救い、帚木蓬生が『アフリカの瞳』の中で託したメッセージ「私は人類の英知として、特定の国、つまりHIV感染が蔓延している国では、治療薬を無料にすべきだと訴えたいのです。無料化の財源は世界規模で考えれば、どこかにあるはずです。戦争が仕掛けられ、数百億ドルの戦費がただ破壊のためだけに空しく費やされています。その何分の一かの費用を、エイズに対する戦いにあてれば、私たちは確実に勝てるのです。」を実践したわけです。
ダルコーさんのようには出来なくても、体制の枠の中で意識の持ち方を少し変えるだけでやれることもあります。八十年代の後半に、朝日放送がジョハネスバーグの日本人学校を取材したことがあります。有名企業から派遣された「名誉白人」に話を聞いたわけです。校長は治安の悪さから子供を如何に守るかについてだけを語り、母親たちは政治的無関心を貫き通し、子どもたちは、自分の家にいるアフリカ人のメイドたちのことを「住むかわりにやっぱり働かせてあげるっていう感じで」と答えていました。(註32)もし、同じ立場に立った時に、「折角の機会なのですから、子供たちにはこちらの子供たちと友だちになって、次の時代の橋渡しをしてもらいたいと思います」と校長や母親が言い、「一緒に遊んで友だちになり、将来いつかまた戻って来て何かのお役に立ちたいと思います」と子供たちが言えれば、親の世代が続けてきた損得だけの南アフリカとの関係を少しは変えて行けます。先ずは自分を大切にし、身近な回りを大切にして行けば、相手のことも敬えてたくさんのことを学ぶことが出来るでしょう。
絶望の淵にあっても、ダルコーさんのように、まだ出来ることはあると信じて、十年一日の如く語り続けられたらと思います。
後世は畏るべし、なのですから。
南アフリカ小史 (二〇〇五年九月現在)
一六五二 東インド会社、ケープに中継基地を建設。
一七九五 イギリスの第一次ケープ占領。
一八〇六 イギリス、ケープ植民地政府樹立。
一八三三 イギリス、ケープで奴隷を解放。
一八三五 ボーア人、 内陸への大移動(グレイト・トレック)を開始。
一八三八 ブラッド・リバーの戦い (ズールー人対ボーア人)。
一八六七 キンバリーでダイアモンドを発見。
一八八〇 第一次アングロ・ボーア戦争 (~八一)。
一八八六 ヴィトヴァータースランドで金を発見。
一八九九 第二次アングロ・ボーア戦争 (~一九〇二)。
一九一〇 南アフリカ連邦成立。
一九一二 南アフリカ原住民民族会議〔後に、アフリカ民族会議(ANC)と改名〕結成。
一九一三 「原住民土地法」制定 (リザーブの設定)。
一九二一 南アフリカ共産党結成。
一九三六 「原住民代表法」・「原住民信託土地法」制定。
一九四八 国民党マラン内閣成立 (アパルトヘイト体制強化)。
一九四九 「雑婚禁止法」制定。
一九五〇 「共産主義弾圧法」制定。南アフリカ共産党禁止。「住民登録法」、「集団地域法」制定。
一九五五 クリップタウンの人民会議で自由憲章を採沢。
一九五六 「反逆罪裁判」事件開始 (~六十一)。
一九五八 パン・アフリカニスト会議(PAC)結成。
一九六〇 シャープヴィルの虐殺。ANC、PAC禁止。
一九六一 共和国宣言。ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)創設、ANC武力闘争を開始。
一九六二 ネルソン・マンデラ逮捕。
一九六三 リボニア裁判開始 (~六十四)。
一九六七 「反テロリズム法」制定。
一九七六 ソウェト蜂起。
一九七七 バンツー・スティーヴン・ビコ獄中死。ANC、ゲリラ闘争を開始。ピーター・ボタ首相政権発足。
一九七八 ロバート・マンガリソ・ソブクウェ死去。
一九八二 統一民主戦線 (UDF) 結成。スワジランドと不可侵条約締結。
一九八四 ボタ、執権大統領に就任。三人種体制発足。モザンビークと不可侵条約締結。
一九八五 アレックス・ラ・グーマ、キューバで客死。「背徳法」、「異人種間結婚禁止法」廃止。
一九八六 「パス法」廃止。
一九八七 オリバー・タンボANC議長来日し、中曽根首相と会見。
一九八八 ANC東京事務所開設 。国連総会で対南アフリカ貿易に関する日本非難の決議を採沢 。
一九八九 南アフリカ外相、米国務長官にアパルトヘイト廃止を約束 。マンデラと初会談のボタ大統領、マンデラの声明を発表 。ボタ辞任 、フレデリック・デ・クラーク、大統領に就任 。
一九九〇 マンデラ釈放。
一九九一 アパルトヘイト関連法の廃止。
一九九四 全人種参加の総選挙を実施、マンデラ政権成立。
一九九五 地方選挙を実施。
一九九七 新憲法発効。
一九九九 第二回目の総選挙実施、タボ・ムベキ大統領就任。
二〇〇四 第三回目の総選挙実施、ムベキ大統領再任。
奥付け
玉田吉行(たまだよしゆき)
四十九年、兵庫県生まれ。宮崎大学医学部医学科社会医学講座英語分野教員。英語、EMP (English for Medical Purposes)、南アフリカ概論、アフリカ論特論(教育文化学部日本語支援教育専修)などの授業を担当。
著書にAfrica and its Descendants 1 (1995), Africa and its Descendants 2 (1998) など、訳書にラ・グーマ『まして束ねし縄なれば』(九十二年)、注釈書にLa Guma, And a Threefold Cord(1991)などがある (いずれも門土社)。
「アフリカとエイズ」(二〇〇〇年)、「医学生とエイズ―ケニアの小説『ナイス・ピープル』」(二〇〇四年)、「医学生とエイズー南アフリカとエイズ治療薬」(二〇〇五年)、「医学生と新興感染症―一九九五年のエボラ出血熱騒動とコンゴをめぐって」(二〇〇六年)など、感染症に関わるエセイもある。
執筆年
2007年
収録・公開
横浜:門土社 64ページ