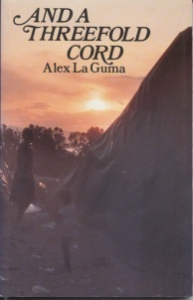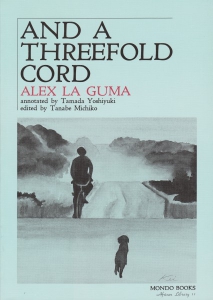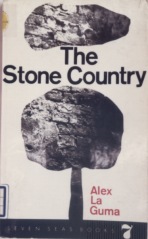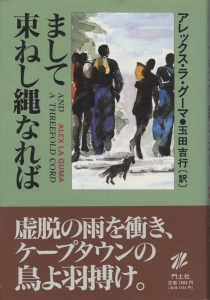概要
(写真と概要は作業中)
本文
Robert・Mangaliso・Sobukwe
ロバート・マンガリソ・ソブクウェというひと
(2) アフリカの土に消えて
「ゴンドワナ」21号(1994)6~19ペイジ
1960年3月21日
政府のブレーンSABRAは、当初、PACがアフリカーナー・ナショナリズムの対局に位置し、自分たちが推し進める「分離発展」の政策に、かえって役に立つと考えました。また、共産党との共闘を拒んだり、ANCと「抗争する」という理由から、治安警察のなかにもPACを歓迎する人たちがいました。しかし、59年半ばには、ANCへの反感を煽るパンフレットを配布して、政府はPACの妨害活動を開始しています。白人政府を倒して黒人を解放しようとするPACが、体制の脅威になると考え始めたからです。ソブクウェは「ランド・デイリー・メイル」紙上で、PACがANCとではなく、白人支配と闘っていることをあらためて発表してその妨害に対抗しました。その後、PACの会議には、スパイを送りこんだ保安警察が会場の外で必ず待機するようになりました。
経験不足や財政難もあって、59年7月までに会員十万人を達成するという目標はかなわず、101支部2万5000人の会員しか集まりませんでした。8月初めの大会では、12月に開く初の全国大会までにあらためて会員十万人という目標を掲げ、PACがとる最初の政治行動「ステイタス・キャンペイン」について、ソブクウェが声明を発表しました。日頃、白人の侮蔑や屈辱に黙って従うことが、黒人の劣等性を認めることになるのだから、先ずアフリカ人自身が人間としての誇りを取り戻したうえで、政治的、経済的、社会的な地位(ステイタス)の改善を求めて広範なキャンペインを展開するというものでした。その後、議論が重ねられたすえ、積極的な行動と抑圧側への非協力をうたった49年の行動計画に沿って、パス法に的が絞られ、具体的に反パス法キャンペインに向けて、行動が開始されました。
パス法は、どの黒人の集会でも議題に取り上げられていましたし、女性にも援用されるようになってアフリカ人の反感や憎悪は極限に達していましたから、非難するのはた易いことでしたが、問題は反パス法キャンペインをどう闘うかでした。
ソブクウェは、黒人労働組合がキャンペインで重要な役割を果たすと考えました。従って、白人労働組合の手助けもあって、産業調停法で交渉権を禁じられながらも58年に黒人だけの自由アフリカ人労働組合同盟が結成されてPACの執行委員が議長に選ばれたとき、キャンペインの具体的な計画を立て始めました。労働者がパスを置いたまま家を出て、仕事に行く途中、最寄りの警察署に出頭して、自らパス不所持の罪で逮捕されるという戦略です。その方法が成功すれば、警察署や裁判所や留置場に人があふれて政府は混乱し、労働者がいなくて雇用者が困るという二重の効果があらわれると、ソブクウェは考えたのです。
国民にパス法反対の積極的な行動をとるように呼びかけること、出来るだけ早い時期のキャンペイン実施に向けて組織の充実をはかること、キャンペインのための特別会費を徴収すること、いかなる事態になっても「保釈金なし、弁護なし、罰金なし」の原則を守ることなどが予め執行部で充分に討議されたうえ、12月の全国大会では、反パス法キャンペインの議題が初めて公の場に持ち出され、約3万2000人といわれる会員の代表271名によって、その議案が正式に採用されました。ただし、開始日については、警察の妨害を避けるため、ぎりぎりまで秘密を守ることになりました。
パス法に対する黒人の不満は募るばかりでした。58年の1年間にパス法違反で有罪判決を受けた者が、およそ40万人にも達していたからです。黒人だけではなく、アジア人やカラードや白人も、パス法に反対して色々な抗議行動を起こしていました。国の外からも、当時吹き荒れていた「変革の旋風」の勢いが伝わってきていました。国民党政権の施策に異議を唱えたイギリスの首相マクミランの演説も、大きな波紋を呼びました。内外の状況から考えて、誰もが今なら変革は果たせるという期待を抱いていました。
一方、ANCは、成果はあまり見られなかったものの、既に59年の6月にパス法に反対する行動を起こし、12月の年次大会では、60年3月31日を「パス反対の日」に設定する次の計画を打ち出していました。したがって、ソブクウェは、ANCに先駆けて、出来る限り早い時期にキャンペインを実施する必要性を痛切に感じていました。当初、3月7日に向けて準備を進めていましたが、ビラの印刷が間に合わず、2週間後の3月21日に開始日を設定して「大地の子供たちよ、アフリカを忘れずに!」で始まる最終的な指示を出しました。自分たちの踏みだす第一歩が歴史的で、可能性に満ちていること、あくまで非暴力を貫くこと、闘いは独立が達成されるまで続くこと、アフリカ大陸も歴史も自分たちの側に味方していること、今日の独立と明日のアフリカ合衆国建国に向けて前進することなどが強調されていました。
3月18日にはジャーナリストに記者会見をして、キャンペインの予告と説明を行ないました。また、ANCと、黒人も所属する自由党には呼び掛けの手紙を、南アフリカ警察警視総監には、非暴力を貫くキャンペインの予告と、警察による武力行使の回避を要請する手紙を、予め送付しました。
二月中、ケープタウンを中心にケープ州を精力的に回ったソブクウェは、その時かなりの手応えを感じました。特に若い層の反応は大きく、ソブクウェも各地を回った他の執行委員も必ずキャンペインは成功すると確信しました。
1960年3月21日月曜日、ソブクウェはいつもより一時間早い5時に起き、6時半に家を出て、オルランドにあるソウェトの中央警察署に向かいました。ヴェロニカと、取材で同行するポグルンドが、自宅前でソブクウェを見送っています。途中、PAC会員と合流して、一時間後に警察署に到着し、8時20分には、数名と共に建物の中に入って、パスを携帯していないので逮捕してほしいと申し出ています。しかし、今は忙しいので外で待つようにとの指示を受けて、11時頃まで外で待つことになりました。警察署内は、どう対応すべきかが決まらず混乱しているようでした。中庭には、私服の保安警察とライフルを手にした数多くの白人警官が待機し、玄関前には、150人から200人のアフリカ人が集まっていました。
外で待っている間に、事態は思わぬ展開を見せました。ポグルンドの同僚が、何箇所かの黒人居住区で、警察の発砲によって死者も出ているというニュースを運んできたのです。ポグルンドからニュースを告げられたソブクウェは、動揺を隠せませんでした。ポグルンドは、さっそく居住区の一つシャープヴィルに駆けつけました。そして、大量虐殺を目のあたりにしたのです。死者68名、負傷者186名。300人の警官が、2万人近いアフリカ人に対して無差別の銃撃を行なったのです。死傷者の中には、女性や子供も含まれ、大半が背後から撃たれていました。警察の放った705発の銃弾によって歴史を大きく塗り替えられた南アフリカは、もはや元の状態には戻りませんでした。
シャープヴィルで惨状が繰り広げられていた頃、ソブクウェは既に逮捕されていました。11時頃に3人の保安警察が到着したあと、ソブクウェと数名のリーダーの名前が読み上げられて警察署内に入り、逮捕されています。ソブクウェが罪状を聞くと「扇動罪だ」と告げられました。その後、警察は、外にいるアフリカ人を追い返そうとしましたが、群衆はどうしても立ち退こうとはせず、結局、全員が逮捕され、リーダーたちとは別の場所に収容されました。
その後、ソブクウェはヴェロニカの病院に連れて行かれたあと、自宅と大学の捜査に立ち合い、午後1時には、ジョハネスバーグの中央警察署マーシャル・スクウェアに連行されています。他のPACのリーダーも、ソブクウェと同じように家宅捜査などに応じてから、全員がマーシャル・スクウェアに集められました。
シャープヴィルだけでなく、各地でキャンペインが展開されました。特に、ケープタウンとその近郊では、ソブクウェに深く感化を受けた21歳のケープタウン大学の学生フィリップ・コゥサーナの指揮のもとに、活発な活動が繰り広げられています。21日の朝には、ワインバーグで1000人以上が逮捕され、ランガなど3箇所ではたくさんの人が集まりました。5000人が集まったランガでは、武力衝突を避けるため、コゥサーナは群衆を一時家に帰していますが、夜になって再び一万人が集まったとき、警察は武力を行使して群衆を追い返しました。しかし、おとなしかった群衆が警察に投石したり、店や政府の建物に放火したりするなど、事態は騒然となりました。夜には、警察と軍隊の増強がはかられました。
シャープヴィル事件の翌日、PACは新聞に、あくまでパス法が廃止されるまでキャンペインを続けるという挑戦的な声明を発表しました。シャープヴィル地区では、何千人という黒人が、丸一週間、仕事をボイコットしたため、保安警察による明け方の家宅捜査が繰り返され、たくさんの地域で集会が禁止されました。にもかかわらず、3月24日には、ケープタウンでは数千人が警察に自ら出頭して、逮捕されています。3月25日には、コゥサーナに率いられた2000人が、町の中央警察署に詰めかけ、逮捕をめぐって押し問答をしたすえ、事態が収まるまでケープタウンではパス法を一時停止する、という約束を警察から取り付けています。ANCは、この時期に、3月28日を「哀悼の日」として、全国一日在宅ストライキを呼びかけました。
政府は、事態の収拾にやっきになりました。25日に、必要ならばPACとANCの活動を禁止させる法律を議会に提出するという声明が出され、翌26日には、警視総監を通じて、パス法の一時停止が発表されました。すぐ後に、法務大臣が、事態が正常に戻ればパス法を復活させることを補足して一時的な措置であることを強調しましたが、政府の譲歩とPACの勝利は明らかでした。
PACは、一時的措置を拒否して直ちに声明を出し、パス法キャンペインの継続を宣言するとともに、政府に、逮捕されているリーダーとの交渉を促しましたが、リーダーの逮捕による組織の弱体化は隠せませんでした。連絡の不行き届きや資金不足などの問題が表面化してきていたのです。悪いことに、ANCがキャンペインの主導権を握ったことで、組織は更に混乱しました。パス法の一時停止措置などの流れに乗じて、ANCが黒人にパスを焼き捨てるように呼びかけたからです。27日の新聞には、パスを焼き捨てるルツーリの写真が大きく掲載されました。当初はキャンペインに反対し、非難まで浴びせておきながら、パス法の一時停止措置などの成果を見て、永年の消極策を変更して急に積極策を打ち出してキャンペインに便乗してきたANCの日和見主義的なやり方を非難する声明を、ソブクウェは議長代行のジョロベを通じて伝えましたが、PAC会員も含めたアフリカ人大衆の勢いと時の流れの早さは、ソブクウェの読みをはるかに超えていました。
28日の在宅ストライキは史上最大のものとなりました。ケープタウン、ジョハネスバーグ、ポートエリザベスなどの大都市では、黒人労働者の90パーセント近くが、またピーターマリッツバーグなどの小さな町でも、相当数の労働者がストに参加して、仕事に行きませんでした。
ジョハネスバーグでは、ストに参加しなかった人たちが、帰宅したところを黒人に襲われ、パスが焼かれました。警察が強硬な手段で対処したため、夜になって黒人警官が殺されるほどの騒ぎとなりました。ケープタウンでは、約六万人の黒人がストを続行して仕事に出なかったために、牛乳や新聞は配達されず、パンや肉などの必需品も品切れになりました。又、ホテルや港や工事現場などでも、人手不足で大混乱が起きました。白人の恐怖は今や現実のものとなり、高揚する黒人の抵抗に直面しなければならなくなりました。
28日、政府はPACとANCの活動を禁止させる議案を国会に提出し、30日には裁判なしに人々を拘禁し、集会を禁止できる権限を警察に認める非常事態宣言を出して、事態の収拾に乗り出しました。朝早くから、数百人のリーダーが逮捕されています。タムボのように、辛うじて国外に逃れた者もいました。ケープタウンでは、リーダー逮捕の報せやその日行なわれたランガの強制手入れなどに刺激された群衆が行進を始め、夜になって国会議事堂の前に三万人が集まりました。先頭にいたコゥサーナは、法務大臣との会見の約束を警察と交わして、群衆を引き上げさせましたが、その後、約束を反古にされて逮捕されたうえ、9ヵ月間拘禁されました。ランガやニャンガなどでは、リベラルや反アパルトヘイト女性組織ブラック・サッシュなど白人の支援を受けながら、黒人はその後も抵抗を続けましたが、警察は大量動員を行ない、電気や水道を切って黒人に圧力をかけました。
4月8日には、PACとANCを非合法化する法律が発令されました。しかし、その時には、既に両組織とも壊滅状態で、組織としては機能していませんでした。
そして、4月10日にパス法が復活しました。PACの呼びかけに呼応して立ち上がった黒人勢力は、警察や軍隊や議会などを駆使した少数派白人に、完全に封じこめられてしまったのです。
ソブクウェは、3月21日付けで、ヴィットバータースランド大学に、辞職願いを郵送していました。手紙には、自分の行動が、大学をつぶす口実に利用されないように辞職を申し出ることや、PACの議長になってからの政府の圧力を無視してくれた大学側へのお礼などが書かれていました。大学は、3月31日付けで、正式に辞表を受理しています。
禁固刑三年
ソブクウェはマーシャル・スクウェアに二晩拘留されたあと、法廷に連れ出されました。「法律に反対する抗議の手段としてパスを持たないという罪を犯すように原住民を不当に、不法に扇動した」ため、被告第一号のソブクウェとリーダー22人に刑事法修正令が適用されるというものでした。同修正令はもともと、ANCの不服従運動をつぶす目的で1952年に改悪されたもので、500ポンド以下の罰金もしくは五年以下の懲役が課せられる重刑でした。ソブクウェは、白人が作った法律のもとで、黒人が公正な裁判を受けられるとは思えないので、抗弁はしないと述べて「保釈金なし、弁護なし、罰金なし」の原則を貫きました。そして、その日のうちに、未決囚として裁判所近くのフォート刑務所に移されました。
5月4日に「法に反する罪を犯すように人々を扇動した罪により、ソブクウェと18人は有罪、四人は無罪」という判決が出されました。ソブクウェには3年、レバロを含む4人に対しては2年、ほかの14人には1年半の禁固刑が言い渡され、今回は囚人としてフォート刑務所に送られました。判決が言い渡される前に、ソブクウェは「被告だれもが、少数白人によって作られた法律に従う道義的な責務はないと感じていました。裁判官の個人的な名誉を非難したいと願うものでは決してありませんが、不正な法律が公正に適用されることはあり得ないのです。たとえ私たちが刑務所に送られても、いつも代わりをしてくれる人たちがいます。自分たちが起こした行動の結果と対峙するのを恐れたりもしませんし、慈悲を乞うつもりも毛頭ありません」と語っています。
ソブクウェが法廷で闘っている間、政府は軍と警察を総動員して「秩序の回復」をはかりました。非常事態宣言後の大量逮捕第一波で、コミュニストやリベラルを含む千八百人が逮捕されてフォート刑務所に送りこまれ、ソブクウェが、南アフリカ共産党とANCの幹部であるジョー・スロボと刑務所内で鉢合わせするひとこまも見られました。多くの黒人居住区では、ランガやニャンガの場合と同じやり方で強制手入れが繰り返され、5月初めまでに、黒人の逮捕者は、18001人にのぼりました。刑務所は過密状態となり、囚人の待遇はますますひどくなりました。
政府は、8月31日に非常事態宣言を解除しています。「秩序を回復した」南アフリカは、一見いつもの様子を取り戻したかのように見えましたが、3月21日以前の南アフリカとは全く違った国に変貌していました。
フォート刑務所に収監されたソブクウェは、今度は、囚人としての扱いを受けました。刑務所にもアパルトヘイトが徹底されおり、「ナンバー・フォー」と呼ばれる黒人用のセクションに入れられ、惨めな食事や敵意に満ちた看守の残忍な扱いを強いられました。身に着けていた衣服の代わりに囚人服が支給されています。ショーティズと呼ばれる、膝上までのズボンと、カーキ色か赤の作業服と、セーターです。初冬で、コンクリートの床にもかかわらず、当初の2,3日間ははだしで、その後、ゴムのサンダルが支給されただけでした。靴下も与えられていません。頭はかみそりで剃られました。囚人同士が、少量の水と石けんをつけて剃るために、しばしば出血したり、切り傷が残りました。
通常、1室に10人から15人が収容されました。部屋にはトイレ用のバケツが一つ置かれていましたが、紙はありませんでした。1日に2度、2人が交替でバケツを空にして、汚物を洗い流しました。他にもう一つバケツが置いてあり、1日に2回、水が補給されました。サイザル麻のマットと、薄くて汚ない毛布が支給されましたが、枕はありませんでした。毎朝、マットと毛布はたたんで通路に置かなければならず、日中は、コンクリートの床の上で過ごさなければなりませんでした。面会も許されず、本や新聞はおろか、通常なら許される聖書さえも禁じられました。
食事は、1日3回、ドアの下の隙間から金属の皿を滑らせて配られました。朝食は、パップと呼ばれるとうもろこしのかゆに、濃い色の砂糖が少し入ったコーヒーのような飲み物、昼は11時から12時の間に、ゆでたとうもろこしと、たまに人参かビートの根、夕食は、3時に、パップかゆでたとうもろこしと、週に3回、2,3きれの肉が出されるだけでした。果物や牛乳などが付くことはなく、とうもろこしは腐ったような味で、パップにはいつも虫が入っていました。
待遇のひどさはどこも似通っており、ボクスバーグでは、食事のあまりのひどさに堪えかねた会員が2人、出された食事を投げつけて抗議し、罰を受けたほどでした。同調して抗議しようとする者も出ましたが、ソブクウェは、食事のことはささいな問題で、あくまで自分たちの闘いをやりぬくようにとその人たちを諌めています。そんな悪条件の中でも、会員たちはあくまで規律正しく、グループに別れての討論会や勉強会も行ないました。ソブクウェは、現在の政府やPACが理想とする政府や、ANCとの分裂やコミュニズムについてなどを議題に、主に政治的な局面について語っています。
政府の資料入手が不可能なので、正確な日時はわかりませんが、判決が言い渡された後しばらくしてから、ソブクウェはレバロといっしょにプレトリア中央刑務所に移されました。その後、ボクスバーグの二箇所、ストフバーグ、ヴィトバンクの各刑務所に回されたあと、急増する「政治犯」を収容するようになっていたプレトリア地方刑務所に移されています。
ポグルンドがシャープヴィル事件のショックからなんとか立ち直ってソブクウェを訪ねたのは、このプレトリア地方刑務所でした。ポグルンドはヴェロニカに連絡を取って手紙を書いたあと、ソブクウェから61年10月4日付けの返事を受け取っています。週に一通の手紙と一回の面会を許可されていたソブクウェと、看守の厳しいチェックを受けながら、金網の張られた分厚いついたて越しに、「ジャーナリスト」としてではなく「友人」として、ポグルンドは面会を果たしました。
三年の刑期を終えて、63年5月3日に出獄するはずのソブクウェの運命は、獄中にいる間の急激な展開によって、大きく変わってしまいました。その最大の要因は、ポコと呼ばれる集団のテロ活動でした。ポコは「アフリカの本当の持ち主」という意味のコサ語の文句「アマ・アフリカ・ポコ」の短縮形で、61年の暮れに、ケープタウンの黒人居住区でにわかに起こった運動です。非暴力を貫いた反パス法キャンペインを力で押さえこまれて遣り場を失なったPACの若者たちの憎しみが、白人に向けられたのです。容赦ない手入れを繰り返されて仕事を失ない、妻や子供をホームランドに送られたランガやニヤンガの住人や、政府の押しつけたバンツースタン政策に協力する傀儡(かいらい)に反発するトランスカイの若者や、スラムにたむろするチンピラなどを巻きこんで、ポコは急速に勢いを増しました。そして、2年の刑期を終えてバソトランドに逃れたレバロが指揮を取り始めた八月には、ますますその勢いを強めました。
ポコはすでに黒人の警官や通報者を殺していましたが、11月22日に、ケープタウン近くのパールで、白人2人を殺害し、翌年2月2日には、トランスカイで、2人の少女を含む5人の白人を惨殺しました。既にウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)を創設して、ANCが61年12月に武力闘争を開始していましたから、白人社会に与えた衝撃は尚更でした。裁判所は、「シャープヴィル」3周年の3月21日に、ポコがPACと同一体で、年内に革命的な手段による政府転覆の意図があるので、政府の迅速な対処を促すという報告をまとめています。
3月末、レバロはバソトランドで記者会見し、ポコは会員が15万人、PACとは同一体で、63年中にアフリカ人を解放すると話しました。そして、質問に答えて、革命では白人を殺すことも避けられないだろうと付け加えました。
ポコは4月の7日と8日に蜂起し、警察署を襲って武器を奪い、石油タンクに火をつけたり、白人の雇用者に毒を盛ったりして出来るだけ多くの白人を殺害する計画を立てていましたが、連絡の手紙を持ったメンバーがバソトランドで逮捕されて、計画は未遂に終わりました。3000人以上が逮捕され、ポコは消滅しました。レバロ自身は、イギリスの支援でタンザニアに亡命し、ダルエスサラームを拠点に79年までPACの議長代行を務め、86年に死去しています。
レバロは、釈放されるソブクウェにPACの主導権を戻したくなくてあのような行為に出たのか……その動機は推測の域を出ませんが、レバロの無謀な行為は、体制側にソブクウェの拘禁を延長する口実を与えました。ソブクウェがポコに関係があろうとなかろうと、白人支配の体制の脅威には違いなく、時の首相フォルターは、刑期終了後も法務大臣が認めれば、拘禁を再延長できる「ソブクウェ法」を考え出し、議会に提案しました。既に議会に提出されていた一般法再修正令俗に言う90日間無裁判拘禁法(本誌16号14ペイジから18ペイジを参照)と並んで審議され、5月1日には効力を発揮しました。「ソブクウェ法」は、一応、64年6月30日が期限となってはいましたが、国会の承認があれば1年毎に延長が可能という法律でした。共産主義に反対する立場を貫くソブクウェが、こともあろうに共産主義を弾圧する法律で拘禁されるという皮肉な結果となりました。
そして、ソブクウェはロベン島に送られました。
ソブクウェ法とロベン島
テーブル湾の真んなかに浮かび、テーブル山から一望できるロベン島は、長い所が3.2キロ、短かい所で1.6キロのほぼ楕円形をした小島です。一番高い所でも海抜20メートルという平らな地形で、ケープタウンからわずかに八キロしか離れていません。しかし、大西洋の波が荒く、しかも岩肌のために近寄ることさえ難しく、古くから流刑の島として使われてきました。早くは16世紀の初めに、ポルトガルの囚人が、17世紀にはイギリスの囚人が、そして19世紀初頭にはコサのリーダーがその島に流されたと言われています。その後百年ほどは、ハンセン病や精神病患者の隔離施設として使われましたが、第二次大戦中は、海からの攻撃に備えて大砲が据えつけられていました。60年には、島が最高治安刑務所となり、増えつつあった黒人男性の政治犯が収容されるようになりました。60年半ば頃までには、囚人の数は1500にも膨れあがっていました。
ソブクウェは3ヵ月ほど仮の場所に収容されたあと、建物番号158、159、160が付けられたバンガロー式の住宅が建つ、フェンスに囲まれた場所に収容されました。フェンスの上には有刺鉄線が張りめぐらされ、入り口の門には昼は1人、夜には2人の看守がつけられ、番犬も配備されていました。「万全を期する」ために、看守はすべて白人でした。
4辺が45メートル、51メートル、27メートル、54メートルの土地がソブクウェに与えられた世界でした。しかし、世論の非難をかわすためにフォルスターが言明したように、独房には監禁されずに、通常の囚人とは違う扱いを受け、あてがわれた敷地内での「自由」は保障されました。白いペンキで塗り替えられた建物には、小さな部屋が2つあり、ソブクウェは一つを書斎兼寝室に、もう一つを台所として使いました。部屋には、鉄製のベッドとマット、食器棚、テーブルと木の椅子、本棚と床マット、それにシーツと毛布が用意され、数か月後には、両方の部屋にカーテンがつけられています。敷地内の少し離れた所に、シャワーと洗面が出来るブロックと、使われていない別棟がありました。
食事は以前より内容のいいものが出されるようになり、囚人に許可される本や雑誌に加えて、新聞の講読や国営のラジオ放送を聞くことも許されました。時間の制約はなく、申し出れば、夜の明かりも消されることはありませんでした。
しかしながら、ひとり隔離された毎日の生活は詫しく、話しかけることの出来る相手もアフリカーナーの看守だけでした。その看守でさえも、ソブクウェには喋りかけないようにとの厳命を受けていました。
検閲を受けて、ソブクウェは週に2通の手紙のやり取りを認められましたが、面会は殆んど許可されませんでした。最初の九ヵ月の間に面会を許されたのは、ローマカトリック教会とメソジスト教会の牧師とイギリス国教会の司祭、それに兄のアーネストとヴェロニカの5人だけにしか過ぎません。
ソブクウェは、島内の囚人との接触は禁じられていましたから直接言葉を交わすことはありませんでしたが、遠くから目で挨拶を交わすことがありました。ソブクウェの存在を知っていたPACやポコのメンバーが、強制労働の作業中にソブクウェのいる敷地の近くまで来て、懲罰を覚悟して敬意を払ったからです。PACのサークル内でよく読まれていたトーマス・マコーレイの詩「ホレイシャス」をコサ語で大声を出して吟じた人もいます。ソブクウェはコサ語でその詩に応じています。
ソブクウェは、殆んど外部と接触することなく、ラジオを聞いたり本を読んだり、登録を済ませたロンドン大学の経済学士号の勉強をしたりしながら毎日を過ごしています。8月には、野菜や花を畑で作り始めました。2,3ヵ月のちに水不足で中断していますが、わずかな慰めにはなりました。食事が良くなり、強制労働がなくなったお陰で、年末までに体重がもとに戻りましたが、長い間刑務所内で体を冷やしたために、左肩の付け根と背中の下の部分に痛みを覚えるようになっていました。
この頃から、本格的なポグルンドの経済援助が始まっています。国際世論を気遣った政府が一応は特別待遇の措置は取ったものの、その措置が表面的で、充分でなかったからです。2人の手紙のやりとりは続きましたが、検閲により黒く塗り潰された箇所のない手紙は一度もなく、数か月遅れたり、手紙そのものが消えることもありました。ポグルンドは衣服や本も送りました。ソブクウェの通信教育用の本を貸してくれる図書館が見つからなかったからです。また、募金の協力を得て「ケープ・タイムズ」や「ランド・デイリー・メイル」などの新聞や、ソブクウェの好きな「リーダーズ・ダイジェスト」などの雑誌の講読手続きをして、ロベン島に郵送されるように手配しました。お陰で、ソブクウェのもとに、読み切れないほどの新聞や雑誌が届けられるようになりました。
12月には、ヴェロニカが3人の子供を連れてソブクウェに会いに行きました。ヴェロニカは、ロベン島でソブクウェと一緒に過ごせるように頼むためにフォルスターに手紙で面会を申し込みましたが、取り合ってもらえず、週に3回の訪問を許可されただけでした。訪問を許可されたといっても、日本の3倍もある国土のほぼ端から端、ヨハネスバーグからケープタウンへの1600キロの移動はそう簡単なものではありません。ソウェトで助産婦をしていたヴェロニカは、長期の休暇をもらって出かけています。助産婦や看護婦は、当時のアフリカ人女性の職業としては、一番恵まれた部類の仕事でしたが、アフリカ人であり、女性であるがゆえに最低の賃金しかもらえないヴェロニカに、まして、一家の柱を拘禁されたヴェロニカに、夫に会いに行くだけの経済的な余裕があるはずもありませんでした(本誌8号25ペイジでは、同じように助産婦や看護婦として働いていた、アレックス・ラ・グーマ夫人のブランシさんを紹介しています。また、15号の「ミリアム・トラーディさんの宮崎講演」では、2重の抑圧に苦しむアフリカ人女性の生の声を聞くことができます)
経済的な問題だけではありません。当時、乗り場近くにアフリカ人を泊めてくれるホテルがなかったために、ケープタウンに着いても宿泊する場所がなく、当初は、ロベン島へのフェリー乗り場から遠く離れたカラードの居住区ランガから、ロベン島に通わなければなりませんでした(のちになって、かろうじて市街地の端のカラードの居住区内に泊めてくれるホテルを見つけています)そればかりではありません。フェリー乗り場でも、島に着いてからも、白人看守の厳しいボディチェックや持ち物検査を受けて、毎回惨めな思いを味わいました。そして、小さな面会室で、やっと夫に逢うことを許されたのです。
ヴェロニカのロベン島行きを支えたのは、ポグルンドと友人のユラリ・ストットでした。ストットは、ブラック・サッシュの前議長で、当時ケープタウンの市会議員を務めていました。60年のステイタス・キャンペインでは、警察の弾圧を受ける黒人居住区に食料を援助をするなどして、政府に立ち向かっていました。資金集めやケープタウウンでの家族の世話などを快く引き受け、何年間にもわたって、ヴェロニカと家族を支援し続けました。このストットともう一人、同僚であったヴィットヴァータースランド大学のウェリントン元教授が、ソブクウェの面会を拒否されています。2人が、おそらく、政府の意に反してソブクウェを援助した鼻持ちならないリベラルだったからでしょう。
64年の1月から4月までの3ヵ月間、ポグルンドは記者として面会を許されました。手紙のやり取りを続けながら面会の機会を探っていたポグルンドは、治安警察の長官ヘンドリック・ファン・ダル・ベルフを通じて面会の許可を取りつけました。ベルフは、61年にポグルンドが投獄された時の判事で、その後も何回か食事をともにして議論をたたかわせたりしていました。そのベルフが、法務大臣フォルスターの友人であったために急きょ長官に抜擢されて、思わぬ面会の機会が訪れたのです。面会には、ベルフのラインを明かさない、という条件が付いていました。政府のねらいは、「新聞記者」の取材を使って、ソブクウェを虐待しているという国際世論を打ち消すことと、「友人」を利用して、政府にとってなお脅威の存在であるソブクウェの本心を聞き出すことでした。政府にとって、ポグルンドはうってつけの人物であったわけです。
政府の思惑がどうであれ、用意された小さな部屋での2人だけの3ヵ月が始まりました。2人は、盗聴器を予測して、隠して置きたいことは筆談を交えながら、家族や友人のことから、1960年3月20日以降の出来事や、パン・アフリカニズムの定義やバンツースタンなどにいたるまで、様々な問題について話し合いました。話のなかで、ソブクウェは、ヴェロニカが弁護士を通じて永久追放ビザの申請を行なっていることを告げました。ソブクウェは、いつ釈放されるかわからない状態のまま家族に犠牲を強いるのは堪え難い、このままロベン島で化石にならず自分の能力をアフリカのために使いたい、他の囚人よりいい待遇を受けるは忍びない、と考えて亡命を希望したのです。しかし、八月にはその申請は却下されています。おそらく、反アパルトヘイトの国外からの脅威になる可能性がある限り、ソブクウェを国内に閉じこめておく方が得策だと政府は考えたのでしょう。(本誌10号「祖国を離れて」で、永久追放ビザを取得して、家族でロンドンに亡命したラ・グーマを紹介しています)
6月には、65年6月30日まで「ソブクウェ法」が延長されています。今回、更に悪いことには、次回からの期間延長には議会の審議は必要なく、法務大臣の命令さえあればよいという改悪がなされていました。
地下活動をしていたPACやANCのメンバーが大量に逮捕されたり、国外に亡命したり、さらに、同年六月にはマンデラに終身刑が言い渡されるなど、政府の強硬な対応によって黒人側の状況はますます厳しくなり、ロベン島にいるソブクウェの情勢も、全く先が見えなくなっていきました。
65年2月早々に、「ソブクウェ法」は66年6月30日まで再延長され、以後、68年まで延長措置が続きます。今回は「海外に逃亡したPACの会員がソブクウェを指導者とみなしており、国内で活動の再会の動きがあるために釈放できない」という法務大臣のコメントが出されました。
1月31日には、ケープタウンのカール・ブレメ病院に入院し、2月1日に前立腺の手術を受けています。カール・ブレメ病院は、アフリカーナー政府のブレーンを育てるステレンボシュ大学の医学生の養成機関で、通常、黒人が入院することはなく、冷たい視線のなかでの辛い入院となりました。8日には退院して、ロベン島に戻されています。
体制の締め付けが強化されるにつれて、黒人だけでなく、白人も数多く国外に脱出し始めました。また、大量の逮捕者が出て、刑務所は囚人であふれ、待遇もますます悪化していきます。その刑務所の実態について、ポグルンドは6月から7月にかけて「ランド・デイリー・メイル」に12回のシリーズで記事を書きました。記事は反響を呼びましたが、ポグルンドと編集長ガンダは嫌がらせを受けたうえ、起訴され、四年と三ヵ月に及ぶ裁判に引きずりこまれました。
政府の締め付けは、ロベン島のソブクウェにまで及んでいます。ケープタウンから定期的に届けられるはずの果物が届けられなかったり、アメリカのリンカーン大学から授与された名誉博士号の連絡が本人に届かなかったりしています。また、白人アフリカーナー看守の敵意も厳しく、無言で置かれた食事がさめてしまうなどもたびたびでした。社会から完全に隔絶されたソブクウェの生活は詫びしく、辛い日々が続きます。
この時期、ヴェロニカはケープタウンに来ている間は、毎日ソブクウェを訪問する許可を得ましたが、反面、それを支えたポグランドや友人の経済的な負担が増しています。同伴した子供の分も含め、ジョハネスバーグからの旅費や滞在費、食費だけでなく、当時バソトランドの学校に通っていた子供の学費から、ソブクウェに送る果物や生活必需品などの費用を、すべてポグルンドとシャーロット・テイラー、モイラ・ヘンダーソン、ノエル・ロブなどのリベラルがまかなっていたからです。
9月に首相のファヴールトが暗殺されて、代わりにフォルスターが首相に就任しましたが、アフリカーナーの路線は引き継がれました。67年に、政府はテロリズム法を制定して権限を広げ、隣国ジンバブウェと南西アフリカ(現ナミビア)からの脅威に対抗しました。南西アフリカでは、アフリカーナー政府が国連の勧告を無視して支配を続けていたため、黒人解放戦線の活動が激化していましたし、アイアン・スミス白人政権を支援するジンバブウェからは、PACやANCの破壊活動要員が南アフリカ国内に潜入し始めたからです。そのような内外の厳しい状況のなかでのソブクウェの釈放は望むべくもなく、「ソブクウェ法」は当然のように延長されました。数年におよぶ孤独拘禁によって、ソブクウェの体と心は、すでに想像以上に蝕まれていました。この時期に訪問を許可されてソブクウェに会ったヘレン・スズマンは次のような手紙をポグルンドに送っています。
わたしがソブクウェに会ったのは、その時が初めてでした。「ヘレン・スズマンと申 します。ソブクウェさん、お加減はいかがですか」と言いますと「わたしは話し方を忘れかけています」という返事が返ってきました。私はその答えにびっくりして、ただあの人を見つめました。するとソブクウェは「さて、私は誰に話しかけるべきなんでしょうかね」と言いました。
その後、ソブクウェからスズマンとの会見についての手紙を受け取ったポグルンドは、手紙を読みながら、肉体的にも精神的にも追い詰められたソブクウェの近況を思って涙を流しています。
結果的には果たせませんでしたが、厳しい現状とあまりの将来の希望のなさに、ポグルンド自身も、この頃に、アメリカへの出国を希望しています。
67年の暮れに二週間、69年1月には数週間、家族はロベン島での長期滞在を許されて、ソブクウェは楽しいひとときを過ごしました。もちろん、すべての費用は、ポグルンドと何人かの友人が工面しています。そして、突然、4月24日に、6月30日をこえない出来るだけ早い時期にソブクウェを釈放するという法務大臣の声明が出されました。長い間の孤独拘禁によって、健康状態が悪化したり、精神障害の兆候が見えだしたソブクウェをこれ以上ロベン島に監禁して国際非難を浴びるよりは、釈放して自宅拘禁にして監視した方が得策だと政府は考えたのでしょう。
キンバリーで
「ジュウショハ、キンバリー、ハリシュウェ、ナレディドオリ六。スグニアイタシ」5月14日に、ポグルンドはソブクウェからそんな文面の電報を受け取りました。ソブクウェが連れていかれたのは、ジョハネスバーグから南に470キロ離れた小さな町キンバリーでした。もちろん、ソブクウェに選択の余地はありませんでした。
キンバリーは、1860年代にダイアモンドが発見されてから栄えた町で、白人36000人、アジア人1000人、カラード36000人、アフリカ人66000人が住んでいます。黒人居住区ハリシュウェは町の外れにあり、他のスラムと同じように、貧しい地区です。ツワナ系のアフリカ人が主流で、コサ出身のソブクウェには初めての環境でした。ソブクウェは、鉄製のベッドとわずかな家具しか準備されていないトタン屋根の家を割り当てられ、そこでの五年間の「自宅」拘禁を言い渡されました。キンバリー市内からは出てはならない、午後六時から朝の六時までは自宅内に留まること、医者や家族以外の自宅訪問は許可しないなど、様々な制限を受けています。また、黒人労働者のコンパウンドや工場、裁判所や学校などへの出入りはもちろん、自分の子供以外の教育や、拘禁処分を受けている人々との接触も厳しく禁じられました。それでも、世間から全く隔絶されたロベン島の生活に較べれば、大きな変化でした。
自宅拘禁は、武力闘争を開始した黒人勢力の破壊活動を封じるために62年に改悪された一般法修正令、俗に言う破壊活動法に規定された行政拘束処分ですが、大量逮捕によって刑務所に収容仕切れなくなった反体制勢力の活動を安上がりに禁じようとしたものです。ラ・グーマもビコも、この処分を受けています(本誌9号「拘禁されて」、10号「遠い夜明け セスゥル・エイブラハムズ氏への手紙」で、自宅拘禁について触れています)事実、法務大臣ペルサーは、国民党のある集会で、一ヵ月に百ランドを稼げない白人の鉄道員もいるのに、なぜソブクウェに無料の住宅と月額100ランドを保障するのかと党員に問い詰められたとき、ロベン島ではソブクウェに年間1万2500百ランドが必要だったこと、ソブクウェが教育を受けた人間で逮捕前には相当な収入があったので、国際世論の非難をかわすためにも三ヵ月は無料の住宅と月額百ランドの保障は不可欠であることなどを強調して、その党員をなだめています。
ソブクウェにとって、キンバリーでの当面の問題は、家具と仕事でした。家は元々白人が所有していたので広く、家具をととのえるのは経済的にも大変でしたが、キリスト教会南アフリカ評議会が提供してくれた資金で、何とか最低限の家具を購入することが出来ました。
仕事は、なかなか決まりませんでした。70年の初めには、法律の仕事に携われるようにと、南アフリカ大学の法学部の通信教育課程に登録しています(76年の6月に、下級弁護士に認められて、小さな事務所を開いています)市から、キンバリー市役所のバンツー行政局の事務官の仕事はどうかと言ってきましたが、ソブクウェが政府の傀儡(かいらい)の役を引き受ける訳もなく、アフリカーナー政府の「最大限の譲歩」も、ソブクウェには通じませんでした。ソブクウェの要請もあって、ポグルンドがスズマンを通じて、ドゥ・ビアーズ社での仕事の可能性を問い合わせましたが、何の返事もありませんでした。
キンバリーで拘束されてからも、ソブクウェは家族への責任を感じ、アメリカへの出国を希望して、ポグルンドにその可能性を探ってもらっていました。70年3月には、アメリカのウィシコンシン大学から、研究員・教員として受け入れるという手紙を受け取り、政府にパスポートを申請しましたが、再度、申請は却下されています。
ポグルンドは、69年6月の初めに、キンバリーのソブクウェを初めて訪問しています。ソブクウェの自宅はおろか、黒人居住区に入る許可もおりませんでしたが、2人は市内で再会しています。以後、ポグルンドのキンバリー通いが始まりますが、ジョハネスバーグから車で5時間か、キンバリーまで飛行機で、その後空港からレンタカーかの長旅でした。折りからのオイル・ショックに加えて、各国の経済制裁を受けた国内情勢は厳しく、訪問の度毎に、保安警察の監視、尾行、盗聴、おどし、密告者の危険なども付きまといました。また、ポグルンドが白人、ソブクウェが黒人であるがゆえに、レストランでの食事も、カフェに立ち寄ってコーヒーを飲むことさえもかなわず、美術館の中や、車に乗ったまま炎天を避けた茂みの下での逢瀬となりました。六時の門限に間に合うように、黒人居住区の近くでソブクウェを車からおろしたあと、舗装されていない道路の砂煙の中に消える後ろ姿を見送りながら、自宅拘禁を強いられるソブクウェの不自由な境遇を思って、ポグルンドは胸を締め付けられています。
少し落ち着き始めてから、ソブクウェは庭での野菜作りを再開したりしていますが、九年間の拘禁生活によって蝕まれた体と心は、容易に回復しませんでした。自分の思う距離が歩けないなどの体力的な衰えに加えて、精神的に不安定な状態が続いたので、政府の許可を取り付けて、ジョハネスバーグからポグルンドの友人の精神科医を呼んで診察を受けています。
70年初めには、ソブクウェに援助し続けたモイラ・ヘンダーソンとユラリ・ストットがケープタウンからソブクウェに会いにきています。リベラルと拘束中の黒人が会見する「場所」はなく、結局、ドゥ・ビアーズ美術館の端のガレージのようなところにテーブルを用意して昼食をともにすることになりました。
この時期、何人かのアメリカ人がソブクウェの訪問を許されていますが、その中に公民権運動のリーダーで、黒人国会議員のアンドゥリュ・ヤングがいます。74年にソブクウェに会ったあと、長女ミリズワと長男ディニをアトランタの自宅に引き取って、アメリカで教育を受けさせてはという提案をしました。その結果、ビザの発給が認められ、2人は75年6月に出国しアメリカ留学を果たしました。ミリズワは心理学を専攻して大学を卒業したあと、結婚してカメルーンに移り住み、ディニは卒業後結婚して、ワシントンの法律事務所で働いています。残念なことに、その後、ヤングは南アフリカを訪れても、なにか政治的な思惑があったのでしょうか、2度とソブクウェには会いませんでした。
75年5月に、母親が90歳で死去し、ソブクウェは葬式に参列するために、800キロ離れたウムタタ行きの許可を得ています。そして、帰途、キングウィリアムズタウンでスティーヴ・ビコに会いました。拘束処分を受けたもの同士が、警察に知られることなく、密かに会っていたのです。ソブクウェによれば、少なくとも6回のメッセイジが2人の間を行き交っています。
77年6月になって、ソブクウェは体調の不調を訴えました。熱が高く、ひどい咳がなかなか取れなかったからです。一応キンバリーの医者の診察は受けましたが、不安を覚えたポグルンドが、ジョハネスバーグで友人の医師ボウド・コックの診察を受けるようにソブクウェに奨め、法務大臣クルーガーに連絡をとって、何とかヨハネスバーグでの診察を実現しました。ヨハネスバーグ行きは公表しない、ポグルンドが指定した医者以外の診察は受けないなどの条件がついたため、レントゲン撮影も出来ず、ソブクウェキンバリーの病院のX線写真を持参することも許されなかったので、コックは正確な診断は下せませんでした。その時点での診断は、細菌感染によって心臓の筋肉が弱り病状は思わしくないものの、治療次第では良くなるだろうということでした。
しかし、9月にキンバレーの病院からコックのもとにX線写真が届けられて、ソブクウェが肺癌に侵されていることが判明し、直ちにアメリカにいたポグルンドに知らされました。ポグルンドから連絡を受けた政府は、オレンジ自由州の首都ブルームフォンティンでの手術を指示しましたが、ソブクウェはその命令をかたくなに拒否しました。敵意渦巻くアフリカーナーの病院でメスを受ければ、生きては帰れないと考えたからです。政府が、どこで手術を受けてもよいと発表したのは9月9日、ソブクウェがケープタウンで肺除去の手術を受けたのは、9月14日でした。その後、放射線治療を受けるために、キンバリーとケープタウンを何度か往復しましたが、移動の度毎に許可を取ったり、報告するために警察署に出頭するのは、重症のソブクウェには辛いことでした。78年1月には、痛みもだんだんと激しくなり、2月には危篤状態に陥りました。
そして、ついに1978年2月27日の早朝、54歳の若さで、ロバート・マンガリソ・ソブクウェは、2度と還らぬ人となりました。 (続)
1992年初夏 宮崎にて
ロバート・マンガリソ・ソブクウェ(Robert Mangaliso Sobukwe)年譜
| 西暦年 | ロバート・マンガリソ・ソブクウェ | 南アフリカ |
| 1652
1806
1899
1910 1912
1913
1921
1924
1925
1930
1935 1936 1940 1942 1943 1944 1946
1947
1948
1949
1950
1952
1954
1955
1956
1957 1958
1959
1960
1961
1962
1963 1964
1965
1966
1967 1968 1969 1970
1974 1975
1976 1977 1978 1982 1986 1988
1990
1991
1992 |
12月 5日、ケープ州フラーフ・レイニェトに生まれる。
ロケーション内のメソジスト教会系の小学校に入学。
イギリス聖公会系の学校に入学。 ヒールドタウンの高校に入学。 小学校教員養成課程を終了。進学課程に進む。 肺炎で入院、休学。 復学。 進学課程を終了。大学入学許可試験で好成績を収める。 フォート・ヘアの南アフリカ原住民大学(フォート・ヘア・カレッジ)に入学。セスゥル・ントゥロコと出会う。 「原住民行政」学を通して、目を開かされる。ントゥロコの研究室に入り浸り、友人と共に感化を受ける。 学生代表者評議会の会長に選ばれる。ビクトリア病院にて初めて、ヴェロニカ・ゾドゥワ・マテと出会う。 スタンダートンのジャンドレル高校に赴任。
不服従運動に呼応して、スタンダートンでANCの集会を開き、教職を失ないかける。父ヒュバート死去。 ヴェロニカと結婚。ヴィットバータースランド大学バンツー語学科語学助手に採用され、ジョハネスバーグに転居。 長女ミリズワ誕生。
ベンジャミン・ポグルンドと初めて出会う。 ヴィットバータースランド大学の名誉博士号を取得。 パン・アフリカニスト会議(PAC)が創設され、議長に選出される。3月21日、パス法反対闘争でオルランド警察署に出頭し、拘禁される(扇動罪で禁固3年の刑)ヴィットバータースランド大 学を辞職(3月31日付け)
マンデラ、逮捕される。一般法再修正令(90日間無裁判拘禁法)成立。リボニア裁判の開始。 「ソブクウェ法」成立し、ロベン島に送られる。 ポグルンド、記者として、三ヵ月間の取材。(一月から四月)「ソブクウェ法」延長。出国ビザ申請が却下される。 手術のため、ケープタウンの病院に入院。「ソブクウェ法」再延長。アメリカのリンカーン大学から名誉博士号を授与されるが、連絡されず。 「ソブクウェ法」再々延長。
「ソブクウェ法」、4目の延長。 「ソブクウェ法」、5回目の延長。 キンバリーに追放され、24時間自宅拘禁に。 南アフリカ大学法律学部通信課程に登録。モイラ・ヘンダーソン、ユラリ・ストット、ソブクウェを訪問。アメリカのウィシコンシン大学から研究員・教員として受け入れるとの手紙が届く。パスポートの申請、再度却下される。 アンドゥリュ・ヤング、ソブクウェを訪問。 母アンジェリーナ死去。キングウィリアムズタウンでスティーヴ・ビコと密かに会う。ミリズワと長男ディニ、出国して、アトランタに留学。下級弁護士として認められる。
ケープタウンで、肺癌の手術を受ける。 二月二十七日、死去(享年五十四歳) ポグルンド、ソブクウェの墓の前で演説。 ポグルンド、ロンドンに移住。 ポグルンド、国連アパルトヘイト特別委員会で演説。
|
オランダ東インド会社、ケープに中継基地を建設。
イギリス、ケープ植民地政府を樹立。 第二次アングロ・ボーア戦争( -02) 南アフリカ連邦成立。 南アフリカ原住民民族会議結成。 原住民土地法成立(リザーブの設定) 南アフリカ共産党(SACP)結成。
南アフリカ原住民民族会議、アフリカ民族会議(ANC)と改名。
全アフリカ人会議結成。 原住民代表法、原住民土地法制定(人種隔離政策を推進)
ANCユース・リーグ結成。
国民党マラン政権誕生(アパルトヘイト政策を強行)
共産主義弾圧法、集団地域法、住民登録法など制定。SACPが解党し、非合法化される。 ANC、不服従闘争を展開。
クリップタウウンで国民会議が開かれ、自由憲章が採択される。 会議運動の指導者百156名が逮捕され、反逆裁判開始される( -61)
ANCが分裂。
シャープヴィルの虐殺。パス法一時停止。(3月28日)ANC、在宅ストを呼びかける(同日)非常事態宣言(3月30日)PAC、ANCが非合法化される(4月8日)パス法復活(4月10日)非常事態宣言解除(8月31日) 共和国宣言。ANC武力闘争を開始。
マンデラら、終身刑でロベン島に送られる。
ファヴールト首相暗殺され、フォルスターが首相に。 反テロリズム法制定。
ソウェト蜂起。 ビコ、獄中で殺される。 ピーター・ボタ、首相に。
フレデリック・デクラーク、大統領に。 PAC、ANC等、合法化され、マンデラ、無条件で釈放される。 ANC武力闘争を停止。アパルトヘイト法全廃される。 白人の信任投票で、デクラークの改革路線が支持される(三月) |
執筆年
1994年
収録・公開
「ゴンドワナ」21号6-19ペイジ