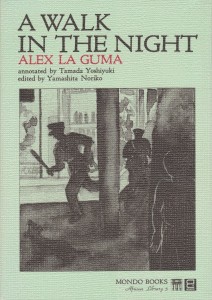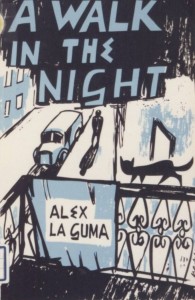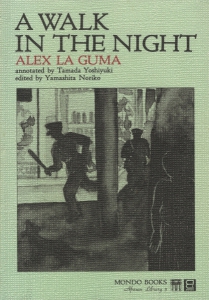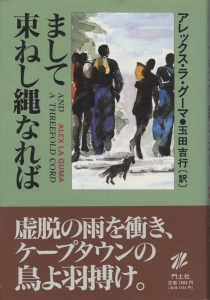概要
(概要・写真作成中)
本文
ミリアム・トラーディさんの宮崎講演
1989年8月6日 宮崎医科大学臨床講義室(105)
(講演の前の佐竹さんと私の挨拶・紹介は省きました。あとは講演会の順序どおりに並んでいます)
トラーディ この論文を読む前に、少しお話させていただきたいと思います。
私たち二人を日本にお招き下さる際にご助力いただいたすべての方々に対して深く感謝致します。ご想像できますように、南アフリカの黒人女性が日本に来ることができるというのは、画期的な出来事です。昨晩、私はとても思い出深い仏教的な行事(納涼花火大会のこと。コニーさんが、商店街の七夕の飾り付けを「仏教的な行事」とトラーディさんに説明したため)に参加することが出来ました。きっと忘れ難い出来事として、その思い出を南アフリカに持ち帰ることになるでしょう。皆さん方には、南アフリカでは、今現在も、違った形での行事(デモ行進のこと)が進行中であるということを覚えておいていただきたいと思います。
1956年に、私たち南アフリカの黒人女性は、何千人ものアフリカの女性は、パス法を女性にまで援用することに反対し、抗議するために、プレトリアの政府の官庁にデモ行進致しました。南アフリカじゅうから集まった女性がパス法に反対して抗議しましたが、パス法は南アフリカの女性にも適用されてしまいました。その結果、本当にたくさんの人たちがパス法の下で死んだり、苦しんだりしてきたのです。
ロベン島についてご存じの方もおありかと思います、多分ご存じだと思いますが。そこは、何世紀にもわたって、男性、女性を問わず、著名な私たちの指導者たちが、南アフリカの厳しい法律のために、監禁されたり、牢獄死してきた所です。
1948年以来、南アフリカのアフリカ人の人権は絶えずおびただしく侵害されてきました。そして、抗議に次ぐ抗議が繰り返され、私が南アフリカを離れるその日まで、プレトリアにデモ行進するに至りました。南アフリカでの人権のおびただしい侵害に反対して黒人女性は何度も立ち上がって、実際の行動としてあるいは心理面においても、抗議に出掛けました。皆さん方に、南アフリカの女性と連帯していただきたいと思いますのは、こういった感情からなのです。
「南アフリカの文学と政治」。それが今日の私のお話のタイトルですが、皆さん方には、南アフリカでは政治的でないことを語ろうとしても何も語れないということにお気付き願いたいのです。そして、私たちの国における政治は多くの人の意志に反して、少数の人間によって決定されています。南アフリカでは、黒人であるかぎり投票することは出来ません。自分たちの運命を決める人間を国会に送ることが出来ません。南アフリカでは人口のわずか10パーセントが90パーセントの運命を決定しているのです。
◎ 南アフリカの文学と政治
(中途まで。残りは質疑応答のあとに続きます)
書物や文学は知識の源泉であり、知識は力です。書物は歴史を変えてきました。偉大な作家や学者が皆、大の読書家であるのは周知の事実です。ジャーナリスト志望の学生たちが読むことにあまり関心を示さないのに不満を持つホレイス・クーンは、次のように尋ねました。
「もし現在何が起こっているのかを知りたいと思わなかったり、今何が起ころうとしているのか、自分たちの運命がこれからどうなるのか、或いは自分たちの生活が各国の事情や国家や国際的な政治とどのように密接に係わっているのかという真相を究明してみたいと思わないとしたら、一体どうして君達はこの世の中に生きているといえるのか。考えることを恐れているのだ。君らがあまりにも考えることをしないものだから、私は時々、ひょっとしたら君らには考えるべきことが何もないんじゃないかと思うことがあるよ」
クーンはどうしてそんなにたくさんの若者が自分の信ずべきものを懸命に探ろうとしないでいられるのか、その人たちがたくさんの本を読まずにいかにして自力で問題を解決するつもりなのかを疑問に思ったのです。
アーノルド・ベネットは次のように言います。「文学は付属品でなく、完全な生活を達成するための基本的な〈必須条件〉である・・・・文学の自由をまだ経験したことがないなら、人はいまだ胎児時代の眠りから醍めていないのと同じだ。その人はただ生まれていないというだけではない。見ることも、聞くことも出来ず、十分感じることも出来ない。単に食事をして食べることが出来るだけだ。文学の本当の働きを知り、文学の恩恵に与ってきた人たちには、実際には冬眠している熊とよく変わらないのに、自分たちは生きているという幻想を抱きながら生活している人があまりにもたくさんいることが、何より腹立たしく思えるのである」
私が自分の作品を通して何かを表現しようとする以前の段階で、信頼し得る情報源、つまり本当の人間の感情や願望、或いは愛情や欲求などを徹底的に究明していて、私がなじめる書物が全然ないのに不満を覚えていました。タウンシッフ(都市部の黒人居住地区)のいわゆる図書館の本棚には、黒人の子供を洗脳するためにアフリカーナーの学者が書いた本が並んでいました。私はエスキア・ムファーレレ、ルイス・ンコシ、アレックス・ラ・グーマ、ピーター・エイブラハムズ、ダニエル・クネーネ、デニス・ブルータス、アイ・ビー・タバタ、アルバート・ルツーリ、ネルソン・マンデラ、ロバート・ソブクウェのような作家の書いた本を探しましたが、どこにも見付けることは出来ませんでした。
南アフリカでは、いわゆる学校教育を受けた「原住民」や学者は危険な敵、競争相手と絶えずみなされてきました。そのような「原住民」がいると、何らかの理由で、特にいつも不安を感じる人々の集団が国民党員で、いわゆるアフリカーナーと呼ばれる多数派の人達でした。政権に就くずっと前からその人達は自らの胸に手をやり、挑戦状の中でも、とりわけアフリカ人の教育を先ず最初の達成目標にしようという誓いをたてたのです。1948年の普通選挙で勝利を収め、政権を握ると直ちにその人達は、アフリカ人を文学や普通教育に近付けないようにするためのありとあらゆる手段を考案しました。
国会の討論の場で、次のように語ったのは、当時農務大臣であったJ.N.ラ.ルー氏でした。
「非常に積極的な人もいるが、原住民には学校教育を授けるべきではない。もしそんなことをすれば、後になって、十分に学問的教育を受けたヨーロッパ人や非ヨーロッパ人という重荷を背負うことになる。そうしたらこの国の単純労働を一体誰がやるというのかね。学校に通う原住民に自分がこの国の労働者になる必要があると悟らせるように、我々が学校を管理すべきだとする見方に、私は大賛成である」
私たちの国が植民地化されて以来学校で教えられたり、ヨーロッパ人の歴史家によって書かれた「南アフリカ史」と呼ばれる文献は大抵、真実を反映していません。委託されたアフリカ人の手によって私たちの歴史が書き直されているのはそのためです。本当に長い問、私たちアフリカ人や他の第三世界の国々についての真実はおびただしく歪められてきました。ヨーロッパ人の学者や歴史家は、歴史だけでなく宗教や科学、それに文学や芸術分野でのアフリカ人の発達について多くを隠すために労苦を惜しみませんでした。私たちはこのような嘘を暴き出して、自分たちの肯定的なイメージや自尊心を取り戻すための本当の礎を築かなければなりません。アフリカ人の心の中からだけではなくて、もっとそれ以上に「大いに洗脳された」ボーア入たちの心の中からこれらすべての神話を払拭しなければなりません。
公法を研究するステレンボシュ大学教授ド・プレシ博上は、著書『ティン・パールスペクティヴァ』(『十の把握能力』)の中で、こう認めています。
「アフリカーナーは、未開の原住民とみなす者たちの唯一の統治者として、手に政治権力のこてを持って、自分たちだけで新しい南アフリカを作り始めました」
南アフリカのいわゆるアフリカーナーを自己崩壊から救済する必要があるのは明らかなので、ド・プレシ教授は「誤ったアフリカーナーの幻想中でも先ず取り除くべきだと思えるのは、その人達が南アフリカを支配し、なお支配し続ける権利を持っていると考えていることです」とうまく言いあてています。
教授は「そして今、80年代の終わりに、アフリカーナーとその政府は、自らの幻想状態から醒めて、裸のまま立っているのです」とも述べています。
(論文の残りは質疑応答のあとにつづく)
◎ 質疑応答
トラーディ このまま論文を読み進むべきかどうかずっと迷っていたんです。というのも時間があと一時間しか残っていないようですから。多分ゆっくりなら、この論文は読めるでしょうし。もし私が読めば、あともう一時間半はかかります。時間をもっと質問などに割いたほうがいいのではと考えていたんです。
参加者 提案してもいいですか。たぶんですね、この論文は皆さん家に帰ってから読めると思うんです。現在南アフリカがどんな状況に置かれているかについてあまり知りませんから、質問させていただけたらいいですね。皆さん方もトラーディさんの国についてとても関心があり、いろいろ知りたいでしょうから、もし質問させていただけるなら、その方がいいと思いますが。
トラーディ そうですね。あと一時間しか残っていませんから、そうする方がいいでしょうね。
佐竹 もっと具体的に質問を出して彼女に答えてもらいたい、なぜなら、今このぺーパーはみんなの手元にあるのだから、という意見が出たんですけれども。彼女もその方がいいとおっしゃっています。
玉田 いかがでしょうか。
参加者 賛成!(賛同の拍手)
トラーディ 南アフリカの生活について色々な観点からどんなご質問でも結構です。どうぞ。
参加者 二つ質問があります。一つ目ですが、日本へは、今回初めてですか。
トラーディ そうです。
参加者 どんな種類のビザを取られたのですか。ぶしつけな質問かもしれないと思うんですが。
トラーディ そうですね。ビザの種類を明かすべきかどうか私には分かりません。それは個人的な問題ですから。南アフリカの一黒人が日本の方々の助けなしに日本に来るのは容易ではありませんでしたし、不可能でした。関係者の方々は私たちがこちらに来るのを強く望まれて、日本の政府に働きかけて下さいました。それで観光者として来ることが出来たのです。
参加者 ビザを取るのに時間はかかりましたか。また、政府の役人からたくさん質問を受けましたか。
トラーディ ええ。二人ともたくさん質問されました。そして、ビザを取るのにとても時間がかかりました。例えば、どちらもプレトリアに行って、そこで日本の役人と会わなければなりませんでした。そうです、ヨハネスブルグからプレトリアまで行ったんですよ。
他にご質問は。はいどうぞ。
参加者 英語と母国語のソト語でお書きになっているというお話ですけれども、二つの言葉を使い分けるということには、何か政治的な意味があるんでしょうか。
トラーディ ええ、そうです。もし自分の好みでいきますと、出来ましたら自分自身の母国語で書きたいと思いますね。南ソト語かアフリカ語のどれかです。ご存じのように、言語は文化の一部で、もし別の言葉でものを書くとしたら、自分の文化を書くことにはなりません。お話しましたように、南アフリカではあらゆるものが政治的なのです。政治的な理由があるのかといえば、確かにあるのです。たくさんのアフリカ人の学者は英語で書くことにしなければなりませんでした。自分たちが昔から使っていた言葉でものを書こうとしたときには、既にずっと以前に、南アフリカ政府が出版やすべての権利を手中に収めていたので、アフリカ人がたとえどんなものを書いても必ず政府の手を経なければなりませんでした。従って、政府が認めない考えを述べるのは不可能でした。南アフリカの中で、アフリカの言葉でものを書いたり、作品を出版したり、白由に意見を述べるのは尚のこと不可能で、決してた易いことではありません。
ご存じのように、殆んどすべての出版社は白人の手の中にあります。出版は大変お金のかかる仕事で、アフリカ人でその費用が出せる人は殆んど、いえ誰もいません。南アフリカで黒人の出版社を設立したのはやっと一九八三年になってからでした。ですから、それ以来はじめて、政府が必ずしも認めていないものでもいくらかは出版出来るようになりました。
最初書き始めた時、私は英語で書きました。そして出版してもらおうとその作品をイギリス人の出版社に持ち込みました。私が南アフリカの白人の生活に合わない考えを言っているというので、作品は削られました。たくさん削られていました。この『メトロポリタン商会のミュリエル』のタイトルでさえ、初めに私がつけたタイトルではないのです。理由は、私が本を白人の出版社に持っていったからです。私自身では出版はかないません。あまりにもお金かかかり過ぎるからです。それが白人の出版社が私の本にしたことです。その本がやっと世に出たときには、わずかに半分だけでした。後に完全なかたちで海外で出版されて、南アフリカに届いた時、発禁処分となりました。それでお分かりのように、南アフリカで書くというのは極めて政治的な問題なのです。
参加者 もう一つよろしいですか。
トラーディ もちろんです。
参加者 検閲の具体的な例みたいなものを二、三でもお示し願えないでしょうか。
トラーディ 南アフリカの検閲制度について語れば、実際にはアパルトヘイトの制度全体を語ることになります。いわばアパルトヘイトは、南アフリカの黒人に対する検閲制度の形態なのです。
南アフリカでは、白人であるという理由で10パーセントの人々が自分たちの考えや信条を、黒人であるという理由で90パーセントの人々に無理やり押し付けていると私は言いました。つまり、アパルトヘイト制度全体が検閲制度だということです。
ここでは、南アフリカで書いたり、自由に意見を表現したり詳しく述べたりすることに関して、著作検閲に影響を及ぼす法律をいくつか読み上げるだけにしておきましょう。例えば「公共安全法」と呼ばれる法律がありますが、その法律ではいかなる方法であれ政府を批判したり、人々の敵意を煽りたてるような出版物はどんなものでも発禁処分に出来るという権限が法務大臣に与えられています。「バンツー政庁法」では、原住民と白人との間に敵意を煽ると思える目的で演説したり、行動したりする者はすべて有罪とする、となっています。アフリカ人居住区の飢餓や貧困状況や政治的騒乱についての記事を書いたジャーナリストがこの法律で提訴されてきました。また、「出版法」というのもあります。公共の道徳もしくは宗教的感情を害したり、住民間の関係を損なったり、国家の治安秩序を脅かすと法務大臣が判断するものが含まれる出版物はすべて、この法に従って、望ましからず、との判決が下され、結果的には発禁処分となります。「刑事訴訟法修正令」というのもあります。その法律には色々条項がありますが、なかでも、抗議の目的につながりがあると思われる郵便物を没収するという条文は効力を発揮しています。「刑事集会法」「刑事訴訟証拠法」のような、同種の色々な検閲法があります。「テロリズム法」もあります。
これらの法律はすべて解放運動家や、特に人々の著作を取り調べるためにありますが、なかでも最悪なのは、「バンツー教育法」で、精神的な検閲のために制定されたものとしては、もっともひどい法律として際立っています。お分かりのように、数えきれない程の検閲法があるんですね、もし読み上げていれば、丸一日はかかってしまうでしょう。ほんのさわりの所だけ、ご紹介させていただきました。
参加者 厳しい法律がたくさんあるというのは分かったんですけれども、例えば、ここにある小説の中で、実際に検閲されて、どういうものが削除されたのか、説明していただけませんか。具体的にですね。例えば、女性のどういう所を書いたらいけなくて、削られたのか、そしてまた、半分くらい削られたということですが、それで、小説として成り立つのかどうか、構成がですね。その辺を教えていただきたいと思います。
トラーディ そうですね、そのような本は発禁処分を受けるに違いないと考えたのは出版する側の問題だったのです、その人は出版をする人で、売って利益を上げたいと思うわけですから、本が売れるように工夫しようと考えます。当然その人は、南アフリカでの読者層と販売目標が主として白人の読者層だと知っていますから、その白人の読者層の感情を害さないようなやり方でその本を出したいと考えたわけです。
削られた後も、それで小説として成り立つかどうかがお知りになりたいということですが、そうですね、それでもなお、なんとか小説として成り立っていたと思いますね。実際、最初はそれをはねつけましたし、そのような形で出版されるのは嫌だと言いました。でも、最終的には自分の考えを表現する手立てが私には全くありませんでしたし、母も「先も長くないし、死んだらお前の本が出版されるのが見られまい。先方の言うように出版してもらったら」と言うものですから、私もそれに従いました、それから本が世に出たんです。削られた半分の箇所は、南アフリカの法律に関しては、法律を解釈した部分とか、黒人の感情について語った部分でした。
参加者 (『メトロポリタン商会のミュリエル』を見せながら)もう少し、この本の中で。
トラーディ 例えば、第一章。第一章の後半部分が削られました。私は南アフリカの背景、政治的な背景について語りました。例えば、私が次のように書いた時、すべてが削られました。
「南アフリカ共和国は二つの世界に分断された国である。一方は、すべて日頃の生活のために整えられた、豊かで、快適な白人の世界、完全なまでに武装された、恐怖の世界。他方は、惨めなほど疎外され、秩序を破壊され、声も出せず、抑圧され、落ち着きを失ない、混乱して、武器すら持たない黒人の世界、取り返しのつかぬほど、すべての『部族的な』絆を断ち切られて、変転する世界。」
参加者 他にどの部分が削られたのですか。
トラーディ (本をかざしながら)この部分全部が削られました。
参加者 その本は国内で発行されたものですか。
トラーディ そうです。あとでお見せしましょう。ほかの削られた部分をたくさんお見せ出来ると思いますよ。他の方にご質問の機会を譲ったほうがいいと思います。
他にご質問は。
参加者 私は一年ちょっと前に「クライ・フリーダム」(「遠い夜明け」)という映画を見ました。あれは確かスティーヴ・ビコさんの運動を主にしたお話で、南アフリカ人でいらっしゃる新聞記者のドナルド・ウッズさんとの友情の物語だったと思うんですけれども。さきほどのお話の中で、10パーセントの白人たちが90パーセントの人々の運命を支配しているんだとおっしゃいましたが、白人の中で事態を憂えて何か行動を起こす人たちは全くいないのかという疑問があるんですが。
トラーディ そうですね、いることはいますが、何せ比率が10対1でしょう。南アフリカの白人は色々恩恵に浴しています。自分達が特権を与えられる立場にいますから、白人は誰のためにも闘う必要がありません。これまでずっと、白人が快適で、豊かで、満足するように、現状がすべて整えられてきたのです。だから、白人は立ち上がらなくてもいいのです。ですから、本当に極く極くわずかで、5本の指で数えられます。黒人の権利のために立ち上がる人は殆んどいません。
最近になって、白人有権者の間で、黒人の抗議を取り上げようとしたり、黒人に近付こうとする動き、前よりも大きな動きが見られますが、それも国際的圧力やランド価値の低下、それに自国の経済不況によるものにしか過ぎません。多くは今の状態が自分達の非常に居心地のいい立場にどう係わってくるのかが心配だからというのが実状なんです。その人達は不安を感じているのです。極くわずかですが、黒人のために純粋に関心を示す白人もいるにはいましたが、お話しましたように、その数は本当に極めて少ないのです。
参加者 二つご質問したいと思います。
「バンツー教育法」について述べられましたが、黒人と特権を与えられた白人との間にはどのような教育制度の違いがあるのでしょうか。また、有能な黒人の学生が高等教育を受けるのは可能でしょうか。
トラーディ 要は違った教育制度があるということなのです。白人のための教育は、皆さんが多分この国で受けているような教育です。しかし南アフリカでは、申し上げましたように、国内の労働者として黒人を作り上げる必要があるだけだと白人達は言いました。ですから、白人のそのような教育は、そういう種類の人々、つまりただ国内の労働者になるしかない階層の人々を供給するために効率的に行なわれてきました。
(白人を頂点に、アジア人、カラード、黒人の順で存在する教育制度を示すピラミッド型を黒板に書いて説明しながら)
このような普通教育制度があります。これが普通教育です。アジア人の教育があります。カラードの教育があります。これですね。バンツー教育庁。アフリカ人はバンツーと言われています。四つの別々の教育庁。(ピラミッドをなぞりながら)教育はこのようになっています。(ピラミッドの一番上を指して)白人のための良い教育。(二番目の部分を指しながら)アジア人のためのすこし良い教育、皆さん方のような日本人やインド人などのようなアジア人ですね、時には名誉白人とみなされますが。そして教育はピラミッドの下の方へ行くに従って絶望的となっていきます。(一番下の部分を指して)下のこの部分がアフリカ人の教育です。南アフリカにはピラミッド、社会的なピラミッドがあります。白人がこの上で、それからアジア人、カラード、そしてアフリカ人。(白人の層を指し、ピラミッドをなぞりながら)そして、この人達だけが投票することが出来、基準賃金はこのように低下していきます。格付けやあらゆるものがこのように低くなっていき、ついにはアフリカ人と呼ばれる最下層の人々へと至ります。この人達だけに侵されない権利があり、残りの人口の90パーセントの人々は、アパルトヘイト政策によって不利な状態に置かれています。
例えば、仮にあなたが教師である場合について考えてみましょう。教師にも、白人の教師、アジア人の教師、カラードの教師、それにアフリカ人の教師がいます。給料の額は自分の属する人種グループに従って違います。また、どこに住むかも属する人種グループによって決まります。私が南アフリカで佐竹さんと一緒に住みたいと思っても、一緒に住むことは許可されません。もし仮に、佐竹さんが私と一緒に住みたいと思ってもそれは叶わないのです。皆さん方との場合なら、もっと事態は悪くなるでしょうし、白人との場合なら尚更のことです。
ほんの表面的なことだけに触れましたが、バンツー教育によって私たちアフリカ人にどういうことがなされてきたのかを正確に解説するとしたら丸一日はかかると思います。いずれにしても、バンツー教育というものが結果的に、ひとつの大抗議行動を引き起こす要因となりました。1976年のその抗議行動では、千人以上もの生徒たちの命が犠牲となりました。
他にもっとご質問は。
コニー (飛び入りで)皆さん、すみません。私の娘はおととしから日本の学校に行っています。私の娘は、国語、算数、そういうものを勉強しているけど、私の娘は社会も勉強している。社会の教科書の中に色々書いてありますね。郵便局とか、映画(館)とか、郵便屋さんは何をしているとか、時々娘を郵便局まで連れていって。公園も書いてありますね。色々のものが入っていて、シーソーとかジャングルジムとか、けど、黒人の教科書の中にはそういうものは絶対入っていない。なぜなら、ソウェトは大変大きいけれど、二百万人が住んでいるけど、There is no park. 子供たちの公園がない。There is no swimming pool there. というのは、黒人たちにそういう公園とか何かを見せたら、黒人たちもあそこへ行きたいと思うから。だから、出来れば、そういうことを見せないで、教えないで(と政府は考えている。)すみませんね。
トラーディ 他にご質問は。
参加者 日本だったら、小学校から大学まで日本語ですけど、ソト語ですか、マザーズ・ランギッジで本を書かれると言われたんですけど、読む人たちはソト語を学校で習うんでしょうか。学校での授業はソト語で行なわれているのですか。
トラーディ ええ、アフリカの言葉は教えられています。私がアフリカの言葉で書けるのもそのためです。今、英語とアフリカの言葉で書いていると申し上げましたが、私たちアフリカ人は選んでそうしているのです。今まで十分にご説明しましたように、アフリカ人が自分たちの言葉で書こうとすれば、政府は色々な権利を使って介入してきますので、私たちは仕方なく英語で書くことを選んでいるのです。
でも、もし私が英語で書かなければ、ここにはいませんし、皆さん方も私の考えがどんなものかお分かりにならないでしょうね。
アフリカ人にも、私が生まれたころからずっと自分たちの言葉で書いてきた人たちもいますが、誰も知りません。アフリカの言葉で書いてきた、という意味ですが。そして、そのような種類の文学を取り扱ってきたのが黒人だという理由でその人たちについては誰も知らないのです。
参加者 さっきから、母国語と英語のことが、非常に話題になっていますが、トラーディさんが多分英語でお書きになった一つに、今の母国の状況をたくさんの人に知ってほしいということがおありだったと思うんです。けれども、同時に、そうやって目覚めてきたたくさんの国内の人たちに、ソト語で書きたいという気持ちがすごくあるだろうと思うんですね。そのお気持ちで本をお書きになる中で、さっきから出ている字も書けない人たちのためにどういうことをお考えになっていらっしゃるのかをお聞きしたいと思います。
トラーディ ええ、そうですね。私たちにはいわゆる口承文学と呼ばれるものがあって、それは代々引き継がれてきています。例えばですね、南アフリカに関する映画をご覧になれば、何千という大衆が動員されているのがお分かりになると思います。私たちには大変豊かな口承の歴史がありましたから、何が起こったのかを伝達出来ましたし、今も伝達出来ているのです。私たちは代々、口承文学を引き継いできました。この種の情報伝達機構は政府の手によっても破壊されはしませんでした。
例えば、たくさんの詩人がいます。その人たちはタウンシップで非常に活躍し、いつも詩を通して言葉を伝えています。詩人たちは、誰かを埋葬したり、誰かが結婚したりする時などのような殆んどあらゆる儀式で詩を詠じます。詩人たちが口承文学を通して、言葉を、政治的な情報を伝えているというのがお分かりでしょう。
ご存じのように、例えば、南アフリカが白人の土地と呼ばれているのを知っている人達は、世界中でもごくわずかです。それは白人が私たちの祖先から土地を奪い取ったからです。私たちは土地にあくまでしがみついてはおれませんでした。そのためにみんなずーっとメイドやボーイのようなことをして来たのです。アフリカ人の多くは白人の家庭で働いています。ですから、たとえ学校に行っていなくても、特に英語は知っているのです。
他にご質問は。
参加者 極めて簡単な質問をしたいと思います。黒人と白人の間にはいつも対決があると思うんですが、問題を解決するために折り合うつもりのある人はいないのですか。
トラーディ そうですね、黒人はいつも切に願ってきましたし、またずっと白人に理解してもらおうと努めてきました、「いいですか、こんな状況の下では私たちは生きてはいけません。あなた方が土地を自分達のものだと如何に言い張っても、土地が私たちのものだったのははっきりしているのですよ」と。
しかし今、その人達はあまりにも権力を持ちすぎて独善的になっています。現在、南アフリカで何が起こっているかをご覧になればお分かりいただける、という意味ですが。本当にたくさんの人種差別法、犬以下の如くに黒人を取り扱う法律があります。そのような人達は、ナチのような人達はですね、自分達は他の民族を打ち滅ぼすために生まれてきていると信じています。そんな人達に考えさせるのはなま易しくはありませんし、そんな人達に、こんな法律でアフリカ人が苦しめられているのを十分解らせるのは容易なことではありません。白人の心の中にその効き目が表われるのは、国外からの経済制裁や国内の抗議行動、それにゲリラ戦などのような非常に大きな圧力があるからに他なりません。さもなければ、その人達を交渉の場に引きずり出すのは殆んど不可能でした。現在も尚、全世界はアパルトヘイトに抗議して立ち上がり、その人達を交渉の場に引きずり出そうと努力しています。
しかし、思い当たる節がおありだと思いますが、人間はいったん権力を手にして自分が強いと思い込んでしまうと、弱い立場にいる人の問題などは目に入らなくなってしまうんですね。
参加者 今、経済制裁の話があって、経済制裁のことをお聞きしたいんですけれども。日本の新聞で日本の企業がずいぶん南アフリカと貿易していると、ずっと前読んだことがありますけど、やっぱり日本の企業なんかに怒っていらっしゃるんでしょうか。それと、経済制裁は南アフリカの中に住んでいる黒人もやっぱり労働者だから、制裁を受けると、経済的にはあまり得なことはないと思うんですね。どっちかというと、解雇になる、それでも制裁はあった方がいいんでしょうか。
トラーディ もちろん必要です。黒人の窮状を白人に聞かせるにはどうしたらいいかみたいなことを述べてきたに過ぎません。しかし、それは私が日本にやってきて、南アフリカの問題で現状について皆さん方にああせよと指図したり、日本政府にこうせよと命令したりすることとは違います。私にそれは出来ません。南アフリカの人々のために何が出来るかを判断し自分で結論を導き出すのはあくまで日本人自身なのです。
私がここに来て皆さん方に何をすべきかを指図することなど、勿論出来ません。皆さん方はとても知的な人々です。日本は東洋でも、何世紀ものあいだ植民地化を免れてきた数少ない国です。何世紀にも渡って、自分たちの文化を傷つけられずに保ち続けてくることが出来ました。ですから、皆さん方が強く、逞しくて、他の人が困っているときにどうしたらいいかを考える際に必要とされるあらゆる資質を備えておられるのが、私にはよく解るのです。
私が怒っているか、ですか。いえ、怒ってはおりません。そうですね。私は自分の個人的な感情についてお話するためにここに来たのではありません。作家としてここにいて、南アフリカの黒人のお話をさせていただいているのです。私たちは本当に色々な点で制限されているんですね。従って、作家として見方は客観的でなければいけませんし、自分自身の個人的な感情を述べるのではなく、人々の一般的な感情についてお話しなければなりません。
他にもっとご質問は。
参加者 女性に関する情勢について質問したいんですけれども。というのは、黒人の人たちというのは、白人社会から一応労働力を搾取され、抑圧されています。そういう社会の中で、その人種差別以外に、女性であるということで同じ黒人の男の人達から抑圧されている、つまり黒人の女性は二重の意味で抑圧される立場にあるのかということをお尋ねしたいと思います。
トラーディ (黒板のピラミッド型の図を使って)南アフリカのピラミッド、社会的なピラミッドについて先程お話致しました。申し上げましたように、てっぺんのところに白人の主導権があり、白人の選挙民がいます。そして、男性が・・・・もし南アフリカのピラミッドをよくご覧になれば、この部分が更に別れているのにお気付きになります。
人々の、そうですね、教師の給料についてお話しましたね。白人の男性教師は白人の女性教師よりたくさん貰っています。同じことがアジア人の女性教師についても言えます。アジア人の女性教師は男性教師よりも貰うお金は少ないですね。いわゆるカラードも男性の方がたくさん貰っています。そしてピラミッドのこの一番底のところに、アフリカ人女性、私のような人間がいるのです。南アフリカ全体の構造のなかでも、最も卑しめられ、虐げられた人々です。黒人女性の権利や南アフリカの黒人女性の政治的な諸権利の侵害について私が取り扱わなければ、と考えますのはまさにこの部分なのです。それは全体に深く係わっており、その部分についてだけお話しても午後が丸々かかってしまいます。しかしここでは、黒人女性がピラミッドの最底辺におり、アフリカ人男性は南アフリカの黒人女性以上にある程度の権利を与えられてきたということ、更に、南アフリカのアフリカ人女性の状況には要求していかなければならないことが未だたくさん残されている、ということだけを皆さん方に知っていただくだけでよしと致しましよう。
例えば、書き始めた時のこと、原稿を仕上げて出版社にそれを持っていったんですが、その本の契約書にサインすることが私には出来ませんでした。理由は私がアフリカ人女性だったからです。現在の法律の下では、私には何の権利も、何の政治的な権利もありません。夫だけが契約書にサイン出来る人間だったのです。アフリカ人女性としては、いかなる権利も、いかなる契約の権利も私にはありません。
それだけではなく、家や土地、それに電話、家具、車などのようなものを購入することも私には出来ません。黒人女性であるという理由でそれができないのです。黒人のアフリカ人女性がこういう状況から這い上がり、はしごを昇っていくのは、殆んど不可能に近い仕事です。私が座って書けること自体奇跡だと考えている人が今でもたくさんいます。書き始めた時、私は小説を書いた初めての女性、南アフリカで小説を書いた初めてのアフリカ人女性でしたし、今日でもやはり唯一のアフリカ人女性です。もうすでに30年ほどにもなります。
佐竹 他にございませんか。
参加者 二年くらい前に、私は、南アフリカ出身のホワイトの人と話す機会があったんです。その時、その人は、私は彼の言うことが正しいのかどうかというのがよくわかんないのですけれども、南アフリカの土地というものはですね、三百年、四百年くらい前から、一応、白人によって支配されてきたというふうに言うんですね。確かにあそこの土地は、彼らが支配していた土地であるという考えですね。私がそれを聞いて思ったのは、要するに、白人というのは、彼等が自分達の土地だという意識を持っているような感じを受けたんです。そのような白人の意識というものが、果たして、南アフリカに対する共通の見方というふうに考えられますか。またそれに対して、黒人の方として、その土地自体の所有権について、歴史的にどのように見られるのかということをお聞きしたいのです。
トラーディ 大抵の白人が、土地を自分達のものだと信じているかどうかについてあなたはお知りになりたいんですね。そうです。白人達は確かにそう信じています。白人は自分達をヘレンボック、つまり選民と呼んでいます。そして自分達がヨーロッパから南アフリカに来て定住し、土地を自分達のものとして所有するために送り出されたのだと言います。アフリカーナーの、少数派のアフリカーナーの党綱領の前文をじっくり読めば、あの人達は神が南アフリカで自分達に土地を与えてくれたことに感謝しているのがわかります。
あなたはアフリカ人も同じように感じているかどうかをお知りになりたいのですね。もし南アフリカの歴史、本当の南アフリカの歴史をじっくり見れば、白人が南アフリカを植民地化し始めたずっとずっと昔から、侵入者に抵抗する戦争が本当にたくさんあったことがわかるでしょう。アフリカ人は侵入者と非常によく闘いましたが、その人達がすぐれた武器を使ったので、白人達がすぐれた武器を使ったので、打ち負かされてしまいます。ご存じのように、その人達は東洋の国々から火薬を手に入れ、それをとても巧みに南アフリカで使いました。そして、アフリカ人は武器がその人達のものより、白人達の武器よりすぐれていなかったために、自分たちの土地を失なってしまいます。アフリカ人は土地が自分たちから奪い取られたという事実をとても強く感じていますし、誰もがそれを残念に思っています。そして単にそこにとどまっているだけではなく、白人に抗議して立ち上がっているのです。それが、アフリカ人が永遠に土地を奪われている事実をどうしても受け入れようとしないで絶えずストライキを続けている理由なのです。それでお答えになりましたでしょうか。
参加者 その南アフリカの白人は、もちろんそれは彼の個人的な意見になりますから、全体の意見とは思いませんけれども、殆んどのいわゆるアフリカのブラックスも、彼らと同様に、イミグラントである、要するに、労働者としてイミグラントとしてもってこられたという意見を言われたんですが、それは正しいでしょうか。
トラーディ その人たちはどこから来たんですか。
参加者 ちょっとそのことについては・・・・。
トラーディ その人たちはヨーロッパから来たんですか。いつ?
コニー ちょっといいですか。多分あの方は、鉱山労働者のことを言っているんじゃないですか。
トラーディ 鉱山労働者は移民ではありません。その人たちはアフリカの出身です。その人たちがアフリカでどうして移民なんですかという意味ですが。その人たちはずっとそこにいたんです。ただ何が起こったのかといえば、南アフリカの産業が盛んになって近隣諸国から労働力が必要になったというだけなのです。私たちは何世紀もずっとそこにいたのです。
アフリカ人はもとからアフリカに、南アフリカにいたから侵入者と闘ったとお話しました。アフリカ人はいつもその人達と闘いました。ケーフタウンの近く辺りで始まったいわゆる「カフィル戦争」などがありますね。絶えず侵入者達と闘ったのです。白人達がやって来た最初から、黒人はそこにいたのです。来た時から黒人がいることを白人が知っていたというのに、いったいどうして黒人が移民だと言えるのですか。
参加者 玉田先生にお聞きしたいのですけれども・・・・あの・・・・。
トラーディ (コニーさんが黒板に書いた南アフリカの地図を使いながら)
この人たちがここにきたんですね。ヨーロッバから南アフリカに来たのです。その人達はスパイス等を手に入れるためにインドに向かう途中にここを通っていたのです。(喜望峰を指しながら)ここをよく通ったんですが、そのうちにここに新鮮な野菜などを補給する中継地が出来るとわかったんです。
(各州の境界をなぞりながら)この境界線でさえその人達自身がつけたものなんですね。それは私たちの境界線じゃありません。私たちの境界線はそんなところにありません。オレンジ自由州と呼ばれる州があります。また、いわゆるトランスヴァール州があります。それらはすべてあの人達の境界線なんですね。決して黒人の境界線じゃありません。それはあの人達のものです。その人達が境界線を作ったんです。黒人じゃありません。黒人に関する限り、アフリカじゅうに、ここ南アフリカじゅうに住んでいました。ずっとそこにいたのです。その境界線は白人の境界線です。ですから、その人達は、その人達、つまり白人はボツワナ、レソト、スワジランド出身の人たちを移民だとみなしているのです。私どもは移民だとはみません。その人たちが南アフリカ黒人の人口の一部だと私たちにはわかっているんです。「移民」自体もその人達の用語で、すべてたわごとです。
1913年、その人達だけで、白人だけの議会で、国を黒人と白人に分けることに決定しました。87バーセントが白人のもの、13パーセントが黒人のもの、と決めたんです。黒人に属する土地について自分達で勝手に決定したのです。この比率を見て下さい。そうです、土地の13パーセントを90パーセントに与え、87パーセントを10パーセントに与えると白人達は考えたのです。白人は非常に強力で、銃を使いますから何でも白人のものです、白人はずっとそうやってきました。でもそれは南アフリカの黒人とは何の関係もないのです。
参加者 要するに、私は、一人の人しか聞いてないので・・・・そういうような概念というのは、比較的白人の中では共通の捉え方なのかということなんですけどね。
玉田 そうです。共通の捉え方だと思います。結局、アパルトヘイト政策の根幹には、土地の問題が深く関わっています。その土地の問題について、1913年に、それまで実際に行なわれていた慣習を白人が一方的に法律で決めてしまったわけです。その辺のところについては、今日お配りした資料「アパルトヘイトの歴史と現状」(本誌14号に全文掲載)の中で、日本語でも書きましたし、それについては何冊かその中にあげている本を読んでいただいてもわかります。三冊くらいあげているんですが。「アパルトヘイト」がいわゆる土地政策だったというのがよく理解していただけると思うんです。
つまり、今、ミリアムさんが少し怒っていらっしゃるのは、そういう歴史的な背景は、みんなの共通の認識というか、少なくともここにきて、アフリカの文学、黒人文学について聞いてくれるという人に関しては、それくらいの歴史的な認識はあると思っていらっしゃったんじゃないでしょうか。だから、そんなふうに言われること自体に、又そういう質問が出ること自体に、やっぱり少し心外な感じをお持ちになったんじゃないでしようか。
そういう意味で、予め、日本語で書いた歴史をお届け出来たらよかったんですが、何しろ、決まったのが一週間程前でしたから、そこまでいかなかったんです。でも、今出版されているものを読んでも充分に分かります。ただし、白人の書いた、従来の、「伝統的」なヨーロッパの歴史を読むと、そうは書いていないんです。大分違うんですね。
もう一つだけいいでしょうか。今、白人が侵入してきて黒人が武器でやられたという話がありましたが、それに関して、イギリスが映画を作っているんです。「ズールー戦争」(ZULU)という映画ですが。それを見ると、野蛮人を銃で撃って征伐し手柄を立てる、それに対して女王様が褒美をやるという構図で、その戦争を賛美しているのが分かります。レンタルビデオでも借りられます。それがいわゆる白人側の伝統的なものの見方だと思うんです。その辺は、少なくとも、こういう所に聞きにこられる人にとっての共通認識だと考えられて、ミリアムさんはお話されたと思うんですね。昨日の晩も、色々お話していて、どういう層に対して話をするのかということになりました。最初は、南アフリカの作家のことですね、今日話に出ていたアレックス・ラ・グーマとか、50年代までに国内にいらっしゃった人とか、そういうことについてかなり詳しく、とおっしゃったんですが。たぶん一般の認識がまだそこまでいっていないのではということで、「アパルトヘイト」のことも含めてお話しようということになったんです。一般の方もたくさん来られるということで。
実を言いますと、今のような質問などが出てくるとは思ってなかったんです。
参加者 お疲れのところすみませんが、現在のアフリカの、お宅の国での宗教・・・・特にIndependent churchですか、独立教会というのがどのような役割を果たしているのかについてお尋ねしたい。
トラーディ 皆さん方のお手元にある今日の論文の原稿をご覧になりますと、例えば私が次のように述べているのがお分かりいただけると思います。「現在、南アフリカでは熱心に解放の神学を説いている新しい世代の聖職者たちがいます。」それが独立教会の取る立場です。2頁の一番最後のところで、カイロス・ドキュメントと南アフリカの抑圧に関してその人たちがどんな立場に立っているかについて述べてありますが、体制が聖職者に望んだやり方でなく、キリスト教の真の精神に立って聖書を解釈し直すことに、今教会は非常に積極的になっています。
玉田 最初、2時間くらいのつもりで会場を取りました。前後1時問の余裕をもって4時間とっていますが。実質的に1時間お話していただいて、あと1時間質疑応答の予定でした。既にかなり時間もまわっていますので、最後に少しだけ今回のことも含めて、宮崎における状況についてお話させていただいて、終わりたいと思います。もし個人的にどうしてもお話したいとおっしゃる方は残っていただいて結構です。5時ぐらいまで学校にいるつもりですから。
今回は最初にお話しましたように、僕の個人的な判断でお呼びしました。
僕は去年の4月にこちらに来て、まだあまり知り合いもいないものですから、どうしたものかと最初は迷ったんです。しかし、宮崎大学の方とか、ここの医科大生の人からも、僕が思っていた以上にいろいろご協力をいただきました。それから、今日そこにいらっしゃる川原さんにも新聞社とかいろいろまわっていただきました。報道関係も意外と反応がよく、殆んど取り扱って下さいました。当初、この会場は学生にということで借りていたんですが、急きょ一般の方にも公開するということになって、少しバタバタしました。
来ていただくだけで精一杯で、僕自身、まさか通訳までまわってくるとは思ってなかったので、少し慌てました。新聞社を回っているとき、一般の方に公開するんだったら通訳を、ということになったわけですが。まあ、宮崎に南アフリカの、特に文学者を迎えるというのは初めてでしたし、僕自身としては、どこでもいいんですけど、医科大学で、宮崎でこういうことをやっているというのを知ってもらえたらなあ、と考えました。ですから、たくさんの人が来られるということ自体はあまり期待していませんでした。大概、アパルトヘイト否(ノン)の美術展などがあっても、この前講演に行ったところでも、会場が広くてもあまり多くなかったですからね。どこでも、そんな状況でしたから、今日これほど来ていただけるとはまったく予想していませんでした。そういう意味では、お呼びしてよかったなあと思っています。最近特に日本にいろんな人が来る機会が多くなりましたから、その人たちをこちらに呼べる機会が持てたらいいなあ、そしてこれをひとつの機会に出来たら、と考えています。
今回は結果的に個人的な招待ということになりましたが、そういうやり方では長続きしませんから、次回はみんなで分担してやれたらいいなあ、と思っています。
今日お配りしたなかに、感想とか、お知りになった方法とかを聞く用紙があります。今後もし誰かをお呼びする場合、どういうふうにすれば来てくださるとか、どういうふうなことを望んでここに来られたとかがわかれば、僕の方でも少しは動けるんではないかなあという気がしていますので、是非お書きください。
おそらく、トラーディさんのほうは東京に戻られて、関西、広島と行かれる予定です。そこでは、今最後にあったような話ばかりになると思うんです。日本では、ですね。そういう意味で、最初はもっと気軽に、気軽にと言ったら叱られるかもしれないんですが、文学の話をしたいと、他の所では多分出来ないでしょうから。それで、最初文学の話を始められたんでしたが、こういう状況でしたので、僕の方としましても、最後のほうでバタバタとしまして申し訳ありませんでした。十分に準備も出来なかったうえ、不首尾なことが多かった点、深くお詫び致します。今度、こういう機会が持てましたら、もう少し準備してやりますから、その時は、是非ご協力をお願いしたいと思います。
では、最後に少しミリアムさんのほうから・・・・。
トラーディ 日本語なので、玉田さんのおっしゃることが殆んど分からなくて申し訳ないのですが、ここに招待していただき皆さんとお会い出来たうえ、皆さんから質問をお受けすることが出来たのを本当にうれしく思います。拙いやり方ではありましたが、南アフリカで私たちみんなが思っている考え方の幾分かでもお伝え出来たとしたら有り難いと存じます。
(参加者は立ち上がり、長い間の拍手)
玉田 (二人とも通訳出来ず、顔を見合わせながら)どうもすみません。僕も、最後ホッとしまして、聞いてるだけで申し訳ありませんでした。それでは、一応これで終わらせていただきます。
お話されたことについては、録音していますから、原稿を起こし、活字にして、もういっぺん考えていただけたらと考えています。かなりの作業になりそうなのですが、出来るかぎりやってみたいと思っています。出来上がりましたら、お送りしたいと思います。
どうも、今日は長いことありがとうございました。
(拍手)
トラーディ 南アフリカでは、解放に向けて闘いは続きます。アマンドラ!(権力は!)
コニー ガウェツゥ!(我らに!)
(拍手)
◎ 南アフリカの文学と政治
(論文のつづき。講演会で読まれなかった部分です)
南アフリカでは文学によって真実を見えなくする作業が、驚くほど広範囲にわたって行なわれてきました。1988年4月25日付けの「スター」紙の社説で、レヴェル・メイスン教授という人が1600年前のブルアダールスツゥルワァムの古代遺跡を再度埋めると脅迫していると、その驚きを述べています。この遺跡はかなりひどい状態で放置されたままになっていると言われています。
ローマ時代後期に、黒人の鉄や銅の鍛治職人がたくさんいたという事実が明らかになってしまうので今まで無視されてきたのではないかと邪推されてもおかしくありません。「過去を埋もれさせるな」という表題で、アフリカ人の指導者たちは次のように言っています。
「トランスヴァール州には、人類学上大切な王権を象徴する儀式用の遺物がたくさんあります。しかも、世界で最初に発見され、ダーウィンの正しさを裏付けた「欠けた環」(系統的に類人猿と人間の中間を繁ぐと考えられる仮想の動物)であるトーン頭骨のような宝物は南アフリカでは今まで一般に公開されることはありませんでした。そのトーン頭骨はニューヨークで大評判になりました」
このこと一つを取ってみても、自分達の誤った考えや他の人たちに抱いている恐怖を永遠のものにするために、白人達がどの程度のことまでやれるのかがはっきりと分かります。意図的に一民族を精神的に衰退させようとするいわゆるバンツー教育のような仕組みを制度化しようなどという考えを思い付くのは、野蛮人か歪んだ心の持ち主だけです。
いわゆるバンツー教育に抗議して若い詩人たちが国じゅうから集まって来ました。その詩人たちはドラムをたたき、亡命中の指導者や作家の詩をうたい、白分たち自身の詩をつくりました。普通の環境の中では書くのは殆んど不可能ですから、自分たちの衰え知らぬ抵抗を口承文学の詩に託してうたったのです。詩人たちは斃れた英雄たちの棺を墓所に運んで行きながら詩をつくりました。
南アフリカの解放運動のなかで、侵略時の宣教師の役割を忘れてはなりません。ヨーロッパ諸国から宣教師達がアフリカの大陸に渡来してきました。着いたとき、その人達は顔には聖職者の笑みを浮かべ、手には聖書(神の御言葉)を携えていました。行く先々で、本当の動機が侵略であることが明らかになりました。宣教師達は軍隊と土地掠奪者達のために道を拓きました。ヨーロッパの自分達の国の旗を立てました。そして元からそこに住んでいた人たちは土地を失ないました。
現在、南フリカでは熱心に解放の神学を説いている新しい世代の聖職者たちがいます。その聖職者たちは現存する秩序体系に異議を唱え、聖書を使って政治的な偽りを行なうという不信の行為を暴き出すところまでいっています。例えば、カイロス・ドキュメントには、以下のように述べられています。「民衆を抑圧する際に、国は再三再四、神の名前を利用している。軍専従の牧師達は南アフリカ国防軍を鼓舞するのに神の名を使い、警察付きの牧師達は宣伝活動の講演のなかで、警察官や閣僚を励ますために神の名を使う。しかし、なかでもその本性が最も如実に表われているのは、神の神聖な名前が冒涜的に使われている新アパルトヘイト憲法の前文である。
前文
『国々の命運や臣民の歴史を司り給う神、多くの地から我らの祖先を集め、この我らの土地を与え、世代から世代へと導き給うた神、我らの祖先を取り巻く危険から奇跡的に救い給うた全能なる神の御心に従って。』
ここには明らかに、侵入者の側に立ち、正当な持ち主から現実に土地を取り上げ、自分達を『選ばれた民』と考えるものにその土地を与える神が存在します。
今日のアフリカの神学者たちは「今直面している危機感によってこの神学に、その傲慢さに、そしてその含意や実用性に疑いを持たざるを得ないのです」と言っています。
南アフリカでは、あらゆる独裁政権下でもそうであるように、文学や知識に近付けさせまいとする政策と政治的な抑圧はいつも表裏一体で行なわれてきました。非常事態宣言、ジャーナリストや教師、生徒の拘禁、書物の発禁処分、マスコミの厳重な取り締まり、これらすべては、ものを自由に考えたり、いろいろな考えが広まるのを押さえる仕組みのかなめなのです。
私たちは自らの心を解き放つために本を読むのです。
私は小説を書くことで助けられ、アフリカの女性として存在しなければならない、残忍で惨憺たる状況から、感情的に、そして心理的に逃れることが出来ました。私は一所懸命に自らの運命を切り開き、問題を解決したいと願う登場人物を創作しました。そして実際、私はその人たちと一緒に生きてきました。そうすることによって、すべてを諦め従順で、そのうちのたいていはとっくにタオルを投げ込んでしまった、やたら腹立たしくてしゃくに障る親威の者たちと、私が辛うじて我慢してやっていけるということに気が付いたのです。時にはその者たちに他の人たちの闘いについての本を読んでやりました。そのことで、何世紀にもわたる抑圧から生まれた、次第に従うことに慣れさせられてしまうという麻痺感覚から、私自身解放されたのです。
執筆年
1990年
収録・公開
「ゴンドワナ」15号9-29ペイジ
ダウンロード
「ミリアム・トラーディさんの宮崎講演」(講演記録)(作成中)