つれづれに:読む(2024年4月18日)
つれづれに:読む

薊(あざみ)がだいぶ咲き始めた
英語の話の続きである。たくさん喋(しゃべ)って、聞いているとき、今まで読んで馴染(なじ)んだことが意外と役立った。喋ったり聞いたりすることに慣れてくると、これまで読んだ蓄積みたいなものが互いに繋(つな)がって、感覚的になるほどなあと感心する場面が増えてくる。書き言葉と話し言葉の語彙(い)は違うが、両者が有機的に繋がってくると喋られている含意や、書かれたものの背後に潜む意味みたいなものがじわーっと感じられるようになる気がする。

イリスが枯れだした
敗戦直後に生まれたこともあったし、何よりあまり恵まれた環境ではなかったので、生きること自体がきつかったせいもあるが、戦争相手のアメリカ人が使う英語に反発を感じたし、住んでいた地域社会にもいつも疎外感を感じていた。だから、受験に馴染めなかったとはいえ、→「夜間課程」を選ぶしかなかったとき、英米学科に入るとは考えても見なかった。しかし、英米学科には語学・文学コースと法経商コースがあって、ま、文学もやれるか、という都合のいい解釈をして願書を出した。日本文学の夜間は大阪市大しかなく、地理的に家から通える範囲を越えていた。
だからという訳ではないが、大学では単位を取れる範囲を越えて英語はしなかった。当然だが、学割を使えるんならと受けた大学院(→「大学院入試」)で26人中飛び抜けて一番だったそうである。採点した人も呆(あき)れたと思う。それでも英語をしようと思わなかったが、母親の借金で定職に就くために教員採用試験を受けて、英語をすることになったのである。

キャンパス全景(同窓会HPから)
しかし、今から思うと、敗戦でアメリカ化を強要されたために英語関連の就職口は多かった。一つの言葉なのに、中高でも英語の時間数は多くて必修だったから、それだけ教員も必要だったわけだ。他の教科なら、1年では間に合わなかったかも知れない。→「運動クラブ」の先輩で神戸の一番手の高校からスペイン学科を出た人が、卒業後に他の大学で補足単位を取って採用試験を受けたが受からなかった。社会の枠が少なかったのが大きかったようである。その点、英語の募集人員は多かった。
一年目に受けるだけ受けてみて、→「購読」と→「英作文」(→「英作文2」)で行けると感じ、準備を始めた。要は読んで書ければよかったわけである。そのために読んだ。購読は好きなアメリカ文学の人の研究室で本の名前を聞き、図書館で借りて読んだ。英作文も言語学の専門家の研究室で本をあげてもらい、→「古本屋」で手に入れて読んで、書いた。
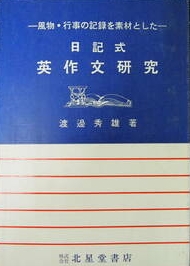 紹介してもらった英作文の本の1冊
紹介してもらった英作文の本の1冊
最初に読んだ本は1026ページあり、辞書を使って3ケ月ほどかかった。これでは間に合わないと意識を変え、辞書を引かずに一気に読んだ。分厚い本も、余りわからないまま取り敢えず読み通した。1ほどしかなかったが、わかる言葉を手掛かりに時間をかけずに想像して読むようになっていた。いわゆる文脈を読むというやつである。聞くことも話すこともそうだが完璧にはいかない。何割かの知った言葉や雰囲気や文脈をてがかりに、理解するのである。
結果的に、1026ページを辞書を使って3ケ月で読んだ時より、短時間で理解の深さも増すように思えた。たくさん読めば語彙も増えるが、それよりも短い時間にいかに内容を把握して理解するかを身体(からだ)で覚えるのだろう。同じ1時間が前とは違うわけである。このときのやり方が、雑誌の記事や学術論文を書く時に役に立った。あるまとまりを仕上げるには、書くためのばねのようなものが要る。何冊か関連の本を並べて、短期間に一気に読めばそのばねのようなものが湧いてくる。あとは、必要な部分は、時いんは辞書やウェブを使って丁寧に調べて補足する、そんな風に書くようになった。
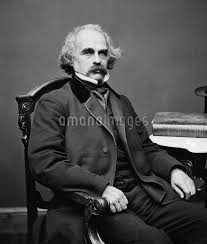
セオドア・ドライサー(『アメリカの悲劇』、1925)