つれづれに:アメリカ文学(2026年2月7日)
つれづれに:アメリカ文学

アメリカ関連の続きである。南北戦争からトランプまでの政治と経済の両面から→「南北戦争のあと:政治篇」、→「経済篇1」、→「経済篇2」、→「ソウル」、→「トランプ2」、→「トランプ3」を書いた。実は偶然にもその時代に書かれたアメリカ文学の作品をいくつか読んでいたことを思い出した。その作品は、ある意味その時代を映し出している。小説はフィクションの形を取るが、大抵は事実に基づいて脚色されているので、その時代を色濃く投影している。最近は小説を書く時間が多くなっているので、その思いは強くなっている。

アメリカ文学に興味があったわけではない。それどころか、早くに世の中をすっかり諦め(→「諦観」)、斜交いにものを眺めながら「生きるには余生は長すぎる」とぼんやりと考えていた。ただ、大学には行きたかったが、どうも入試勉強が性に合わなかったみたいである。大学で勉強や学問をしたいと思ったわけではなく、小説でも読みながら大学の空間があればいいと思っていただけだった。今から思えば、周りの人のように恋愛もして希望に燃えて入試勉強も出来ればよかったのだが。姉は早くからよく誘われてデートをしていたようだが、僕には別世界の人間だった。たぶん家族にも地域社会にも学校にもいつも腹を立ててばかりで、自ら心を閉ざしていたのだと思う。
しかし、もっても30くらいまでだろうと余生を過ごしていられなくなった。母親から→「百万円」借りて来て、と言われて状況は一変した。5人から借りて、母親をせっついて何とか返したのだが、人に金を借りてまで生きてはいけないと思ってしまった。それまで考えたこともなかったが、借金をしなくても済むように定収入を確保しようと思い、高校の→「教員採用試験」を受けてみることにした。ただ、そう思いついたのが試験も近い時期で、一度受けて対策を考えるかと、実際に試験を受けたのである。卒業するかどうかは決めかねていたが、英会話を残して4年の最終学年にはなっていたので受験がかのうだった。1年浪人をして入学し2年間留年していたから、25歳の時である。(→「採用試験」、→「面接」)
大学は→「夜間課程」の英米学科だったが、英語はしなかった。受験でも英語はしていなかったので、予想通り取り敢えず受けてみただけの結果だった。学割のためだけに→「大学院入試」も受けていたので、購読と英作文をしとけば大丈夫だろうという感触だけは得ていた。すぐに準備を始めた。購読と英作文について具体的な方策を聞くために、2人の研究室に出かけた。英作文と購読の授業を受けた2人である。→「英作文」の人はアメリカ文学が専攻で、坪田譲治の童話の文庫本がテキストだった。購読の人は英語学が専攻で、淡々としていた。後に教職大学院(→「大学院入試2」、→「分かれ目」)の推薦書を、淡々と書いてくれた。

事務局・(2人の研究室があった)研究棟(同窓会HPより)
英作文の人が「本でも読んでみますか?」と言って、紙切れに著者名とタイトルを書いてくれた。先ずは読んで力をつけることですね、という意味だと理解した。それがアメリカ文学の代表作だった。(→「購読」)
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter
Theodore Dreiser, Sister Carrie, An American Tragedy
William Faulkner, Sanctuary, Light in August
Richard Wright, Native Son
John Steinbeck, Grapes of Wrath
その時読んだ分厚い本が、今書いているアメリカを映し出している作品だとは、まさか思わなかった。
先ずは『アメリカの悲劇』からで、著者はセオドア・ドライサーである。。
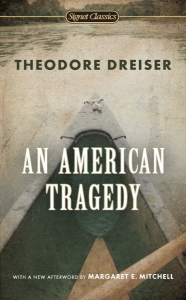
Theodore Dreiser, An American Tragedy