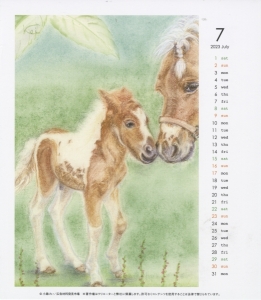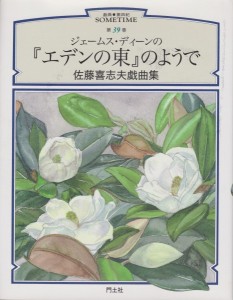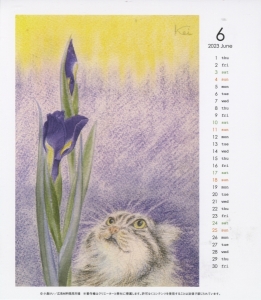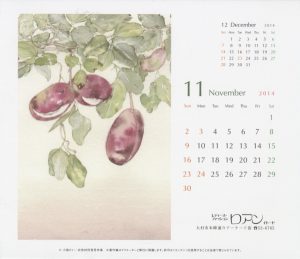つれづれに:自転車で

堀切峠道の駅展望台から、下に海岸道路が見える
畑に出る時間が少し増えたからか、旧暦の言葉が身近になる。一年で夜と昼の長さが同じになる夏至(げし)を過ぎてから15日目、昨日は小暑(しょうしょ)の始まりだった。24節気の第12節、夏の節気の5番目である。
第12節の大暑(たいしょ、7月23日~8月7日)が終わるまでは一番暑い時期、小暑は「大暑来れる前なればなり(たいしょこれるまえなればなり)」らしい。アゲハチョウや鰻(うなぎ)に七夕の季節である。今日は白浜だったが、自転車をこぎながら、浜にアキアカネが飛び交うのが見えた。そろそろ梅雨も明ける。

生体組織検査で運動のできない時もあったので、充分に運動が足りているとは言えないが、だいぶ戻ってきている。週に一度はマッサージで手入れしてもらうために白浜に自転車で往復し、たまに宮崎の街まで行くこともある。足を延ばす平和台の餃子屋さん(↓)が目下の北限である。白浜までは片道1時間弱、街までは1時間ほど。清武の歯医者かハンズマンまでは片道半時間余りである。

この前は、久しぶりに2週続けて、白浜帰りに内海の南風茶屋(→「堀切峠下海岸道路④」、2021年11月7日))に行った。そこまで行っても1時間余り。今はその辺りが南限である。南風茶屋では久しぶりに南風饂飩(うどん)と何皿かのおかずが美味しかった。富土(ふと)漁港で獲れたての刺身が食べられないのが申し訳なかった。
「さしみは食べられないんです。すいません」
すぐに、揚げたての白身魚を持って来てくれた。「魚も肉も食べないので‥‥」とも言えず。揚げたては臭みもなく、食べられる。普段は食べない小さめのチキン南蛮も食べている。違う要素が体に入り、びっくりしているかも知れない。

営業時間をウェブで調べたとき、熊本出身の有名な歌手がお馴染みの南風茶屋の店先を背景に撮った写真をインスタグラムか何かに載せていた。「歌手がきたそうで。どうでした?」と聞いたら「大変でしたよ。宮崎市民ホールであったコンサートで紹介したようで。座った席で写真を撮ったり。冷や汁用に胡瓜をすってすって。多すぎるお客さんも、ね。バイパスが出来、南からはその道で医大病院に行く人が増えて、お客さんが三分の一くらいになりました」と店のおかみさんが嘆いていた。客足の戻る術はないものか?

店内から内海港付近を望む
行き帰りは、海岸道路を利用したが出口のところでは雑草が生い茂り、大きな石ころが散乱していた。通るのは難しい。途中で大きくはみ出した雑草で通りに難かった場所が何個所かあった。水捌(は)けがうまく行かずに、2箇所で水が溜まっていた。フェニッスク道の駅に上がる階段は、草が生い茂り、階段も崩れて通行できなままだった。道路は国交省の管轄らしいが、道の駅は宮交あたりか?どちらも、保全のための予算は計上していないようだ。

南風茶屋正面
筋肉や体の回復力も落ちているが、電動でゆっくりなら、まだあちこち何とか行けるようである。マッサージをしている時に、自転車も長距離なら鼠径部の血流が悪くなるかも知れませんねと助言してもらった。以来、立ってこいでいる。時たま座ることもあるが、血流のことを考えて、片方の尻に体重をかけている。自転車に乗るのも大変だ。そのうち、難しくなるかも知れないが、今しばらくは大丈夫のようである。

海岸道路から見える日向灘は格別である