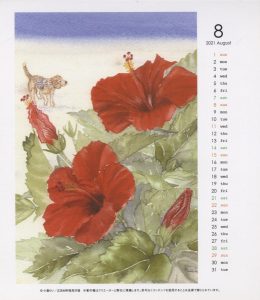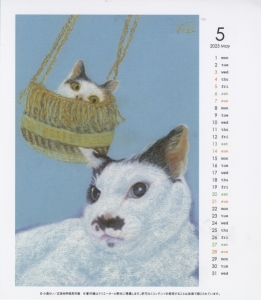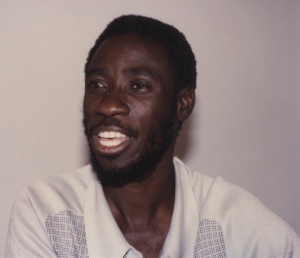つれづれに:暑い最中に
すっかり諦めて生きても30くらいまでだろうと考える身には、余生は永過ぎた。小さい頃から食べるのも自分で何とかしないといけない毎日が続くと、食べること自体も億劫になる。体にいいものをという選択肢は元より持てなかった。考えたこともない。食べるだけで精一杯だったからである。きちんと大学に通い、卒業して就職すると考えたこともなかった。もちろん、結婚も考えたことがなかった。

当時は木造2階建てだった中学校(同窓生のface bookから)の1年生の母親に頼まれた
受験勉強は出来なかったが、大学に行かないという選択肢はなかった。大学の学費が月1000円だったから通えたのだが、生きていると何が起こるかわからないものである。受験に馴染(なじ)めず行き先も選べなかった私が→「家庭教師」を頼まれた(↑)のだから。前期も後期も地方の国立大を受けたのは、無意識に家を出るつもりだったんだろう。しかし、どの教科もしないで受けても、通るはずもなかった。間違って英語でもしていれば、話は変わったかも知れない。結局、それでも→「夜間課程」なら入れる所(↓)があった。

キャンパス全景(大学HPから)
家庭教師を頼まれて少し経済的に余裕が出たのは確かである。毎日朝早く決まった時間に起きる必要がある→「牛乳配達」に比べれば、楽なものである。何より、時間的に融通が利く。大学では時間だけはあるのだから、その意味ではだいぶ気が楽になったのかも知れない。讀賣新聞の夕刊に連載されていた立原正秋の『冬の旅』を読んでから→「古本屋」で手当たり次第に本を買って読み始めた。自分の中に書きたい衝動があるのを意識するようになった。

よく通った古本屋のあった神戸元町の高架下
突然出かけるようにもなった。意識にはのぼらないが、芯辺りに熱がこもって、その衝動を抑えられない感じだった。諦めが強くなって、それまでの常識の殻が破れて行くにつれて、その衝動を抑えきれなくなって行ったのかも知れない。→「暑中」に風も通らないトタン屋根の6畳にいると、なぜか一番暑い8月の初旬に遠くまで自転車で行きたくなった。計画もなく、取り敢えず中国山脈の真ん中辺りにある→「生野峠」(↓)を自転車で越えることにした。瀬戸内海側に住んでいたので、本州を南北に縦断して、日本海側に行ったわけである。

夏の暑い最中に、自転車で生野峠を越えた。それだけのことだった。ずいぶんと前のことなので、詳細は覚えていないが、足の裏全体で踏ん張れるように桐下駄を履いて、自転車から一度も降りずに生野峠を越えた、鳥取砂丘で寝袋の中で寝たとき、一晩中一匹の蚊に悩まされた、山陰側の海岸沿いの坂道はきつかったが、そこでも降りずに大声を出しながらペダルを踏んだ。印象に残っているのは、それくらいである。
もうすぐすると、何十年か前のその時と同じ季節になる。あの暑い最中に、よく熱中症にやられなかったものである。
香住海岸