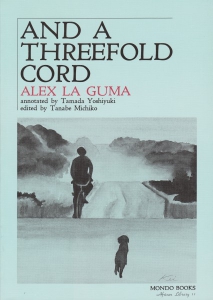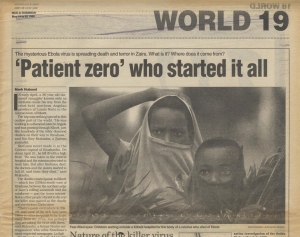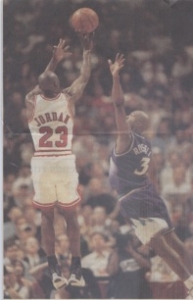つれづれに:ニュースを聞く

赴任した当時の宮崎医科大学(大学HPから)
独り言や面接で英語が勝手に口から出て来るようになったあと、次は聞く、だった。相手の言っている内容を正確に聞き取れないと理解出来ないからである。会話も続かないし、意志の疎通も図れない。聞けるようになるには、聞くしかない。英語も言葉の一つだから、当たり前と言えばごく当たり前のことである、やってみて実感しただけの話である。
聞いて理解できるようになるために、英語の授業で映像や音声をたくさん使っていたので、それを利用した。バスケットボールをやったときもそうだったが、シュートやドリブルなどの各部分の力を集中して高める分習法と言ったところか?ちょうど衛星放送が使えるようになったので、先ずはBBC(British Broadcasting Corporation)、ABC(American Broadcasting Companies)、CNN(Cable News Network)、NHKBS1などのニュースを録画して、繰り返し聞いた。特にマンデラの釈放時前後の英語放送は全部予約録画した。1995年の淡路阪神大震災の時も可能な限り録画して聞いた。
ニュースを聞いてわかったことがいくつかある。一つは意外と簡単だったことである。考えれば、キャスターが予め用意された原稿を読む場合が多いので、スピードも速くないし、いわゆるわかり易い標準的な喋(しゃべ)り方なので慣れればそう難しくないわけだ。俗語や聞いたことのないような言葉もそうは出て来ない。中に挿入されるインタビューが早かったりするが、流れで慣れれば大体わかる。
NHKBS1のニュースはわかり易かった。取り上げる題材が国内のことが中心なので、内容が大体わかっている場合が多い。それに、キャスターのレベルがたかい。シンショウカルナというキャスターがCNNのメインキャスターだったという話も聞いた。概してできる女性の集団で、微笑みながら軽快にニュースを読んでいるという感じだった。女性の声の質や音の高さの方が耳に心地よい気がする。一度、ネクタイを締め髪を七三に分けた男性のキャスターが登場したが、その違いをはっきりさせるために登場させたんやない?と思えるほどだった。緊張気味で頬(ほほ)の筋肉が固まっていたせいか、音がくぐもって聞きづらかった。おそらく真面目で優秀な人だったと思うので、かえって気の毒な感じがした。2ケ月ほどで交代した。

1995年エボラ出血熱を報じるCNN
1995年の震災後、各国は地震をどう伝えたか?という特集があった。英語ニュースでは、アメリカやイギリス以外に、香港やフィリピンのニュースがおもしろかった。香港はイギリス英語ぽかったし、フィリピンはたぶんタガログ訛(なま)り?という感じだった。その頃、バングラデシュの人がよく研究室に来ていて舌を巻くベンガリーズイングリッシュに慣れていたし、ジンバブエではショナイングリッシュの洗礼を受けていたので、そう苦にはならなかった。

赴任したすぐあと、4年生がひとり部屋に来た。英語をするにはどうしたらいいでしょうか?と聞かれたので、いやー、英語が苦手でどうしたらいんでしょうねえ?と答えた。最初の年は2年生と1年生しか持たなかったので面識はなかった。今度来た新しい人どんな人やろと覗(のぞ)きにきたのか、いまだにその真意はわからない。その後何回か部屋に来て、次の年の講演会を手伝ってもらったり、家に来たりもしたが、そのあと医者になってからは会っていない。
だいぶ英語が使えるようになった頃、授業で顔を合わせていた1年生が部屋に来て同じような質問をした。その時は、最初にニュースを聞いてみたら?とテープをたくさん渡した。陸上をやっている背の高い真面目な学生で、トラックの上やキャンパスでヘッドフォーンをつけた姿を時々みかけた。1年ほどあとに部屋にきて言ったのが印象的だった。
「大体わかるようになりました。株価まで聞き取れます」
卒業後、精神科でバイトしながら基礎系の研究室で博士号を取った。そのあと大学内で何度か通りすがりに会った。研究室に残るような話をしていたが、今はどうしているんやろ?

宮崎医大講義棟、3階右手厚生福利棟に研究室があった


 折生迫の県水産試験場のさくら
折生迫の県水産試験場のさくら