寝不足が続いてて、夕方から寝てたんで遅くなりました。今年で70、体調を崩さないようにするだけで、一杯いっぱいです。
<今回は>
1回目でした。楽しくやれそうか?
最初に、用語の合同授業の日程の確認です。
11版のがなくて8版の表紙の画像です
**********
5月8日(水)4コマ目、後半のクラスと合同:1、2章(6月5日(水)は休講)
5月15日4コマ目、後半のクラスと合同:3、4章(7月24日(水)は休講)
やってみて、希望者が多ければ、5章、15章もやってもいいと思っています。特に後期の骨の試験のことを考えれば、前期に15章を一度インプットしとくとええんやないかと思うけど。5章の消化器系も一番よう出てくるし。みんなで決めてや。みんな次第やな。
**********
課題についての例で挙げてる「アフリカの蹄」の編集版の半分くらいを観てもらうつもりやったけど、結局歌を聴いてもらうだけしか時間が残らんかったね。
ブログは実際にみてもらえました。このあと、参考ファイル(ファイル置き場)に授業で見てもらった1章、2章のフォールダーを置いときますので、各自ダウンロードして使ってや。それなりに作るのに時間と手間がかかってるので、役に立つなら嬉しい限りです。気持ちがないと、あんな大変な作業、出来ひんもんなあ。
連絡網、一色泉くんが引き受けてくれました。よろしくね。ブログで済めばそれに越したことはないけど、何かのときに頼むかもしれないんで、そのときはどうかよろしく。
ごちゃごちゃしゃべったけど、3つほど伝えたかんたんやと思います。
①入学は最終目標やないんで、モードを変えんとあかん、そのための機会になれば嬉しいです。金持ちの都合のいいように作られた社会、その中で、自分について、将来について考える時間もそう多くなかった人も多いやろから、出来るだけ、意識下に働きかけて、今までの価値観や史観を見直すきっかけになればと思います。なんで英語の時間にアフリカやねん、という反応が多いけど、英語は教養の枠組みやし、意図的に避けられて来た分野の話は、値観や史観を見直すきっかけにはいい材料なんで。
②英語も言葉の一つで、言葉が使わんと、使えんと意味がないんで、英語をする、やなくて、英語で何かをする、に切り替えんとあかんと思う。出来るだけ、実際に使われているものを使い、インプットしたものを実際にアウトプットしながら、道具として使えるようにする、それが大事やと思います。
③原爆を使われて無条件降伏してアメリカを押しつけられた一環でヨーロッパ医学がアメリカ医学に代わった限り、英語が元で、医者にとっては医学用語は必須、やっておくに越したことはないと思います。特に「折角医学部に入ってきたのに、医学のことひとつもせえへん」と文句をいうまえに、インプットするのに時間を割く方が賢明やろな。教養をばかにしてやらん人は「専門になっても勉強してませんよ。」(今年卒業したよう勉強してた人が言ってたな)インプットせんと始まらんけど、インプットしながら、実際に使えるようにもせんと。ま、次の段階やとは思うけど。
Soweto Gospel ChoirのAmazing Graceはどうやった?服部くんが「とりあえず見てくれ、聞いてくれ」というだけはあるやろ。南アフリカのプリントの一枚目の「南アフリカの最近の音楽とDVD、CDについてのコメント」は服部くんに書いてもらった分です。
配ったプリント:
*僕の自己紹介
*(みんなの)自己紹介の用紙→次回出してや。
*2019年度前期~(授業、課題と評価、課題、エセイ、課題図書、トーイックについて)
*申し込み用紙
*The Struggle for South Africa
*南アフリカの最近の音楽と~(DVDとCD、闘いが生んだ美しい歌、コシシケレリアフリカ楽譜、遠い夜明け、ユッスー・ウッヅ・ワシントン、遠い夜明け続き、映画優待券、A chronology of South Africa、南アフリカについての用語解説)
*用語(Pronunciation of Terms①~④)
*専門分野の名称
*用語抜粋(The gastrointestinal tract, Pathway of food through the gastrointestinal tract, Bones of the thorax, palvis, and extremities)
<次回は>
何人かのコメント、課題の説明、次々回に発表する人を決める、南アフリカの歴史背景を英語で少々(今日配った南アフリカに関するプリントの最後の一枚にある A Chronology of South Africaと南アフリカについての用語解説をみておく方がわかりやすいと思います)、それから「アフリカの蹄」を時間の許す限り観る、やろかな。
では、来週また。
今はきんぽうげがあちらこちらに。そろそろ薊もあざやかになる頃やねえ。見上げると山藤。都会から来た人には、色あざやかやに映るやろなあ。木花キャンパスから望める加江田渓谷の借景も、すてきやもんなあ。木花の研究室からも見えるで。下に学生が通ってて、木花渓谷が見渡せる、窓から見える景色も、ええなあ。



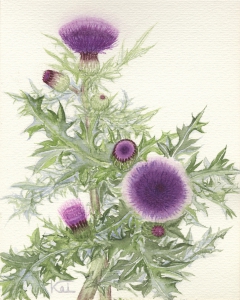


 絹莢
絹莢