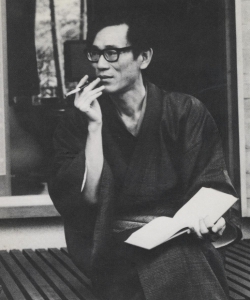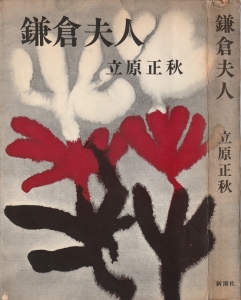つれづれに:春の嵐

木花神社の展望所から、田植えはほぼ終了
おとといの夜半過ぎから風がざわつき始めた。そして昨日は朝から風が強く、一日中風はやまなかった。
「前線上の低気圧が急速に発達しながら本州の南岸を東へ進むために暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり」、全国的に春の嵐になった。ガレージに立てかけていたアルミの梯(はしご)が倒れていた。人がいなくてよかった。自転車に被(かぶ)せていたナイロン袋などがあちらこちらに散らばっていた。畑でも、ナイロン袋などが飛び散り、大根の花が一部倒れていた。春の嵐といっても相当な荒れようである。

金曜日に白浜に行ったとき、田植えの光景が目に入ってきた。先々週くらいに田起こしをしている風景を見たと思ったら、もう田植えの季節である。下の県道から田圃(たんぼ)道にはいる定位置で写真を撮った。(↑)専業農家が減っているそうだから、今度の土日くらいにはすべての田植えが終わるだろう。台風が来る前に刈り入れをする超早場米である。

それでも二日ほどぐずついた天気で鬱陶(うっとう)しかったので、晴れると一気に気持ちも晴れる。ただ、風が強いと中国から汚染物質が含まれる空気も流れてくるので、毛布が干せないのが何とももどかしい。1960年代、70年代は日本も同じことをやっていたのだから、何とも言えない。

散歩の途中に木花神社に寄ったら、若い人が何人かで竹を切ったり、神社横の広場(↓)や99段の階段の手摺(すり、↓)などに提灯(ちょうちん)をかけていた。30日(土)にさくらまつりをするらしい。おそらく、若い人は地元の青年団の人たちで、上の公園で夏祭りを開催したりしている。

神社は無人だが、仮社務所が丘の下の家にあって、宮司の人もいるようである。下支えをする小さな組織もあって、公園の花植えをしたり近くの畑で野菜を作っている顔見知りの人も役員の一人のようである。新年などの節目には小さな行事をしている。夜中から明け方にやっているので、見たことはない。秋には木花神社と書かれた大きな幟(のぼり)が立つこともあるが、ここしばらくは見かけていない。

散歩の途中にどくだみを見かけて、2週間ほど前から摘んで帰って風呂に浮かべている。ほんのり漂うかおりもそうだが、なぜか贅沢(ぜいたく)な気分になる。去年は皮膚にいいというドクダミ液を作るのに大量のどくだみの葉っぱを集めたが、今年は風呂に浮かべる分だけでいい。毎日摘めるといいが‥‥。歩けるというのは調子がいいということだから、そんな毎日が続けばと願っている。

どくだみの葉