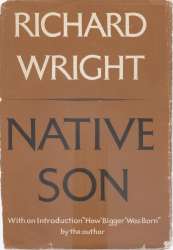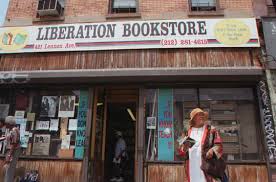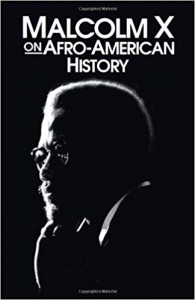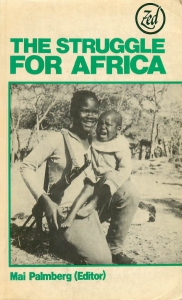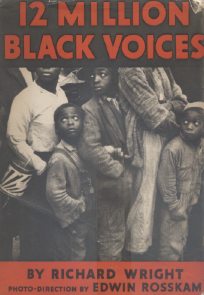HP→「ノアと三太」にも載せてあります。
つれづれに:米麹

「中朝霧丘」(6月17日)の家に転がり込んでから暫くは時間が取れないままだったが、大学院に通うようになってからは(→「キャンパスライフ2」、6月15日)、買い物や子供との時間もずいぶんと増えた。買い物はまだ小売店が存続できる時代だったので近くの店屋で済ませることもあったが、大抵は明石駅の南側にある魚の棚に出かけた。行く途中にもその近辺にも結構立ち寄れる店屋があって、大体はそれでこと足りた。明石駅デパートにも店屋が入っていて、持ち帰りの出来る何個所かは定期的に利用した。自転車なら行動範囲も広がるので、あちこちに寄りながら買い物が出来るのは有難かった。魚の棚(↓)は京都の錦市場ほど大規模ではないが、魚や海産物の他にも野菜の店屋もある。店は東西の通路沿いの両脇に並んでいて、夕方などは買い物客も多い。年末はお正月用の鯛などが目当ての客が大勢押し寄せて盛況だ。この2年間はコロナの影響もあったはずだが、大丈夫だったのか心配である。突き当りの出口を南に折れれば、明石港の方角で、港へ行く途中にも店屋がある。

ある日、その通りの右側にある麹屋(最初の写真)の店先に真っ白な麹が並べられているのが目に入ってきた。洗濯板くらいの長さの板枠で出来た専用のケース(↓)に米麹が均等に引き延ばされて、そのケースが立てかけられていたのである。陽に干して、乾燥させていたようである。あまりの白さに誘われて店に入ってみた。聞いてみると、江戸創業で赤松藩の時代から代々続いている麹屋だった。

その日は、味噌を買って帰った。その味噌が絶妙な味だった。それ以来、その店の味噌がかかせなくなった。よく行くので、店屋の同年代のご夫妻とも懇意にしてもらい、たまに甘酒もご馳走になった。室町あたりから続く味だと思うと、感慨深かった。京都では先の大戦と言ったら応仁の乱どっせ、とは聞いたことがあるが、身近に室町、江戸創業の店屋があるとは知らなかった。大発見である。今は娘さん夫婦が店を切り盛りしているようで、注文するときに電話で元気な声を聞く。明石より宮崎の方が長くなってしまったが、その間味噌はずっと取り寄せて、切らせたことがない。娘も愛用してる。先日は味噌を切らせて、初めて味噌の味がわかったと電話で言っていた。体調を崩しそうになった時、生活習慣を見直す必要性を思い知って、食生活も見直した。肉も野菜も苦手な私には、発酵食品の味噌や豆腐や納豆は命綱、味噌汁が毎食飲めるのも、この味噌のお陰である。

近くなら米麹も買いに行くのだが、甘酒は毎食欠かせないので、地元産の米麹(↓)を使っている。
次は、あのう……、か。先輩に頼むしかない教歴の問題である。