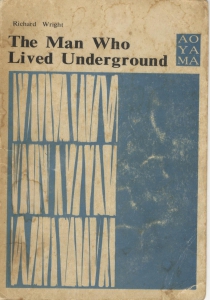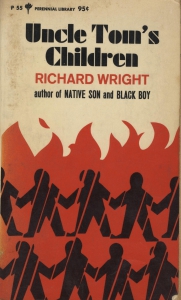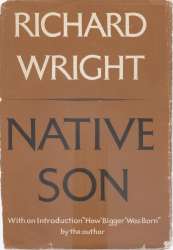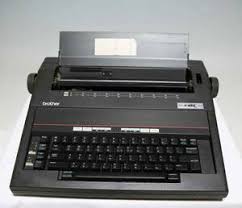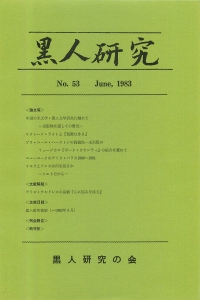HP→「ノアと三太」にも載せてあります。
つれづれに:修了と退職

一昨日から小暑(しょうしょ)、梅雨が明け、暑さが本格的になる頃で、今年は7月7日から、23日の大暑までの期間らしい。アゲハチョウや鰻に七夕の季節である。昨日は久しぶりにいつものコースを歩いて来た。歩くのが基本やなあと思いながら気持ちよく歩けた。その途中の「急傾斜崩壊危険個所↑」(→「 歩くコース1の④」、2021年7月11日)の近くでアゲハチョウを三匹別々に見かけた。陽射しが強かったが、先週、木崎浜の帰りにアキアカネがたくさん飛んでいるのを見かけた。季節は確実に移り変わっていて、すぐに秋が来そうである。台風4号で少し生活のリズムがおかしくなったが、大した影響もなく済んでくれたので、ほんとうに助かった。

修士論文は提出が締め切り日ぎりぎりになってしまったが、受け付けはしてもらえたので、当初の目的は果たしたわけである。あとは、高校(↓)に行き、校長に退職を願い出て認めてもらうだけだった。早めに校長室を訪ねた。教職大学院に行く前の5年間、いろいろと好き勝手を許してくれた校長の鉄ちゃんが、入学の前の年に退職でいなくなっていたので、初対面の校長だった。

鉄ちゃんはいなかったが、守ってくれた元担任の教務主任は健在で、気持ちの上では心強かった。「管理職」そのままの校長の顔を見たとたん、あちゃーと思ったが、話を聞いて「大学で頑張って下さい」とすんなりと認めてくれた。再養成の期間が終われば、元の学校に戻るのが前提で、県の教育委員会が推薦し、県から給与も出ているいるわけだが、当時は教員採用試験の倍率もそこそこあったし、辞める教員がほとんどいなかったので、比較的スムーズに辞めることが出来たんだと思う。次の職場の予定の目途も立たないのに、辞める人もいなかったらしい。とにかく、大学の職を探すための最低条件の修士号の取得と高校の退職は、無事クリア出来そうである。
嫌なことは可能な限り避けるという範疇に式の類も入っていたので、県からの派遣で勤務日にあった式にも出なかったが、修了式(↓)と英語分野の懇親会にも出てしまった。ゼミの担当者に博士課程の推薦書を依頼する必要もあったし、ゼミ生が二人なので、避けようがなかったという事情もある。それに、英語分野の人といっしょにいても嫌な思いをしないで済んでいたので、自然に、顔出ししとくかという気持ちになった。

3人を家に招待してお昼を食べたこともあるし、修了してしばらくは音信があった人もいたし、公立中学で英語で授業をしていた52歳の「同級生」には、後日、東京の自宅まで訪ねて英語訳の相談に乗ってもらったりもした。予想通り、よく出来る人だった。日曜日に押し掛けて、長時間付き合ってもらった。休日までお父さん大変そう、大丈夫かなという感じでお茶を運んで来てくれた娘さんの表情を見て、申し訳ない気持ちで一杯になった。自分の書いたものを英訳して、ファーブルさんに見て欲しかったとは言え、それほど切羽詰まっていたからだと思う。人に助けてもらってばかりの、恥ずかしいことだらけの人生である。
次は、大学院入試3、か。