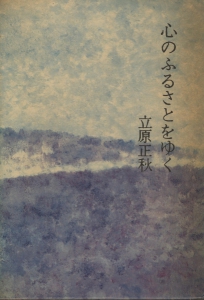百万円
ある日、「百万円、すぐに借りて来て」と母親から言われた。
事態が呑み込めなかった。百万円の意味もわからなかった。すべてを諦め、生きて30くらいまでやろと考えて生き永らえていたのだから、わかる筈もない。

近くの川の河川敷
なぜか、金を借りに行った。行った先は、留年で違う学年になった元クラスメイトと元プレイメイト、入学後に出会った人たちである。一人から借りるには額が多すぎると考えて、5人から借りた。4人は神戸近辺に住んでいたが、一人は篠山産業高校の教員をしていたので丹波の下宿まで出かけた。ちょうど時期がよかったんだと思う。私が2年間留年している間に卒業してすでに定期収入があり、まだ結婚前で、一人20万の額も何とか融通出来る範囲内だったんだろう。
しかし、借りたあと、これはあかんやろと思い直した。諦めて生きる意志に欠けているとはいえ、毎日面倒臭いと思いながらも息をして、腹が減ると食事もしていた。授業料が月に1000円(→「夜間課程」、3月28日)、牛乳配達(→「牛乳配達」、3月30日)が5000円、家庭教師(→「家庭教師1」、4月10日)が3000円か5000円、百万円はどうしてもそんな生活と結びつかなかった。そんな生活の中でどう返して行くのか。すべてが生きている普段の枠を越えていた。

六甲山系を背にした講義棟(同窓会HPから)
取り敢えず、返そう。手形の決済がどうのこうのと切羽詰まった弁解をしていたが、その百万円で一息はつけたようでだった。今しかないと覚悟を決めて、何度も何度も催促をした。無理をしたようだが、何とか5人に返すことは出来た。よくもすんなりと貸してくれたものだ。しかし、借りてすぐに返した、という話ではない。行くところがなくて入ったとは言え、5年ほど接する中で返すあてもないのを承知で、貸してもいいかと思ってくれたのは、5人の好意である。それを考えると、これから合わす顔がない気がした。事実、それ以降、5人とは会っていない。続くかもしれない絆を断ち切ってしまったのである。
30くらいまでしか生きないにしても、金を借りてまで生きてはいけない。そのためには、定期収入が要る。スーツを着て面接という就職活動は難しそうだが、教員採用試験なら可能性はある。なぜか教職課程を取り、2週間の実習にも行った。高校の教員免許はもらえそうである。幸い5年目にロシア語(→「ロシア語」、4月5日)も取り、英会話(→「英会話」、4月7日)を残して卒業に必要な単位は足りている。問題は教科が英語で、全くしていないということである。先ずは夏に教員採用試験を受けてみるか。大学院もありか。そんなことを考えた。思わぬ展開だった。
百万円は氷山の一角だった。教員になり、結婚を機に家を出てあとしばらくして氷山が全貌を現わした。
次回は、教員採用試験、か。
今日で4月が終わる。高台の公園や溜池の周りに咲いている薊も、すでに盛りを過ぎたようである。