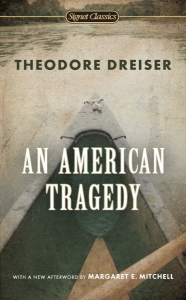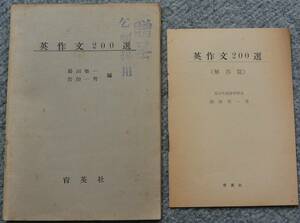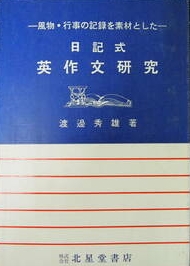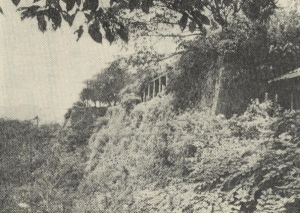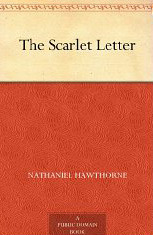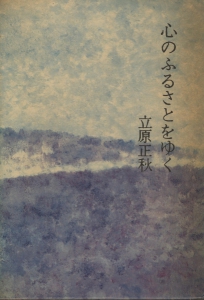面接

兵庫県庁
1次の筆記試験には合格したものの(→「採用試験」、5月8日)、問題は2次の面接試験だった。心の問題で、髭をどうするかだった。
母親の借金で人に金を借り、30くらいで死ぬにしても人に金を借りてまで生きてはいけないと感じたのが受験の直接の動機だったから(→「百万円」(2022年4月30日))、そんなに悩まなくてもよかったのかも知れないが、あほなプライドみたいなもののせいである。当初、特に髭を生やすという意識はなく、生えてきてるものを無碍に剃るのもなあ、そんな軽い気持ちだったが、当時の過激な学生運動の闘士に、下駄履きに髭面の私の風体が似ていたらしく、毎度毎度警官に呼び止められるうちに、いつしか「反体制」の意識が密かに芽生えていたらしい。入学後6年目、採用試験を受けることになったときは、髭を剃る音も俗世間の音のように聞こえていたから、困ったものである。さて、どうしたものか。そうや、一年の時に非常勤で来てはった人も夜間やったみたいで、33歳で指導主事になったと言うてはったから、ひょっとしたら面接官の経験があるかも知れへんな、聞いてみるか。結局、連絡を取って会って話を聞いてみると、「髭か?そうやな、ワシやったら、4段階の一番低い1をつけるな」ということだった。出願時に、すでに髭面の写真を貼って送ってある。どうすべきか。(→「髭と下駄」(4月19日))

妻に描いてもらい授業で配っていた似顔絵
当日、髭は剃っていた。ただ、それでは自分に後ろめたい感じがしたので、普段通り素足に桐下駄、よれよれのズボンで出かけた。桐下駄は雑巾で丁寧に拭き、ズボンは予め洗っていた。それまでもそうだったのか、その時だけそうだったのかはわからないが、案内されたのは県庁会館の板間の部屋で、3人の試験官が前に正座をして座っていた。面接を受ける側は、5人だったように思う。他の人はみな背広にネクタイ、緊張気味に正座をしていた。ええい、もういいや、あかん時はまた来年や。どうしても同じように正座は出来ずに、胡坐(あぐら)をかいて座った。面接が始まった。面接官の一人が受験票の写真を見ながらか、開口一番「この髭よろしいな。酒の肴がのうなったら、ちびりちびり舐めとったらよろしいやん」と言った。写真の口髭が相当伸びていんだろう。年配の飲み友だちから指名を受けて指導主事になって面接経験のある先輩でも言わなかった言葉である。「まあ、そう硬くならんと、足を崩してや」が次の言葉だった。僕へのあてつけという風でもなかったので、敬意を表して、座り直して正座した。そのあと、どう展開したのかまったく記憶に残っていない。
面接試験に落ちなかったのは、時代のせいだったと思う。一年遅れて入学した年に中央で国家権力にぺしゃんこにされた学生運動が地方でしぶとく生き延びていて、入学直後に学舎が封鎖され機動隊までが出動した。

学生がバリケード封鎖した木造校舎、機動隊に排除された(同窓会HP)
その後、同和問題にからんで、高校紛争にまで発展した。このあと高校の教員になってわかったのだが、その高校にも紛争時に体を張ったという人が二人いた。体制と闘う日教組側だったのか、体制を守る管理職側だったのか。大学紛争と同じく、過激な突き上げで当時の管理職の中にはつるし上げを食った人もいたようだ。殴られた人は痛みと怖さを実感した筈である。そんな高校紛争の熱がさめない時期で、制服や校則の廃止などの動きもあり、現に神戸の進学校でも制服が廃止されている。宮崎に来て、子供の転校のこともあって学校とかかわるようになった。その時に、大学紛争や高校紛争の余波もなく私のいた30年前の体質と同じや、と強く思い知らされた。宮崎なら、最初から合格はあり得なかったと思う。時期が違えば、兵庫県でもきっと2次の合格通知は届かなかっただろう。(→「高等学校1」、1月17日)、→「高等学校2」、年1月19日、→「高等学校3」、1月21日))

高校ホームページから
次回は、大学院入試、か。