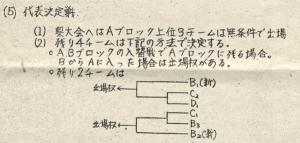新採用一年目
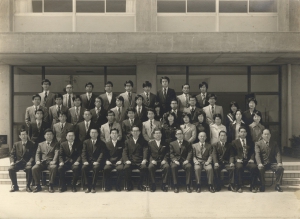
新任研修のあと、新校舎での一年目が始まった。30くらいまでだとしても人に金を借りてまで生きてはいけないというのが採用試験を受けた動機だから、教育に燃える、理想に燃えるなどはあるはずもなく、初日を迎えた。木造2階建ての校舎はこじんまりして温かみもある気がしたし、職員室の人数も多くなかったのでそれほど感じないで済んでいたような気もするが、新校舎の職員室は最初から馴染めなかった。入って自分の席に歩いて行くときに、先は長くなさそう、もって2年くらいやろなあ、とぼんやりと考えていた。
てっきり担任を持たされると思いこんでいたが、ど真ん中、教頭がこちらに机を向けている列に、教務と生徒指導用の机が並べられ、私は通路脇の3番目の席に座らされた。教務と生徒指導が学校運営の要だったようである。いっしょに新任研修に行った人は一年生の担任らしかった。ま、無難なんやろな。親から「勉強するように言って下さいよ」と言われて、「そんなあ、勉強した人は子供に勉強するようには言いませんよ、僕には言えませんね」、と親に言いそうなのがわかったんやろか、担任のないことを一応そう思うことにして、気持ちに区切りをつけた。
時間割などを扱う部署に校長が引っ張って来た人で、カリキュラムを実質的に動かす一番の実力者らしい。嫌で嫌でたまらなかった高校生の時に、1年と2年次で担任だった人である。数学の担当で淡々としていた。ほとんどしゃべったこともない。その人の部署とは、と思ったが、たぶん校長の思惑だろう。あいつ元気はあるけど、一年目から担任やらせるのも危険やし、一年は手元に置いてちゃんと見とってや、そう頼んだに違いない。その魂胆が透けて見えた。ま、しゃーないか。実際、毎日気の休まらない部署だった。休んだ人の授業の手配は、毎日緊急を要する職務だ。朝に連絡を受けて、その授業を誰が持つかを黒板の持ち駒票を見ながら手配するわけだが、滞ると生徒が右往左往する。この立場にいると、うかつに休むのが難しくなる。春休みには大きな授業の駒版を前にして全職員がどの時間に授業をするかをあれこれ考えて持ち駒を当てはめて行く。たっぷり何日かかかる。ここがしっかりしていなければ、職員は右往左往させられる。その点、筋金入りで、混乱した事態を見なくて済んだのは、その人の実力だろう。寡黙な人だったが、誰からも一目置かれているのは肌で感じた。
そや、校長に挨拶に行ってなかったな、行ってみるか。校長室に挨拶に行った。
「どや、毎日おもろいか」
「そうですね」
「玉田クン、その髭伸ばしてるんか?」
「はあ、剃ってないだけですけど。生えてくるもん、むやみに剃るのもなんなんで」
「そうかぁ。たしか、男の和服は着たらあかんと職務規定にあるみたいやけど、髭を伸ばしたらあかんとは書いてないみたいやしな。その髭、伸ばせ、伸ばせ」
「そうですね」
へえ、校長と、学内で一番の実力者が好きにやったらええ、と言ってくれてるんか。何とかやれそう。3ケ月の非常勤で慣れたところで新校舎に移転、新採用一年目がこんな感じで始まったようである。
写真を焼いて以来(→「諦めの形」、3月26日)撮影を避け気味なのであまり写真が残ってないのだが、嫌々参加した集合写真は何枚か残っている。最初の写真は、新任研修のあとに撮った集合写真である。
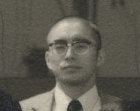
(↑)切り取った写真と、その少し前に→「県大会」(5月16日)に参加したときに取った集合写真から切り取ったもの。(↓)
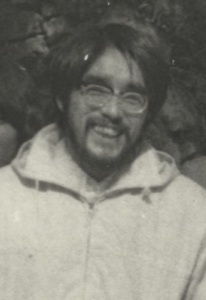
次は、懇親会、か。