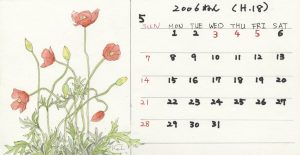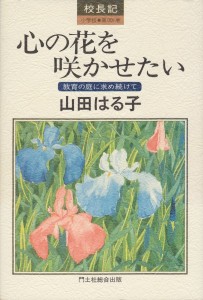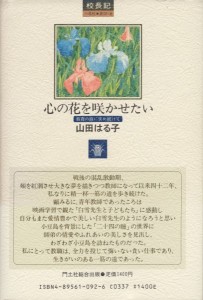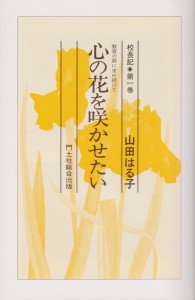家庭教師4

木崎浜から北側に尾鈴山系をのぞむ
今日は朝からきれいに晴れている。昨日も雨だったし、この先1週間ほどぐずぐずした天気が続くらしい。短い時間でも、布団を干しておこう。昼からは白浜だから、晴れている分、きれいな海を見ながら行けそうである。

青島海岸
100点の中学生を毎朝にしてもらうように頼んだのは、夜間課程の時間帯では捌けない数の家庭教師を頼まれていたからである。(→「家庭教師1」)11歳下の妹の元同級生の母親から頼まれた。妹とは小学校の3年生か4年生の時に同じクラスだったようで、かなり離れた川の上流の田舎の祖父母の家に引っ越しをしていたらしい。妹が家庭教師の話をしたのかも知れない。母親が声をかけた近所の同級生と、高校生の姉も合わせて4人でやって欲しいということだった。自転車で行くのも時間的にきつそうだったので、バイクを乗っていた弟に相談したら、YAMAHAの50CCのバイクを用意してくれた。中学校の時に「殴られて血を見たらかーっとなって遣り返したら、いつの間にかグループの頭になってしもうて。わい、血ぃみたらあかんねん。」と言っていたが、そこから抜けるために、中卒で大手の車輛会社の養成所に入って家を出ていた。期間が過ぎたあと家に戻り、家から神戸の会社に通勤しながら夜間高校に通っていた。元々機械やバイクに関心が強かったようで、出入りしていた整備会社の人を兄貴分と慕うようになっていた。その人に都合をつけてもらったらしい。バイクや車に関心がなかったので運転免許は考えたことはなかったが、運転免許を取って足を確保することにした。原付は筆記試験だけでよかったので、免許はすぐに取れた。当時のバイクは50CCでもエンジンがかなり強力だったようだ。夜中に川の堤防の道路を南に下ったが、100キロは軽く超えていたと思う。バイクて、速いもんやなあと思いながら、誰もいない真っ暗な道でエンジンを噴かした。

バイクを飛ばしたのはこの川の堤防である(→「作州」、3月14日)
引き受けたのは、元同級生と二人の男子中学生と高校生の姉の4人だった。やりながら、今までの人たちとどうも勝手が違うようやな、と感じ始めた。姉妹と男子中学生の一人は、元々勉強に向いてないようだった。親から言われて何となく、そんな感じだった。もう一人は頭もよく、する気もあったようだ。その3人をいっしょに、というのはなかなか難しい。幼馴染でもあるし、一人だけ、よう出来るなあと褒めるわけにもいかなし。親に別にやった方が本人のためになりますよ、とも言えないし。姉の方は、別の意味で大変だった。二番手の県立高校には行っていたが、商業科で教科書は中学校用に毛が生えた程度なのだが、進学する気もないようなのに、どうして英語の家庭教師?という程度なのである。同時並行という時間の制約もあって、一週間たまっていた話を話したくて仕様がないようだった。ここまではやっときや、と言ってもなかなかやって来ない。半ばお手上げである。ある時、父親が二人で話している所に、あんな成績で、一体何をやってるんですかと怒鳴り込んで来た。何も言わなかったが、やめなかったのはなぜだろう。高校生の話を聞いてやりたい気持ちもあったのかも知れない。この家庭教師は、なんだかもやもやが残っている。思わずたくさんの家庭教師をやらせてもらったが、やっぱり勉強は自分でするもんやろな、という思いは変わらなかったものの、暫くのあいだ、経済的にも気持ちの上でも余裕をもたせてもらったのは確かである。その後、高校の教師になり、長いこと大学で授業を持つとは夢にも思わなかった。
次は奈良西大寺、か。

折生迫のきんぽうげ、もう盛りを過ぎている