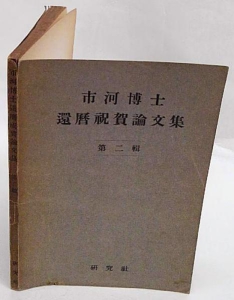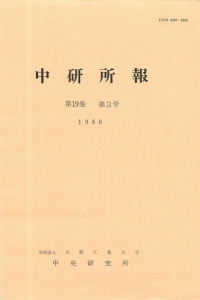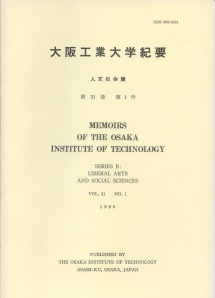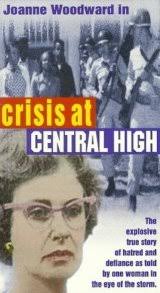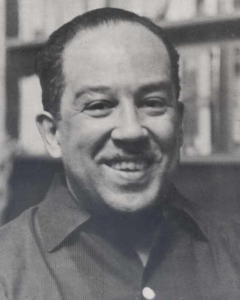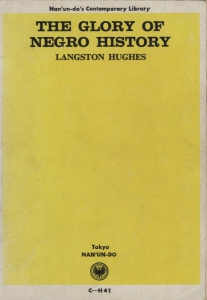HP→「ノアと三太」にも載せてあります。
つれづれに:二つの学院大学

1983年に大阪工大(↑、→「大阪工大非常勤」、7月11日)で非常勤を始めて、工学部の学生相手に「LL教室」(7月12日)を使って補助員3人に助けてもらいながら教養科目の英語の授業をさせてもらった。次の年に桃山学院大学(↓)、その次の年に神戸学院大学、二つの学院大学から非常勤の依頼があって引き受けた。どちらも黒人研究の会の人の知り合いからだった気がする。一度教歴が出来ると、非常勤なら口がかかるようだった。英語の必修時間が今と比べてかなり多かったから、それだけ英語の非常勤の需要も高かったというわけである。大概は専任のある人がお互いに助け合って非常勤に行っているのが普通だったようだが、私のように教歴のために引き受ける人もいたわけである。大阪工大は1コマ16000円だったが、桃山学院大は24000円、神戸学院大は22000円だったと思う。国立大はこなしたコマ数の謝金が翌月に支払われるが、関西の場合は、総謝金を12ケ月で割った分が毎月支払われるのが慣例だったようだ。地方で大学も少なく非常勤の需要がない所は、1コマでも引き受けたりするが、一日3コマで頼まれることがほとんどだった。一年間30週の規定は今も同じだと思うが、実際は23週か24週だった。月額支給なので、何かの都合で休講にしても減額になることはなかった。慣例的に少しの幅を持たせて運用しているようだった。

たぶん、運営交付金が削られて、国立大の非常勤の謝金の基準も下げられ、その影響で私学の基準も下がっているのではないか。それに予算削減で締め付けられて、英語の必修の数を大幅に削っているところもある。文部省(現文部科学省)は英語は演習科目と考えて単位数を普通の講義科目の半分に換算して来たが、それを悪用して名目は同じ単位数でも実質は半分という裏技を当然のように使って、英語の必修科目数を減らしているところも多い。つまり、英語の非常勤の需要も大幅に減っているというわけである。その意味では、非常勤でもまだめぐまれていた頃だったかも知れない。水曜日の夜と金曜日の昼は大阪工大だったので、月曜日に引き受けた。1コマ目からだったので、朝早くから満員電車の一日だった。

桃山学院大学は大阪府和泉市にあって「明石」(6月16日)の自宅からは2時間ほどかかる。しかも、大阪で地下鉄に乗り換え、難波で南海電車に乗り換える。梅田や難波は相当な混みようである。大学は1959年創立のミッション系で、文科系の大学だった。そこの教養の英語を頼まれたわけである。大学のバスケットボールのチームメイトがその大学の付属高校だったので、名前は聞いたことがあるくらいで、中身は知らなかったが、可もなく不可もなくという印象が残っている。学生はまじめで、おとなしい人が多かった分、あまり印象にも残っていないようである。時々、図書館(↑)を使わせてもらった。ライトの日本語訳が載っている『新日本文学』を探してコピーさせてもらった記憶がある。

3年目に引き受けた神戸学院大学(↑)は家から近かったので、満員電車の心配をせずにすんだが、きつい坂を登る必要があった。それでも自転車で半時間ほどで大学に着いた。土曜日も授業をしていた頃で、土曜日の3コマを引き受けた。1966年創設の新しい大学(↓)で経済学部の学生の英語を担当した。1972年に栄養学部と薬学部が出来てから徐々に大学の評価が上がったようである。隣の市にある私が出た進学校から当時進学した人はいなかったと思うが、最近は進学している人もいるようである。学生の印象は、桃山学院大と同じで、まじめでおとなしく、可もなく不可もなくといったところか。特に困ることはなかった。専任の話があったわけではなかったので、教歴の一つとして引き受けたというのが正直のところだ。どちらも学院大学で、学生の雰囲気や反応、事務員の対応、教室の施設など、よく似た感触が残っている。
次は、横浜、か。